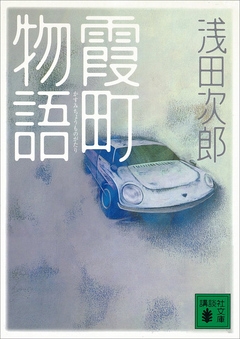感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「お腹めしませ」が途中で忽然と消えてしまった。江戸時代から一気に昭和にタイムトリップして微に記憶に残る時代の匂いを感じながら読んだ。
へぇ、こいうのも書くんだというのが率直な感想。
で、読み進める間に夢中になった。不思議な余韻を残す「夕暮れ隧道」に惹かれ、各話で語られる写真館と伊能夢影の頑なな生きざまに惹かれた。オーティスは通な音学好きが贔屓にしてたのかと思ってたけど、そうじゃなかったみたいだな。浅田次郎に忌野清志郎の物語りを書いて欲しいなぁ。
Posted by ブクログ
浅田次郎氏の、高校時代の思い出を綴るエッセイ(?)。都内の進学校に通う著者は、クラスメートたちと、車だ酒だ女だたばこだと、派手な遊びを繰り広げる。その主な舞台となるのが、霞町、今でいう西麻布だ。霞町という名前は聞いたことが無かった。都会の谷間にあり、本当に霧が満ちるのだという。
麻布にある小さな写真館を営む祖父と、写真を撮りに旅に出てしまう父と、芝居鑑賞ばかりの母、おしゃれな祖母、と愛すべき家族や悪友たちが出てくる。自由で素晴らしい青春時代を過ごしたことがうかがえる。
浅田次郎、さすがの筆力。うまいな~とうならされる。面白くて一気に読んでしまった。彼らしい、ほろりと甘く切ない本である。もう20年も前に出版されたようだが、本書の存在を知らなかった。読んでよかった。
Posted by ブクログ
戦後の昭和、高度経済成長で東京も都市開発が活況を見せ始める時期、学生運動華々しい時期に、東京の霞町で高校時代を過ごした主人公と家族、そして仲間たちの物語。連作短編という形式を採りながら、少しずつ家族の歴史が紐解かれていく。
Posted by ブクログ
いくら浅田次郎が賢い子どもだったとはいえ、小学生や高校生時代のことをこんなに詳細に覚えているはずもなく、やはりフィクションなのでしょう。そうは思ってもこれは彼自身の物語、そんな気がします。
本作は、町の写真館に生まれた「僕」の回顧録。短編8話で語られ、前半はおもに僕の高校生時代。両親と呆け気味の祖父と僕で暮らしています。由緒正しい写真館でしたが、時代が変われば住人も変わり、記念日だからと家族で写真館に来るような客は激減。いっそのこと店をたたんで引っ越すほうがいいのだけれど、昔気質の祖父が生きている間は許されないこと。ヤケクソ気味の両親は、祖父の財産を食いつぶす勢い。父はふらふらと写真を撮りにあちこちへ出かけ、母は芝居見物三昧。まだ一応ぼんぼんの僕は、高校生ながら車を所有。学校の所在地の環境のせいで、同級生と酒場に入り浸ることもあります。
こんな前半もいいのですが、素晴らしいのは僕の小学生時代が描かれる中盤と、再び高校生時代の話に戻る後半。当時は存命だった祖母のこと、呆ける前の祖父のこと。遊ぶことについては何も言わないのに遊び方についてはあれこれうるさい家族がものすごくいい。嘘をつくな、見栄を張るな、愚痴を言うな、一瞬をないがしろにするなと教えてくれたおじいちゃん、おばあちゃん。
決してお涙頂戴に走ってはいないのに、浅田次郎の本を読むと涙で目がかすむことが多すぎる。この余韻があるから、本を読むのは止められない。たまりません、浅田次郎。
Posted by ブクログ
浅田次郎さんの作品は、物語の中に「幽霊」が出てくるものは最高の出来。もちろん、白い着物来てでてくるわけじゃないんだけど。「霞町物語」にもしっかりでてくる。どの作品のどこの部分で出てくるかは秘密。かなりあとになってからでないと、あそこで出てた人たちは、その時はもう死んでたんだ、という推理があって、初めて幽霊だったとわかるんだけど。
Posted by ブクログ
浅田次郎が1970年代の青春を描く、自伝的な面もある連作短編集。
連作短編文芸の最高峰だと思う。
ストーリー、台詞、論調、テンポ、人物、時代、アイテム…味のあるかっこよさがひたすら漂う。
他人事なのに懐かしく、切なく、誇らしい。来世はこんな青春を送りたい。
こういう話が描ける作家がたくさん出てきてくれれば、いつまでも飽きないと思う。
5+
Posted by ブクログ
「雛の花」と「卒業写真」が特に好き。
平成生まれで大学受験時には学校と塾に引きこもってた自分とは全く違う生活を送る高校生たちの生活を中心に、主人公「僕」の幼少時代やその家族に纏わる物語だけど、どんどん引き込まれる。最後は思わず涙。
Posted by ブクログ
これは、私が初めて読んだ浅田次郎作品。
赤川次郎と間違えて買ったんだっけか?
なんで買ったのかはよくわからない。
それでも、この小説は何十回も読むくらい引き込まれた。
短編だったから読みやすかったというのもあるだろうが、
いっぺんで浅田次郎が大好きになったのだった。
後日、「浅田次郎が面白い〜」と私の浪人時代の一番気の合う友達に言うと、
その子も、「私も浅田次郎が一番好き!」と言っていて、
性格が似ていると好きな小説家も似るのかな、と思ったりして笑った。
この本の中の作品、本当にどれもが面白い。
でも、読んだのはもう3年前の話なので実はどんな話があったか2つくらいしか覚えていない。
帰国したら読みたい一冊の1つである。
Posted by ブクログ
なんだか夢のような物語でした。
田舎育ちではなく、かといって都会になじんで育ったわけでもない私にとっては、こんな青春時代を送った人たちがいたんだろうかと。
おとぎの国の話を聞くような感じでした。
一方、主人公の祖母の話は、都会育ちだった私の祖母の話を思い出させるもので、かえってリアルな感じがしました。
そういえば、亡くなった祖母は浅田次郎作品が好きでしたねえ。
祖母の琴線にふれる光景が描かれることが多かったからなんだなあと改めて思いました。
Posted by ブクログ
すばらしい。瑞々しく清々しいあの時代の人びとの描写が。正に自分も一緒に過ごしているような錯覚に陥るような。
この時代に産まれ育ったことを心底羨ましく思う。浅田次郎作品はあまりしらなかったが、ジャンル問わず読んでみようと思う。
雛の花は名作!
Posted by ブクログ
1960-70年代の東京にタイムスリップした感覚が得られる。
オーティス・レディングやブルース・スプリングスティーンの嗄れた歌声を聴きながら読みたい本
Posted by ブクログ
昔の青山はこんな感じだったんだろうか?若者の服装、車、お店、全然知らないけどかっこいい。座ったとたんにお寿司が出てくるお店に怒り、鰻屋で「遅いね」と言った僕を野暮だと叱り飛ばす祖母がいきでかっこいい。それになんといってもライカを首に下げている名人のおじいちゃんがすごくかっこいい。都電の一番スピードをあげてくる瞬間を捕えた写真はどんなにすばらしいことだろう。読んでいるうちにどきどきしてきた。僕の友人たちを撮った写真はどんな感じなんだろう。浅田さんらしい人情味あふれている作品で泣けてきてしまった。
Posted by ブクログ
「青い火花」の後半、どこかで読んだことがあるなぁと思って思い出してみると、高校時代に受けた模試の現代文で読んだのだった。模試であることを忘れて、ひきこまれたのを覚えている。模試が終わってから、全文読みたいと思っていたのにいつの間にか忘れていた。数年越しに読めたことに運命を感じる。
「卒業写真」はずるいなあ。感動しないはずがないストーリー。
Posted by ブクログ
目次
・霞町物語
・夕暮れ隧道
・青い火花
・グッバイ・Drハリー
・雛の花
・遺影
・すいばれ
・卒業写真
著者の青春時代を反映した自伝小説?
甘く切なくほろ苦い?
ちょっとナルシズム入っちゃってたりしたら、読めたもんじゃない。
ところが、主人公であるはずの僕よりはるかに魅力的なのが、彼の祖父母だ。
江戸っ子で、粋で、気風(きっぷ)がよくて、ボケている祖父。
写真技師としての誇りが高く、妥協をしない。
その祖父が心から愛していたのが、元深川芸者の祖母。
学生運動の嵐が通り過ぎたころの東京の高校生。
学校から帰るとバリッとしたコンテンポラリィのスーツを着て、タブカラーのシャツに細身のタイを締め、髪はピカピカのリーゼントで固め、ブルーバードのSSSやスカイラインに乗ってダンスに繰り出す。
酒もたばこも女もあり。
進学校なので、校内の成績が多少悪くても、まあ慶応くらいには行ける。
そんな主人公の青春物語よりも、はるかに祖父母の物語の方が深くて濃い。
ちょっと影は薄いが、両親もいい。
優しくて、写真の師匠である祖父に頭の上がらない入り婿の父と、あっけらかんと明るい母。
祖母を巡る、口にされることのない家族の秘密。
大人が大人であった時代。
死期を悟り、家族がまだ寝ている早朝に、ひとり荷物をまとめて病院へ向かう祖母も格好いいが、好きなシーンはこちら。
“僕が高校を卒業する年の冬、祖父はスタジオの籐椅子の上で、ゴブラン織りの絵柄のようになって死んでいた。
駆けつけた父は、祖父の膝からライカを取り上げると、胸に抱きしめて、わあわあと泣いた。検死の医者や警察官が来ても、近所の人がおくやみに来ても、そのままどうかなっちゃうんじゃないかとまわりが気を揉むほど、スタジオに立ちつくして泣き続けていた。”
血のつながりより強いきずなのあった祖父と父。
いつも頭ごなしに怒られていても、二人だけにわかる信頼がそこにあったのだなあと思わせるシーン。
家族の在り方が、とても美しくて泣けた。
Posted by ブクログ
浅田次郎といえば「泣かせ」ですが、この作品集は自伝的小説のせいか、余りエモーショナルに走らず、自制が利いています。私よりも少し年上の、しかも都会の少年の自叙伝になりますが、不思議な懐かしさがあって気持ち良い作品です。
一族の描き方も良いですね。特にボケが始まった名人かたぎの祖父の正気のときの格好よさ、いかにも明治の江戸っ子。そして深川芸者だった祖母の伝法さ。著者の思い出の暖かさがにじんでくるような文章です。
一気に読み上げてしまいました。
Posted by ブクログ
オリンピックの頃の東京の山手っ子の、夜遊びを含む高校生活。まだ、その頃にはいくばくか残っていた江戸っ子風味の家族(語り手の祖父母)のやりとりを、軽いタッチで描くことによって、時代の移り変わりと家族の情愛を浮かび上がらせる。うまいね。
Posted by ブクログ
1章1章は独立しているのだけど、全体で面白い構成になっているからか、感情移入しやすい。ラストの『卒業写真』の複数箇所で泣いてしまうのもきっとそのせい(笑)。
Posted by ブクログ
著者自身?の青春時代を描いた、連作短編集。
スカイラインGT-R、ブルーバードSSS、エヌコロ、ディスコ、コンポラスーツ、アイビールック、めちゃくちゃ懐かしいし、共感。
「雛の花」の章では心ならずも涙が、、、、
やはり浅田次郎はいい。。。
Posted by ブクログ
まとまった読書の時間が取れなくなった中で、こういった短編集は非常に良い息抜きとなってくれるものである。
「青い火花」と「卒業写真」が特に気に入った。時代設定はまだまだ戦後と呼べる時期であり、主人公たちからは一抹の厭世観のようなものも感じられたが、それと同時に持っている少年らしい心が絶妙に混じり合っていて、何となく懐かしい心持になれる短編たちであった。
もう少し詳しく感想を書きたいところであるが、翌日の仕事に頭が占領されてしまうのがひよっこサラリーマンの悲しい性である。
Posted by ブクログ
なんか、こういう高校生は好きでない…
でも、こんな時代、こんなまちがあったんだ、というのを興味深く読ませてもらった。
これが当時のこのまちの当たり前だと思うと、この時代の地方に住む自分は、すごいなぁと思う。
『雛の花』のおばあちゃんは色々美しくて、憧れる。。。
『卒業写真』は、ベタな話と言えばそうなのだけど、同じく職人の祖父を持つ身としては、もう切なくて切なくて仕方なかった。一番心にきた。
おじいちゃんおばあちゃん、両親を大事にしようって思える、そんな読後感。
Posted by ブクログ
なんだか泣かされる。
都電を知っているこの年齢の人達は、そのころの東京を懐かしく思っているのがよーく分かる。江戸っ子の粋があった最後の時代なんだろうと思う。街が変わり、「ダムに埋もれた故郷と変わらない」と語る作者の表現は、都会でも変わり行く姿を現していて物悲しい気持ちになる。
Posted by ブクログ
かつて子供の高校受験用の国語の問題文で一部が掲載されており、それをきっかけに購入したものです。
端的な読後の感想は、男性目線の青春小説だなーということ。
舞台は東京の中心街、青山・麻布・六本木の才知に囲まれた谷間の霞町。そこは昔からの旧家や商家が存在し、そこのぼんくら達の成長の過程を描いています。
ぼんくら、と表現しましたが、高校生で車とか持ってたり(もちろん親から買ってもらう)ちょっと鼻につきます。
ただ、うっすらと将来への不安を感じながらも、エッチなことばかり考えていたり、男の友情が妙に固かったりとか、そういうのは微笑ましく楽しく読めました。
これが森絵都さんや瀬尾まいこさんの青春小説だと、大体主人公は女性であり、視線はたいてい冷静なのであります。男性はこうはなりません。おばかです。
その他、癖のある写真屋の祖父、元芸者を身受けした話等々、主人公家族の家の歴史にうねりがあり、そうした点もドラマチックでした。
・・・
1970年代に青春を迎えた人の話はどう考えても古い。解説のDJ氏は胸を熱くして本書を読んだと書いてあるが、私はもちろん古いなあと辟易しながら読みました。
にもかかわらず、本作を面白いと感じさせ、また試験問題にも選ばれる理由は、やはり高校生特有の心情を瑞々しく描いているからであり、また波乱がありながらも家族の繋がりを温かく描いているからだと思いました。
描かれる風俗がやや古くさいのですが、それを除けば楽しく読める青春小説だと思いました。エッチな事ばかり考えている高校生が主人公なので女子受けは余りよくない気がします笑
Posted by ブクログ
著者・浅田次郎の若かりし時代を振り返ってみた、自伝的小説?という感じでしょうか?ふむう、当時の東京の若者は、ザックリと、こんな感じで、生活していたのか?という雰囲気が、ザックリ、うむ、感じられた、ような気がします。気がする。
で、気がするのですが、うーむ。すみません。それほど、こう、読んでいて、グッと来た!とか、そういった事がなく、、、すみません。淡々と、読み終えてしまいました。うむ。本当に失礼な表現になってしまいますが、「可もなく不可もなく」という、、、感じ?
ちょっと前に読んだ、同じ浅田次郎さん著作の「壬生義士伝」は、ウルトラ面白かったのですが、こちらは、、、ごめんなさい。あんまり、ハマれなんだ、、、すみません。なんだろうなあ、ちょっと、相性悪かったなあ、、、
ちょっと、変な表現ですが、この小説が、心の底から好きだ!という人と、いっぺん、じっくり語り合ってみたい気がします。「どこがそんなに好きなの?」っていう事を、お互い、内容知っている訳ですからね、お互い、それぞれこの小説を手に取りながら、何処にグッと来たところがあるのかを、教えてもらいながら、語り合いたいなあ~、って、思った次第ですね。コレって、妙な考えかなあ?
とりあえず、うむ。極めて普通だ。という感想に、なってしまいました。でも、浅田次郎さんは、大好きな小説家なので、別の作品、またドカドカ読んでいきたいものです。
東京と、地方都市の違い
作者と同じ年代ですが、名古屋で、暮していたので、ここまで女性に対してドライな感じでは、つきあえなかった。
少なくとも私達の周りでは、もっと真摯に付き合っていました。
Posted by ブクログ
浅田次郎、こんな青春時代を送ったのかー。江戸っ子、いなせ。今の東京人(本物はもう少ない)からは考えられない。時代がいいなぁ。ただ、男女関係については、Westside Storyみたいに、よそ者の女は遊び、っていうのがちょっと。女も自己責任の原則。この時代の女が頼り甲斐のある男と結婚したがるのは当然と思った。自分はこんな時代でなくて良かったと思うが、きっぷのいい、お祖母さんのように年を取ったら身を処すことができたらいい。
Posted by ブクログ
作者の自伝的(?)連作短編集。カッコよすぎ、あるいはカッコつけすぎな部分が鼻につくところもあるけれど、家族について書かれた「雛の花」「卒業写真」あたりは、素直に良いと思える。読む人それぞれの家族を思いださせる作品ではないでしょうか?
Posted by ブクログ
霞町…麻布と青山と六本木の中間地点
今では西麻布と呼ぶのだろうか
不思議な魅力のある町。
めっちゃ都会やねんけど
田舎の町っぽい雰囲気もあるというか
なんかエエとこやねん。
東京は
東池袋⇒南池袋⇒渋谷⇒東池袋⇒西池袋⇒北池袋⇒麻布十番と移り住んだが
遊びに行くのは、ルネス(現warehouse702 ※)か霞町がメインだった。
平日の夜中は静かな町やねん。ようカフェに行って仕事してた。
行ってた一つのカフェは地下にsoundbar+という会員制バーがある。
でももうないか?
※warehouseはゲイと噂の俳優のN宮君が常連らしい。1回しか見たことないけど。
そんな霞町に住みたくなった1冊。