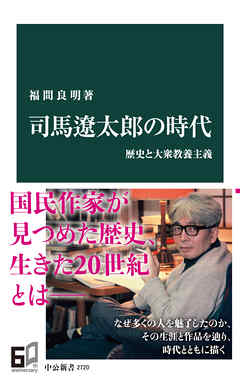感情タグBEST3
Posted by ブクログ
司馬の学歴・職歴が傍流であったことや軍隊経験が作風に与えた影響、作品がサラリーマン層にある種の教養主義として受け入れられた背景、没後に司馬史観批判が発生した理由等、司馬遼太郎を理解するための入門書として最適な一冊。得るものが多く、付箋貼りまくりでした。
新聞記者時代に、政治や事件などを扱う花形部署ではなく、歴史・宗教や文化関係などを扱う比較的落ち着いた部署にいたため、読書の時間を確保でき(1日5時間!)、それが作家としての下地になったという話に、残業は糞だと思いました。
司馬作品に滲むエリート批判、組織批判はただのやっかみではなく、ボロい戦車しか用意できないのを精神論で乗り切ろうとして(そんな戦車に乗せられて司馬自身も死ぬかもしれなかった)、結果として国家を破綻させた軍部の上層部に対する憎しみが根底にあると考えると至極真っ当なものだと感じました。
司馬遼太郎没後の司馬史観批判は、戦後歴史学を自虐史観と非難して自由主義史観を唱えるグループが『坂の上の雲』を根拠としたことで歴史学者が危機感を覚えたことが要因。
それまで歴史学者が歴史小説を批判するのは「大人気ない」ことであり、司馬以外の歴史小説家が槍玉に挙げられることも無かった。
著者の福間良明氏も指摘してますが『坂の上の雲』が明治礼賛というのは誤読もいいところで、僕はこの作品を終電の電車で読みながら、組織というものがどれだけ糞であるか、戦場では個人の命がどれだけ容赦なく捨て石にされていくかを書いたものだと受け止めました。人は読みたいように読むわけですね。
本書は司馬遼太郎について議論する際の前提知識としたい本です。
ただ、著者の専門が労働者の教養文化史などのため、漫画アニメ等への影響の分析が無く、女性読者層の捉え方(企業勤めの男性が中心で女性読者はいても少なかった)も疑問があるので、その辺を分析した本がほしいですね。
ちなみに僕が把握できてる範囲だと、るろうに剣心、銀魂、進撃の巨人はそれぞれ作者がインタビューとかで司馬遼太郎作品(燃えよ剣、坂の上の雲等)からの影響を話してます。
Posted by ブクログ
国民作家司馬遼太郎の作品、思想について、「教養主義」という立場を交え、略歴、戦争体験から探る。
司馬遼太郎ファンならずとも楽しめる内容だろう。作品を読むだけでは見えてこない氏に対する評価、俗に言う司馬史観など。大衆教養主義やサラリーマン社会がヒットの一因。
学歴と職歴、傍流の立場を指摘した所は慧眼。
単なる小説家でも歴史学者でもない独自の立場。本書を読めば司馬作品の魅力がさらに増すだろう。
Posted by ブクログ
司馬作品が生まれる同時期に生きてきた私としては、福間さんの分析は納得できる部分が多々ありました。
文学者ではない産業社会学部の教授が分析するのがよかったと思います。
史実を司馬さんなりに分析・加工し司馬作品として世に問う。
司馬史観、おおいに結構じゃないですか。
読み手も、司馬史観にここちよく酔い、自分の人生を豊かに出来ていたら、それはそれでいいと思います(笑)。
Posted by ブクログ
軍隊経験がバックボーンになっていることは周知の事実だろうが、学歴職歴の視点は私にとって新しかった。
でも、淀殿を淀君と表記してるのはいただけない
Posted by ブクログ
司馬遼太郎の作品を、客観的にどのようにとらえているのかを知りたくなりこの本を読みました。
自分も「坂の上の雲」を、仕事の行き帰りなどの隙間時間を使って7巻まで読破しました。
この新書の著者は、司馬遼太郎は「坂の上の雲」を書き「明治の明るさ」を描いたのと同時に「昭和の暗さ」を現したかったのだと強調していました。
これから最終巻を読みますが、上記の視点を参考にして読みすすめていこうと思います。
Posted by ブクログ
司馬遼太郎著作って、あんまり読んだことがない。燃えよ剣と新撰組血風録くらいかな。
司馬史観という言葉は聞いたことがあって、興味があったんだが。
かなりコンプレックスと、軍の精神主義に対する批判、技術に対する信頼とかがベースにあって。
書かれている小説自体も、その、司馬先生の主観を通した仕上がりになっているようだ。
それは全然いいと思う。小説だし、面白ければ。
教養主義、高度経済成長、文庫本化などが重なって広く読まれていったようなのだが、その、主観を通した「解釈」がいつしか歴史上の事実みたいに受け止められていったってことなのかな。
多分、受け入れられやすく、分かりやすいパラダイムに基づくものだったのだろう。
司馬史観「ワールド」に展開する「小説」であるということが忘れられてしまったのではないかと感じた。