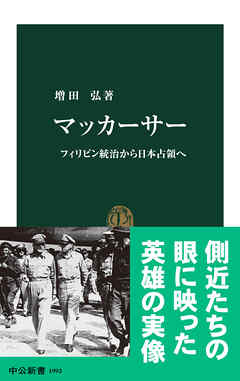感情タグBEST3
Posted by ブクログ
マッカーサーについて、フィリピン軍事顧問時代から朝鮮戦争時の国連軍司令官解任までの調査に基づき、その人間像を明らかにしたもの。二次大戦における個々の戦闘や日本占領期の施策については詳細の記録が残っているが、バターンボーイズの調査を通じマッカーサーという人物を軸に縦にそれぞれの出来事を450頁に簡潔にまとめられている。「終章」でマッカーサーの人間像についてまとめられているが、それまでの分析が的確であり、説得力があった。
Posted by ブクログ
GHQのマッカーサーが日本に来る前に何をしていたのか―日輪の遺産を読んで、マッカーサーは親子2代でフィリピンを統治していたときに莫大な遺産を作っていたと聞いて、気になって読んでみました。マッカーサーは一度日本に敗れ、フィリピンからオーストラリアに逃げた。そしてそこで一緒に逃げた部下たちで組閣し直し体制を立て直して、フィリピンを再奪回し、その奪回後の占領政策でのテストを経て日本の占領政策を進めていった。社会の教科書にはそこまで書いていなかったので、初めて知ったマッカーサーの姿がたくさんありました。そして偉い人の部屋が大きい理由に得心できたのもこの本でした。そうか考えるとき、歩きながら考えをまとめる人は昔から多かったんだ。そんなこんなで、歩きながら考えることの効果を改めて見直したのでした。
Posted by ブクログ
ハルバースタム著の朝鮮戦争でマッカーサーの人となりに興味がわいたので読んでみた。フィリピン統治時代から第二次世界大戦を経て日本統治に至るまでの流れにおいても、朝鮮戦争時代におけるマッカーサーとは本質的に変わらず、朝鮮戦争での解任は起こるべくして起きたと認識させられる。
ハルバースタムがマッカーサーの負の面を大きく描いたのに対し、本作では正の面にも焦点を当てて描いており、一言では語り切れないマッカーサー像を補完している。その結果、全体としてまとまりにかける印象があるが、そこがまた面白い。
Posted by ブクログ
東洋英和女学院大学国際社会学部教授(日本政治外交史)の増田弘によるマッカーサーの評伝。
【構成】
第1章 フィリピンとの邂逅
第2章 バターンボーイズの誕生
第3章 日米開戦前夜からマニラ脱出まで
-1941年10月から同年12月まで-
第4章 マニラ陥落と第一次バターン攻防戦
-1942年1月初旬から2月初旬まで-
第5章 コレヒドール島脱出計画
-1942年2月初旬から2月下旬まで-
第6章 マッカーサー一行のコレヒドール島脱出
-1942年2月下旬から3月中旬まで-
第7章 第二次バターン攻防戦と”バターン死の行進”
-1942年2月初旬から5月上旬まで-
第8章 オーストラリアからフィリピンへ
-1942年3月から1944年10月まで-
第9章 フィリピンから日本へ
-1944年10月から1945年8月まで-
第10章 日本の非軍事化・民主化
-1945年8月から1947年12月まで-
第11章 ワシントンの対日政策転換とマッカーサーの抵抗
-1948年1月から1950年6月まで-
第12章 朝鮮戦争とマッカーサー解任
-1950年6月から1951年4月まで-
終章
著者の増田弘は、『石橋湛山』(1995年)『公職追放』(1996年)『自衛隊の誕生』(2004年)などの占領期の実証的研究で知られている。
扱う題材は、日本史上で最も有名な外国人の一人であるアメリカ陸軍元帥ダグラス・マッカーサー(Douglas MacArthur)である。一般的にマッカーサーと言えば、戦後占領期に日本に君臨した連合国軍最高司令官(SCAP)として知られている。
本書の大きな特色は、1945年の占領期に限定するのではなく、その前段となる戦前のフィリピン時代から軍人・行政官としてのマッカーサーを描き出そうとするものである。 敢えてフィリピン時代から説き起こすことで、SCAPの隷下として占領行政を担ったGHQのメンバーの中核となった「バターンボーイズ」とマッカーサーとの関係が明らかにされている。
太平洋戦争開戦直後において、日本軍の侵攻を食い止められず、マニラ湾西岸のバターン半島とその南のコレヒドール要塞に部下の将兵を残して、単身脱出を図らざるを得なかったことは輝かしい軍歴を持つ軍人マッカーサーにとって屈辱の記録であった。そして、その苦境をともにした少数の側近たちが「バターンボーイズ」であった。
戦中におけるフィリピン政府とマッカーサーの関係について、従来の研究をベースにしながらもより詳細な検討を行っているところに、本書の研究上の成果があると言えるだろう。しかし、政治史の流れとしては、バターン攻防戦からコレヒドール脱出までの側近との細々としたエピソードが続くのはやや冗長と感じる。日本占領期への連続性を論じるなら、日本軍から奪還後のフィリピン復興行政をより詳細に論じた方がよかったのではないかと思う。
その一方で、フィリピン→オーストラリア→フィリピン→日本という動きを追っていくことで、軍司令官としてのマッカーサーの権限拡大が提示されており、竹前英治『GHQ』などで紹介されていた「GHQの沿革」がより明快に理解できる。
また、後半の日本占領期については、著者の「朝鮮戦争以前におけるアメリカの日本再軍備構想 (一)(二)」という論文に基づいて、占領政策の転換と日本再軍備のテーマをめぐる東京のマッカーサー、ワシントンの陸軍省と国務省という3者の対立関係が簡潔に描かれている。
この中でマッカーサーとワシントンの反目が、徐々に再軍備容認へと傾いていく様子が時系列で説明されている。
しかし本文で述べられているようなマッカーサーが滔々と述べる再軍備反対の根拠は、いかにも建前ばかりである。平和憲法への自負や根っからのロマンチスト、楽観主義といったフィリピン以来の人物像を重ねあわせていけば、単なる自信過剰な最高司令官という印象を与えかねない。
個人的には、マッカーサーの日本再軍備反対の根拠を説明するためには、柴山太(愛知学院大学)が指摘するように、マッカーサーはソ連侵攻時には沖縄から発進させる爆撃機によって原爆4発を朝鮮半島に投下する緊急戦争計画を立案していたことを考慮に入れる必要がある。つまり、マッカーサーが日本再軍備をせずに沖縄と日本駐留米軍によってどのような防衛戦略を構想していたのかということが、マッカーサーの反対の実証的根拠になるのではないだろうか?残念ながら本書ではそういうことには踏み込まれていない。
マッカーサーはその英雄的とも言うべき個人的な資質や性格で語られやすい人物である。ただ、その反面、事態の推移の根拠をマッカーサーの個性にし過ぎるきらいがあるように感じる。本書は、フィリピン時代からの「経験」「人脈」という点に着目し、戦後日本に君臨したマッカーサー像を掘り下げようとしたものであり、アプローチの方向性は大いに共感できる。しかし、掘り下げが側近達の人物像という極めて主観的でミクロな分析になりがちであり、司令官としてのマッカーサーがどのような情報に基づいて、どのように判断し、どこに指示を出したのかという事実関係を俯瞰的に見られていないように感じられた。
本文460頁と新書の中ではかなりボリュームが大きく、これまで日本ではほとんど知られていなかった「バターンボーイズ」とマッカーサーの関係を一次史料を駆使して明らかにしたことは大いに評価できるが、司令官マッカーサーの歴史的な評価という点ではやや物足りない。
Posted by ブクログ
マッカーサーといったら高校の時に習った世界史の本のあの写真、軍用機から降りてくるパイプを持った姿が思い浮かぶ。
あとはGHQの最高司令官だったこと、フィリピンから撤退するときに”I shall return.”と語ったこと、朝鮮戦争時、中国軍に対して原子爆弾を使用するしないでトルーマンと対立して解任されたこと、「老兵は死なず、ただ消え去るのみ」との言葉くらい。
この本には彼の負の部分、PRが巧みだったこと、責任を他人に押しつけることがあったこと、日本軍の軍事力を見くびっており奇襲によって在フィリピンの米軍が甚大な被害を被ったことなどが語られている。
良い点としては、勇敢な将軍であったこと、決断力があったこと、戦時の司令官としての能力はもちろん、平時の行政官としても高い能力を証明した、カリスマ性を持っていたことなど多々ある。
大統領候補への関心が高かったのは意外だった。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
連合国軍最高司令官として日本占領の責任者となり、日本人にとって最も印象深いアメリカ人の一人となったダグラス・マッカーサー。
彼の考え方や行動を探ろうとしても、厚木飛行場に降り立ったとき以降は見ただけでは判明しないことが多い。
本書では、父の代から縁の深いフィリピンとの関係、またコレヒドール島脱出時に同行した側近たちについて、詳しくその足跡を辿りながら、不屈の英雄の全貌を明らかにするものである。
[ 目次 ]
第1章 フィリピンとの邂逅
第2章 バターンボーイズの誕生
第3章 日米開戦前夜からマニラ脱出まで―一九四一年一〇月から同年一二月まで
第4章 マニラ陥落と第一次バターン攻防戦―一九四二年一月初旬から二月初旬まで
第5章 コレヒドール島脱出計画―一九四二年二月初旬から二月下旬まで
第6章 マッカーサー一行のコレヒドール島脱出―一九四二年二月下旬から三月中旬まで
第7章 第二次バターン攻防戦とバターン“死の行進”―一九四二年二月初旬から五月上旬まで
第8章 オーストラリアからフィリピンへ―一九四二年三月から一九四四年一〇月まで
第9章 フィリピンから日本へ―一九四四年一〇月から一九四五年八月まで
第10章 日本の非軍事化・民主化―一九四五年八月から一九四七年一二月まで
第11章 ワシントンの対日政策転換とマッカーサーの抵抗―一九四八年一月から一九五〇年六月まで
第12章 朝鮮戦争とマッカーサー解任―一九五〇年六月から一九五一年四月まで
終章
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
マッカーサーの日本占領時の本はたくさん出ているが、この本が圧倒的に分量を割いているのはその前のフィリピン時代の話。
そこに彼のキーがある。
彼が重用する人間たちもこの時代の「バターン・ボーイズ」が占めることとなる。
尊大で自己顕示欲が強く、インナーサークルを使って物事を動かす彼は敵も多かったが、それでもワシントンが彼を使い続けてのは彼の優秀さにある。
士官学校の成績はいまだに破られてないようだが、単なる軍人ではなく平時の際にも圧倒的な才能を示すことができたのが、彼の強みだった。
そのことが日本の占領を成功させてことは疑いようもない事実だろう。
が、その優秀さと裏腹に彼の欠点というべきものがあり、それが後年、足をすくわれることとなる。
そのあたりも丹念に描かれている好著です。
Posted by ブクログ
“I shall return.” GHQのカリスマ将軍。日本では印象の薄いフィリピン時代に重点を置いた本。
やはりフィリピンの内容が多いので興味薄い内容が多かった。それでも、フィリピンでの苦い体験があったことが、日本占領時代にすくなからず影響を与えているはずだから、こういう日の当て方の本はとても大事だと思う。
____
pⅴ フィリピンは日本の実験台になった
フィリピン統治を担当したマッカーサーはその経験で日本の占領統治をした。だからフィリピン時代からマッカーサーを見ていくことが大事なんだ。
p5 38歳で准将
は当時の最年少記録であった。第一次大戦ではライン川西岸のドイツ占領行政に携わった。
p6 親フィリピン
マッカーサーは1938年からフィリピン方面愚司令官として赴任した。現地人のスカウトと訓練に力を入れた。この部隊がいずれフィリピン防衛のカギを握ると考えていたのである。そのため、現地の有力者と交友を深め、フィリピン人を対等に扱うようにした。
p13 フィリピン防衛の難しさ
海軍中心で飛行機の登場した第一次大戦以降、防衛力不足ある。また、占領下で防衛費は削減され、不足だらけであった。アメリカ中央政府も、日本軍が攻めてきたらフィリピンは墜ちるしかないだろうと予想していた。
p76 フィリピン兵では歯が立たず
訓練された日本兵を前にしてフィリピンの市民兵は逃げ出し、マニラから撤退せざるを得なかった。
マニラを無防備都市にして、コレヒドール島に政府を打つ作戦に出た。その際ケソン大統領を同行させることで、日本軍に大義名分を与えないようにした。
p83 父、アーサー
マッカーサーの父、アーサーは米西戦争で活躍し、フィリピンにもいた。
p88 ヘルメットをしない理由
勇敢を見せびらかすためではなく、兵の士気を鼓舞する一つのパフォーマンス。でも、全く恐れずにそれを続けられる精神はヒロイズムに酔っていたように思える。
p99 最大の決定
「バターンへ撤収したことは、フィリピン防衛戦で、私が行った最も重要な決定であるばかりでなく、そこから生じた影響という点では、全太平洋戦争を通じて私の最も重大な決定の一つだ。」作戦ミスのせい、日本の判断ミスなどで助けられた面もあったようだ。
p110 マッカーサー新聞に利用される
反ルーズヴェルト派の新聞には「ルソンのライオン」とか「太平洋の英雄」とか書かれて利用された。でもそれだけ国内で影響力のある軍人だった。
p114 マッカーサー is baby
補給や援軍を中央に要求するマッカーサーのことをアイゼンハウアーはこう喩えた。しかし、それでも彼に戦わせなくてはいけないのが実情だった。
p119 違法献金
マッカーサー以下参謀長らにケソンから特別報奨金が与えられた。
p145 自称、フィリピンからの信頼
ワシントンからマッカーサーをフィリピンから脱出させる指令が出たことへの返信で、「フィリピン戦線がここまで耐えられたのはフィリピン人が私に全幅の信頼を寄せているからである。もし私が居なくなればフィリピンは危うい。」と打電した。マッカーサーらしい。
p152 閉所恐怖症
マッカーサーは閉所恐怖症らしく、フィリピン脱出の際、潜水艦ではなく魚雷艇のPTボートを選んだ。結果、功を奏したが、ここにも神懸ったものがある。
p165 脱出人数
PTボートでフィリピンを脱出したのはたったの21人だった。各ボート4~8名
p168 脱出か残されるか
脱出メンバーに入れるか否かは生死に直結する、だからマッカーサー周辺は当時微妙な空気になった。しかし、脱出メンバーの情報は事前に漏れ、ドラマがあった。
p172 マッカーサーの銅像
マッカーサーらが出港したコレヒドール島の港湾に記念の銅像がある。
p182 見つかった!?
ミンダナオ海南を航行中に日本の戦艦だか巡洋艦に遭遇、奇跡的に何もなくスルーできた。フィリピンの漁船と間違われたか、マッカーサーの奇跡の一つ。
p225 バターン死の行進
南京大虐殺と並ぶ日本軍の非人道的行為の象徴。当時ワシントンは情報を非公開にした。ヨーロッパ戦線に注力するため、国内世論を対日戦線に傾けたくなかったという予想。
p231 日本軍には捕虜受け入れ態勢がなかった
日本軍では投降するという考え方がなかった。だから8万人もの捕虜を受け入れる準備もなにもなかった。捕虜500人を15人の兵士で連行するという無理難題で、捕虜に蜂起されれば数で圧倒されるかもしれないので、気が気ではなかった。また、日本軍すらも食料などが不十分で、捕虜に回せるほどではなかった。
p241 マッカーサー落胆
フィリピンからオーストラリアに奪取できたマッカーサーだが、オーストラリアの軍隊は北アフリカや中近東戦線に駆り出されており、すぐに反攻に出ることができなかった。オーストラリアから援軍を連れてフィリピンを取り戻すというマッカーサー脱出の大義名分が崩れ大きなショックを受けた。
p277 マッカーサーは死なない
レイテ島に戻った後、日本の飛行機がマッカーサーの寝床を襲ったことがあった。機銃の弾が枕元45センチに着弾したり、味方の迎撃砲の破片が寝室のソファに突き刺さったり。なんで死なないのか!
p308 マンハッタン計画を知らず
原爆プロジェクトのマンハッタン計画はマッカーサーも知らなかった。マッカーサーは原爆投下のニュースを見て「これで日本は降伏する面子が立った。」そういった。
p309 ルーズヴェルトが生きていたら
マッカーサーがGHQ総司令官になれたのも、マッカーサーに猜疑心を抱いていたルーズヴェルトが死んでいたからというのもあるだろう。これまたマッカーサーの奇跡である。
p312 厚木基地に降り立つ苦労
「最初に日本の土を踏む任務を喜べるほど、日本を安全だと思っていなかった。」自暴自棄になった軍人が狂気を犯すかもしれないし、民間人だって恐ろしい。
p314 芸者
日本側がマッカーサー来日の際に芸者を用意するかと尋ねたが、断られた。マッカーサーはそういうたぐいのものを許さなかった。
p328 天皇責任
①日本の統治には天皇を利用した方が効率が良いから天皇を残すために天皇責任は問わない。②ドイツの直接統治から反省して日本は間接統治にする。③日本はアメリカが一人で攻め落としたからドイツのように分割統治はしない。
p330 日本の非武装化
日本は降伏時点で兵力257万が武装化されたままで、軍事力の90%が壊滅してたドイツ軍と勝手が違った。これに対する米軍は二個師団半しか始めはおらず、武装解除は難しく緊張感のあるものだった。援軍がきてからものすごいスピードで行われた。そりゃあ怖いもんな。
p332 戦犯の賄賂
戦犯の逮捕は対敵諜報部CICのソープが担当した。A級戦犯の38名を決定し登場らの逮捕に踏み切った。A級犯が終わると、戦犯認定の拡大を怖れた旧指導者層からの贈り物と招待が殺到した。最終的に108名になったA級戦犯だが、ソープはこれが遡及法の適用だったため疑問を持っていると告白している。
p333 マッカーサーの天皇との会見
二人は通訳を交わして二人きりで会見したが、ジーン夫人とエグバーグ副官は部屋のカーテンに隠れて盗み聞きしていたという。
話は、占領行政の説明やこれからの日本がどうなっていくべきかということがされた。その中で、天皇は戦争責任を回避するよう持ちかけると思われていたが、逆に戦争の全責任を負おうとする態度を示し、マッカーサーを感動させた。
p337 日本は餓死者にあふれているという嘘
戦後間もなく日本の子供たちは栄養失調で赤痢にかかっていた。アメリカ本国で大半がヨーロッパへ運ばれる予定だったスキムミルクを、「日本は餓死者が多数でている」と嘘をついて配給させ、1800万人もの人命を救った。
p350 芦田修正
憲法九条の条文に、芦田均が「前項の目的を達成するために」と挿入した。結果、「日本国民は正義と秩序のを基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない、国の交戦権は、これを認めない。」となった。
条文の追加は「一定の条件のもとに武力は持たない」と解釈でき、自衛のためなら武力をもつことができるようになった。
これに対抗して、第66条第2項に「内閣総理大臣その他国務大臣は、文民でなければならない」と挿入され、軍部の政治への介入を阻止した。
p353 農地解放こそ最大の業績
マッカーサーはそう自負した。戦前の半封建的な地主の土地所有がなくなり農業生産性は向上した。
実は父アーサーもフィリピンで土地改革の実績を残しており、マッカーサーも父に倣って土地政策に力を入れた。
p355 共産主義の防壁にもなった
農地改革は小作人の解放により、共産主義の温床を除去する狙いもあった。
p363 内務省解体
明治に創設されて以来、官庁の官庁として絶大な権力を持った内務省は解体された。(大久保利通が内務省を強くしたんだよね)
始めは集権された力を占領行政に利用したが、そのうち非軍事化・民主主義化を阻害する組織と見られるようになり解体に至った。まず「人権指令」により治安維持法などを廃止し、それを運営した警察関連の高官が罷免され、次に公職追放令で翼賛会関係の主要官僚がパージされた。この後、内務省は管轄を新しい官庁に再編して解体されていった。
p379 逆コース
ワシントン側はマッカーサーのパージは追放者が共産主義側に回る原因になっていると考えた。さらに中国で毛沢東が中華人民共和国を作ったり、極東情勢が思わしくないので、マッカーサーを無視して逆コース(日本の軍備化)に方向転換を決めた。
p394 マッカーサーvsワシントン
マッカーサーは日本占領行政に対して楽観的なところがあって、ワシントン中央政府と意見対立が多かった。ソ連共産主義の影響は薄いと考えていたし、パージも悪影響はないと考えていた。
p406 警察予備隊への二枚舌
マッカーサーは朝鮮での熱戦が現実味を帯びてきて、日本の軍備化の必要性を感じ始めた。しかし、自分が作った平和憲法を早々に覆すような二枚舌はできない。意地と誇りである。そのため、ワシントンからの打電には反論したし、予備隊創設の流れも「マッカーサーが日本に警察の武装強化を許可し、日本が軍備を申し入れる」という形をとった。
日本は当初、本当に警察力の拡大だと思ったが、実際は小規模軍隊レベルの武装で驚かされたのだ。マッカーサーとワシントンの冷戦に巻き込まれ、日本から再軍備したように図られたのである。
p412 朝鮮戦争で機雷除去
朝鮮戦争では日本「特別掃海部隊」として朝鮮海域の機雷撤去の任を務め、活躍した。戦時中に急増された木造船や老朽船ばかりの部隊は計27個の機雷を除去した。その際1隻が触雷して沈没し、一人が死亡した。この業績をアメリカは賞賛し、海上自衛隊の誕生につながった。
p426 中国は来ないと思って
朝鮮戦争に介入した国連軍は順調に北朝鮮を追い詰め中国国境の鴨緑江まで攻め込んだ。ここまで攻めれば戦争は終わると考えていたが、中国の義勇軍が現れ、猛反攻にあう。マッカーサーは日頃から中国は参戦しないと楽観視していた。
この時、中国はソ連に応援を頼んだが、対米直接対決は避けたかったソ連はこれを拒否し、中国と仲が悪くなる。
中国の猛攻を受け、北緯38度線まで後退した国連軍は撤退を余儀なくされ、現在でもいまだ休戦状態である。
p432 マッカーサー解任へ
朝鮮解釈の対立説(朝鮮戦争での失敗)と台湾訪問原因説(1950年にワシントンに事前相談なく台湾の蒋介石を訪問した)
とにかく、マッカーサーは極東統治は自分の責任と思い込みすぎていたのが原因である。
p434 なぜ独裁的だったか
マッカーサーを解任するには極東委員11か国の承認も必要である。ワシントンはそれを得られないだろうから、自分は中央政府から独立していられると過信していた。結局、一人の米陸軍将校でしかなかった。
p436 老兵は死なず、ただ消えゆくのみ
マッカーサーはアメリカに帰国した。サンフランシスコでは50万人以上の慣習が彼を出迎えた。後日、上下両院合同会議の場で、この有名な演説を行った。
同時にトルーマン批判も行い、次期大統領への意欲も見せた。しかし、共和党内大統領候補選でかつての部下アイゼンハウアーに敗れ、その夢はついえた。
p441 忠誠
マッカーサーは「忠誠」を重んじた。それは部下からのものもそうだし、自ら部下へ忠誠を尽くすということも含まれる。
p445 優秀な部下
マッカーサーは強力な統率力を発揮した。しかし、それを実現するには、常に有能で気の利く優秀な部下を必要とした。アイゼンハウアー、サザーランド、ホイットニーの三名がまさに最良の補佐官であった。
信長の秀吉、秀吉の三成みたいな。
p447 マッカーサーは内向的
レセプションで温かく参列者に挨拶するも、愛想よく挨拶はできなかった。食事でも初対面の者と会食するのを嫌い、いつもお気に入りの部下と食事を共にした。
p457 マッカーサーの不運
戦時中は想像しなかった冷戦が戦後に発生したことがマッカーサーを困難に陥れた。冷戦により日本占領行政は流動的になり、ワシントンとの衝突を余儀なくさせた。さまざまな功績も上げたが、最終的に中央と対立した人物になってしまった。
_____
462ページの大容量ですごく疲れた。マッカーサーはものすごい濃度の人生を生きたな。その中に奇跡を幾つも起こしている。常人の精神力じゃあ耐えられないだろう。きっとヒロイズムがあったからこれだけのことを夢中になって完遂できたのだろう。
もう一冊、日本占領行政について詳しい本を読む。こちらも分厚くて大変だ。
読むのよりもこうやってまとめるのがきついね。頑張ろう。