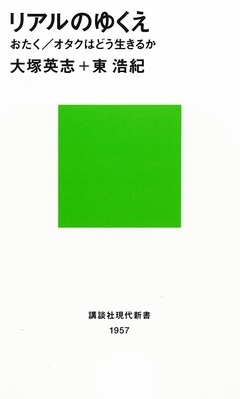感情タグBEST3
Posted by ブクログ
大塚英志と東浩紀の、4度にわたる対談を収録したもの。
二人の議論は、さながら紙媒体出版世代の価値観と、ネット世代の価値観のぶつかり合いが見える。大塚英志は「どうして自分が東の主張に納得いかないか」、ということを追求して説明を求め、東浩紀がそれに冷静な返答をしているため、二つの価値観にどのような違いがあるのか、どのような背景の上にそれらの価値観が成り立っているのかが、よく見えるようになっている。
紙の出版物に触れて育ちながら、ネット世代としても生きる自分が、どちらかに(というか両方に)対して感じていた違和感の原因を探る手掛かりになったと思う。
Posted by ブクログ
東浩紀氏の「動物化するポストモダン」、「ゲーム的リアリズムの誕生」を読んだ上でさらにコンテンツの本質に近づきたくて購入。本書は、東氏が「動物化〜」や「ゲーム的〜」の論の元として挙げる大塚英志氏との対談。今までで最も読みやすい一冊だった。その理由は、渡井が東氏のこれまでの著書やメディア・Twitterでの発信を自分なりに整理しかけた上で開いたこともあるが、本書の対談形式が大きい。大塚氏が執拗にツッコミ→東氏が応戦、という図が自然に論を左右に振ることで読者に分かりやすく読ませている。私は、2人の主張のポイントや違いがかなりクリアになり、これまでの東氏の著書の解説本のような感じで読めた。2人の対談はスタンスの違いが興味深い。大塚氏はとにかく東氏に議論をしかけ、自分のフレームワークに当てはめようとし、さらに東氏の論を昇華させようとしている風に見える。対して東氏は、大塚氏と積極的に議論する気はない。自分の論を発信し、それに対して批判する大塚氏に応戦しているようだ。大塚氏の主張の傾向の印象は、主体的な権力、公的、そもそもの議論をしたい、批評家としての責任感。東氏の傾向の印象はシステム的な権力、今そこにある具体的で個人に関わりの深い問題、気負いすぎずに自分がどうするか。2人の対談は回を増すごとにヒートアップし、全4回の3回目は特に大塚氏の攻撃が激しく、東氏も「人格攻撃では」と不快感を露にしている。だが、全体を通してみて、大塚氏はあえてそういう議論を仕掛け、そうすることでしかお互いの進化はないと考えているかのようだ。東氏も、それを受け止めつつも自分のスタンスを貫いているかのようだ。大塚氏は、世代を代表して議論をしかけているのかもしれない。初めから東氏寄りで読み始めた私も、大塚氏が仕掛ける論戦を通してより東氏の主張や、本質について理解を深めることができた気がする。引用箇所も多く濃厚で読んで良かった一冊。
Posted by ブクログ
対談の起し本だが、大塚氏と東氏とのやりとりの臨場感が、ものすごい迫力を持って感じられ、引き込まれるように読んだ。
サブタイトルの「おたく/オタクはどう生きるか」の「おたく」と「オタク」は、大塚氏と東氏の暗喩であろうか。
両氏の差異が鮮明に現れるのは、書き手(知識人)として、公共性というものに対してにどう向き合っているか、という点であり、大塚氏が自身の文章や発言が公共に対して影響を与えることに自覚的である種の責任を追うべきと考えるのに対して、東氏は公共に対する影響は認めつつもそのような責任は追いきれるものではないとする。
公共に対する東氏の考えは自分自身の感覚としても理解できるが、最後のところで明快なことばに翻訳しきれていないようなもどかしさがある。一方大塚氏の公共に対するある種の責任感は、自分の職業柄いつも考えていることであり納得できるのだが、そこから逆に、ひとりの人間が出来ることの無力さみたいなものが照射されて感じられてしまう。
しかしながら、両氏が「リアル」というものに向き合っていることは紛う事無き事実であって、読み手に何かが届くだけの「リアル」がこの本にはある。大塚氏がこの本に付記するつもりであった注釈とあとがきを、校正の最後に削除したのは、この対談のリアルなやりとりをそのまま読者にぶつけたかったのだろう。氏のその意図は、見事に当たっている、と思う。
Posted by ブクログ
大塚英志と東浩紀が、四回にわたっておこなった対談の記録です。第一回は2001年、第二回は2002年で、東が『動物化するポストモダン』(講談社現代新書)の頃の東が、『物語消費論』の大塚英志と、サブカルチャー批評について議論を交わしています。
第三回は2007年で、今度は東が『ゲーム的リアリズムの誕生』(講談社現代新書)を刊行した後の対談です。そして2008年におこなわれた第四回は、秋葉原連続殺傷事件の直後の対談になっています。
対談を通して、大塚は愚直なほどにおなじ問いかけを東に向けています。彼が問うているのは、「公」のことばをもう一度立ちあげなければならないという義務感であり、そうしたことばを語る批評家や作家の登場への期待であり、さらに批評家はそのようなことばを読者へ向けて語りかけなければならないという倫理だといえるように思います。こうした大塚の問いかけに対して、東は一貫して、批評家のことばがもつ力に対する諦念を表明しています。
大塚の主張するような公共性の再建が可能だとは思えないのですが、それ以上に気になるのは、時代状況の変化によって、東のおなじことばが異なるニュアンスで受けとられてしまうのではないかということです。たとえば2001年、2002年の対談での東の立場は、言論の無限の可能性を素朴に信じるのではなく、新しいオタクの消費行動を前提にしなければならないというところへ収斂するのではないかという気がします。しかし2007年、2008年の対談では、東のおなじようなスタンスを語ることばが、アーキテクチャ原理主義のように響いてしまうのも事実ではないかと思います。
両者の対話が噛みあっているということは、まったくといっていいほどないのですが、大塚のいい意味での「いやらしさ」が出ているという点でも、おもしろく読みました。すくなくとも、おなじく話が噛みあっていない、東と笠井潔の往復書簡よりずっと刺激的だったように思います。
Posted by ブクログ
対談集なので構造的な話題ではないが、示唆に富んでいた。
対話だからこその、わかりやすさもあった。
情報があふれて、動物化するというイメージがわかりやすい。
また、創作が、他者の知識に依存するというはなし(昔からそうだろうけど)も、面白かった。
物語が無価値化していく、しかし私はそこに抗いたい。
ただ、世代間のラベル付けのような形式になっているところは、あまりに乱暴な気がして感情移入できなかった
Posted by ブクログ
東浩紀が大塚英志に絡まれ続ける対談集。もの凄く息苦しくなるのは,過去に大塚英志にダメ出しされた経験故だろうか(爆)東浩紀の忍耐力には感服します。いたたまれない気分を殺して読み進めると,第3章あたりでモダンを信じる大塚英志とポストモダンを堅持する東浩紀の対比がぱっと頭に浮かんで来て,ああ,対話って重要だねと思った。どっちの言うことも分かると思ってしまう自分はどこに居るのか?ポストモダンとモダンの対話からポスト・ポストモダンを考えさせられる。
Posted by ブクログ
為政が見えにくくシステム化していく社会にあってなおも為政する側の主体の存在を疑い、また、社会に関わるための「主体のあるべき」を議論しようという大塚氏と、まずは主体を切り離した中から見えてくる世界像を考察しようという東氏の、立脚点の差異に最初から最後まで互いが歩み寄らず、話が噛み合わない。が、現在の社会の状況についての洞察には両者ともに肯けるところが多く、両者ともに基本的に相手の考察を認め合っているので、「その噛み合わないところはいいから話を進めてくれ」と思うことはあっても、対談そのものが破綻しているというわけではない。どちらのとらえ方をするのかで、どちらがどういうものが見えてきて、どういうものが見えにくくなるのか、そんなことを考えてみる刺激には満ちている。それぞれの著作を何も知らずいきなりこれを読んでも、何を議論しているかよくわからないかも。
Posted by ブクログ
2019.9.9
今更ながら読むが、現在でも有用な話なんじゃないかしら。僕自身が会社勤めをしつつも社会から隔絶して生きているので(消費者としては繋がっているが)、この10年の両氏の仕事ぶりなどはわからないが、十年前の現実も現状とさほど変わりない。むしろ体感としては問題は尖鋭化してるんじゃないのかなー。
2人の会話が噛み合わないのはお互い倫理について話ているからだろう。
Posted by ブクログ
「物語消費論」の大塚英志と「データベース消費論」の東浩紀の対談本。
あくまでそういう軸というか立場でしかとらえてなかったので、思ってた以上に議論が深いところというか政治とか概念にまで広がってて、正直自分にとっては難解でした。
世代が近い(あくまで相対的に)ということもあってか、
個人的には大塚さんよりは東さんの言説(というか話であったり口調)の方が分かりやすい。
なぜあんなに大塚さんは苛立ってたんですかね・・・
あとがきや注を削除する要請をしたというのも気になるところ。
Posted by ブクログ
二つの観点を前提にしなければならない。一つはインターネットに象徴される情報コミュニケーションの革命的変異が一気に進んでいると言うこと。2つめは情報交通政治思想のグローバル化により価値観が急速に陳腐化しつつあると言うこと。
2つの前提が成立する以前ならば、ある哲学者・知識人の言説や芸術家の独創性は長い間独創性として維持されてきた。しかし、2つの前提が成立すると、独創性は即時的広範囲に模倣され、アレンジされて記号化されることになった。そして一般的には今日生産される差異はひとつひとつが記号化されデータベースに積み上げられてく。
この状況下で批評家の為す役割というのは変異するか、しぼんでいくかのどちらかに陥る傾向が強くなった。なぜなら、批評家は例えば理想と現実の差異を分析し、その性質を論じ、方向性について読者や社会に啓蒙する働きを期待されるからである。さらに、これまでは応える余地があった。しかし、それは差異がいつまでも差異として存在し、かつ正体不明の扱いにくいものとして維持し続ける環境あってこその批評であった。
2つの前提が成立すると、批評家のその役割は縮小し、0に向かって限りなく収束することになる。ここにおいて著者の2人のスタンスは異なる。それでも社会に啓蒙する役割の可能性を信じる大塚と可能性を信じない東とである。
2つの前提がこれから一層その傾向を強めたときに、批評家の飯の種である差異は一般的な存在から個人的なレベルのに落ちる。つまり差異は個人的なものにしか存在し得ないと言うことである。はたしてそのときに極めて個人的な差異を論評する価値や意味があるのだろうかという疑い。また仮に一般的・社会的に評価・共感しうる差異を発見し得たとしても、すぐにその差異は記号化され、批評家の叫びとは無関係に修正・アレンジされていく。いわば、記号のデータベースというカタログに載らない差異が差異といしての価値を持つが、価値を持った瞬間それはカタログに載せられ、その価値の所以であった「カタログに載ってない」価値は消失するのである。
そしてこの差異の消費活動は促進され、スピードを増し、批評家の出番はなくなる。批評家に残された仕事の可能性と言えば、新たなる価値(差異)の予言であるが、そこまでいくと批評家と創作者の区別はなくなるのである。
ネットによる差異のデータベースとアレンジゲームはまだ始まったばかりでかつその進歩と共に構造までも変えていく。それはカオス的に見れば、構造変異が表出するまで継続するのであろうが、それがいつになるかは誰も予見し得ない。
Posted by ブクログ
若い人がレビューであげてるとおり、私自身は主張として東さんが言ってることにしっくりくることが多かった。最初の方の議論は読んでて面白かった。若い人は物語に耐えられないっていう話とか。でも2007年のなんか特に頭がいい人の喧嘩を見ているようで、根底諦めている東さんになぜと突っかかる大塚さん、ずっと平行線でつまらなかった。
Posted by ブクログ
大塚さんにも東さんにも共感できる点はあるけど、俺たち現在20代前後の世代の感覚って、やはり時代感、絶望感として東さん、そこから大塚英志的な文壇左翼になるのか、想像力が足りないネトウヨ的な行動を示すのかに分かれると思う。自分は前者寄りかな
Posted by ブクログ
大塚英志と東浩紀の対談本。章の間に長い月日が経っている所がある。そのなかに2人の関係の変化が少なからずある。あとがきにも書いある。コミュニケーションの可能性については僕はどちらかといえば大塚さん寄りで、他人との関わり合いに肯定的なところがある。
Posted by ブクログ
息苦しくもどかしいすれ違いに終始する対談は結局オタクというものの分析と扱いを世代の立場を超えて共有することすらの難しさを浮き彫りにする。たった二人の間ですらせせこましく対立するくらいならそんな後追い批評なんかやめればいいのにと身も蓋もないことを思ったりするのは、結局僕自身が分析される側として奔放に無反省に消費行動に身を委ねることをよしとしているからなのかもしれない。批評なんて所詮本能より先回りはできないのだから。
Posted by ブクログ
東浩紀の特徴の一つとして「諦め」というものがあって(確か本人自身口にしていたように思う)彼のそういう部分に対して大塚英志は苛つきを見せているんだろうというのが伺える。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
「知識人」は希望を語れるか。
「世代間闘争」の末に見えた地平は?
いまの日本は近代か、それともポストモダンか?
サブカルチャーの諸問題から国家論まで、「わかりあう」つもりのない二人が語り尽くす。
[ 目次 ]
はじめに 世代間闘争について
第1章 二〇〇一年-消費の変容(なぜ物語に耐えられないのか 見えない権力システム ほか)
第2章 二〇〇二年-言論の変容(雑誌は誰でも作れる 論壇誌でいかに語るか ほか)
第3章 二〇〇七年-おたく/オタクは公的になれるか(メタ化するか、空気を読むか 啓蒙か、ガス抜きか ほか)
終章 二〇〇八年-秋葉原事件のあとで(同時代の事件に責任を持つ 彼らは何に怒っているか ほか)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
二人の喧嘩を「オタク第一世代」と「オタク第三世代」の世代差、と捉える向きもあるが、果たしてそうなんだろうか。
ちょうど『集中講義!アメリカ現代思想―リベラリズムの冒険』を読んだあとだったので、大塚英志氏の意見の方に共感できた。
大塚氏の東氏への苛立ちによって延々と議論が長引くのだが、その苛立ちは理解できる。
「若手の旗手」として衝撃的なデビューを飾った東氏だが、もう年齢的には「若手」とは呼べなくない。大塚氏の苛立ちはひとえに、その「失われた時間」に対するものであろう。
30歳(2001年当時)というのは批評家としては若い部類ではあるが、宮崎勤事件が起きたときの大塚氏も30前後である。覚悟を決めようと思えば決められる年齢だとも言える。
に対して、東氏がときおり口にする「人格批判」という虚弱なセリフはいかがなものかと思ってしまった。こういう人ってオタクによくいるよね、と。一緒に仕事をしたくないタイプの発言である。
もっと言えば、この感じ、このセリフがゼロ年代の日本のどうしようもなさを象徴してる気もするのである。時間はいっぱいあったのに変える努力をしなかった、だから変わらなかったよね、という気が、今から読み返すとしてしまう。
しかし、2008年の「加藤の乱」を転換点として東氏にも変化が見られ、希望の持てるラストとなっている。これで最近の東氏の仕事を読めるなあ、と胸をなでおろした。
Posted by ブクログ
予備知識がちょいちょい必要で分からなくなる所もありました。ポストモダン社会の中で多様化していく人々がどう生きていくかを議論していました。途中で議論ではなく口論みたいな方向に進んで大変なことになっています。だから他の新書と比べて分厚い(笑)
Posted by ブクログ
2人が繰り返す禅問答は両者の過去の著書の吐露にすぎないが、当時のポジションを再確認する意味では重要か。
そして大塚の苛立ちが引き起こす堂々巡りは退屈だけど、噛み合わない議論はスリリング。