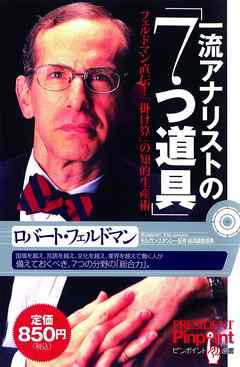感情タグBEST3
Posted by ブクログ
テレビ東京のワールド・ビジネス・サテライト“WBS”で御馴染、蝶ネクタイのロバート・アラン・フェルドマン博士の一冊です。
テレビと同様、簡単な単語と言い回しによってアナリストに必要な姿勢が綴られています。
しかし、アナリストとは関係のない素人にとっても有益なものが多いと感じました。
Posted by ブクログ
分析して人に伝える
どの仕事でも必要な能力について7つの側面に分けてポイントをのせています
知的生産術に関しての本はたくさんあるけれど、この人はプロ中のピロなんでしょうか、書いてあることは今まで読んだ本とは少し違っていました。少し難しいけれどより具体的でした。
ハウツーではなく思考過程を指南した本だと思います。
Posted by ブクログ
WBSへの出演でおなじみの米国人エコノミストによるコラム集。以前より、当人について感心があったことから手に取った。関心はやはり、WBSにおけるあの日本語能力とわかりやすい解説である。エール大、MITで経済学を学び、IMFやソロモンブラザーズなどでキャリアを築いたというだけあって、そもそも頭脳明晰であろうが、それだけで彼を語るのであればあまりにも一面的であろう。書中では、スケジュール管理をどう行うかといった、日常的な話題からビジネスマンとしての心構えや、人生についてといった哲学までが、明快かつ簡潔に述べられている。やはり、フェルドマンの最大の魅力は、本来こ難しいことに関しても、極めて分かりやすく、しかしながら手を抜いた感じは全くしない、表現であろう。書中にも触れられていたが、他人とのコミュニケーションにおいて、彼自身が重視し実践しているのが、いかに簡潔に物事を伝えるかということだそうだ。
本書は、ページ数も少なく、行間も広いため、実際にはもう少し薄い装丁で出版されてもいい位の分量であるが、内容的には非常に濃く、読んで良かったと思える本である。
Posted by ブクログ
当たり前のことを当たり前のようにやれることのいかに難しいことか。
そして当たり前のことたちをつなぎ合わせていって、当たり前じゃないところにたどり着く者になりたいと思わされる。
手段を手段として縦横無尽に使いこなせるかが鍵。
Posted by ブクログ
アナリストの採用基準を「分析力」「プレゼン力」「人間力」「数字力」「エネルギー管理力」「言語力」「商売力」の7つのスキルにわけて解説した本。
どれか1つのスキルだけが重要というわけではなく、複合効果で決まってくる。つまり、弱いスキルが1つあると、他のスキルがいくら高くても、全体として0になるという、掛け算で能力を判断される。と解いている。これからのビジネスマンも段々とこのような能力を求められてくるのではないかと思った。
印象に残った言葉
欧米では、情報と情報をつないで、そこに新たな意味を見いだせる人が専門家として認められる。
人前で話す際に忘れていけないことは「舞台になっている」という自覚です。話すことは演技です。コツは「ゆっくる話す」ことです。
会話の底流を掴む。L1:事実についてのやり取り。L2:起きた事実に対する自分の思いと相手の思い。L3:品位や自分のアイデンティティに関わる問題。
交渉の前にBANTAを考えておく。交渉の家庭では「水をもって火を制す」
数字力を身に付けることは「数字を怖がないこと」が大切
アメリカには「数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う」という格言がある
「人の幸せは人生を面倒くさいと思うか、冒険と思うかによって決まる。面倒くさいと思ったら幸せにはなれない。冒険だと思えば幸せだ」
Posted by ブクログ
アナリストという職業は、冷静に客観的に物事を分析し、人に伝える職業である。
本書は、①分析力 ②プレゼン力(分析した内容を人に伝える)③説得力(伝えたことを人に納得させる)という大きく3つのパートより構成。
①分析力=仮説力であり、「混沌(情報)から(見えていなかった)意味を引き出す」という情報のつなぎ方が重要である。
◇分析力が求められる背景
文化的背景の違いは人が物事を捉える際の着眼点に影響を与える。
→この背景の違いを乗り越えて、人を納得させる為にも的確な分析力が求められる。
◇分析力の4分類
・ジャーナリズム
・理論
・計量分析
・テクニカル分析
であり、事実、モデル、物語、数字の4ファクターの組み合わせにより分類される。
*現在、自分がどのスタイルで物事を観察、分析しているかを考えることが重要。
②プレゼン力
目的を明確にする=何の為に、誰に向けて、何を伝えるのか?
グラフ、表、孫子の兵法(道、天、地、将、法)をマトリックスにするなど、ビジュアルに働きかけることも有効。
③説得力
人を納得されるには、意見が対立する理由を理解することが重要。
・情報の違い(統一が必要)
・解釈の違い(ベースとなる解釈の共有)
・損得の違い
⇒詳細は、「ハーバード流交渉術」
○補足
人間力 : 軸は、 「協調性」×「能力」
数字力 : 数字はウソをつかないが、ウソつきは数字を使う。
時間管理力 : どこまでやるかは、自分で決める。
中長期的スケジュールを立てる。
Posted by ブクログ
WBSへの出演でおなじみの米国人エコノミストによるコラム集。以前より、当人について感心があったことから手に取った。関心はやはり、WBSにおけるあの日本語能力とわかりやすい解説である。エール大、MITで経済学を学び、IMFやソロモンブラザーズなどでキャリアを築いたというだけあって、そもそも頭脳明晰であろうが、それだけで彼を語るのであればあまりにも一面的であろう。書中では、スケジュール管理をどう行うかといった、日常的な話題からビジネスマンとしての心構えや、人生についてといった哲学までが、明快かつ簡潔に述べられている。やはり、フェルドマンの最大の魅力は、本来こ難しいことに関しても、極めて分かりやすく、しかしながら手を抜いた感じは全くしない、表現であろう。書中にも触れられていたが、他人とのコミュニケーションにおいて、彼自身が重視し実践しているのが、いかに簡潔に物事を伝えるかということだそうだ。本書は、ページ数も少なく、行間も広いため、実際にはもう少し薄い装丁で出版されてもいい位の分量であるが、内容的には非常に濃く、読んで良かったと思える本である。
Posted by ブクログ
WBSにておなじみのフェルドマン氏の著作。フェルドマン氏のコメントはいつも的確かつ納得のものなので、書名買いしてみた。内容については、著者が言うように、平易な表現ではあるけれども、分析視点とそれを伝えあい高めあうために必要となる素養についてまとめられている。別にアナリストを目指していなくても基本的なビジネスマンとして具備すべき素養として捉えればよいのではないか。誰もがいくらでも情報を収集できる現在では、それを分析・取捨選択し、整理することが基本素養になっている。また、自身の整理した仮説を検証する、議論してブラッシュアップしていく(共感の輪を拡げて行く)ことに付加価値があると感じているので、重要な意見だと思う。それにしても、議論するのを嫌がる(面倒くさいと思う)人が本当に多い世の中になったなあと思う。各人が自身の仮説をしっかり整理したうえで行う議論であれば身がある議論になるのだが、そのあたりが浅くなるのは、みんな物事を考えるのが面倒だと思うからなのだろうか・・・?
Posted by ブクログ
プロデューサはアナリスト的な視点も必要かと思い読みました。とてもロジカルな例が多いので読みやすい。ロバート・アラン フェルドマンの顔を知っていたので読んでみましたが、想像通りの内容で勉強になった。
Posted by ブクログ
《要旨》
アナリストとしての能力は7つのスキルの複合効果で決まってくる。だからこそ、どれか一つのスキルだけ特に大事ということはない。
1つ目は分析力。情報と情報をつなぐ線を引き、絵を描く。そうすることで混沌とした情報の中から今まで見えていなかったものを引き出す。それが「分析」の真髄。
2つ目はプレゼン力。最初に目的を決めることが大事。また「自分と会話」するとよい。
3つめは人間力。会話力、交渉力、人観力に大別される。会話では「事実」「その裏にある思い」「品位やアイデンティティ」などがゴチャゴチャだと噛み合わなくなる。交渉には「情報の違い」「解釈の違い」「損得の違い」に注意するとよい。また人を見極めるには、仕事では協調性と能力を見るようにしている。
4つ目は数字力。数字はわかりやすいこと、客観性があることに利点がある。それだけに「数字の精度の虚偽」には注意したほうがよい。
5つ目は時間・エネルギーの管理力。時間管理はコツではなく「人生計画」の問題だと思っている。健康も重要であり、自分の「数値」を知っておいたほうがよい。
6つ目は言語力。大おじ名ポイントは「楽しく勉強する」こと。
7つ目は商売力。顧客に目を向け、顧客が買っているものの本質を見極めることが重要。また、自分のブランドを確立することも重要である。
《印象に残ったコトバ》
アナリストの能力は「足し算」ではなく「掛け算」で決まります。(略)この違いは、スキルの磨き方にも大きく影響します。スキルが足し算関係にあるなら得意科目を強化した方が得策で、掛け算関係なら逆に苦手科目を強化することが得策になります。
《感想》
アナリストの成分表示が分かって面白かった。改めて、再発見する事項もあり良かった。
《目次》
1.混沌から意味を引き出す「分析力」
2.逆算して組み立てる「プレゼン力」
3.意見の違いを乗り越える「人間力」
4.下品になってはいけない「数字力」
5.見落としがちな「時間・エネルギー管理力」
6.“ハブ性”で勝負する「言語力」
7.自分ブランドで差別化する「商売力」
Posted by ブクログ
WBSでお馴染みのフェルドマンの本。
アナリストとして必要な7つの能力について書いています。
?分析力、?プレゼン力、?人間力、?数字力、?エネルギー管理力、?言語力、?商売力
面白かったところ
?分析力
分析のスタイルを、横軸(物語・数字)と縦軸(事実・モデル)に分けていた点で状況に応じて使いわける必要があること。
?人間力
・意見が対立する3つの原因
1.情報の違い、2.解釈の違い、3.損得の違い
・フィッシャーの交渉の4つの基本原則
1.人と問題をわける、2.姿勢より利益、3.双方の利益となる選択肢、4.進捗は測定可能な基準で評価
?エネルギー管理力
・中長期的なスケジュール管理について1枚のペーパーにリストアップ
・日々のスケジュールはやるべきこと・優先ランク・所要時間で管理
?商売力
信頼の方程式
T=E+R+I/S
T:信頼、E:専門性、R:約束を守る、I:親密性、S:私欲
ポイント、ポイントで為になる本でした。
Posted by ブクログ
■ビジネス色々
?欧米では専門家を、情報と情報をつないでそこに新たな意味を見出せる人。
?人前で話す際に忘れてはいけないことは「舞台に立っている。」というじかくです。意識をしてゆっくりと話す。低い声で話す。
?どんな業種においても時間管理と健康管理は仕事のうち。
Posted by ブクログ
アナリストであるために必要な能力とは、に関する本。とはいえ、一般的に働くにあたって必要となるものであることが多く、アナリストとしてでなくとも役に立ちそう。
一つ一つ大したことではないが、どうあるべきかという点が簡潔に書かれているので、非常に分かりやすい。すぐに行動出来そうな内容。足りない能力ばかりなのでもっともっと頑張らねば。
個人的には、もう少し専門的な話が読みたかったので満足感は低め。
Posted by ブクログ
書かれていることは目新しいものではない。自身でも意識して実施していることも書かれている。当たり前のことを当たり前に実践出来ることが一流への道なのだろう。彼がどうして日本に関心を抱く様になったのかが気になる。
Posted by ブクログ
アナリストの能力は掛け算で表わされる。すなわち、どんなに一つの能力が英でていても何らかの苦手がある人は使えない、とフェルドマン(モルガンスタンレー証券アナリスト)は語る。
相当に頭の切れる方のようで、次元が違うとすら感じた。でも今後そのような人々と一緒に仕事をしたり、競争していかなければならない事態も大いに考えられるので、精進して勉学や社会勉強に励みたい。この一冊で世界トップクラスの頭脳にほんの少し触れることができた気がする。
そういえば、先週参加した説明会では、モルガンスタンレーの社員が最も楽しそうに説明していたな…(備忘録)
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
情報が溢れ、すごいスピードで世界が動いているいまの時代。
アナリスト的なスキルは、どんな仕事にも共通して必要になっている。
日本経済・世界経済の未来を見通す「蝶ネクタイの賢人」が、経験に裏打ちされた情報の「つなぎ方、見せ方、伝え方」を伝授。
[ 目次 ]
序章 アナリストほど掛け算が大事な仕事はない
第1章 混沌から意味を引き出す「分析力」
第2章 逆算して組み立てる「プレゼン力」
第3章 意見の違いを乗り越える「人間力」
第4章 下品になってはいけない「数字力」
第5章 見落としがちな「時間・エネルギー管理力」
第6章 “ハブ性”で勝負する「言語力」
第7章 自分ブランドで差別化する「商売力」
付録 「私が読んできた本」「支えにしてきた言葉」
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
ワールドビジネスサテライトでおなじみのロバート・アラン フェルドマンの本
アナリストの視点で書かれてはいたが内容はあまり満足できるものではなかった。
参考になったところは
「分析スタイルの四分類」
アナリストは大抵、テクニカル分析、計量分析、ジャーナリズム、理論の4つの分析手法を用いるが
TPOに応じて組み合わせたりして使いましょうということ。
「信頼の方程式」
これはフェルドマンが考えたことではないが
T=E+R+I/S Tは信頼 Eは専門性 Rは約束を守ること Iは親密性 Sは私欲、利己心
分母のSが大きいと導かれる信頼度は低くなる。
おもしろいのは、私欲は極限までなくして0になると信頼も0になる。
尽くしすぎはよくないってことだね。
Posted by ブクログ
◆モルガン・スタンレー證券経済調査部長でありアナリスト採用をしている著者が重視している採用基準を「7つのスキル」に分けて説明している。
◇アナリストの能力は「足し算」ではなく「掛け算」で決まります。足し算ならひとつがゼロでも他のスキルのレベルが高ければ補うことができますが、掛け算ではひとつがゼロなら、他がいくら高くても、全体ではゼロになってしまいます。
◇第1のスキル「分析力」
・情報は「量」ではなく「つなぎ方」。欧米では「情報と情報をつないで、そこに新たな意味を見出せる人」が専門家として認めらます。
・意外な結論を説得力のあるかたちで提示するには、物語性と、その物語を裏付ける数字の数字のコンビネーションが効果的です。
・情報と情報をつなぐ線を引き、絵を描く。そうすることで混沌とした情報の中から今まで見えていなかったものを引き出す。それが「分析」の神髄です。
◇第2のスキル「プレゼン力」
・人に何かを伝えるには、最初に目的を決めることが大事です。何のために、誰に向けて、何を伝えようとしているのか。そこから逆算することで、プレゼンの方法が決まります。
・簡潔でわかりやすい文章を書くためのルール
?要らない言葉を省く
?二重否定を使わない
?文章は単純な構造に
?能動態を使う
?強調したい言葉を文章の最後に持ってくる
◇第3のスキル「人間力」
・多様な相手とともに仕事をする能力。
・人間力は大きく3つに分けられます。1つ目は会話力、2つ目は交渉力、3つ目は人観力(人を見る力)。
◇第4のスキル「数学力」
・企業や公的機関の出してくる数字は、時に批判から逃れることを目的として操作され、結果として実態とかけ離れたものになっている場合があります。
・わざとわからない数式を使って、ごまかしているのではないか」と感じたら、「こちらにわかる言葉で説明してくれ」と要求しなくてはなりません。
◇第5のスキル「エネルギー管理力」
・健康管理、時間管理、空間管理を効果的に行う能力。
・面白がってやっているうちはいいのですが、会社から「あれをやれ、これをやれ」と言われるがままにどんどん仕事を増やしていくといつの間にか滅私奉公状態になってしまう。「どこまでやるかは自分で決めなさい」
・「時間管理のコツは問題ではありません。『人生計画』の問題です」まず人生の大きな目標があり、その目標から逆算して時間の配分を考えていく。
◇第6のスキル「言語力」
・外国語は10年先、20年先を考えると一段と重要性が増してきます。とくに英語は、インドや中国の人と話すためにも必要です。
◇第7のスキル「商売力」
・農業はこれからの日本で伸びる産業です。政治的な改革が進めば、日本は北半球のニュージーランドになれるでしょう。