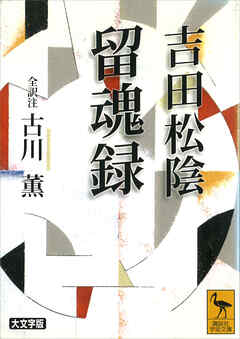感情タグBEST3
Posted by ブクログ
吉田松陰
処刑前日に書き終えた遺書「留魂録」
身はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬとも
留め置かまし 大和魂
無念のうちに散ったの思える松陰も
留魂録の中ではこう言っている。
人それぞれの人生には四季がある。
10代で死ぬ者も、その人生の中には四季があると。自分の29年という人生も、実は身を結んでいるのだと。
年数ではなく、その与えられた人生を如何に生きたかにこそ価値があると。
吉田松陰が教育者として当時の中で一線を画していたのは、
身分制度を越えた横の関係で、塾生と繋がっていたことだろう。
身分に関係なく師と生徒が互いに学び合う。
身分制度の束縛が強すぎると藩に松陰が提言したほどの封建制の社会。
西欧の民主主義の概念を吉田松陰が知る前に、既に藩主に提言していたのだから、元からして近代的な思想を持っていたと言える。
横目でアヘン戦争によってズタズタにされているあの大国である清の惨状を見れば、ペリー来航による危機意識をもつのも当然のことと思える。
松陰神社に静かに佇む、松陰の墓を目の前に、
松陰の影響は小さくはなかったと、想いにふけった。
Posted by ブクログ
吉田松陰が死の前日に書いた遺書であり、自らの魂を受け継がせる塾生に宛てた手紙である。
留魂録を読み、死ぬこととはどういうことか、その日まで自分の命をどう使うか、その死生観を考えさせられ、30歳の若者が死の前日にここまで落ち着いた文章で、自分の人生を総括できるものなのかと驚嘆する。
松陰の死生観と至誠をもっと学んでみたい。
Posted by ブクログ
全訳されているため、意味は現代語で理解できる
自身の誠を持って話せばわかってくれると
最後まで信じていた吉田松陰が死を前に
門下生を焚きつけた文章。
→間部詮勝暗殺計画を自ら口走ってしまった
人には何歳で人生が終わるとしても四季がある
→その中でどんな実を結び、次の種をつくるのか
飛耳長目、外に目を向けることに重きを置いていた
Posted by ブクログ
吉田松陰の残した言葉そのものを知りたく読んでみました。
留魂録は松陰が処刑される前日に書きあげられたもので、松下村塾で共に学んだ弟子に対しての最後のメッセージがかかれています。人間は10歳には10歳の、30歳には30歳の、70歳には70歳のそれぞれの人生の四季があるという死生観は印象的でした。「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留置まし大和魂」という留魂録冒頭の句には、松陰の死に対する覚悟と、攘夷を未来に託す志が表れていると思います。
吉田松陰かっこいい~
Posted by ブクログ
「留魂録」は、幕末の長州藩において、維新回天の原動力となった志士を幾人も育てた吉田松陰の遺書です。この訳は大変読みやすく、後半は松陰史伝も載っているのでオススメです。
中身は門下生に宛てた後事を託す内容になっています。刑死するに至る顛末のほか、死前の獄中生活において出会った有志の士の紹介、そして死に臨んでの松陰の辿り着いた人生というものの境地などがまさにありのままに書かれています。
全編松陰の思いが刻み込まれていて感慨深いものがありましたが、特に深く感銘を覚える箇所がありました。その一つが有名な「人生の四季」を述べるところです。
「四季について」は、「どんなことをしようとも、人は生まれてから死ぬまでに種を撒き、苗を植え、育て、収穫し、蓄えているものである」という松陰の人生論です。結果として、人生が大義をなすかどうかは、四季を過ごす自分次第、また、それを受け止める周囲次第なのだと思いました。後者は自分が決めることではないから、自分にできることは他人に左右されることなく、"四季"を「自分の意志で生きること」だと思いました。
松陰は30歳で自身の四季を閉じます。史伝や解説を読むと、そこに無念という思いが皆無だったとは私には思えないのですが、最終的には「生ききった」という思いもあったのではないかと思います。
そして、その後、松陰の教えを受けた門下生たちは維新を成し遂げ、新しい国造りをし、日本の危機を救いました。それぞれの先人の考え、行動において、自分のいまの仕事や行動に考えるべき部分がないか、今一度振り返ってみようと思わせてくれた本です。今後も手元に置いて、迷ったときには開きたいと思っています。
「愚かなる吾れをも友とめづ人はわかとも友とめでよ人々。」留魂録末尾の五句のうちでもっとも好きな句です。
Posted by ブクログ
まず疑問に思ったこと。留魂録は果たして遺書か?それとも遺言か?どちらでとらえるかで、松陰の伝えたかったメッセージの意味が違って見えてくる。著者は遺書ととらえている。死生観を綴っているところは特にその印象が強い。しかし私はこれを遺言ととらえた。なぜなら、松下村塾の門下生はその意思を受け継いだからだ。松陰の攘夷論、教育観、人生観には非常に感銘を受ける。しかし、伝えるのは「生きること」と「教育」の2つであってほしかった。討幕や暗殺といった過激な思想まで伝え、そして自ら大獄に死してしまったがために、死が美化され、門下生の大半も死に至り、代わりに「維新=暗殺」という観念だけが、昭和初期まで生き残ってしまった。そんな気がしてならない。
Posted by ブクログ
『身はたとひ 武蔵の野辺に朽ぬとも 留置まし大和魂』
この歌から始まる「留魂録」は、吉田松陰が江戸小伝馬上町の牢内で書き上げた遺書である。
門下生に宛てた、最後の言葉たちが述べられている。
その中ではやはり、死生観を四季に例えて語った部分が印象的であった。
『今日死を決するの安心は四時(四季)の順環(循環)に於て得る所あり』
自分自身の生き方を考えさせられる一冊であった。
Posted by ブクログ
@yonda4
安政の大獄で死刑になった吉田松陰が獄中で書いた、弟子への手紙。
松陰が弟子の高杉晋作からの「男子の死すべきところは?」という質問にこう返しているそうな
「死は好むものではなく、また憎むべきでもない。世の中には生きながらえながら心の死んでいる者がいるかと思えば、その身は滅んでも魂の存ずる者もいる。死して不朽の見込みあらば、いつ死んでもよいし、生きて大業をなしとげる見込みあらば、いつまでも生きたらよいのである。つまり私の見るところでは、人間というものは、生死を度外視して、要するになすべきをなす心構えこそが大切なのだ」
時が流れ、時代が移り変わっても、人間の生き方は変わらないものなんだと思う。
Posted by ブクログ
吉田松陰が門下生に充てた遺書、『留魂録』に、解説と松蔭史伝を加えたもの。「身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ちぬとも とどめをかまし 大和魂」という辞世の句を残し、この国の行く末を案じながら刑死した松蔭。死を目前にしてこのような文章を書けるというのは、生死を超越した悟りの境地に達していたからだと思う。
松蔭いわく、「10歳で死ぬ人には10歳の人生なりの春夏秋冬があり、同じように20歳には20歳の、50歳には50歳の、それぞれの人生にはそれぞれの四季が備わっている」という。松蔭もまた、その30年の短い生涯の中に春夏秋冬があったであろう。内に激しい感情を秘めながら、謙虚で心優しい青年だった松蔭。その思想が垣間見えるこの本、是非一読をお勧めします。
Posted by ブクログ
人は、本から学び、旅先の土地から学び、歴史から学び、人との議論から学ぶのだと思った。そして、どんな人生であろうと、その人生に意味をつけるのは後世の人であり、自分ではない。である以上、自分は自分が納得し、悔いを残さないように生きるべきだと感じた。
幕末と現代では、社会が抱えている問題は大きく異なるけど、松陰先生が言っていることは普遍なのだろう。だからこそ、読んでいて、心に染み渡る感覚が生まれる、そう感じさせてくれる作品。
自然と一つ一つの言葉を、ノートへ書き写していく自分がいた。
萩、もう1回行こうかな。。
Posted by ブクログ
吉田松陰が松下村塾門下生にあてた遺書。処刑の前日に書き上げられた。有名な、どの人間の生にも春夏秋冬はあるとの死生観には心を動かされる。例え不治の病を宣告されても、それは直ちに人生の終わりを意味しないと松陰は教えるのではないか。人生が秋を迎えたのだと捉えることで、そこにまだ生きる道を見出せるのではないか。
Posted by ブクログ
激烈なまでの大和魂で、処刑されるまで疾駆した吉田松陰。本書は死に臨んで同胞達に訓戒した書である。あまりに死を超越したような覚悟をもって大言壮語する様子は痛快だが、現代においてこうまでして激烈な思想信条をもって行動を取る姿勢は、時代の歓迎を受けないだろう。一つに、科学を取り込んで冷静に考察する態度は重要である。とはいえ、科学の思考をもってただ言論を交わしているということでは、科学など取るに足らないと考えてしまうだろうが、科学によって実際に果実を手にすることができると分かれば、気合い一点張りで進めることはやめ、科学の冷静さを認めることになるのではないか。確かに、吉田松陰の熱情は、今触れてみても、痛快である。しかし、現代において現実を動かすには、熱意は必要だが、それに加え、科学によって冷徹に外堀を埋めるということは、かなり重要であると思う次第である。
Posted by ブクログ
吉田松陰 留魂録
松陰が牢獄で弟子に遺した遺書。死に対する覚悟、死後のきめ細やかな配慮に 感動する。
「死して不朽の見込みあらば いつ死んでもよし」とする死生観(大和魂)は 生の否定でも、運命論でもなく、生死を超えた生き方、心構えの到達点と感じた。
儒学だけでなく 詩歌にも長けていることに驚いた。「二十一回猛士」が、吉田松陰のペンネームとは 知らなかった。死ぬまでに全力をあげて21回の行動を起こす誓いをこめているらしい。
「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂」
「至誠にして動かざる者は未だ之れ有らざるなり」誠を尽くせば 人は必ず動かされる(孟子)
「此の心 吾れ此の身を惜しむ為めに発するに非ず」
*死して不朽の見込みあるなら いつ死んでもいいし、生きて大業の見込みあるなら いつまでも生きればよい
*人間は 生死を度外視して〜なすべきをなす心構えこそ大切
「今日 死を決するの安心は 四季の循環に於いて得る所あり」
知性と意志力で死を克服しようとした〜到達点は 穀物の四季の循環に例えた死生観
「彼の長技を以って 彼の長技をふせぐ〜以夷攻夷の上策なり」
松陰の攘夷論は 排外思想でなく 先進文明を吸収するためのもの
Posted by ブクログ
かくすれば、かくなるものと知りながら、やむにやまれぬ大和魂
身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂
時の日本にとって、吉田松陰を得たことはなんと幸運であったと。日本が結果、独立を保てたのは、松陰が後進に託した大和魂であったと思います。
Posted by ブクログ
吉田松陰が死刑執行の直前に書いたもの。遺書のようであり、松下村塾の塾生に向けた手紙のようなものだった。松陰の史伝についても載せられている。その史伝と、留魂録を照らし合わせて読むと、松陰の為人や考えがより伝わってきた。
常軌を逸するほどの熱量を持ち、自身を顧みない性格や、塾生をはじめとして周りの人々をやさしく、それでいて強く感化していくところから、彼の偉大さを実感し、感銘を受けた。
Posted by ブクログ
吉田松陰が弟子たちに遺した遺書。内容自体は何と言うことはない。解題・本文よりも、本書後半部の訳注者による松蔭の伝記がおもしろい。松蔭をとりまく状況や松蔭の人となりがよくわかる。士籍を失った経緯や幕府の取り調べに対していらぬ自白をしてしまうところなど、松蔭のやや浅はかというか、自ら苦境にはまっていくような面がうかがえる。しかしそれもこれも、結果的には弟子たちに大きなインパクトを与える刑死につながっていくのだ。訳注者が「あとがき」で、松蔭の死とイエスの死を並べて論じているが、なるほどと思った。同じことがソクラテスの死についても言えるだろう。
Posted by ブクログ
松陰先生の遺書。
「死は人生の終末ではない生涯の完成である」
というマルティン・ルターの言葉があるが、
吉田松陰の生涯は「至誠」の二文字をもって完成した。
彼が信奉した儒教の祖である孔子も孟子も
一種のしたたかさを持っていたため天寿を全うしたが、
彼は愚直なまでに至誠を貫き、至誠に殉じた。
その姿はキリストやソクラテスと被る。
そして彼の思想は松下村塾の門下生に受け継がれ、
明治維新という奇跡を生み出す原動力となるが、
その際に多くの塾生達が非業の死を遂げて、
それが原因と言ってしまうのは少々強引だが、
日本全体が無謀な戦争に突入していくと思うと、
手放しに称賛する気になれないのも事実である。
だが、彼の生き方は奇跡を起こした。
口先だけでは無く実際に行動を起こし、
身分が固定されていた江戸時代において、
門下生達を弟子と呼ばずに友と呼び、
身分に捉われず、彼らの可能性を信じた。
繰り返すが、人を導くのにはこの方法が最善である。
Posted by ブクログ
「留魂録」 たった3文字で、凄まじい力が伝わる見事なタイトル…。 「私の魂(想い)を記録として留めておく」という事か。 自身の命を以て仲間達に志を問う事、人生には春夏秋冬がある事、そしてその人なりの四季があり、松陰自身それを知り得た事…。 人生を賭け、覚悟を決める壮絶さが胸を打つ一冊。 自分には何の覚悟が出来て、何をなし得る事が出来るのか?を考えさせられる。
Posted by ブクログ
松陰先生の遺言書とその訳。全十六章のうち最も濃厚なエキスのような第八章だけでも読んでもらいたい一冊。自分のような子孫がいない人間にとって「後来の種子未だ絶えず」の部分は心に沁みた。
Posted by ブクログ
学校の課題で この本を知り 読んだ
吉田松陰のこといえば 松下村塾というのしか 知らなかった
この 留魂録は 吉田松陰が死に直面した時に 自分自身を冷静に見つめ塾生たちにも問うている
これから 生きていく指針になるのではと 再読し 課題に向かいたい
Posted by ブクログ
『留魂録』は、吉田松陰が1859年10月27日に死刑判決を受けて即日処刑された、その前日に江戸小伝馬町の牢獄で書き上げた遺書である。本書には、『留魂録』本文のほか、解題、史伝が含まれ、松陰の生涯と時代背景についても詳しく解説されている。
松陰は、同じ遺書を二通書き、一通は萩の高杉晋作、久坂玄瑞らに届けられたが、その後所在不明になり、今日その正確な全文が伝わっているのは、牢名主であった男が自分が出獄した後、1876年に元長州藩士の元に届けた、もう一通によるものである。
『留魂録』の中で最も心に残るのは、穀物の収穫に例えて死生観を語った第8章、「(現代語訳)今日、私が死を目前にして、平静な心境でいるのは、春夏秋冬の四季の循環ということを考えたからである。・・・十歳にして死ぬ者には、その十歳の中におのずから四季がある。二十歳にはおのずから二十歳の四季が、三十歳にはおのずから三十歳の四季が、五十、百歳にもおのずからの四季がある。・・・私は三十歳、四季はすでに備わっており、花を咲かせ、実をつけているはずである。それが単なるモミガラなのか、成熟した粟の実であるのかは私の知るところではない。もし同志の諸君に中に、私のささやかな真心を憐み、それを受け継いでやろうという人がいるなら、それはまかれた種子が絶えずに、穀物が年々実っていくのと同じで、収穫のあった年に恥じないことになろう。」の件であろう。
また、高杉晋作の「男子の死すべきところは」という問いに対する、「死は好むべきものではなく、また憎むべきものでもない。世の中には生きながらえながら心の死んでいる者がいるかと思えば、その身は滅んでも魂の存する者もいる。・・・人間というものは、生死を度外視して、要するになすべきことをなす心構えこそが大切なのだ」という返信も印象的である。
明治維新の精神的指導者の熱い思いが伝わってくる。
(2010年9月了)
Posted by ブクログ
文章で読んでいるだけでも教育者としての凄さが伝わってくる。諄々と諭すような講義を面と向かって学んだときの感化力は相当大きいのだろうなあと思った。ただ、松陰先生は行動に関しては粗忽なくらいに機を見ずにやっちゃう人だったのか?友人の仇討旅行につきあう約束をしたけど藩からの手形が間に合わなくて脱藩したり、黒船に乗せてもらおうと小舟で近づいたり、門下生に檄文飛ばして皆から諌められて錯乱したり、あげくに幕府が気づいていない計画倒れに終わったことを披露して死罪になった。革命の種子を蒔く人は、キレキレの頭の良さと、同じくらいにキレた行動をする人なのだろうなあ。
Posted by ブクログ
偉人であるとの先入観を持って読んだため、
若干肩すかしに感じた部分があった。
(現在の日本に与えた影響は計り知れないとわかりつつ)
しかし、松陰とのやり取りで、今も昔も、お役所ってこんな感じだったのねと思った。
100年後もおそらく同じなんだろうな。
Posted by ブクログ
吉田松陰の遺書「留魂録」の全訳・解説の本です。以前読んだ「世に住む日々」を深掘りする意味で読みました。「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留置まし大和魂」という有名な書き出しで始まる。歴史的な価値のあるものなのだろうが、その内容は死を前にして少し女々しい感じもしてしまう。又幕府につかまり、余計な事までしゃべってさらに刑を重くし遂には死罪となるくだりなど「なぜ」そんなにしゃべってしまうのかと思ってしまう。改革実行者というより師として卓越した先見性と指導力があったのだろうと思う。その後の松下村塾ほとんどの塾生は戦死、自刃しているが、彼らは師の意志をついで幕末から明治維新にかけて、歴史を動かす人々となった。
Posted by ブクログ
長州好きにはおなじみの古川先生が全訳・解説をつけた1冊。書き下し文もちゃんと載ってます。また、後半に吉田松陰史伝もついていて嬉しい。字も大きいので見やすいです(笑)松陰好きは勿論、村塾生のファンの方なら見てみることをおすすめ。