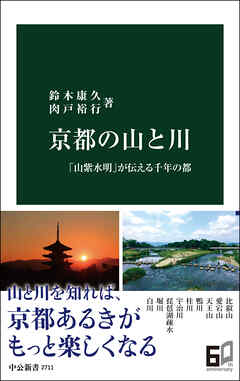感情タグBEST3
Posted by ブクログ
題名を見て惹かれ、入手して紐解き始めた。かなり興味深かった。
「京都」とでも聞けば、思い浮かべるモノは色々と在るのだと思う。それらはそれらとして、山々が視えている場所に街が拡がっている様子や、その市街に鴨川のような川が流れているというような様子が、或る程度強めなイメージなのかもしれない。山や川と共に在るという感が強いということになるであろうか。
その「山や川と共に在る」という辺りに着目し、東山、北山、西山という街の3方向に在る山並み、鴨川、桂川、宇治川、琵琶湖疎水、その他の川と街の中に在る流れを取上げ、様々なことを論じるというのが本書である。
本書の題名にも入っている表現だが、「山紫水明」という語が在る。これは「山は日に映えて紫色に見え、川の水は澄んで清らかである」という語義で、「山や川の景色が美しい様子」を表現すべく用いられる語だと思う。
この「山紫水明」という語句が起こった、または或る程度広く使われるようになった契機が京都に在るのだという。江戸時代の後半に活躍した学者の頼山陽(1781-1832)が京都に長く住んだ際、東山の眺望を愛し、その眺望も愉しめる場所に住んだ。書斎として離れを設けた際、「山紫水明処」と命名したのだそうだ。そこから「山紫水明」という言い方が拡がったという。本書の本文にもこの挿話への言及は見受けられる。
794年とされる平安京の建設という頃から、現在の京都の地は人の営みが盛んになって行ったのだとされる。そういうような古い時代からの様々な営みは山と共に、川と共に在った。山や川は利用される中での変貌を経て現在の様子になっている。川に関しては、様々な用途の水路として造られたことが起源となるモノも交るが、水害から地域を護ろうという改良工事が繰り返されたモノも在る。そして市街は山や川と共に、時代毎の様々な動きを経て来た。
本書にはそういう経過が手広く取上げられている。行ってみれば「山や川と共に在る古都の履歴」を紐解いてみる試みが為されているのが本書だ。
多分、何処の地域にも地形的要件の故に生じた変遷というようなモノは在るのだと思う。が、山並みや川を眺めた感じを形容するような事に起源を有する「山紫水明」という語が京都から起こったとされるように、京都という地域の変遷の中で山や川の存在感は殊更に大きいのだと思う。
個人的な事なのだが、最近は少しばかりの縁が出来て、京都を訪ねる機会が何度か生じ、その都度に時間を設けて歩き廻るようなこともするので「微妙な土地勘」というモノが芽生えていると感じる。本書を読むと、その感覚が程好い刺激を受けた。本書の情報を思い起こしながら、山並みが視える街並み、水辺の歩道を歩き廻ると非常に愉しいかもしれない。
なかなかに愉しい内容だったので、広く御薦めしたい。
Posted by ブクログ
<目次>
第1章 東山~歴史と景観に彩られた山紫水明の地
第2章 北山~都を支えた農山村と自然
第3章 西山~信仰と竹林の道
第4章 鴨川~暮らしに応じて役割を変えてきた水辺
第5章 桂川~平安を語る「別業の地」と「水運」
第6章 宇治川~秀吉が造った新たな河道
第7章 琵琶湖疎水~社会の求めに応じて進化する水路
第8章 洛中の川~千年の間に生まれる川、失われる川
終章 山と川の価値を考える
<内容>
丁寧な筆致で、京都が京都たる由来である、京都の周りの山と川について、地形と歴史を交えて語る。単なる歴史ものとは違う、地形的要素をしっかりと盛りこんだ解説になっている。