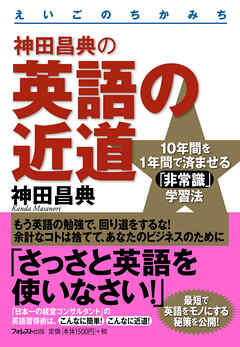感情タグBEST3
Posted by ブクログ
タイトルは胡散臭さを発しているがそれだけで読まず嫌いするにはあまりにもったいない良書。僕が今までずっと抱いていた「言語を形式化して学問として勉強すること」に対する違和感をすっきりさせてくれた。効率の悪い努力を◯年という単位で続けることができてしまうほどに日本人の英語を学ぶことに対する姿勢はずれてきていると思う。読まなきゃ損。
Posted by ブクログ
自分が英語をマスターするまでの過程が鮮明にイメージ出来た!
必要なことは捨てること。
過去の英語の勉強に囚われないことが重要。
あと、目標を立てることはとても大切だね。
ということで目標管理に関する本を数冊大人買いしてしまった。
Posted by ブクログ
外資系の会社に勤務していますが、昨年(2011)8月から支社長まで本国(米国)人となった今では、メールは勿論のこと、会話も英語が浸透してきました。すると会話は、言葉のキャッチボールであり、一定のリズム・スピードでのやりとりが重要であることに気づきます。言葉が出なくて困るときも黙り込むのではなく、何かを発することが大事であることが分かってきました。といっても毎日試行錯誤していますが。
この本はカリスマ経営コンサルタントとして有名な神田氏が、ビジネスで必要な英語をマスターするという目的に絞って書かれた英語の勉強法です。英語勉強において捨て去る6つ(p61)は衝撃的で、「6つを捨てたうえで、目標を明確にして、英語をさっさと使うこと」が大事ということです。
今まで「英語の映画が字幕なしで見られるようになりたい」と思っていたことがありましたが、それが「大きな間違い」であることに気づきました。
また、ブロンドの美人にもてる様になるには「英語を上手に話す」のではなく「多分実体験に基づいた成功例?=ブロンド美人といるのが普通と思える環境に身を置く」が書かれているのは大いに納得しました。
特に、人間は文章を全部聞いて意味を把握するのではなく、会話に含まれるほんのいくつかの単語を拾って、自分なりに意味を再構成している(p101)というポイントは、私のヒアリング及びスピーキングにおいて役立つものでした。
以下は気になったポイントです。
・日本発展の発火点が、昭和から平成に至るまでアメリカであった、しかしアメリカ的資本主義には末期症状が現れていて、遅くとも2020年までには新しい体制に移行するものと考えられる(p17)
・アメリカには、日本で成功するためのビジネスの種子が、いままで以上に溢れかえっている(p18)
・神田氏が成功したビジネスは、全部アメリカから持ってきたもの、顧客獲得に絞った「コンサルティング事情」、加速教育法を使った「速読法・能力開発講座」、日本向けに改善は必要(p23、25)
・アメリカは日本の10-15年先を進んでいる、しかもその革新スピードは衰えることは無い、一流を目指して世界トップクラスの人材が集まってくるから(p33)
・アメリカは「知価社会=知恵が価値を生む社会」に日本より先に移行したという事実をしっかりと見据えること(p50)
・アメリカが進んでいると思われる分野の一部として、マネジメント・マーケティング・コーチング・自己啓発&能力開発・金融個人向け資産運用・リスク管理、医療サービス、心理カウンセリング、ヒーリング等(p52)
・英語学習において捨てるもの、1)日常会話、2)専門外のトピック、3)単語力を増やすこと、4)文法的に正しく話すこと、5)ペラペラしゃべること、6)きれいな発音、である(p61)
・日常会話が難しいのは、単語力ではなく、文化や言語に独特の発想が関わるから(p65)
・ビジネス分野でなんとかするには、想定される質問に対して答えを用意しておくこと(p69)
・神田氏がコンサルタントとして行った2000の質問は、大きく分類すれば13しかなかった、しかも質問の8割は3つの質問でカバーできた(p73)
・自分が今まで生きてきた人生を記録に残した場合、現実は悲しくなるほど少ない(p76)
・アルツハイマー病の最適予防策は、自分史と書くこと、するとデータが失われにくくなる(p77)
・外国語が話せるようになるには、自分の専門分野の関連CD(対談もの)を3枚暗誦する、これが一番効果的、それでもしようとする人間がいないので英語ができるようにならない(p85、86)
・全く新しい言語を学ぶ場合は、暗誦からではなく、NHK講座等からスタートする(p87)
・日常生活でもっともよく使われる単語数は300程度、何でも表現できる単語レベルでも850(p93)
・会話が続かないのは、単語力ではなく、発想力の欠如、発想自体を英語にする必要がある、英語は論理の言葉で、日本語は感情の言葉、英語はまず結論を言って、その理由3つを示す、その後に詳細を話す(p97)
・人間は文章を全部聞いて意味を把握するのではなく、会話に含まれるほんのいくつかの単語を拾って、自分なりに意味を再構成している(p101)
・ビジネス英語で大事なのは、自分の言いたいことを表現するための文章パターンをいくつ持っているか(p102)
・小沢征爾氏の英語は日本語アクセントもあり発音は綺麗でないが、その瞳に、音楽に対する自信、楽団員に対する愛情がこもているから誰もが彼の言葉に動かされる(p112)
・日本語のアクセントがなければ二世に思われるが、アクセントがあればバイリンガルと思われる(p112)
・英語のトーンを身に着けるには、1)大きな声でしゃべる、2)声のトーンを1オクターブ下げる、である(p115)
・英語学習をするための魔法の質問に答えること、1)寝ている間に奇跡が起こって、朝、目覚めてみたらビジネスにおいて自分の英語が100%満足いくような状況であったら、それはどんな状況か、2)周りの人はどのようにあなたの変化に気づきますか?、3)あなたはその時、どんなことをしていますか、何か見えるものは、聞こえるものは、どんな感じを持っていますか(p144)
・適切に目標(1年後、3年後、5年後のイメージを明確に)を設置すると、右脳(潜在意識)はその目標を実現するまで働き続ける、自分だけが得するのではなく最低でも3人以上に役立てられるもの(p150,157)
・多くの人は、成功できないのではなく、成功するのが怖いから成功しない、英語が使えるようになるのが怖いから、英語が使えるようにならない(p167)
・英語を話すときには、英語名のセルフイメージを持ってみるべき(p173)
・どんな人に対しても、6-9歳あたりの子供時代の家族について尋ねるのがポイント、その時期に顕在意識が明確になってくるから、その頃の体験は大人になっての人間形成の根っこになっている、徐々に遡って質問するのがポイント(p208)
2012年6月3日作成
Posted by ブクログ
習得が難しいと言われている日本語を外国人力士は何故、いともたやすくモノにしているか、という例えが面白かった。
このままではヤバい、フツーのやり方では英語の遅れが取り戻せない!と焦った私にぴったりだったかも。
Posted by ブクログ
「英語は勉強すればできるようになる」というのは間違い。英語はあくまでもツール、「英語を学ぶ」のではなく、「英語で学ぶ」という考えが正しい。
① 日常会話を捨てる。実はこれが一番難しい。それに比べてビジネス英語は意外と簡単。
② 単語力を増やすことを捨てる。
③ 文法的に正しく話すことを捨てる。
④ ペラペラ喋ること、キレイな発音をすることを捨てる。
Posted by ブクログ
もうこういうノウハウ本は読まなくなってしまったのだが、歯医者の待合室に置いてあったのを何気なしに手に取ってしまった。
貸し出しもしますということだったので、家で続きを読んだ。
涼しくなってきたので、少しは読書しなきゃね。
尤も、こんな1時間もあれば読めるような本は読書とはいわないかもしれませんがね。
ハッキリ言って面白い。
ノウハウは出し惜しみするものだが、この人は例外。
まあ、外国人って日本人のように出し惜しみをしないのが普通なんだけどね。
ノウハウを書いても全員真似できるわけがない。
出来ないのが分かっていて書くのは、自慢話。
この著者も、自己陶酔の世界に入っていないとはいえない。
だが、ナルホドと唸るヒントが沢山あるは認めなければならない。
例えば:
あなたの英語が通じないのではなく、単に聞こえないのだ。
結局我々は英語のせいにして、世界の舞台に出て行かない言い訳をしているように見えて仕方ない。
英語が出来ないのは心の中でサイドブレーキを無意識のうちにかけているという話の流れで:
「英語が出来てもいい」という許可を、自分に与えてあげてはいかがだろうか?
初対面の人と打ち解けるノウハウとして:
I see your kindness.
I see your fierceness.
I see your wisdom.
I see your love.
I see you.
と心の中で唱えること。
15分で苦手な初対面の人と15分で信頼関係を築くのは:
相手が6歳から9歳のときの、子供時代の家庭の関係を聞くこと。
などなど。
一々頷いてしまった。(;^ω^A
まだ49歳の若さだが、よく世の中が見えていると感心させられた。