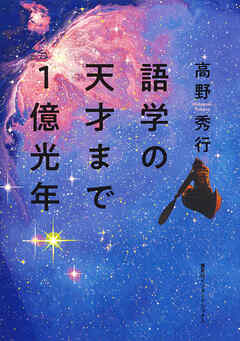感情タグBEST3
Posted by ブクログ
言語を冒険で便利に使える"魔法のツール"と称して世界中を冒険しつつ言語を習得してきた著者の語学冒険譚。
私も趣味でインドネシア語や英語、中国語を少しながら学んでいるので著者の「魔法のツール」という感覚がとてもわかる(そして学ばなくなると穴の空いた器の如く知識が漏れ出ていく感覚も)。一方、ここまで色々な言語を文字通りテキストもない中での独学をする中で得られた語学のコツや落とし穴、語学と民族性の関係の話などとても為になった。使う言語を切り替える時なんとなく話者の人格を切り替えるという話は身に覚えがあるしその理由の解説がとても参考になった。
Posted by ブクログ
さすが高野さん、語学学習法という観点でも体験談という観点でも非常に面白かった。
最初の衝撃的なエピソードにはじまり、新しい言語への出会い方、学び方など、どれ一つとっても面白い。
言語のノリ、ムベンベの正体やえつとue の関係、中国の日本族など、現地語を少し話せるだけでこれほど見える世界が変わるのかと非常に言語学習への意欲が高まった。
民族を聞くのはタブーなのにどんな言語を話すかは喜んで教えてくれる
フランス語の成績が悪すぎてフランス文学専修送り
ザイコランガランガのニッポンバンザイ
うっかりコカイン工場に出くわしてしまうコロンビア、あらゆる文明の発達段階と階級をつなげるスペイン語
中国の日本族
ロシアも同じ感じだったな
アメリカもミャンマーも知らないワ人
前近代の言語にはあいさつがない
友達も文明語
Posted by ブクログ
辺境ノンフィクション作家高野秀行さんの語学体験記。
英語、フランス語、中国語などポピュラーな言語から探検・取材に合わせてリンガラ語、ボミタバ語、シャン語、ワ語など学んだ言語は25以上とのこと!
語学体験に伴う各地の辺境体験は最高におもしろくて、以前高野さんの『西南シルクロードは密林に消える』を読んだ時のものすごい衝撃を思い出しました。
やっぱり高野さん、すごい!!
たとえマスターしきれなくても、現地の人と現地の言語で交流するのは語学の一番の喜び。
聞いたこともないような言語、その高野さんらしい体当たり学習法はなかなか上達しない中国語学習中の私にはおおいに刺激になりました。
中国語学習のところは私も「あるある」「そうそう」と共感することばかり。
・現地の人っぽく話す物真似学習法
・ネイティヴの音声を繰り返し聴く
「さまざまな言語を学んでいくと、どの言語にもその言語特有のノリとか癖とか何らかの傾向などがあることがわかる。それが語学で決定的に重要だと気づかざるをえない。」
学習法だけでなく、他民族国家と日本の言語観の違い、国のあり方などについて改めて考えたり気づかされたりしました。
Posted by ブクログ
著者が好奇心旺盛。
普通の人が行かないところややらないことをどんどんやるところが面白い。
この本を読むと、語学を学習して現地で使ってみたくなる。
Posted by ブクログ
語学学習の仕方を教示する本ではありません。語学学習又は世界中の言語について、作者が実際に現地で体験した事や、考えが主な内容でしたね。しかし作者の言語が必要なくなったらすぐ忘れる特性が相まって最初から最後まで面白いです。まさに語学の天才まで一億光年だなと。笑
Posted by ブクログ
言語とは、言語を学ぶとはどういうことかといった問いに対する深い洞察があった。
辞書や教科書がある言語を学ぶなんて生温い。著者は文字がない言語を学び、自分で法則性を見出し文法を作る所から始めることもある。
現代において言語を学ぶ意義はどこにあるのかといった考察もある。英語だけが外国語では決してないことを教えてくれる。
評価は⒋7くらいをつけたかったが、便宜上5とした。
外国語学習に行き詰まっている人にもおすすめだ。
Posted by ブクログ
辺境の地に出かけて行っては自分で体験したことどもを客観的な事実と主観的な考察を交えて本を書くという独自の存在である高野さんが、語学(外国語の習得)を軸に大学時代からこれまで通ってきた人生を振り返る面白本。かなり期待して読んだのですがそれを上回る面白さでした。書評や何やらで目にするたびに、「あ、高野さんだ」と注目しつつも実は実際に読んだことがあるのは確認すると『アヘン王国潜入記』だけだったのですが、この本にまとめられた体験をするためにタイとミャンマーとカンボジアの国境にまたがる地帯、いわゆるゴールデントライアングルにたどり着くまでのことが時系列で章立てされる構成だったので、一作だけ読んだことのある本がこのエッセイの到達点になっており、なんだか感慨深かったです。ご自身のことをあけすけに分析して大変ざっくばらんに語っておられ、すごいなと思いました。楽をしようと、重要英単語を集中的に10だけ覚えてあとは放置しようと決めたあとに、覚える単語を選ぶために教科書に出てくる単語を全て数え上げて集計するという地道な作業をするところがこの方の強みというか地力なのではと思いました。この強みはその後の語学学習でもずっと同じ様子で続いており、先生の話すのを録音して全会話を書き起こすとか、教科書が無い言語を学ぶときにはひたすら例文を教えてもらって比べて法則を見出して文法や語法について仮説を立てて検証していくとか、そうして25の言語を身に着けようと努力した体験から、民族と言語の関係だとか、話し言葉と書き言葉の違い、教科書には表現しきれない言語の身体性(高野さんは「ノリ」という言い方をしていましたが)であるとか、興味深い考察が山盛りでした。暮らしている地域の言語の状況(公用語が複数あったり旧宗主国の言葉の影響を強く受けていたりいなかったり)による世界の捉え方、外国・外国語の認識、の話がなかでも大変興味深かったです。感想をまとめることが出来ないくらい、面白かったです。
Posted by ブクログ
言葉を絡めての冒険・探検ドキュメンタリー。言葉=民族=文化=そこに住む人。なにより著者の壁の無い人間性が凄い。羨ましい。言語学的な分類とか、各民族の言語を通じての世界観とか、なるほど〜。ネイティブの話す言葉にはついていけない、片言の外国語を話す人には優しくなる、とか、あるあるです。冒険ものとしても、笑いも多々あり、楽しめる一冊でした。
Posted by ブクログ
何度も何度も聞いてリピートが一番と語学の天才ではない人が言う。そうだろうな。それと話したいこと、聞きたいことがあるというのも重要。それもわかる。
日本語は孤独、という表現が面白かった。
Posted by ブクログ
奇抜なタイトル。この本を読んだ人から面白い、お勧めというコメントを受け、読み始めるが、本当に面白く、超絶人生そのものを感じた。
著者のポリシーは「誰も行かないところへ行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く」とあるが、まさにそれを実践している。そもそも語学に取り組み始めた目的が、辺境地帯で未知の巨大生物を探すとか、謎の麻薬地帯に潜入するといった、普通の人は考えないだろう常軌から外れた探検心からである。もともと語学は得意ではなく楽して覚えたいという発想から、独特の習得法を編み出し、結果的に話せる達人の領域に至り、ツールとして使いこなしながら、ポリシーに沿った人生を歩んでいる。側から見れば無謀に見える行動や壮絶な体験も、ときには笑いを誘いながら、巧みにぐいぐいと追体験の世界に引き込まれていく。かなりボリュームのある本だが、内容の濃いボリュームであり、読後に達成感さえ感じられる。とにかく面白かった!
Posted by ブクログ
著者が、読みやすく書いた、というだけあって読みやすく面白い。ただなぜか時間かかった…
辺境すぎてついていけなかったのか?
世間一般が知らない言語すぎて興味深いところと、引いてみているところが両立して複雑な気分。
ボミタバ語、シャン語、ワ語、初めて聞いた…
好奇心旺盛な著者らしく、大学の探検部時代から赴くままに生きている。
その勢いのまま言語も学び習得する姿はすごいとしか言いようがない。探検の道具であり、探検の対象にもなる言語。新しい探検テーマを見つけるとそのテーマと同じくその場で話される言語にもワクワクするそうだ。
リンガラ語を学んだ時は東アフリカのスワヒリ語より文法がシンプルで、アフリカのリズムを感じたそうだ。アメリカの遺伝子調査でもアフリカ系アメリカ人の大半がコンゴ民主共和国(旧ザイール)とそのとなりのアンゴラに由来することがわかったそうだ。
もしそうなら、リンガラ語の元になったコンゴ、ザイールのバントゥ諸国のリズムが奴隷貿易でアメリカに渡り、ジャズやロック、ヒップホップになったのではないか。 p. 52
興味深い…
ザイール人はエネルギッシュでハチャメチャ。
コンゴ人はそれに圧倒され、大人しい印象…
語学の勉強法は、ネイティブの懐に入り教えてもらう。生きた言語しかいらない、と言いつつもルールを探し自分なりの解釈で、リアルな言語を習得していく。誰もができる方法ではない。ネイティブに読み上げてもらった文章を繰り返す、シャドー法。
各地の話や作者の行動力、コミュ力にはあっぱれ。
福建省、客家はっか、土楼とぅろう
円形、たまに四角形の伝統的な巨大集合住宅のこと。
客家語を使用。
Posted by ブクログ
南米ぐらいで挫折しそうになったが、タイくらいから一気に読み切った。
「情報を伝えるための言語」と「仲良くなるための言語」がある。仲良くなるために言葉を学ぶのはロマンがあると思う。
Posted by ブクログ
チェンマイで日本語をマンガで教えたやり方がすばらしい。
「言語を話す時のノリ」が語学で決定的に重要。
文法、言葉の使い方だけでなく、発音、口調、話す時の態度、会話の進め方など。タイ語はなよなよ。英語は喉の奥から声を出し、相手の目を見て笑顔。日本語は目を合わせず、ちょっと恥ずかしげな、おどおどしたような態度。中国語は声がでかい、語気が強い、屈託や遠慮がない。
スペイン声は平安京言語。驚くほど規則的で親切設計。
フランス語は旧植民地での優位性が支えとなっている。
日本語は孤独な言語。
非常に興味深い内容だった。
Posted by ブクログ
語学に対する認識が少し変わったような気がする。旅をする人は将来に不安を抱えながらも自分の信じた道を進むんだなあ。深夜特急と似てるなと思った。そんな姿が最高にかっこいい。
Posted by ブクログ
道具として様々な言語を学んだ著者の経験を記したノンフィクション。学術書ではないので、この本をそのままリファレンスに使えるかと言うと難しいが、学術書でないが故のリアルな言語学習とそこから生まれた言語学習観がある。
筆者の経験は90年代のものが中心なので、今よりも言語学習環境が悪かったはずなのだが、その環境的制限があるからこその奮闘記となっている。環境的に良い現在で、このハングリーさがどこまで通用するか、とも思うが、伝えたいことを伝えたいと言う気持ちの強さが言語習得の鍵であることを再確認した。
Posted by ブクログ
それぞれの国の人によって、言語観が違うのが面白い。言語観がそのままその人の行動に影響していて、フランス人あるあるみたいなのがめっちゃ共感できる。言語も確実にその人を構成する要素の一つだと強く感じた。
翻訳機能などが発達している中で、最後の筆者の語学に対する考えにとても共感した。言葉には情報伝達だけでなく、心を通じるという役目は絶対にある。言語を学びたくなった。
Posted by ブクログ
冒険譚と言ってもいいかもしれない。
その環境に身を置き、語学を習得してゆく様。
トレーニングも同じだけど、それそのものを目的とするより、手段としたほうが身につきやすいということを体現してくれている。
昔勤めていた会社の先輩は、海外の女性がいるお店のおねーちゃんと話がしたくて英語がものすごく上達していた。
自分に置き換えた場合、日本語でもコミュニケーションが苦手なので、なかなか語学が身につかないのがよく分かる。
それにしても、アヘンでラリっていたなんて!
Posted by ブクログ
ノンフィクションは余り得意ではないが、本作はNHKで紹介されていたのをたまたま目にし、購入してみた。
非常に面白く読み進められ、奇妙な没入感に包まれた。よくぞ無事に、と思うシーンが何度もあり、身内ならハラハラするだろうが、言葉が通じないさまざまな出来事を通じて「最後は人と人」ということが改めて思い知らされる。良作。
Posted by ブクログ
著者が自分とあまりにかけ離れすぎていて、未知なる世界を開拓した気分になりました。笑
世界ウルルン滞在記(もう終わってしまった?)を素でいく人なんですね。
体験談が腹を抱えて笑えるレベルですので、語学に興味のない方でも充分楽しめると思います。
実はこの本を手に取ったのには理由があります。
過去、仕事で英語(メールのやり取りのみ)を使っていたので、英会話に通っていました。
「これを機に英語を勉強して英語が話せるようになろう。転職の時に有利になるだろうから」とかそんな理由で。
ところが、英語学習を始めて数年後、英語を全く使わない部署に異動に。
目的を失い、英語はフェードアウトしていきました。
(日ごろ使わない語学のために、時間とお金はつぎ込めません)
自分の中では英語は終わったものになっていたのですが、転職したら再び英語がカムバックしてきました。
(今回もテキストのみのやり取り。メールに加えてチャットがついてきました)
もはや英語からは逃れられないのか。。。
「(英語)どうするかな~」
英語を勉強を再開しようか決めかねていた時に発見したのがこちらの書籍。
(タイミングが良かった!)
(英語を)やるにしても前回の敗因は何だったのか?
そして、前回の二の舞になるのだけは避けたい。
(7年間も通っていたので、かなりの金額を英会話につぎ込んでいた)
敗因を分析したうえで英語と向き合おうと思い、読んでみました。
うん。読むだけの価値はありました。
私が英語を喋れない理由がよーーーくわかった。
理由は主にこちらになります。
”話したいことがあれば、英語は話せるのだ。”(抜粋)
”言語はあくまで道具。それが私のスタンスなのである。何か大きな目的のために学ぶのだ。”(抜粋)
私、英語ネイティブに何が何でも死に物狂いで伝えたい事がない。。。(文章ではあるが、話す必要性はない)
それに英語を学んだ先に何がしたいのか、目的がなかった。英語を学ぶことが目的化していた。
そりゃ、喋れるようにならないわけだよ。
(そもそも英語って必要なの?な感じが)
この本を読んだら、英語に対して完全に吹っ切れる事ができました。
私には著者のような言語で伝えたい情熱は持っていません。なので、著者のような語学勉強をやる気力も持ち合わせておりません。
現時点では英語は「情報を伝える言語(テキストOnly)」として使いこなせればよい。先方の要望を読み取り、失礼のない言い回しでそれに回答する。反対も然り。私が今困っているのはこれなのです。
であれば、今の私に必要なのは、英会話に再び通って英語が話せるようになることではなく、洋画を字幕で観れるようになることでもないのです。
最も必要なテクニックは、Google翻訳を上手く使いこなせるようになることなのではないか……。(身も蓋もない解決策な気も)
まずは目先のお困り事を解決することに集中しようと思った次第です。(選択と集中)
※ちなみにGoogle翻訳を使うにしても、ある程度英語の知識はあった方がいいかもですね。単語を微調整しながら使ってます。7年間の英語学習は全く無駄ではなかったようです。
Posted by ブクログ
大変面白く最後まで読めた。
高野さんの行動力と謙遜と優しいユーモアが多分に感じられ、自分も楽しく謙虚に生きていきたいという気持ちが自然とわいてきた。
(それで初めて感想を書こうと思ったので書いている)
何をするにも体系的な学習を求めてしまいがちな自分にとって、ブリコラージュという概念は新しいことを気楽に始めるために背中を押してくれる言葉と思った。
頭でっかちから実践の人に変わりたい自分にとって大変ありがたい読書になった。
Posted by ブクログ
【読もうとしたきっかけ】
評価が高く、面白いかなと思ったため。
【読んで感じたこと、自分が認識したこと】
評価が高かったため、めちゃくちゃ楽しんで読めるかと思ったが、自分にはあまりピンとこなかった。恐らく、言語学習についてあまり興味がなかったからである。
筆者は、自分とは全くことなる考え方の人で、異文化圏へ飛び込み、冒険することをめちゃくちゃ楽しめる人である。
このような考えと行動が出来る人は凄いな~と思う反面、現地に行く前にどの程度下調べをしてから行ってるんだろうと無謀さも感じる。恐らく、言語に重きを置いている本なので、そこらへんはあまり記載はないが、念入りにできる限り下調べをしているのだと思うが、現地での行動を見ると破天荒である。
ひとまず、異文化、異なる民族を知るためには、そこの言語を学び、現地の人と話すことが重要であり、親しくなるためには言語学習が不可欠である。また、確とした目的があればこそ、言語を身に付けることができる。
Posted by ブクログ
面白かった!語学が好きな人におすすめ。必要があるからネイティブに習い、必要がなくなったら忘れる、の繰り返し、と書いていたが、とりあえず話せるようになるのが凄い。別に完璧は目指さない。でも楽して覚えたいといつも思っていて、色々な方法を試す。それが参考になるし、面白かった。著者は人間観察力がとてもあるんだと思う。
どこにでも片言で飛び込む勇気や言語の特徴を分析する頭脳はすごい。高野さんの他の本を読みたくなる。
Posted by ブクログ
世界の辺境に突っ込んできた著者の語学(言語)との付き合いが語られる。探検的活動の道具として現地の言葉を習得し、「ウケる」ことで親しくなり開かない扉を開けていく体験は痛快だ。テキストすらない言語を習得する過程も探検的で面白い。著者が潜り抜けてきた危なっかしい現場の空気をダイジェストで感じることもできる。
Posted by ブクログ
現地の言葉で現地の人と仲良くなりたいという気持ちや、何かを成し得る為の貪欲さが語学学習に向かう筆者は充分語学の天才だと思う。
言語の歴史と世界の歴史は繋がっている。
世界の旅のルポとしても楽しめたので、筆者の他の本も読んでみたくなった。
Posted by ブクログ
著者の語学に対する貪欲さは「何者かになりたい」という劣等感やハングリー精神からきているもの。私は、、そこまで劣等感を感じるほど自分と向き合えてないし、貪欲さも持っていないから、羨ましい、真似したいと思いつつも一生できないだろうな。これは著者の才能。
Posted by ブクログ
新聞の書評とタイトルの1億光年に惹かれ、同書を手に取りました。
ジャレッド・ダイヤモンドの「銃・病原菌・鉄」?にも描かれていた言語人類学、言語を通して人類の系譜や文明・文化の発展、浸透具合を探る様な内容です
本書の記述の中には、「話したいことがあれば話せる、コミュニケーションの言語と仲良くなる言語、言語内序列の法則、まんが学習法、言語のノリ、日本語は辺境の孤独な言語」等興味深いものがたくさんあり、特に言語のノリは、民族性の表れとの指摘、日本語や中国語等なるほどなあと思わせられました。
最後は、筆者がチェンマイの奥深くに住みながらケシの栽培をし、アヘン中毒になり、帰国する所で終わりますが、なんとも凄い余人には体験不可能な語学の旅に圧倒されました。
Posted by ブクログ
高野秀行さんの本を初めて読みました。
何故、そんなにあらゆる言語を習得し、話せるようになったのか、本人のキャラクターと熱意を交えて面白おかしく読めました。
ワ語って何!?という感じですが、現地の人と打ち解けるために言語を覚えてコミュニティに入っていくそのエネルギーと感性に脱帽でした。
今、英語を勉強中ですが、言語は手段であって、やはり言語で何を得たいのかが大事なんだなぁと改めて思いました。
以下、感心した文章を記しておきます。
↓↓
自分があまりに無力であり、存在意義がないという絶望感である。
後から考えれば、「アイデンティティ・クライシス」の一種だったのだろう。
アイデンティティを獲得したメンバーを見ると、尋常じゃない焦りが生じた。早く自分も「××ができる俺」にならなければいけない。
↑↑
引用終了。
メモ
何でもかんでも言語を覚えようとするのは、アイデンティティを手に入れるため。