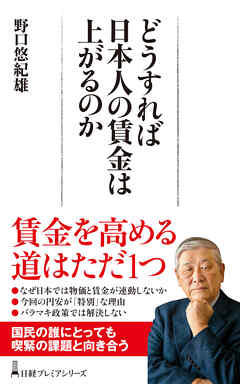感情タグBEST3
Posted by ブクログ
2023.04.08
シンプルな良書。特に、高校生に読んでほしい。この本の内容を理解すれば、自分がどういう職業を選択すべきかについて「ひとつの」有益な示唆を得られる。「ひとつの」と書いた理由は、筆者の「あとがき」そのままである。齢50を過ぎて、この本を読むと若い頃(今も)自分の愚かさに天を仰ぐばかりである。
付加価値を産めない仕事をシャカリキにやっても賃金には恵まれない!
Posted by ブクログ
他国の賃金は上がっているのに日本だけ20年変わらず、他の先進国の5〜8割。低賃金のパートが多い。給与体系や労働環境が時代に合わず、企業に稼ぐ力がない。良い円安などない。円の価値を守れ。
安値安定がいいように思っていましたが、他国が上がっているなら、同じように上がらないとヤバイ、ということを理解しました。昔からじゃなく、ここ10年のことだったとは。
Posted by ブクログ
アメリカの情報産業のエンジニアの給与水準の高さに驚かされる。様々な統計データを駆使した説明はさすがの一言。統計データを諸外国と比較するには前提条件を認識しないとミスリードする。
実感として給与が増えないことが、過去の賃金水準から比較すると下がってることは腹落ちした。またその背景に日本企業の年功序列を前提とした働き方があると理解した。昔ながらの退職金制度を前提とした働き方は無理がある時代にきている。
春闘での賃上げを政策とする時代錯誤も理解できた。高度成長時代は大企業が賃上げをする前提として稼ぐ力があったから、中小への波及も期待できたけど今は全く期待もできないし。そもそも大企業で働いてる人なんて少ないのに、そこの状況だけが趨勢として切り取られることには違和感があったが、やっぱりそうだった。
日本の政策は大企業向けに円安誘導されていたがあくまで企業が見かけ上儲かるだけで逆に個人は搾取されているように思われる。
統計データの一つ一つの分析は専門的で難しさを感じるも総論としてはわかりやすいと思う。
Posted by ブクログ
バブル崩壊以降、日本経済は長期的な低迷に陥っている。それは、「失われた30年」と呼ばれたりもしている。その間、国民の所得も伸び悩んでいる、というか、全く伸びていない。むしろ下がっているのだということを示す統計も存在する。それに加えて、2022年になってからは物価が上がっており、可処分所得は更に下がっており、国民の多くが、苦しさを感じている。
これに対して、政府は春闘での賃上げを経済界に提言したり、それを支援するために賃上げ減税等の検討を行ったりしている。
筆者によれば、それは無駄なことだ。賃金を上げるためには、その原資となる企業の付加価値を上げる必要があるのだ。付加価値を上げるためには、技術革新を進める、新しいビジネスモデルを確立する、新しい産業を起こすといったことにより、生産性をあげる必要がある。春闘の対象はほぼ大企業に限られ、春闘で賃上げが行われたとしても、国民全体の賃金が上がるわけではないことは、過去のデータが示している。また、賃上げ減税を導入しても、個々の企業は実力以上の賃上げを行うことが出来ないのだ。
事業活動の付加価値を上げることは、個々の企業の責任である。政府はそれを、賃上げ税制といったような形でバラマキ的に補助するのではなく、「変化を阻害する条件を撤廃する」ことが大事であると筆者は説いている。
筆者は、色々なところで同様な主張を行っている。主張自体に私は賛成だ。
Posted by ブクログ
資本装備率が、格差を発生させる要因。大企業が優越的な状態に成るは、必然か。
つまり、今の日本は、70年代末、レーガン政権以前のアメリカ。これを冷戦終結とそれ以降の内部での競争激化により、90年代以降、克服。しかし、現在は内部対立の激化にる分断状態へ移行してしまっている。それでも労働者的には、問題ないか。
メインフレームから、パソコンへ、ぐらいから始めるべきかな。スマホか、これだと・・・。
アベノミクス開始時に短期的な株価回復に捉われず、大企業に対する法人税を反優遇的に上げてしまえばよかったんだな。そうすれば、新しい芽が花開いて希望のある社会、賃金の上昇にもつながった、と。現状からは、そう判断できる。大企業病恐るべし。
今あるのは、利権化と中抜きだけだもんな。お花畑のアベノミクスでしたとさ。
ロシア軍の現状の弱さと、日本の賃金が上がらない理由を同列と判断する話は、とても面白い、悲しいけど。
付加価値って、大自然からは直接には得られないのね。広大な国土や四季折々の観光資源、これでは、ダメなのね。少々の付加価値にはなってるけど。
Posted by ブクログ
このおじさんも、遠藤誉さんと一緒で80代なのに、怪物的に頭がキレる。
平均所得はパートタイマー(パート自体の平均給与は増えているが、数の増加が顕著)を含めるから、海外と比べて、とても低くなる。日本のパートタイマー比率25%は高すぎる!OECD 16%。
平均年収700万円の会社に1,000万円プレーヤーが3割いる!
売上高・付加価値の比率は、小企業の方が高い!
円安が、古い産業をイノベーションのないまま温存してしまい、今の資源高、海外企業のイノベーションに対抗できなくなっている。
分配なくして成長なし ではなく、
成長なくして分配なし!である。
成長せずに分配できるような打出の小槌はない!安易なバラマキ政策からは脱却すべき!
既得権の打破、規制緩和で、成長を実現することが、賃金上昇につながる!!
Posted by ブクログ
2022年65冊目。256ページ、累計17,607ページ。満足度★★★★☆
ついにインフレが始まった2022年の日本。しかし、賃金は容易に上がりそうにない状況
本書は、日本の状況を世界の公表データなどと比較することにより、どうして現在の状況になっているかを明快に分析
ただし、どうすれば賃金を上げられるかの策については、非常に大括りの内容にとどまっている
Posted by ブクログ
日本は世界の物差しでみて賃金が安くなったという。
ただ、生活的にはまだまだ豊かである。ここで出たロシアと比べたら比較にならない。
自分は子どもたちがこういった現状を知った上で日本人で良かったと思える国にしたい。
円安は個人賃金を下げて企業が利益を出すこと。安倍さんはそれを知っていてやっていたし、国民はそれを知らなかった。知っていてもどうしようもないんだけど。
Posted by ブクログ
今の日本に繁栄をもたらすにはどうすればよいのかという問いに答えた本。著者の意見は、ほぼ正しいと思う。データも豊富に示されており説得力がある。ただし、既知の内容が多く、新たに得られた知識は少なかった。さらに渡辺努氏のように、学術的な掘り下げはなく、データの読みは表面的で、解釈に疑問が残る点もあった。
「賃金や給与を考える場合には、付加価値=「稼ぐ力」が最も重要な指標だ。本書の議論は、この指標を軸として展開される」p6
「日本人の賃金を引き上げることは、日本経済を再活性化することとほぼ同義であり、その実現には、日本社会を根底からオーバーホールすることが必要だ」p9
「平均賃金が20年間上昇していないという大問題。2000年には日本より低かった韓国に抜かれてしまった。その他の国との乖離も拡大している。日本の国際的地位は、この20年間で低下したことになる」p49
「(ビッグマック指数)日本は390.2円だが、1位のスイスは804円であり、猛烈に高い。3位のアメリカは669.3円で、かなり高い。韓国の439.7円も、日本よりずいぶん高いと感じる。そして、中国が441.7円だ。2021年6月には日本より安かったのだが、ついに中国の価格が日本より高くなってしまった」p57
「従業員一人当たりの付加価値を「生産性」という。したがって、「生産性が高い企業の賃金が高い」ということになる」p90
「アメリカで年収1000万円は、ほぼ大学院卒の初任給レベルである。トップクラスのビジネススクールであればMBA取得後、1700万円程度の年収が直ちに得られる。ボーナスを加えると2500万円程度になる。30歳になるかならぬかの人たちが、これだけの収入を得られるのだ」p116
「OECDのデータによると、パートタイマーが全雇用者に占める比率は、OECD平均では、男10.4%、女22.1%。スウェーデンでは、男11.4%、女17.1%。それに対して日本では、男15.0%、女39.5%だ。男性も高いが、女性のパートタイム率が国際的に見て著しく高い」p218