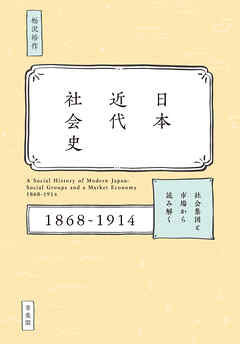感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書は大学における講義内容をもとに執筆されたものだが、とても興味深い内容で広くお薦めするに値する本だと思う。
副題に「社会集団と市場から読み解く」とある通り、「社会集団」と「市場(マーケット)」の2つを軸として、歴史的事象が整序され叙述されていく。
はじめに示されるのだが、明治期日本社会の構造を示した基本的な見取り図(13頁)が参考になる。
まず、日本近代社会を理解する前提として、江戸時代の社会(日本近世社会)の構造についての説明がある。
・領主制
・農村における基本的単位の「村」と、連帯して領主に年貢を納める責任を負う村請制
・「町(ちょう)」と、労働提供義務である”役”
第2章では、近世身分制を解体した戸籍法、廃藩置県について論じられる。これらの大改革は、しかし計画的に行われた訳ではないと著者は言う。戸籍法の契機は、脱籍浮浪人の治安問題であり、廃藩置県も政府内部の対立が克服できないための一か八かの決断であった。
第3章では、地租改正と、大規模な町村合併による村請制の解体が説明される。
以下、興味を惹かれたのは、
「第6章 小農経営と農村社会」の「家」経営体の戦略、現金収入を増やすための副業。
「第7章 女工と繊維産業」。当初は顔の見える関係同士の間で、女性労働者が農家という「家」から、製糸工場主の「家」へと派遣されて働いていたのが、製糸業の発展に伴い、遠隔地からの募集となり、女工の奪い合い、引き抜きが増えたこと。
「第8章 商工業者と同業組合」。近代工場制ではない、職人や町工場的な小規模工場が根強く存在し、また織物業等農家副業による生産も重要な位置を占めていたこと(在来産業と呼ばれる)。
各章ごとに参照文献も紹介されており、自分の関心の高い事項を更に勉強するのに役立つと思う。