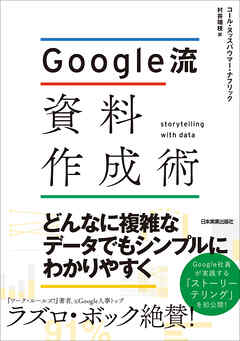感情タグBEST3
Posted by ブクログ
邦題はクソだが原題は「storytelling with data」であり、データからどのようにストーリー立てるか、ということを書いた本である。とてもためになる内容だったので、何度も読み直して使いたい。
Posted by ブクログ
原著のタイトルは「storytelling with data」とあるとおり、データを使った主張の仕方の本。
自分が主張したいことを、データを用いて相手に伝えるにはどのように見せるのが効果的かについてまとめられており、グラフや表の悪い例・良い例を比較して説明されている。
そのため、読者側としても直感的にグラフや表の悪さ・良さが分かりやすく、読んでいくうちに自分のグラフの悪さがどこにあるのかが掴めるようになってくる。
データを使って自分の主張を人に伝え、理解していただくような機会がある人にとって必読の一冊。
Posted by ブクログ
小手先の資料作成テクニックではなく、「形式は機能に従う」をエグいほど徹底するやり方。データを使って相手に何をしてほしいか(機能)を考え、それを視覚化(形式)する。そのためには何が必要で、何を削除する必要があるか。無人島に持っていくレベル。
Posted by ブクログ
分かりやすく、かつ具体的。パワポによるプレゼン資料作成にも活かせる要素がたくさんある。
表はプレゼンには不向き みんなが気になるところをみてしまうから
表の罫線は薄く データが主役
グレーで字を書く。強調する色は、単色、黒、太字。
相手のブランドカラーを使用。
パワポの上部タイトルにアクションをかく!
Posted by ブクログ
「ひどいグラフをこの世界からなくす」
という目標の下、Googleでビジュアライゼーションの講座を担当していた著者によるデータビジュアライゼーションの本。
グラフの書き方に留まらず、いいプレゼンテーション資料とはなにか、というところを伝えている。
正しく意図を伝えるには時間がかかる、ということも説明している。
「文脈を理解し、クラター(ごちゃごちゃ)を取りのぞき、相手の注意をひいて、骨太なストーリーを語る」
そのための準備が相当な時間がいる。
逆に言うと、伝わらない資料を作るぐらいなら、メモで良いのかもしれない。
改めて自分の資料作りを振り返ってしまった。
Posted by ブクログ
1章 コンテキストを理解する
・探索的分析と説明的分析を分ける必要がある。
・伝える相手、なにを(相手に)してもらうための資料か
どのようにアクションをしてもらいたいか
2章 いろいろなグラフの伝え方を紹介されている。
・伝えたい内容によって使うグラフ、テキストを選ぶことが大事。
・さらに事実をすべてバカ正直に全部出すことが大事なのではなく伝えたいことによって表現を変える、強調することが大事。
必要なければ消してしまうこともOK
・第二縦軸は使わない。別の表現を考える。
本では2つの代替案を紹介。
3章 不必要なものを取り除く
・認知負荷を減らす
・グラフは境界線や背景船がなくても成立する
・中央揃いのテキストはなるべく避ける
・テキスト、図形などは斜めに配置してはならない
・ホワイトスペースを大事にしよう
4章 相手の注意をひきつける
・色で目立つ。ただし強調すべきは、絞って強調すること
・正の数字に青、負の数字にオレンジを当てる。強調すべきでないところはグレー(または黒)
・配置に気をつける。重要なことは左上、->右上->左下->右下
5章 デザイナーのように考える
・強調の全体の10%以下が望ましい。
・文字で強調させる手法として太字、イタリック、下線があるが太字がのぞましい
・書体は統一すること
・反転はやめること(背景を黒に白字など)
・色は効果的に使うこと、サイズを変えることは効果的
・全ての情報が重要ではない、残す必要があるが重要ではない場合などはグレー表示などで意識的に
目立させない。
・専門用語は避ける。使う場合は脚注を入れる。
・タイトルに結論を書く(相手に理解してほしいこと)
6章 モデルケースを分解する
7章 ストーリーを伝える
ストーリーが大事
・三部構成にする(始まり、中間、終わり)
・水平ロジック(エグゼクティブサマリー)
垂直ロジック(伝えたいことの全て)、
逆ストーリーボード(振り返り・まとめ)
第三者の目(他者の評価)
8章 さあ、全体をまとめよう
具体例をあげながらグラフを改良していく工程を紹介
9章 ケーススタディ
スパゲッティグラフの回避方法
円グラフの代替案が参考になった
Posted by ブクログ
データビジュアリゼーションに焦点を絞った一冊。データ分析の仕事を普段する中で、どのようにすればわかりやすいグラフが作れるか、どのようにコミュニケーションすればより伝わるかは課題となって現れやすいです。無意識的視覚情報や情報に差をつけるなどためになることがたくさん学べました。
データアナリスト以外の人もぜひ読んでみてほしいです。
Posted by ブクログ
本自体が読みやすく説得力がある。モデルケースもありとても良い。ゲシュタルトの法則と、アフォーダンスの利用は意識したい。書きたいものを書くのじゃなくて、相手にしてもらいたいものの手段として書く。ストーリこそが最重要。
Posted by ブクログ
Google内で「ビジュアライゼーション講座」を担当していた著者によるGoogle流資料作成。コンテキストを理解し意図をシンプルかつ明確にしデザインしてストーリーを伝える。秘伝の奥義や高度な技術は一切なく、王道かつ基本に忠実な資料作成の手順が豊富な実例を持って解説されており分かり易い。
Posted by ブクログ
データの見せ方として重要かつ基本的な内容がまとまっていて良かった。パワポを使うビジネスパーソンやデータアナリストやデータサイエンティストなどデータを扱う人であれば共通知識として持っておけると良い内容だなと思う。
Posted by ブクログ
タイトル通り、資料(特にスライド)を作成するための本。
グラフを印象的かつ正しく用いるための方法論がこれ一冊で学べる。
しかし、本書はマニュアル本ではないため、当たり前だが具体的なグラフの作り方は書かれていない。
そのため、自分でいざ作ろうと思うと追加で勉強が必要。
また、スライドのデザインや配色についての言及は少ない。
そういったことを学びたい方は、「Slide:ology」を読むと良いかもしれない。
自分の作ったグラフがパッとしない時は、本書の美しいグラフを眺めれば改善点が見つかること間違いなし。
Posted by ブクログ
資料作成には、表面的な見た目の美しさではなく、誰に何をさせたいために資料を作るのかを明確にしてからその目的に沿ったものを作る必要があることがわかった。
もちろん、見た目的な改善テクニックも紹介されている。
事例が少ないかなとも思うが、本書で紹介されている論評サイトなどを閲覧してあとは資料作成スキルの取得を自走しながらやりなさいということなのだろう。
Posted by ブクログ
資料作成にストーリーテリンクが必要であることが分かりやすく紹介されている。
とても参考になるとともに、過去に作成した資料がダメな作りだったと恥ずかしくなる。
Posted by ブクログ
資料作成にあたって、ストーリーを考えることが大切
その資料のどこに注目してほしいのか、どう読み取ってほしいのか、資料を見せることで相手にどう行動してほしいのかを想定することでいい資料が作成することができる
Posted by ブクログ
資料作成のヒントについての本。
googleという言葉に過剰になる必要はないが、本質的に重要なことを記載しており、たいへん参考になる一冊。
引算の美学を述べてくれているように思う。
<メモ>
・データを飾りすぎない。メッセージに集中する。シンプルさはセクシーさに勝つ。
・データをつかってストーリーを語るために
1コンテキストを理解する
2相手に伝わりやすい表現を選ぶ
3不必要な要素を取り除く
4相手の注意を引きつける
5デザイナーのように考える
6ストーリーを伝える
・コンテキストを理解するための質問
背景にあるどんな情報が重要か。意思決定者は誰か、メッセージに対する先入観はあるか。ストーリーを強化するために使えるデータはどのようなものがあるか。相手はそのデータを見たことがあるのか、どのようなリスクがあるか、どうなれば成功と言えるのか、限られた時間しかない場合何を伝えるか
・ビッグアイデアが持つ3つの要素
1あなた独自の視点を明確にしている
2何が危機にさらされているかを伝えている
3完全な文章である
・何を相手に知ってもらう必要があるかを考えて、それを明確に表現する。
・色は控えめに使うこと。
・アフォーダンス 重要なものを強調する 気を散らすものをなくす、情報に明確な視覚的階層を作る
・図表を過度に複雑に見せないためのヒント
読みやすくする 整理する 簡単な言葉を使用する 不必要に複雑な情報は取り除く
・優れたデザインがデータ表現を改善する具体例
1色使いを工夫する 2配置に注意を払う 3空白を活用する
・魅力的な物語を書く7つの秘訣
1あなたが本当に関心を持てるテーマを見つける
2長々とおしゃべりしてはいけません
3シンプルを心がけましょう
4減らす勇気を持ちましょう
5自分らしくありましょう
6きちんと伝えましょう
7読者に配慮しましょう
・不必要な要素を取り除く例
グラフの囲みをとる
グリッド線を削除する
データマーカーを削除する
軸ラベルを整理する
データに直接ラベルをつける
類似色の活用
Posted by ブクログ
自分の目がはっと覚まされた一冊。
資料作成には、データビジュアライゼーションとストーリーテリングの2つがあるとして、その解説が詳細にわかりやすく記されている。
今まで、Excelのデフォルト設定のグラフを使用していて疑問すら持たなかった自分が恥ずかしい。常識を覆された気がする。
ストーリーテリングの方については、ちょっと概念的過ぎて頭に入ってこなかった部分もある。
これからは資料作成する際の自分の目線がきっと変わっていることだろう。あとは時間との勝負(笑)
それにしても、ハーバード流、マッキンゼー流ときて、今度はグーグル流ということなのだろうか?
Posted by ブクログ
4/8
グラフの枠は無くす
色を多用しない
見せたいものに色づけし、残りはグレースケール
質問は最後に、まずは話をしましょう、書き留めておいて
最初に結論とその経緯を書いておく
内容
経緯
結論
よくないグラフの例を良くする練習
Posted by ブクログ
訓練が必要。
1.コンテキストを理解する
2.相手に伝わりやすい表現を選ぶ
◯テキストも活用する
◯表は読み物として。罫線は最小限に。ヒートマップは読み物のサポートになる
◯散布図は補助線。折れ線グラフで平均を表示。スロープグラフは一線のみ強調。棒グラフは基準線をゼロ(横棒グラフは読みやすい)
☆円グラフは不必要
・3Dも不要
◯第二縦軸→直接ラベル付け、縦軸を分けるで代替
3.不必要な要素を取りのぞく
◯視覚認知のゲシュタルトの法則
近接、類似、囲み、閉合、連続性、接続でクラスターを減らす
◯整列とホワイトスペース
・中央揃えから左揃え
・斜体は避ける
4.相手の注意をひきつける
◯無意識的視覚情報
・情報に視覚的優先順位をつける。色彩のコントラスト、ただし控えめに使う
◯Z型に読むことを配慮する
5.デザイナーのように考える
◯アクションタイトルと説明を追加する
6.ストーリーを伝える
◯始まり、ひねり、結末の三幕構成