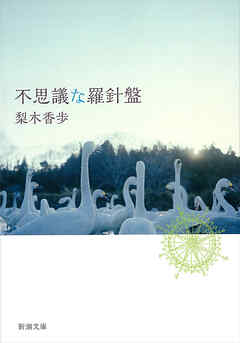感情タグBEST3
Posted by ブクログ
梨木さんのエッセイは、深く、また思い至らないところまで広く。
読んでいて、なぜか深い安心感を感じる。
目にする草花にも
「ひっそりとある、という風情が好きなのだった。自分を強く主張することもない、他の植物の陰になっていても自分が犠牲になっているなんて思わない、淡々と自分を生き切る、そういう日常の満ち足り方。だから華やかな他の花のように周囲に自分を誇る必要もない。」
と、その在り方に、生き方の美しさを見出す。
人との付き合い方、ものの見方についても
あぁ、自分はまだまだ浅いなぁ、
たくさんのことを知り、深く考えねばなぁ
と反省もさせられるが、
そのままでも良い、と受け入れられているような心地にもなる。
深くものを思う、静かにものを見ることの大切さを思い知らされる。
Posted by ブクログ
樹木・草花であれ、ものであれ、人であれ、ひとたび対象に向かうと、五感をフル稼働させて、大切なものを得ようとひたむきな梨木香歩さん。頼るもののあるときは頼り、支えのないときは一人で立つ生き方。植物や鳥たちとの付き合いが人との距離の取り方を教えてくれる。梨木香歩さん「不思議な羅針盤」、2015.10発行。読んでてほっとする28のエッセイ集。エッセイというより、詩情の浪漫を感じます。
Posted by ブクログ
初めて読ませていただきましたがしっかりした人。いかに植物を愛し真面目に生きてらしているようすがありありと解りました。個人的に参考になったのは人との距離の取り方かな
Posted by ブクログ
梨木香歩の不思議な羅針盤を読みました。
婦人誌に連載されていたエッセイ集でした。
草木や動物たちに向き合う姿勢、庭に生えた草や木の実の料理についての話、友人や通りすがりの人とのつながりかたなど、面白く新しい発見のある内容でした。
杉浦日向子さんのご隠居さんの話題は面白く読みました。
konnokもご隠居さんと呼ばれる年齢になったけど、ご隠居さんのようなおおらかさも人間性も全然ないよなあ、と思いながら読みました。
Posted by ブクログ
2007年から2009年までの三年間、雑誌「ミセス」に連載されたエッセイ集。
随所に梨木さんらしさが出ている。
動植物
への深い知識、人間としての大きさ、深い愛情。。
特に最後の「どんぐりとカラスと暗闇」は梨木さんの思いが詰まっている。
この本もまたずっと一緒にいたい一冊になりました。
最近 良い本ばかりに巡り合い、とても充実しているように思います。
Posted by ブクログ
自粛生活に伴い実家から送ってもらった本の中から再読。以前はいつ読んだか思い出せない。
エッセイ本嫌いの私が、なぜかこの著者のエッセイ本だけは夢中になって読んでしまう。
2007年から3年間雑誌に連載していた短編を集めた本だが、社会が少しずつきな臭くなっていく流れを危惧する言葉も並んでいる。2020年の今読み直してもリアルタイムで感じている心の靄を共有できる。今同じように社会がきな臭くなってきたわけではなく、この頃から少しずつ少しずつ、首を傾げてしまうような変化が続いているんだと思う。そして著者の描く他人との距離感は、今の社会情勢だからこそ一読の価値があると思う。
この本の記憶は、狭い世界で豊かに生きる翻訳家「片山廣子」さんの話が強く残っていたけれど、改めて読むと一話一話が美しく、時に3章の話は今の自分の胸に刺さる内容だった。著者の他人との距離の取り方は潔く心地良く、芯の通った凛とした佇まいが文面から伝わってくる。マイノリティを受け入れる姿勢(これは著者が留学していた英国での影響が大きいことが別のエッセイ本「春になったら莓を摘みに」から伺える)と、自分という人間を過去から現在まで客観的に見つめ、自分が好きなものへの造詣が深い。著者のエッセイ本だけは夢中になって読むことが出来るのは日本語の美しさだけでなく、その姿勢への憧れと視座への尊敬があるからだと思う。
私もこんな風に、ぶれずに肩ひじ張らずに、自分という人間と自分の生きる人生を潔く楽しめる人になりたい。
Posted by ブクログ
梨木香歩さん作品、高校生のときからずっと読んでます。
エッセイも大好きで、自分の足元がぐらついたときに読むとちゃんと心地いい場所に戻ってこれる感じがします。
植物に詳しくないので、わからないときもありますが、草花や動物への眼差しが好きです。
透明な感じがして。
Posted by ブクログ
梨木さんのエッセイ集。梨木さんの物語はいつも静かに思想を放っていて好きなのだけど。エッセイでは逆に思いの丈を語り尽くすスタイルになっていて、それがまた自分の対外的なものに対しての漠然とした不満を代弁してくれたような快感がある。ふと目撃した物事から社会、文化の問題点に想いを馳せる想像力の飛翔が素晴らしい。
Posted by ブクログ
先日読んだ本『金曜日の本屋さん』の中で、梨木さんの文章が「文字に色がついているみたい」とありこのエッセイ集を読んだ。
ほんとその通り!
何気ない日常のあれこれについて、梨木さん目線で描かれてあり、五感を大いに刺激された。
野に咲く貝母やスミレを「彼女」と親しみを込めて呼んだり、カラスとも意志疎通したりと自然や生き物に対して丁寧に接する姿勢が伺われた。
中でも「シロクマはハワイで生きる必要はない」「百パーセント、ここにいる」は心に突き刺さり涙が出た。
私にとって刺激されたり感心したりしながら、進むべき道を指し示す「羅針盤」となった。
Posted by ブクログ
雑誌『ミセス』に連載されたものだそうです。梨木さんの穏やかで芯の強いお姿がぎゅっと詰まっています。いろいろ大変な世の中でも、ため息つきながら、くすっと笑いながらくっきりと生きている感じ。憧れます。
Posted by ブクログ
初読。梨木香歩さんらしさがぎゅっとつまったエッセイ。エッセイなのに、なぜか涙腺を刺激する。梨木さんの本を読むと、丁寧にゆっくりと生きていくことの大切さをしみじみと感じ、自分の生活を見直して姿勢を正そうという気持ちになる。でもいつも実践できないままなんだけど。それでも梨木さんの存在と、梨木さんの書く作品の存在が、私の人生のどこか知らない深いところで拠り所になっている。
Posted by ブクログ
まだ読み途中だけど、今まで読んだエッセーの中で一番好き。忙しい毎日の中で、生きることの基本というか、原点に気付ける本。それこそ羅針盤、という言葉がぴったり。心が洗われる。丁寧に生きようと思う。
Posted by ブクログ
梨木香歩のエッセイは、じっくりと噛みしめるように読みます。決して読み難い訳ではないのですが、一言一言が重みをもっているので、しっかりと受け取らないと取り落としてしまいそうなのです。
対象物へ目や耳や心をしっかと向けて受け取ったものを、文章にのせて読み手の元へと届けてくれます。植物や動物たちに向ける目も人に向ける目と同じように、いや言葉をもたない相手だからそれ以上に真摯な心持ちがあります。植物に対して「彼女」と呼びかけるけれど、安易に同化するのでなく距離をおくべきところは距離をおく。それが敬意にも愛情にも繋がっているように感じられます。
婦人誌に掲載されていたということもあるのか、他のエッセイよりも作者との距離が近く感じられます。お茶のお供には少し歯ごたえが強いかもしれませんが、作者と空気感を共にすることの贅沢さにひたれます。
Posted by ブクログ
やっぱり素敵な方だなあと思う。
この人の感覚を感受性を見習いたい、といつも思わせてくださる。
スケールを小さくする、というお話。
はっとさせられた。広くを見ようとして細部に追いつかない、ではないけれど、人間関係とか行動範囲とか身の回りのいろいろなことに通ずる。
他にもはっと、もしくは普段何気なく過ぎることに改めて目を置く気持ちになる。
『夜中にジャムを煮る』が新たに気になりました。引用されている文は梨木さんの感想も含め、目の前にまざまざとその光景が見出され、食べたくなりました。
Posted by ブクログ
いるかさんの本棚で見つけました
梨木果歩さん
濁りのないその目差しにとても憧れる
だけど遠いなあ
だけどとても近く感じる
ふとした動植物、土や風景、人、食べ物にに注がれる見識と愛情が素敵だ
やっぱ遠いなあ
澄み切った秋空のようなエッセイ集でした
≪ 生きていく その羅針盤 すぐそこに ≫
Posted by ブクログ
この本は2010年刊行。人との繋がり、時を満たすことの大切さ・・・コロナ禍にこの本を読む事は、何とも胸が苦しくなるが力づけられる読書ともなった。人と触れ合える時を取り戻してから必ず再読したい。
Posted by ブクログ
梨木香歩(1959年~)氏は、鹿児島県出身、同志社大学卒の児童文学作家、小説家。児童文学関連はじめ、多数の文学賞を受賞している。
本書は、月刊誌「ミセス」に「不思議な羅針盤」として2007~2009年に連載された28篇のエッセイをまとめて2010年に出版され、2019年に文庫化された。
私は、ノンフィクションを好み、小説をあまり読まないため、これまで残念ながら著者の作品に目が留まることはなかったのだが、小川洋子のエッセイ集『とにかく、散歩いたしましょう』を読んだ際に、その中で著者の『渡りの足跡』から引用していた一節に惹かれ、本書を初めて手に取った。
エッセイ集については(当然ノンフィクションなので)、これまで、須賀敦子、白洲正子、藤原正彦、沢木耕太郎、藤原新也、内田洋子、最相葉月、福岡伸一、吉田修一、穂村弘、ジェーン・スー、石川直樹など、幅広い分野の書き手による、硬軟様々なものを読んできたが、書き手の物事の捉え方・考え方、人となりが如実に表れており、とても面白い。
本書に収められた28篇のエッセイのタイトルは、「堅実で、美しい」、「たおやかで、へこたれない」、「ゆるやかにつながる」、「みんな本物」、「世界は生きている」、「「野生」と付き合う」、「夢と付き合う」、「「アク」のこと」、「百パーセント、ここにいる」、「「いいもの」と「悪いもの」」、「変えていく、変わっていく」などとなっており、いずれも、著者の造詣が深い鳥たちや草木のほか、身の回りにあるものや日常の出来事に託して、それらのテーマが綴られている。
例えば、以下のような印象に残る記述がある。
◆「煮詰まった人間関係は、当人がどんなにがんばっても容易なことでは動かない。よく、自分が変われば他人も変わる、というけれど、今の世の中ではそういう法則も働かないことがある。あまりにも複雑な要因が絡んでいるから。「シロクマはハワイで生きる必要はない」・・・」
◆「倫理的でありたい、と願う気持ちと、自分は倫理的である、と自負する気持ちは別ものだ。倫理的でありたい、と願いつつ、それができないことを自覚する人の方が、なんだか「いいもの」のように思えるのはなぜだろう。」
巻末の解説で臨床心理士の平木典子氏は、「読後にはある種の透明感が残る」と書いているが、小雨の降る午後や、静謐な夜に、ひとりで落ち着いて読みたくなるような一冊である。
(2021年5月了)
Posted by ブクログ
タイトルは素敵だが、テーマは「人との距離感」だと思う。少しちぐはぐ。
植物や鳥の名前に造詣が深く、『赤毛のアン』が大好きなんだなぁと思う。ナビを彼女と読んでいる表現なんかは面白い。
ただ授乳中の母親が携帯電話をいじることに批判的な表現は不快だった。傍目の美しさはないかもしれないが、授乳は子供を育てているだけで見せ物ではない。聖母像でも求めているのか、だまらっしゃいと思ってしまう。
Posted by ブクログ
植物にあまり詳しくない私は、度々名前を検索して画像を見ながら読むこともあったけれど、
それでも楽しめるくらい、話の流れが良い。
素敵なエッセイだった。
Posted by ブクログ
おお、文庫になった!よかった!と購入。
単行本が文化出版局だったので、
文庫にはなんないだろーなーっと諦めていたので嬉しい誤算
ありがとう、新潮社さん。
再読。
やはりプラスチック膜のおはなしが一番好き。
今回再読してみて前回は特に思わなかったのだけれど、人というのは群れで生きるものだから、という文脈の中でいろいろ語られていることが多かったように感じた。
梨木さんと群れ、というものがどこかそぐわないイメージもあったりしたのだけれど、よく読むと、鳥や植物だけでなく、人との関わりも多い人なんだなーっと。
一番親近感を抱いたのは車をめったに洗わない、という一文だったりする。
まあ、それでも気になってくると私はついつい洗ってしまうんだが。
ほどよい距離感のある居心地のいい群れ。
それをどうにか見つけたいのだけれど、なかなか。
結局本の中に安住してしまうのだよなあ。
このめんどくさがりをどうにかせねば。
もっと生きることに丁寧にならねばなあ、とぼんやり思う。
Posted by ブクログ
梨木さんの日常のエッセイ集。
ところどころに動植物へ注がれる鋭くも優しい視線に、彼女のほかのエッセイを思い出します。(「渡りの足跡」が好きですので)
このエッセイを書かれた時が「自己責任」という言葉が出始めて、日本が息苦しい時代へと移りかわっていったことが書かれていますが、今、私は国そのものが過呼吸を起こしているような気がしてならない。
白か、黒か、すべてをはっきりとさせる必要とは何なのだろうか? エッセイを読みながら考えた。
曖昧模糊したものがいけないとは私にも思えない。そこにしか出せない答えがあるはずなのだが…。
透き通るような美しいものだけではないことが描かれている深いエッセイだった。
Posted by ブクログ
いつもの著者らしい、自然への敬意を丁寧な表現で紡いでいる静かな本。
この方らしさなのだろうが、
ちょくちょく政治的嗜好を物語に絡めるのは私は好きではない。
せっかくの美しく、清らかで静かな自然のお話が一気に泥臭くなり、物語の透明感が失われる。
せっかくの貴重な『静かな本』をしみじみ静かに味わいたいというのが本音。
Posted by ブクログ
「ウド仕事」のくだりが印象的。
ウドは下処理が大変だけど、それをしている時間が落ち着くらしい。
食材の音や調理の匂い、こっそりつまみ食いする楽しみは料理をする人だけのもので、食べるだけの人に対して申し訳なくなる、と。
めんどくさい、めんどくさいと思いながらする毎日の料理時間に、ちょっとだけ光を灯すフレーズだ。
日常生活は便利になっているはずなのに、私たちの時間は刻みに刻まれ各タスクにとられていく。
私が料理の時間がめんどくさいのは、その時間に寝たりテレビ見たりしたいと思っちゃうからなのだ。感覚がすっかりマヒしていて、他の何かに機嫌をとってもらわないと楽しくなれないのかもしれない。
でも料理のような自分とその家族が生きていくための作業にこういう小さな幸せを見出すことができたら、毎日をもう少しご機嫌に過ごせるかもしれない。
Posted by ブクログ
日常生活から去来する様々な思いを綴っているエッセイ。良くも悪くも全然関係ないことに思考が飛んで行っていたり、スピリチュアルっぽい話にもなっていっていたりしたのが気になった。作者のことが大好きならそれでもいいのだろうが、読んでいて「それはちょっと無理やりすぎでは…」「どうでもいいな…」と思うところもしばしば。
けれど共感できるようなところもあったり。これがエッセイの醍醐味なのかな。
複数の小説と併読していたので、それにはちょうど良かった。
Posted by ブクログ
このエッセイが掲載されたのが2007年から2009年。
10年近くの月日が経って読むエッセイ集なのに古臭さが無い内容でした。
しかし、すべてが新しく新鮮というわけでなく、「変わらないもの」と「変わった(変わってしまった)もの」があり、「変わらないもの」は「変わらないもの」として、生き方のちょっとした参考になったり、日々引っかかっていた小さな事柄とからんで賛同できたり、「変わったもの」もただ古いわけじゃない感覚があったりと、劇的な何かがある内容じゃないけれど、穏やかな気分になれる一冊でした。
植物の話や日常の風景(愛犬との共闘は笑ってしまった……)、虫や動物の生態・本能、人としての在り方・考え方が、自分には無い視点で時々怖くも感じるけど、ついつい読んでしまう魅力があります。
Posted by ブクログ
大きな声で怒ったり、誰かを攻撃したりするのではなく、静かに、でも自分の考えをしっかり持って、あらゆるものをきちんと見つめようとしている人って素敵だ。
Posted by ブクログ
程よい距離感。
梨木さんの文章は主張しない。
何かに憤慨しても心動かされても
それをそれとして
まるで自分のことも含めて
傍らで観察しているような気配。
何ものにも染まず染まらず。
彼女の小説が放つ強い存在感の正体は
彼女のエッセイ集を読み重ねているうちに
少しずつ分かり始めたような気がする。
ご自分の中に生まれる感情や思いを
ごく自然にこぼれ落ちる言葉に
何の違和感もなく託しているのだろう。
不自然も気負いも恣意もない
ただ言葉にしたいだけのこと。
そこに特定のベクトルが あらかじめ
用意されてからの言葉ではないので
無色透明の清々しさがあるのだろう。
だから 私たち読み手が
そんな梨木さんの小説に心動くのは
梨木さんの内面に感応するものが
私たちの中に最初からあるからなのだと
信じたい。
そんな自分なら 好きでいられる。
自然と生き物に触れる言葉は
慈愛…と呼びたくなるような
とびきりの優しさに守られて
私の心にちゃんと届く。
それが うれしい。