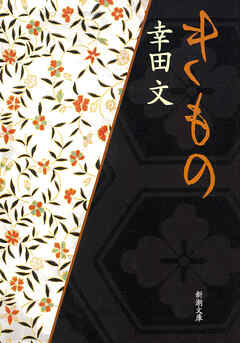感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ルツ子の気の強さや負けん気な子ども時代から姉の行動をみて繊細な心も持ち合わせている。
近所の人からは不幸な子と思われていたみたいだが本人はそうとらえてはいないところからも負けん気があふれている。それを祖母はルツ子の性格から先回りして助言、手助けしてたしなみを教えていた。祖母の言葉は今の自分にも当てはめれて、重さを感じる。
他の作家の暗さがない自伝でこの人のを集めればよかった。
と思うのはまだ一冊しか読んでないからかも知れないが。。
Posted by ブクログ
めっちゃ面白かった!!!!
びっっくりした!
昔の人ってこうだったんだ・・・
手に取るようにわかる
噂には聞いていたあの話、この話、
細かい着物の描写は、どんな生地なのかとかわからなかったりするけど、
だから運針を学校で習ったんだな、
命からがらって関東大震災はこんなだったんだな、
地域が助け合って暮らしていた頃ってこうだったんだな、
日本の良さ、感じられました。感動!
大事にしたい本。
Posted by ブクログ
着心地重視の主人公に完全にシンクロしながら読みました。肌触りがいいとその日1日気持ちよく過ごせるのすごくわかる。
おばあさんの生活の知恵、特に着物の含蓄にうなずきまくりました。木綿、毛織、銘仙、絹、いつどの素材を着るか何故その着物なのか全部理に適ってる。縮緬のお布団ってそんなに寝心地いいのかな、寝てみたい。
少し昔の小説なので読んでてエーッてなるとこいっぱいあるし震災描写は悲しくなりましたけど、当時の文化や流行とか着物を生活品として作る人や着る人の考えることに触れられてよい読書時間になりました。自伝も入っててリアリティ色も強め。
終わりが唐突なのは連載が止まったためだそうで、続き読んでみたかったです。なんとなく想像はできますけどね…。
Posted by ブクログ
主人公の子供時代から結婚するまでの人生の歩みを、着るもの、身につけるもののエピソードをふんだんにちりばめて書かれた小説です。
きかん気が強く、気に入らないことは絶対に受け付けない性質の主人公の子供時代から物語が始まります。姉たちにはからかわれ、親にも持て余されがちな主人公。そして、そんな主人公にじっと寄り添い、気を回す祖母が物語の中心です。
登場人物が魅力的で、癇気の強い主人公、人間の良くできた祖母、どこか対照的な二人の姉、女学校でのふたりの友人、そして父の愛人など、皆それぞれの強さと考え方を持って生きていました。どの女性の半生でも物語が書けると思えるほどです。
ただし、男性の登場人物は父を除いて詳しく描かれていません。兄は途中まで完全に存在を忘れていましたし、夫となる人も人となりを想像するには材料が少ない、といった感じでした。
主人公が初めて自分で着物の生地を選びだす場面や、姉の結婚式に駆けつける場面、「もう着られないお気に入りの服で箪笥をいっぱいにしたい」と話し合う場面などが心に残っています。
人に何かあげるとき、病みついた家族を看るときなど、物事を角を立てずに進めていく祖母の知恵には、読みながら主人公と同じようにハッとさせられました。
この話は幸田文の自伝的小説だそうです。元は雑誌連載されていたもので筆者の存命中には書籍化されず、続きの構想があったようだと解説に書かれていました。
結婚式を挙げた日の夜でこの物語は終わってしまいます。しかし、決して幸せな結婚生活を予感させる文章ではなく、時代から考えても金融恐慌を経て、開戦、東京大空襲、敗戦と、決して先行き明るくはありません。その中で主人公や周りの人、特に二人の姉がどう生き抜いていったのか、読んでみたかった。続編がないことが本当に悔しく思われます。
Posted by ブクログ
登場人物の語り口調がぽんぽんと軽快で、するすると読めてしまう。東京の下町の口調はきっと実際耳にしても私にはついていけないだろう…。
三姉妹(+兄)の末っ子の半生は、進路の悩みや性格の悩み、家族との葛藤など女性なら共感できる部分も多かった。
祖母からいろいろなことを教えてもらい生活のなかの知恵を得ていくのだが、こうした世代を超えて受け継がれていく口伝、女の知恵というものが昔は当たり前に存在していたのだろう。
Posted by ブクログ
女性の生活目線でのお話が好きです。いろんな着物の柄や素材の名称が出てきて、登場人物たちのこだわり方の表現に、時代を超えて女の私は読んでいてウキウキしました。
随分前に読んだので、感想が朧げですが、また時間があるときに読みたいな。女の人って、強いなぁと思った記憶があります。
Posted by ブクログ
日常生活からこんなにも多くのことが学べるのかと驚嘆した。大正時代の話で、人間の品位みたいなものを感じ取っていく主人公が素敵。好きなものは好き、嫌いなものは嫌いという態度も好き。おばあさんが主人公に対して、日常での出来事が意味するもの、各種ハレの舞台での振舞い方、人との接し方等を教えていく。それは主人公に対し手でだけではなく、私にとっても有意義なものであった。続きが気になる作品。
Posted by ブクログ
できれば続きを読みたかったです。ここに登場するおばあさんの「かわいい腰紐をつかってほしい。」という言葉がなんだか印象的で私もそうありたいと思いました。着物話にとどまらず、ここにでてくるお婆さんは素晴らしい事を伝えてくれます。。
人に物を送るとき不用品を送っていながら、親切した気でいる事をとがめるシーンがありましたが、こういう今、人多いのですよ。
Posted by ブクログ
着る、ということについて
深く考えさせられた。
おばあさんが、るつ子に教えること、
戒めることは、
女性が美しく生きるために大切なこと。
着ることも、疎かにせず、
きちんと考えて向き合うことが
生き方に、すっと一本筋が通る気がする。
気になる部分(それはたくさん)を
折り、何度も読み返したくなる
大切な一冊になった。
Posted by ブクログ
読み進みながら主人公るつ子は幸田文と重なって思えました。女学校から結婚までの子供から大人になるまで、姉の結婚、母の死、震災を経て少しずつ変わってゆく、るつ子が幸田文の文章で生き生きと描かれていました。
るつ子は、新しい木綿をきりりと着た。無骨な木綿が身を包むと、それでやっと、いくぶん誇りと自身がもてる。
Posted by ブクログ
2015.11.9
昔の女の人の物語が読みたかった。
着物に関する用語がわからないから、調べながら読んだ。その当時は誰でも知ってるような当たり前のことが、わからない。当たり前は移り変わっていく。その当時の生活のこまごまに対する考え方や心遣い、今より丁寧な印象を受けた。丁寧だけど、ちょっと面倒くさいかなとも。女の人の生き方の当たり前も本当に変わってきたのだのと思った。
Posted by ブクログ
るつ子、みつ子、朝霞ゆう子など、名前がかわいいというか、名前からキャラクターがにじみ出てる。例えば和子とゆう子の名前がもし逆だったなら、なんだか違和感。べつに和子をバカにしてるわけではない、たぶん。
あとお気に入りの古風な?表現
・ふっくら人間が炊き上がる
・ねっちりと腹を立てる
・大福はわずかに白い取粉を落として…貧しさがちんまりと手のひらに落ち着いていた
Posted by ブクログ
この作品を読んで、幸田文さんが好きになりました。
だいぶ前に読んだ本なので内容はうろ覚えですが、雰囲気はとても良く覚えています。
いつか読み返そうっと。
Posted by ブクログ
一度目は高校2年の時。その時はただ読んだだけに終わり、内容もそんなに残らずに終わった。
二度目は23の歳。全く違った。全て自分にはない体験ではあるのだけれど、だけれど何と言うのだろう、書かれている内容が全部染み込んでいった感じ。共感?すごく、「よくわかる」のような気分で読んでいた気がする。恐らくるつちゃんの生きた時間と同じだけ時間を経た分の理解がそこにあったのかもしれない。
自分は、女の子に本を勧めるとしたら、この本を同じようなタイミングで二度読みすることを勧めたいと思っている。下手な道徳よりも考えること思い当たることがあるし、こうすることで、この本の記憶がより鮮烈な体験となる。
Posted by ブクログ
現代人、いや私には理解できない着物の肌感覚。今の洋服にそこまでの感覚を持って洋服をきていないなぁと感じる。色、柄、触感。どれも大切なことなのに、おろそかにしている自分を感じた。
着物を通じて、主人公は成長をしていく。いや、成長を通して着物について深く考えていく主人公。それは女子なら通る道ではあるだけれど、着物というものを通してみていくと時代感覚もあって、理解できるけど今はない、奥ゆかしい女子の成長が描かれていた。
祖母の存在の大きさ。これは現代には薄くなってしまったな。祖母のいうことがいちいち含蓄を含んでいて、また主人公を深く理解していることが伝わってくる。身近な人の話を聴くことの大切さを改めて考えた。
震災の打撃。震災によってみえてくるもの。今だからこそ、この場面が真実味をもって見えてくる。
最初は着物の感覚が鋭すぎて、感覚についていけなかったが、後半に入って俄然面白くなった。
これは男性にはなかなか理解できない小説なんじゃないかと思った。
Posted by ブクログ
名作なんだろうが、小公女とか灰かぶり姫とか、文学少女が好きな童謡を下敷きにされているのではと思うほど、主人公が辛らつな目に遭っていく。
幼い頃は着物に対する美意識がとにかく高くきかん気で、高いものねだりをするヒロイン。末っ子の我がままかと思うが、長ずるにしたがい、気位の高い長女、金に賢しい次女に、奴隷のように扱われる。「鬼龍院花子の生涯」みたいに。
女学校在学中に母が倒れ看病に疲れ、父のかつての浮気相手(?)も登場し、母の葬儀では姉ふくめた親類の酷さを見つけ、震災で焼け出されたあとで就職したものの、父の反対を押し切って結婚する。が、どうも不幸の影が付きまとったような終わり方。
遺作なので半端に切れたようだが、物わかりのいい祖母や苦学生の友人・和子の存在感だけが光り、あまり後味のいい話ではない。ただ着物の美学や当時の女性の感じ方を知るにはうってつけの教材かもしれない。
しかし、子どもだてらに下着をひけらかしたり、痴漢が出たり、初夜がなまめかしかったり。タイトルから品の良さを勝手に期待していたのでびっくりした。
自伝的小説らしいが、父も幸田露伴がモデルなのだろうか。
Posted by ブクログ
もう女性のバイブルという言葉は
会わないだろうが、
随所に学べる箇所がある。
こういう時は、こう考えろ。
こうなったら、こうしろ。
と粋でかっこいいおばあさまが
教えてくれる。
着物もたくさん出て来て、
詳しくないながらも、
興味深い。
るつ子に共感しすぎてしまって、
上の姉が疎ましくてならないし、
最後は、これは全くなんという終わり方だと
思ってしまった。
主人公と一緒に、
スカッとして、モヤモヤして、
学んで成長させてもらえる本。
Posted by ブクログ
見せ場や晴れの場ではなく、きものが生活に密着した体の一部だった時代に触れる事ができました。裏読みすると家族への複雑な心境と疎外感、兄がいかにも想像の産物で浮いた存在に見えてしまう点に、他の小説作品にも増して著者自身の経験と願望が大きく反映されているように思えます。るつ子とおばあさんは幸田文本人というくらいの投影ぶりではないでしょうか。若かった頃と、年輪を重ねた執筆時の自分自身の対話。そんなように映るシーンもありました。震災の場面にはつらい記憶もよみがえりましたが、和の装いと心意気に憧れたくなる作品でした。
Posted by ブクログ
おなじ表現がでてこない。
そのことに感嘆。
物語としては完結?と首捻りしてしまったが、
とちゅうとちゅうの時代に沿ったできごとや、
家族の変遷、それぞれの登場人物の個性、綿密でとても真実味深く、ときに苛立ち、共感し、立腹し、はらはらした。
つまるところ、きもの、を通して、「まっとうな常識」を着ることを知ったのだろう。 なんてことを思った。
Posted by ブクログ
着物に造詣の深いことで知られる、幸田文さんの自伝的小説。
小説を楽しむためには、和服の知識(生地、柄、各部分の名称など)が多少問われるが、いつの時代も女というものは衣服にかけるこだわり、執着、執念が強いということは、伝わってきます。TPO、見栄え、着心地、それら全ての要素が納得のいく衣服に出会うというのは、こだわりが強ければ強いほど難しい。
昨夏、奮発して購入した緋色の浴衣、今年も袖を通して出かけたいです。
長女、次女、そして末っ子の主人公、三姉妹のそれぞれの結婚から、大正時代の結婚価値観も見えてきます。
Posted by ブクログ
るつ子の人生ときもののお話。
おばあちゃんがイキすぎて素敵。
イキと野暮ってこういうこと。
書いている時に幸田文は亡くなったので、若干続きは気になる遺作。
Posted by ブクログ
淡々と綴られる情景と、感情。
当時のきものそのものや作法を殆ど知らずに読んだので、るつ子と共におばあさんに躾られているような心持だった。
細やかな心配り、真心が伴ってこそ、装いや振舞いは美しくなるのだろう。
Posted by ブクログ
女にとって、着る物ってやっぱり大切ですよね。綺麗であればいいというわけじゃないし、TPOに合わせて、自分の気持ちに合わせて。お祖母さんの着物に対する考え方、生き方が素敵でるつちゃんが教わるように、私も一緒に教わった気がします。気になるのはるつ子の結婚のその後。結婚式当日からうまくいかなさそうな空気ですが、どうなるのでしょう?るつ子には幸せになってほしかったのにな。こんな大切な場面で意地っ張りな性格が出てしまったようで心配です。けっこう古い本だけど、読みやすく面白かったです。
Posted by ブクログ
★3.5。
これはいかにも未完というか未発表の作品という感じがする。
前半と後半の筋立てというか視点が若干ブレている感じがあり、タイトルに合わせる訳ではないですが、前半部は唸らされる読感ありです。
その点、後半はある意味の非日常をストーリーに据えてしまったので前半にあった緊張感というか異常とも言うべききものから来る揺れが曖昧になってしまったかなと。
Posted by ブクログ
きものを通して、相手の気持ちに配慮した格好とか、相手の立場、感じ方を考えての贈り物とか、人との交際の仕方を主人公のるつこが学んでいるのに、同じくなるほどと思わされた。
おばあさんがいいあじ出してる。こんなおばあさんがいてくれたらなぁ。そしてこんなおばあさんになりたい。
Posted by ブクログ
箱入りハードカバーを手に入れました。
大正末期の東京下町で両親、祖母、2人の姉と暮らするつ子の物語は清々しくて良かったし、装丁が素晴らしく、本そのものの魅力にも参りました。
Posted by ブクログ
着付けを習っているので手にとってみた。
いろいろな着物が出てくる。着物を中心に、主人公と姉二人、母や祖母との日々が描かれる。
慎ましくも力強い生活が、きちんとした日本語で綴られる。時にはこうした文章を読みたいと思う。