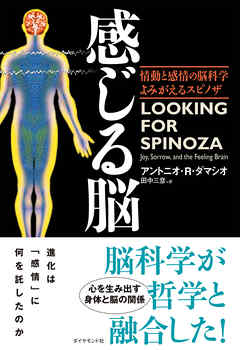感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ダマシオの「一般向け」脳科学書、とばして『自己が心にやってくる』を読んでしまったのだが、『無意識の脳』の次の本はこちらである。前著でやや中途半端に解説が終わっていた「情動・感情」が本作で中心的・徹底的に掘り下げられる。
原題はなんと「Looking for Spinoza」、「スピノザを探して」である。唐突なスピノザ。
そして、本書を読み始めると途中から、突然スピノザの伝記のような記述がはじまって面食らう。ダマシオをこれまで読んできた者には何か異様なものが感じられるだろう。そして本書の最後の方にも、スピノザの評伝のようなものが延々と続く箇所がある。
なぜスピノザか? 著者ダマシオは、あるとき不意にスピノザの本を読み返し、自分の思想とスピノザのそれとの共通点を発見したのだという。
スピノザ『エチカ』に見られる一文「人間の心は人間の身体の観念である」というのが、ダマシオの語る情動・感情の脳科学思想の帰結と重なるのである。ダマシオは「感情とは、ある特定の形で存在する身体の観念である」(P120)と書く。
また、スピノザが「自身を保存しようとする執拗な努力」としてコナトゥスに言及する部分は、ちょうどダマシオの強調するホメオスタシスの原理と符合する。
しかしスピノザについては、私はこれまで読んでもよく掌握しきれなかったように思うし、とりあえず置いておこう。
ダマシオは本書で、前著に続いて情動について詳しく書いている。そしてそれよりずっと難解な独特の概念「感情」について、これまでになく詳細に記述する。
情動とちがって「意識」を必須として成立する「感情」は、ダマシオによると、「特定の思考モードの知覚と、特定の主題をもつ思考の知覚とを伴う、特定の身体状態の知覚である。」(P121)
また、「感情は本質的に一つの観念(身体の観念)」である。(P125)
そして感情の内容とは、「マッピングされた特定の身体状態である。」(P124)
感情を知覚の一種であるとするこの定義は、なじみのものではなく、最初違和感が強かったものの、読み進めていく内になんとなく理解できたと思う。
前意識的に、あるいは反射的に発生する情動は、さらに別の情動を喚起し、また、同時に発生した別の情動などとも並行して作用し、それらの全体が、身体という域で結び合い、場合によっては相殺し合ってのちに、身体全体が「自己の状態」として示すイメージ、それの認識が「感情」となるのである。
そうした「感情」は、進化論上、比較的高度な、後からあらわれてきた機能であり、ダマシオによるとそれは有機体(人間)の生存と幸福の獲得・維持に役立つはずなのだ。
けれども、私たちの実感として、激情的なものはむしろ生存や「幸福な生活」を破壊する場合が多いし、「欝状態」は、たしかに自らが病的状態にあることを示す標識とはなるものの、そこから抜け出せずに陰々滅々としているならば、その感情は、果たして「生存」の役に立っているのだろうか? という疑問は残るように思った。
ダマシオの本は全部そうだが、本書も、結尾部分はあっけないほどオプティミスティックな、明るい、ちょっとステレオタイプな肯定的人生論で終わる。
本書ではスピノザを引きながら、負の感情を正のの感情へと置き換える処世術が述べられる箇所があるが、これは実際のところ、なかなか難しい。
ダマシオは情動・感情が専門分野なので、いわゆる「理性」的な頭脳の活動に関してはあまり書いていない。たとえば純粋に論理的な思考だとか、コンピュータのような演算処理だとかについては触れていないし、そういったものと「感情」との対比に関しては何も語っていない。
しかしダマシオが語っている「感情」とは、「自己感」にたちもどっているときの「知覚」「思考」なのであり、純粋論理だの数学的演算だのについては、「自己感」からまったく離れた思考機能として、区別されているのだろう。
数学ならともかく、とりわけ日常言語を用いた言説空間においては、人の思考にはいつも「感情」が伴っている。その感情とはつまり自己の身体の自意識なのだということを、本書は述べているということになるだろう。
スピノザについては、ダマシオの指摘を経由して再度読み返してみたくなった。
Posted by ブクログ
脳科学者であるアントニオ・ダマシオの著作。以前読んだ『無意識の脳 自己意識の脳』が、神経生理学や脳科学の最新研究を豊富な症例を含めて紹介していて、人間の「意識」についてかなり突っ込んだ議論をしていた刺激のある本だったので、少し高めの期待を持って読んでみました。ただ、少し期待をしたものとは違っていたというのが印象です。そもそも、タイトルの日本語の副題には引っ掛かっていたのですが、そこが違っていたのかもしれません。
原題は "Looking For Spinoza"なので、スピノザが副題といういよりも主題でそのタイトル通りなのですが、スピノザの業績やら当時の歴史や文化背景などもそれなりの紙幅を割いて記載されています。結局は、スピノザの思想を紹介したいのか、著者自身の心身-情動-感情の理論を紹介したいのか、読後の感想としては中途半端な印象を否めませんでした。哲学的にスピノザを消化して読者に伝えるには、その点での力量が著者ととそれを受け止める自分に不足しているのかもしれません。実際に著者がスピノザの暮らした部屋を訪ねて行った場面をそれなりに詳しく記載しているところからも、脳科学最前線というよりも少しばかり力を抜いた感じのエッセイにも近い本なのかなという感じです。脳科学に関する書籍としては前著の『無意識の脳 自己意識の脳』の方が個人的には好きです。
ただ前半はそれなりに面白い仮説展開もあります。情動(Emotion)と感情(Feeling)を区別し、ヒトの進化上で有利に働いた身体的反応(ホメオスタシス・プロセス)としての情動に対して、脳の身体マップを通したフィードバック機構として感情を副産物として発展させてきたという仮説を展開しています。スピノザについて、個の自己保存の本能であるコナトゥスの存在やデカルトの心身二元論に対する心身合一論などを、現在の最新研究の理論にも合致する先進的な知見であると紹介しているので、まあ無理な組み合わせではないかと思います。
期待が大きかったのを考慮して星4つ。
---
スピノザと言えば、大学時代に読んだ柄谷行人さんの『探求II』で大きく取り上げられ、その思想が積極的に評価されていました。その流れで岩波文庫から出ていた『エチカ』も当時購入したのですが、その難解さもあって、とても理解しがたかったのを思い出します。ちょうど本棚にあったので手に取ってみると、今見ても読む気を減退させる構成ですが、もしかしたらあれからの年月を考えると別の読み方が可能なのかなと思います。
---
この本をちょうど読み終わった日に深夜で放送されたCBSドキュメントで、PET(陽電子断層撮影)で撮影した脳の活動状況のパターンから何を考えたか当ててみるというのをやっていました。本書の中でも何度も出てきますが、PET恐るべし。こういうのを見たり、読んだりすると、心というものがとても身体的な現象なんだと実感します。
Posted by ブクログ
ダマシオ 情動は身体という劇場で、感情は心という劇場でそれぞれ演じられる ダマシオは怖いものをみて特有の身体的変化が生じるからそのあとに怖さを感じると考える 特定のオプションを頭に浮かべると、たとえかすかにではあっても身体が反応し、その結果たとえば不快な感情が生じ、そのためそのオプションを選択するのをやめ、こうしたことがつぎつぎと起きて、多数のオプションがあっという間に2つ三つにまで絞り込まれる。合理的思考が働くのはそのあとのこととダマシオは考えている
過去にわれわれがオプションXを選択して悪い結果Yがもたらされ、そのため不快な身体状態が引き起こされたとすると、この経験的な結ぶつきは前頭前皮質に記憶されているので、後日、われわれがオプションXに再度身をさらすとか結果Yについて考えると、その不快な身体状態が自動的に再現される。ソマティックマーカー仮説 情動とは動作または動きであり、多くは外に表れている 感情はすべて心的イメージが必然的にそうであるように、つねにうちに隠れており、その正当な所有者以外の人間には見えない。情動は身体という劇場で演じられ、感情はこころという劇場で演じられる 情動とその関連反応は感情より先に誕生したと思われる 感情の前に情動がある ホメオスタシス調節のレベル 単純から複雑へ 免疫反応/基本的反射/代謝調節 快と不快の行動 動因と動機 狭義の情動(嫌悪、恐れ、喜び、悲しみ、共感、恥) 狭義の情動とは 背景的情動、一次の情動(恐れ、怒り、嫌悪、驚き、悲しみ、喜び)、社会的情動(共感、当惑、恥、罪悪感、プライド、嫉妬、羨望、感謝、賞賛、憤り、軽蔑) まず情動状態ありき、感情はそのあと 脳はさまざまな手段により、われわれが身体状態をごまかすことができるようにしている
Posted by ブクログ
只今読書中。
比較的厚めの本なので、そういうのが苦手な人にはお勧めできない。
※必要な部分を拾い集めて読むことはできる。そして、結構重要なことを述べている。内容はやや専門的。