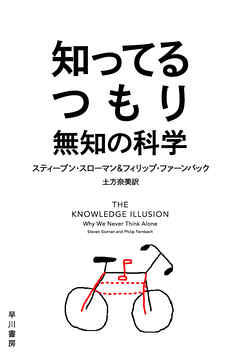感情タグBEST3
Posted by ブクログ
いわゆる「無知の知」に関連する最新の知見に触れることができる。身近に情報が溢れ、知らずのうちに「知っている」感覚に陥ってしまうため、自身の理解度に対して常に謙虚でいる姿勢が必要だと感じた。
また、誤った情報を強固に信じている人々に対して、考えを軟化してもらうアプローチについても述べられており、非常に示唆に富む内容だった。
Posted by ブクログ
人は自身を過大評価する。なのにこのような大きな文明を維持できている。なぜか?人間がどのように思考し、知っていると「錯覚」し、それで時に問題が起きたり、あるいはうまく物事が進むのか?が軽妙な語り口で、読者にも気づかせるように書かれている。非常に注意深くかかれ、「知っていると錯覚する」ことについても利点と欠点とが示されている徹底ぶり。
読みやすいが、一度時間を置いてまた読みたくなる本。まずは一読するのは良いと思う。
Posted by ブクログ
スティーブン・スローマン他が取り組んだ、壮大な問い、私たちはなぜ自分の知識を過大評価するのか。知ってるつもりになって、平気で生活しているのか。トイレの水の流れる仕組み、自転車が動く仕組み、など日常的に使っているのに、簡単に説明できないことがたくさんある。
我々は、分かった気になっているだけなんだと気付かされる。認知科学の観点では、極端な意見を持っているひとは、実は中身を理解していなかったりするんだと。これは、非常に気づきの多い本だと思う。てっきり知ったかのように振る舞っているけど、それは強がりであり、虚勢であり、実は完全に理解していない。
我々は、わかっていないということさえわかっていない時がある。これが、備えられず、一気にやられる可能性もある。戦争であれば、それは脅威だ。なぜ我々がこの世界を、知ってると勘違いして生きていけるのかというと、その答えは筆者からすると、嘘の世界を生きているからということになる。
因果関係の推論、という点に着目すると、我々がいかに愚かな判断をしているかがわかる。水道口の蛇口を撚れば、それだけ多くの水が出てくる。だから、空調の温度設定を急ぐ時には徹底的に低く、または高くセットすれば早くその期待値に到達すると勘違いする。身近な体験が、思い込み、知ってるつもりを生んでしまう。あると思い込んでいた知識は、実は別のところに置いてあるということだ。それが、インターネットのソーシャルの中にあるとすれば、知識は集合知のようなものになっているかもしれない。一方で、断絶すれば真の知識、つまり曖昧かつ限定的な知識のみとなり、判断軸として十分ではないかもしれないという説だ。GPSを切られた自動車、クルーズが、運転を誤った例などが、自動化のパラドックスと言える。自分自身の力で判断、行動できる力が必要だ。
もう一つ、大きな固定反応は、とにかく道徳的反応だろう。中絶はいけないとか、いいとか、戦争は反対、とか理由も個別事象も一切なく、ただただ理由なく決めてしまう。
そして、集団的な知識、チームワークによるアウトプットを最大化することが近年わかってきているという。その上で、正しい、賢い判断をすべきととく。オランダのチューリップを買って、暴落した人もいる。集団知を集めて、極めて賢い選択肢を進む。これには、正しいリサーチが必須だ。ことチームであれば、それぞれの得意分野を活かしてそれぞれ個人の無知、そして誤った感覚と判断をなるべく是正する。
無知であることを理解、集団知を活用する、そのために、しっかり自身の感性を高める。
Posted by ブクログ
主題はすでに題名に書かれている。
「なぜに」「いかに」を読み進める本。
読むだけでも楽しいけど、自身の謙虚さを育てる助けにもなれば、他人様を受け入れる助けにもなるやも。
Posted by ブクログ
笑えてくるほどおもしろい、人間にとっての知識の本質的な本。SNS等に散見される南郭濫吹な人々も仕方ないのかなと諦観できるようになれるかも…?行動経済学や認知心理学の本を読むときの前提知識として読むべき。
Posted by ブクログ
本書の結論は、「知能は特定の個人ではなく、コミュニティの中に存在する」です。
個人は驚くほど無知であり、人類を発展させたのは、集団(コミュニティ)がもっている知性であることをいっています。
巻末に、本書の三つの主題、「無知」、「知識の錯覚」、「知識のコミュニティ」が書かれています。
「無知」
・個人が処理できる情報量には重大な制約がある
・人間は、自分がどれほどわかっていないかを自覚していない
・知識を全て足し合わせると人間の思考は驚嘆すべきものとなる、ただ、それは、コミュニティとしての産物であり特定の個人のものではない。
・たった一つのモノについてさえ、そのすべての側面に精通することは不可能だ。
・人間は、自分が思っているより無知である。
・われわれの認知システムは、要点や本質的な意味だけを抽出する。複雑な因果関係に遭遇すると要点のみを抽出して、詳細は忘れる。
・自分がしらないことをしらないということが往々にしてある。
・テクノロジーが進化していけばいくほど、それを完全に理解できる個人はいなくなる。
・トースターを作ろうとしても作れる人間は限られている。
・本当はわかっていないのに、分かったつもりになっている。
・私たちが知っておかねばならないことの多くは恐ろしく複雑で、どれだけ目を凝らしても理解できない。
「知識の錯覚」
・前向き推論(原因から結果)のほうが、後ろ向き推論(結果から原因)より簡単だ。
・私たちは、近寄ると危険なものに対しては嫌悪反応をしめす。
・人間は共同で狩りをしたことで知能が向上した、それは、社会集団の規模や複雑性が高まったことに起因する
・最も優秀な人とは、他者を理解する能力が最も高い人かもしれない
・技術はもはや人間がコントロールできる単なる道具ではなくなった。システムがあまりにも複雑になったので、もはやどのような状態になるか、ユーザが常に把握できなくなった。
・知覚の錯覚がどこにあるかは個人ではわからなくなった。だから、信頼できる人の意見をそっくり受け入れざるを得なくなった。
・人の信念を変えることは難しい。それは価値観やアイデンティテxと絡み合っていて、コミュニティと共有されているから。ただ、頭の中にある因果モデルは限定的で誤っていることが多い。
・専門家でないのに、専門家のように口をきく集団となって、ますます自らの専門知識への自信を深める危険。
・政治的議論は、きわめて皮相的、たいした議論もせず、さっさと意見と固めてしまう
・優れたリーダは、人々に自分は愚かだと感じせずに、無知を自覚する手助け必要がある。
・また、リーダのもう一つの任務は、自らの無知を自覚し、他の人々の知識や能力を効果的に活用すること、専門家の意見に耳を傾けること。
「知識のコミュニティ」
・個人の知性を表すg因子(IQの一種)に対して、集団の知性を評価できるc因子が発見された。しかも、集団知性である、c因子を重視すべきとの結果がでた。
・集団にとって、一番重要なのはアイデアではない。重要なのは、チームの質である。
・学習の目的は、知識の習得でなく、目標達成のための行動ができることだ
・文章を暗記していても、理解できているとはかぎらない
・本来の教育では、持っていない知識に目を向ける方法を身につけることもある。それには、思い上がりを捨てること、「なぜ?」を自問することが必要
・個人としてもっている知識は少ない。そのために、他の人々の知識や能力を活用する方法も身につけなければならない。
・近年学問の領域が拡大するにつれて、知識コミュニティも拡大の一途とたどっている。専門知識は意図的に分散されている。
目次は以下の通りです。
序章 個人の無知と知識のコミュニティ
第1章 「知っている」のウソ
第2章 なぜ思考するのか
第3章 どう思考するのか
第4章 なぜまちがった考えを抱くのか
第5章 体と世界を使って考える
第6章 他者を使って考える
第7章 テクノロジーを使って考える
第8章 科学について考える
第9章 政治ついて考える
第10章 賢さの定義が変わる
第11章 賢い人を育てる
第12章 賢い判断をする
結び 無知と錯覚を評価する
Posted by ブクログ
タイトルから自分が勝手にイメージした内容とは異なっていましたが、「読んでよかった」と思えた本です。
「ヒトは、自分自身が思っているほど、物事を理解していない」ということについては、自分自身のこととしても何度も体験したことがありますし、他人を見ていても何度も経験したことがあるので、ヒトにはそういう傾向がある、と思ってはいましたが、もっと一般的というか普遍的であることを、この本を通して確認できました。
そもそも、人間どうしがコミュニケーションに使う道具である「言葉(言語)」自体も、まだまだ完成してはいないことを考えると、ヒトが物事をあまり理解していないことについては、まったく違和感ありません。
その一方で、「個人としては理解できていないことが多くても、集団として、個々人の理解している部分をつなぎ合わせることで、集団の知を形成できる」ことについては、これまであまり意識したことがなかったので、読んでいて「なるほど」と思いました。
これまでは何となく、「少数の個人がもっている知によって、集団の知は形成されている」と思っていたのですが、知は少数の個人に偏っているわけではない点は、集団に属する各個人に勇気と存在意義を与える捉え方だと思いました。
しかしながら、「集団の知」は、決してプラス面だけでなく、無根拠な「知」の共有になる可能性もあり、諸刃の剣である点は、心しておきたいことだと思います。
個人の知と集団の知について、そのあり方や活用は改めて考え直す必要があると思います。
また、そういった知の養成の場であり、活用の場である学校や各種組織については、そのあり方を考える上で、必読の書だと思います。
Posted by ブクログ
めちゃくちゃ面白かったです。
「人は自分が思っているほど、物事を知らないよ❕」という事実を、様々な研究を通じて丁寧に考察しています。
「自分の知っている境界線を知る❕」を知るというのは大事なことだと思う反面、「俺は、何でも知っているぞ!」という自信も必要だとも思いました。
なかなか深いテーマで面白かったです。
ぜひぜひ読んでみてください。
Posted by ブクログ
いかに自分が「無知であるか」を知れる良書。
知らないことは知らないと認めること、
「なぜ?」と自問し、思い上がりを捨てることが第一歩
(知識の錯覚を自覚する)
認知的分業は、人が学習する内容に大きな影響を及ぼし、個人は自らの役割にさらに特化するようになる
→その気になれば、その役割を与えられれば、人は学習する
p374の主題のまとめ
テーマ:無知、知識の錯覚、知識のコミュニティ
無知は避けられないものであり、幸せは主観的なものであり、錯覚にはそれなりの役割がある
ということを自覚する、のが本書のテーマ
Posted by ブクログ
理解していると思っていたのに、いざ説明を求められるとどう答えればいいか分からない。そんな「分かったつもり」の状態になっていることは自分も多々あるが、それは人間が、様々な知識を持った人々が集まり形成する知識コミュニティの中で生きているために起こる錯覚である。知識を共有してもらうことで、外から得た知識を「自分の頭の中にもともとあるもの」と混同してしまうらしい。それ故に己の無知にも気がつかない。
大事なのは、全てのことを知るのは到底無理であると理解すること。自分が無知であるということを自覚すること。自分がどれだけ理解できているかを確認すること。そして謙虚に学ぶこと。
本書を読んで、なるほどと思う部分も多々あったが、きちんと理解できているようには感じないので再読の必要あり。
Posted by ブクログ
「無知の知」の科学的解説。「知識のコミュニティ」がポイント。面白くてグイグイ引き込まれた。
目新しい話がそんなに多かったわけではないのだが、重要な示唆を与えてもらった気がする。もう少しよく考えてきちんと消化したい。
概要
・思考は有効な行動をとる能力の延長として進化
・思考は因果的推論が得意
→個人の思考プロセスによる「直観」とコミュニティとともに行う「熟慮」という二つの側面
・思考は自らの頭の内と外にある知識をシームレスに活用
→これらのあいだに明確な線引きができない
→自分が思っているより無知
・知識のコミュニティがますます拡大している中、成功のためには集団内で貢献する能力が重要。
Posted by ブクログ
複雑な世界をすべて理解することなどできないため、人間の知性は新たな状況下での意思決定に最も役立つ情報だけを抽出するように進化してきた。我々は自身の外部、"知識のコミュニティ"に蓄えられた情報に頼って生きており、認知的分業を行っている。そこには、外から入手できる知識と頭の中にある知識を混同して自分が多くを理解しているという"知識の錯覚"が生じており、飛躍的なイノベーションを促すなどのいい側面もある一方、薄っぺらい情報に流されやすいといった弊害もある。まずは自身が無知であることを自覚し、知識のコミュニティへ貢献するという精神を持つことが重要である。
筆者も述べている通り、新たな概念を提唱しているというよりは、無知を自覚しましょう、と促している内容。知識のコミュニティに貢献するという意識は、個々人のキャリア形成やナレッジ蓄積の根幹となるマインドになると感じた。
Posted by ブクログ
前半が特に面白かった。無知と錯覚。人は自分が思う以上に表面的な事しかわかっていない。思考の目的は行動。因果関係の推論。
知識のコミュニティは諸刃の剣。集団浅慮。真摯に学ぶ事、知識のコミュニティの恩恵を享受しつつ、そこに貢献しようとする姿勢が重要。
Posted by ブクログ
【背景】
①なぜ読むか
脳の中の幽霊を読んで認知科学に興味をもった。
②何を得たいか
知っていると錯覚する原因を知り、自身の無知に気づく力を得たい
③読後の目標
それを抽象化し教育や自身の学習に生かす。
【著者】
スティーブン・スローマン
フィリップ・ファーンバック
【出版社】
ハヤカワノンフィクション文庫
【重要語句】
錯覚、認識、無知、思考、直感、コミュニティの知識、CRT、認知的分業、AI、欠乏モデル、因果モデル、理解の錯覚
【要約】
人は自身の知識を過大評価する傾向がある。それは、コミュニティの知識を自身の知識と混同してしまうからだ。私たちは、コミュニティの知識に依存していることを認識すべきだ。
【メモ】
P41 説明深度の錯覚
①ファスナーの仕組みについての理解度を7段階で評価。
②ファスナーの仕組みについて詳細に説明する。
③改めて、ファスナーの仕組みについて自己評価。
P73「自然界で最もよく理解されている神経系はカブトガニのものだ。」
P196、L4「外から入手できる知識と頭の中にある知識を混同するため、たいていの人は自分がどれだけものを知らないかに気づいていない。」
P252~253「地球温暖化について一般人に啓蒙する方法」
P303、L15「個人の知能は、その個人がチームにとってどれだけ重要な存在であるかを示す。」
【感想】
私たちは無知であっても、認知的分業によって生活する事が出来ている。教育的には社会構成主義の前提になる内容だった。個人の知性も重要だが、それ以上にコミュニティの知識が重要である。そうなると、成績の付け方も変わっていくように感じた。
個人的には、自分が無知であることを忘れないようにすることが大切だと思う。
個人↔社会
相互に作用していることも忘れてはならない。
Posted by ブクログ
人間は知っていると思っていることを、実は知らない。このように、本当は良く知らないことを、なぜ人は知っていると思ってしまうのか、本書は、最新の認知科学の知見に基づき、豊富な実例をもって解説してくれる。
また、個人レベルでは人間の認識には限界があり、間違った考えを持ちがちであるのに、どうしてこれほどに複雑で発達した世界を作れたのか?それは知識のコミュニティがあるからだ、という。
一つひとつの事例や分析はこれまでも各所で取り上げられたり紹介されたりしてきたが、本書でのまとまった説明により、どういったことに注意し、どのように個人やチームに働き掛けていったら良いのか、大事な示唆を与えてくれた。