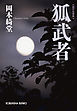岡本綺堂のレビュー一覧
-
下屋敷の、結局どうしてどうなったのかわからないのが良い。
踊り字そのままの歴史的かなづかいなのにするする読める。表紙口絵がまた良い。
デザインはミルキィ・イソベ、口絵は山本タカトだそうで。Posted by ブクログ -
このシリーズは,作品ごとに丁寧な註釈や解説がついているのですが,当時の浮世絵などをもとにした挿絵も的確で助かります。百聞は一見にしかず,といったところ。Posted by ブクログ
-
相変わらず綺麗な絵だなぁ。
玉藻の前の伝説は知っていたけれど、この原作となった岡本綺堂の話は読んだことはありませんでした。
今度は岡本綺堂の方を読んでみよう。Posted by ブクログ -
「つよくも、ゆたかでも、かしこくもなかった頃のわたくしたちの国に、うつくしく、やさしく、おろかな人々が暮らしていた。」解説にある杉浦日向子さんのこの一文ほど、岡本綺堂の魅力をあらわす言葉はないと思う。だけどその「わたくしたち」というやつは、今もっておろかなまま、かしこくなったと思い込んでいる。Posted by ブクログ
-
半七捕物帳で有名な人です。
怪奇探偵小説って銘打ってますが、どっちかというと怪談話です。
話の締めくくりのボカシ加減がいい具合に恐さを盛り上げてくれます。
古いものですが読み憎さは感じません。Posted by ブクログ -
短編集だった1巻とは異なり、2巻は長編『玉藻の前』1作が収録。殺生石のいわれは何となく知ってはいたけど、岡本綺堂の原作は全く知らなかったので、一つカシコクなりました★(^_^;) 読んでくうちに、相変わらず美しく妖艶な世界観にウットリ浸ってしまいます。と同時に、えもいわれぬ怖さを感じさせてくれちゃう...続きを読むPosted by ブクログ
-
美しい絵で岡本綺堂を読む。
原作を読んでいないが、平安時代の怪奇怪談を波津彬子の世界で読めて良かった。
美しく雅な世界観が素敵であるが、もっと醜く哀れな部分があったら更にのめり込めたかも。 -
原作を読みたくなったが
どうしても絵が。。。
山岸涼子なんだよなぁ
作者が読んだというわたなべまさこさんの方が気になる
という意味では、原作の魅力を伝えることができてるということかPosted by ブクログ -
中国の伝奇を読んでいるような感覚だった。さらっとして読みやすいし凄く怖いということもないので野次馬系怖がりとしてはとても助かった。訳も理由も分からないけど興味を引く話っていうのは結構へぇ〜って感じで聞き入ってしまう。Posted by ブクログ
-
はじめての岡本綺堂。しかも新潮nex(!?)。
ずっと読まねばと思っていたが、宮部みゆき氏編というのがよいきっかけになった。
それだけに、90年近くも前の作品とは思えないほどすんなりと楽しみながら読めた。
さすが捕物帖の先駆け。Posted by ブクログ -
岡本綺堂は初めて読んだ。1925(大正14)年から連載され、後に追補されて1932(昭和7)年に単行本として刊行されたもの。百物語形式で、12名の語り手が順に怪談・奇談を語っていく。
この中公文庫版、「雰囲気を伝えるべく」あえて歴史的仮名遣いを採用しているので「さういふわけで」のような表記になっ...続きを読むPosted by ブクログ -
わかりやすく怖いというよりは、じわじわと怖くなったり不思議な気持ちになるような話が十三編。
好きだったのは、以下の三作。
『白髪鬼』
下宿仲間が何年経っても弁護士試験に受からない理由とは。
そしてお土産の鰻からまた様相が一変する。
『妖婆』
雪夜の横丁に座る老婆を目撃した若者たちの顛末。
その...続きを読むPosted by ブクログ