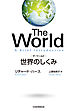上原裕美子のレビュー一覧
-
書きたい事、主張が明確な本なので、硬い文章の様な気もするが、分かりやすい。
要は「規制緩和と言っても、それで自由競争になるわけではないよね」、「政治が市場介入する事をゼロ百で善悪を論じることは間違いだ」という話。
規制緩和について。現実には競争を拡大するためには規制を減らすのではなく、規制を増やさ...続きを読むPosted by ブクログ -
養老先生のYouTube紹介で読んでみたが、本誌の脱成長の考え方、必要性は納得できた。後半の斉藤幸平氏の解説は秀逸!
では、じぶんは今から何をしようか。Posted by ブクログ -
安倍派を手始めに自民党が大変な事態に陥っている安倍晋三氏亡き現在。安倍氏の功績を確認すべく手にした「安倍晋三と日本の大戦略」。日本の安全保障政策の専門家である米国人著者が安倍氏の手腕をどう評価しているのか、非常に興味があった。冷戦後の歴代政権が模索してきた官邸への権限集中や価値観を重視した外交を安...続きを読むPosted by ブクログ
-
Twitterで紹介されて読んでみました。本当にどうすれば、まともな、人間が地球の害でない、人間が浅ましく搾取しない世界が作れるのか、自分に何ができるのか、
生きていくのに、人や自然や動物を必要以上に傷つけなくてすむのか、実際に行動している人々の逞しさを感じました。Posted by ブクログ -
ここのところ、ベーシック・インカムについての本をいろいろ読んでいまして、その中の1冊です。
ベーシック・インカム賛成派による本、ということもあってか、ベーシック・インカムの利点について、いろいろな面から語っています。
ベーシック・インカムについては、既に、様々な地域で実験がなされていて、どの実験で...続きを読むPosted by ブクログ -
まずは、アメリカの文化と歴史について、自分がその場面に居るような錯覚を覚えながら、少しでも知ることができたのが楽しかったです。
3家族が少し混同してしまった場面もありましたが、最後には何とか整理ができました。
特に農業に関する部分の専門的な説明や、取り組みなどが紹介されて、こちらも勉強になりました。Posted by ブクログ -
感想
人間の脳を変化させるビジネス。元来備わっている報酬系の働きを利用し儲ける。報酬の与え方をコントロールすることで人間はどこまでも従順になる。Posted by ブクログ -
依存症の具体例・要因・対策が書かれた本。
現時点で個人的な依存症の兆候は無し。(強いて言うなら、Netflixのビンジウォッチング)今後何か依存症を患ったとき・依存させる何かを開発する機会がある場合に再読したい。
行動アーキテクチャ・ゲーミフィケーションの理論で、生活習慣を良い方向に持っていくの...続きを読むPosted by ブクログ -
翻訳特有のちょっと意味が分かりにくい訳はありましたが、過去を振り返るとGDPによる経済成長のイデオロギーによって世界中で資本主義というシステムができ、富裕層によっての植民地化、グローバルサウス問題、不等価交換。これ以上続けないためにはどうしたらよいか。本当に豊かさはまではいきませんでしたが、どんな解...続きを読むPosted by ブクログ
-
自身の仕事で活かせる部分が少しでもあるのでは、と思い購入した。
依存症ビジネスはどのようにして作られ、消費者を依存へ誘うポイントはどんな部分なのかを知りたかった。
結果として、知ることはできたが体系的に知ることができたかは微妙である。
本にある数々の事例から現代人が依存してしまう理由などは少し...続きを読むPosted by ブクログ -
時系列的にも分野的にも、ものすごく広い範囲を扱っていてすごい。。広く広く浅くという感じ
読みやすいけど何しろテーマが多いので頭に残ったかというと微妙かもPosted by ブクログ -
ゲーム依存で睡眠時間も削ることが多々あり2ヶ月前に遂に売ったが最近またやりたくなってきている。この本を読むことで依存症の再燃を防ぐ助けをしてくれている。Posted by ブクログ
-
RCTと言えば臨床医学の分野がすぐ思い浮かぶ。本書の中でも長く信じられてきた医学上の「常識」がRCTによって否定された例がたくさん挙げられている。
・閉経後の女性に対するホルモン補充療法は心筋梗塞のリスクを低下させるとされており、21世紀の始まりころまでにアメリカ人女性9000万人がこの治療を受け...続きを読むPosted by ブクログ -
ほとんどの大学には「世界情勢」に関する必修科目がなくて、大学生が、今、わたしたちが生きている世界について、なにもしらないままに世の中にでていくことに危機感をもった著者による世界情勢の入門書。
短いイントロという位置づけだが、ページ数はそれなりにあって、分厚い。
本の構成としては、まず歴史があって...続きを読むPosted by ブクログ -
「エビデンスに基づく」というフレーズが流行り言葉になって久しい。政策や意思決定の効果を数量的に検証して得られた結果が「エビデンス」だが、数量的な検証と言ってもさまざまだ。本書のタイトルにもある「RCT」はランダム化比較試験の略で、良質なエビデンスを得るためにはRCTが欠かせないというのが著者の立場だ...続きを読むPosted by ブクログ
-
目次内容に興味持ち、読んでみた。
共感は育てていくことができ、その力は社会にとっても良い影響を及ぼすということを、豊富なデータを通じて教えてくれる一冊。巻末に参考リストもあるのが良い。
もちろん良い影響だけでなく、よく言われる共感疲れにや、共感を薄めていく要因になっているデジタルのポジティブな可...続きを読むPosted by ブクログ -
脱成長というよりは、「脱消費」「資本主義の変革」を目指すべきと説いてる本。現在の成長至上主義の生活システムの抜本から変える、そのためには個々人の運動から政治変革を促す「共進化」を推進すべきと言った本書の見解は新鮮だった。
ただ、これが財源的に可能か、どの程度の規模に収縮すべきかなど、多くの点での検討...続きを読むPosted by ブクログ -
草の根ネットワークから始まる個人の行動力が必要。
GDPの成長は格差拡大につながっている。
成長は必要ない。より少なく生産、少なく消費する生活を指向するべき。
成長には、循環型、永続型、複利型がある。複利型は永遠には続かない。永続型も自然ではない。複利成長を目指すことはできない。
物資使用量と市場取...続きを読むPosted by ブクログ -
公共経済学者であり現在はオーストラリアの連邦議員を務める著者が、RCT(ランダム化比較試験)がいかにシンプルでありながら、世界を少しずつ良くしてくために不可欠なツールであるかを多様な分野での実用例と共に示す良書。
対象となるのはもちろん医療をはじめ、教育、犯罪防止、新興国における開発援助のあり方、...続きを読むPosted by ブクログ -
・行動嗜癖の6つの要素
1)ちょっと手を伸ばせば届きそうな魅力的な目標があること
2)抵抗しづらく、また予測できないランダムな頻度で報われる感覚があること
3)段階的に進歩・向上していく感覚があること
4)徐々に難易度を増していくタスクがあること
5)解消したいが解消されていない緊張感があること
6...続きを読むPosted by ブクログ