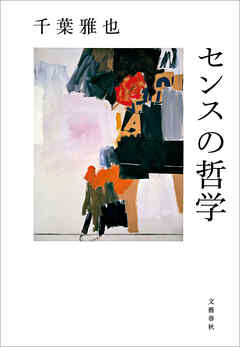感情タグBEST3
Posted by ブクログ
センスが良く以前に、そもそもセンスとはどういったものを指すのかということから話が進んでいく。話の軸となるリズムとは、人固有の揺れ動きを表していて、人間であるがゆえのブレのようなものが滲み出るところにセンスが宿るのかなと思った。漠然としたセンスという印象の輪郭を浮かび上がらせてくれるような本だった。
Posted by ブクログ
納得。私が、2つの方向性が違うものを摂取しようとしてきたのは、無意識なのか意識的なのか。高校時代に読んでしまったら、いろいろネタバレ。最近、文化資本についての言及を目にすることが増えたなあと。
Posted by ブクログ
自分に固有の偶然性
何かをやるときには、実力がまだ足りないという足りなさに着目するのではなく、「とりあえずの手持ちの技術と、自分から湧いてくる偶然性で何ができるか?」と考える。規範に従って、より高いレベルのものをと努力することも大事ですが、(中略)いつかの時点で、「これで行くんだ」と決める、というか諦めるしかない。
デモーニッシユな反復
人は、より自由になろうとする一方で、何らかのモデルや枠組みに頼っている。その間にジレンマがあり、切実さがある。人間の魅力というのもそうかもしれません。バランスがとれた良い人というだけでは魅力に欠ける、というのはよく言われる話で、どこか欠陥や破綻がある人にこそ惹きつけられてしまうことがある。その破綻というのは、その人固有のものというより、「ある種のテンプレのその人なりの表現」だったりする。固有の人生がなぜか典型的な破綻に取り憑かれてしまう…(後略)
今日も今日とて「仮固定」
Posted by ブクログ
難解な純文学や映画、現代美術に触れたとき
意味を求めすぎないとはどういうことか
そこにリズムを感じるにはどうすればよいのか
哲学者による世界の見つめ方。
著者のこれまでの本より遥かにわかりやすく書かれてあるが、後半の実践はやや難しい
でもおもしろかった!
Posted by ブクログ
センスのパーツを教えてもらい、センス良くに対する姿勢を学ぶ。センスとは、というとこの本から学んだ事を、自ら取り組むこと。これが「センスが良くなる」ことと思い取り組む。
Posted by ブクログ
しなやかに自分の感覚を認め、愛し、伸ばす、という姿勢のエッセンスを伝えてくださる本。在り方の多様性という哲学の実践としても読めるけれど、もっと身近に、自分の部屋にセンスとアンチセンスを投影させて、自分なりの享楽をマイペースにじわじわ育てるスタンスでいいな、と思えます。
Posted by ブクログ
すごく親しくてセンスを大事にしている人としか話が出来ないような内容です。
こんな話をすると「意識高い」系の人物と見做される可能性があるので話題に出すのを警戒してしまう。だから作者と話しているつもりになって「そうそう!」等と心中共感しながら読み進めていく事になった。
序盤で「センスが悪いというのは~」と大真面目に語っていて、悪口ではないんだけど結果的に悪口になっていなくもなく、とても笑ってしまった。「あれセンス悪いよね」と公共の場でそうそう発言出来ないフレーズなので「あ、言ってしまいましたね」という気持ちになりました。そんな事言ったら「あいつは自分でセンス良いと思ってんのね」と思われそうですから。「センス」というのはその言葉一言で、人の丸ごとを
評価しているようでなかなか簡単に言葉に出来ないワードです。
文体も柔らかく日常風景を例に出してくれているのでとても分かり易い内容。
作者の生まれ育った環境が美術的に恵まれていたのでそういう感性が育ったのでしょう。
普段無意識に感じていることを分かり易く言語化してくれています。
印象深い点は下記です。
・人間にとって、何らかの意味で不安定な状態は、ただ生物一般として解消したい状態であるだけでなく、どこか「誰かがいないという寂しさ」を帯びているのではないか。
自分だけが寂しいのかと思ってたら、人間とはベース寂しくて、それを埋めるために色んな工夫をして生きているんだな、と思った。
・格好よすぎる物は案外売れないんだよね
・バランスが取れて良い人ってつまらないと良く言われるが、どこか欠陥があった方が人を惹きつける
・優等生はつまらない
・バランスの崩れにこそ魅力が宿っている
・差異とは予測誤差であり、予測誤差が程々の範囲に収まっていると美的になる。それに対し、予測誤差が大きく、どうなるか分からないという偶然性が強まっていくと崇高的になる
共感。バランスを取ろうと完全体(モデル)を目指すことを息苦しくダサいと思っていました。
・下手(真面目にモデルを追求するが叶わない態度)よりヘタウマ
ヘタウマの隙にこそ魅力が宿ると思います。
・リズム、ビート、うねり、反復、差異
生活の隅々に浸透しています。
すごく面白い本でした!
Posted by ブクログ
口語でゆっくりと論が展開されるのでかなり追いやすい。哲学への橋渡しが丁寧なので、学習の起点としても有意義だと思う。
他方、自分はどちらかといえばセンスがある(美的感覚についての関心が強く、インプット量が多い+楽しみ方を知っている)と自負している人間なんだけど、記載内容についてはある意味腑に落ち"すぎる"というか、どうもセンスのよさを自認している作者が自分のアプローチを定式化した内容ではという気がしてしまう。
たとえば、裾の折り返しがチェックになっている七分丈パンツは2024年現在どんなコーディネートでも取り繕えないようなダサアイテムなわけだけど、あれはあれでラウシェンバーグ的リズムが働いていると捉えられるわけで、ではなぜ世間一般で「センスが悪い」扱いなのか?という疑問には本書のフレームワークだけだと回答できない気がする。「センス」という言葉の持つ他者性への言及がないので、センスっていうよりは芸術に関する手引書と言ったほうが正しいのかな。
まあ、一気読みして消化不良を起こしているかもしれないので、また読みます。
Posted by ブクログ
「これはセンスがよくなる本です」の言葉の真偽のほどはわからないけど、センスとは何か、センスを生活の中でどうとらえていくかという事はよくわかった。
本の内容には直接関係ないけど、4章まで読み終えたところにあった「前半のまとめ」がよかった。
論説文をフムフムと読んでいて、途中で「それで結局どういうことだったっけ?」となることがあるのだけど、まとめがあったお陰でそこまでの内容がしっかり整理されて、後半もスムーズに読めた。
このスタイル、広まってほしいなぁ。
Posted by ブクログ
悪くはないのだが、何かしら自分の期待しているものや自分の考えていることとの微差が良い意味での微差でないためか、心のなかで疑いながら読んだ。いささか冗長とも感じるが、哲学専門書ではないだろうからしょうがないのか。それをそう捉える背景と理路に納得いかない、というか。
他方で、実際的に、そういう見方もできるか、と腑に落ちる記述もあり、私にとってまるで合わない本というわけではない。同じ部署だと相性悪いだろうけれど、別の部署の同期くらいなら、ちょうどいい距離の本。
Posted by ブクログ
自分が作品を観て感じたことを言語化するのは美学の観点で有意義だという主張には共感した。作品から見出される美についての説明が続いたが、それが個人から湧き出るセンスとどう結びつくのか、判然としなかった。
Posted by ブクログ
センスをリズムをキーワードにして捉える。
凸凹や揺らぎ、1+0、予測可能性とそれからの逸脱、いろいろ興味深い言葉が並んでた。まあ分かったようなわからないようなが正直なところ。カントの「判断力批判」の崇高の概念にどうして繋がるのかは意味不明だった。これって美学の本なのかしら?