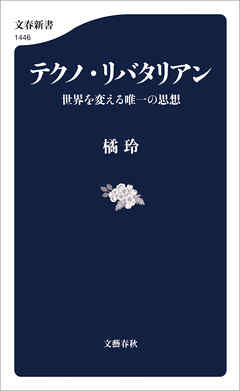感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ギフテッドとリバタリアン
前原政之さんから。
右翼と保守、リベラルの違ひについて丁寧に図解してゐる。まづここが面白かったが、ギフテッドと自閉症(=遺伝)も絡んできて、ああ、剴切な説明だと思ふ。
イーロン・マスクとティールのエピソードは、分析されて示唆に富む。
そして終章ではフラクタル、コンストラクタル法則と社会について触れてゐて、目から鱗が落ちた。進化は自由のある限り、効率的に変化する。階層化こそが自由と引換へなのである。
非常に興味深かった
天才の考えていることが、少しわかった気がします。そして、民主主義が危機にあることも。
その段階まで行き着いていない日本人はどうなるのだろう?
Posted by ブクログ
富を独占するテクノリバタリアンたちが何を考えてどう未来を創造するのか…。最高に面白い1冊だった。内容は難しくて読むのは苦労したが、だがそれがいい!という人にオススメ。最高に面白い、未来。長生きしたい。よりなめらかにより速く。
Posted by ブクログ
期待通りの面白さ。アイザックソンの「イーロン・マスク」でも彼のハチャメチャさがよくわかるが、ピーター・ティールと合わせてテクノ・リバタリアンの第1世代、イーサリアムを作ったヴィタリック・ブリテンやOpenAIを開発したサム・アルトマンらが第2世代、とのことで、いずれも超アタマいい人たちがどんなことを考えているか、がうまく説明されていました。
Part0は「リベラル」と一括りにされがちなものを、正義をめぐる4の立場から、リベラリズム、リバタリアニズム、共同体主義、功利主義、と分類して図示するなど、わかりやすく解説されていて理解の助けになりました。(すべて理解できたわけではないが)
新書のお手本みたいな本だと思います。
Posted by ブクログ
表題の「テクノ・リバタリアン」を語る前段のリベラル、リベラリズム、クリプト・アナキズム、総督府功利主義の解説含め、興味深い内容ばかりだった。特にネクストジェネレーションの中の「COST(共同所有自己申告税)」「QV(平方根投票)」のワイルのアイデアは斬新で、ここだけでも詳しく解説された本を読みたいと思った。
Posted by ブクログ
米国のIT企業を牽引するベラボーに頭がいい人たちが、その頭の良さを使って、理屈として社会の未来を考えたらこうなりますよー、という話。
また、同時にそれに向けての技術開発の現状や、思想面での深掘りがされている。日本ではあまり馴染みのないリバタリアニズムがメインに書かれている。
著者の従来の本とはややテイストが違うが、話のうまさは流石で、面白かった。(思想の全体像などは、従来の著作でも触れられているので、本書はそれのスピンオフといった感じか。)
Posted by ブクログ
先端テクノロジーのAIとかブロックチェーンとかの思想的な部分についてが詳しく書かれていて、それと同時に日本での政治の対立部分に感じる違和感が説明されている感じが興味深かった、確かにリバタリアン的な考え方があまり含まれていないと、増税か減税か、とか規制か緩和かという対立ではなく、増税するかさらに増税するかや、規制するかもしくはさらに規制するかのような、程度による対立になってくるなと、、.。COSTによる所有物への課税とかのような希望の持てる話もいくつかあり、コンストラクタル法則の流れがあり、かつ自由な領域があるなら、より速く、より滑らかに動くように進化する、というのは当てはまる物事は多いかもなと感じた。