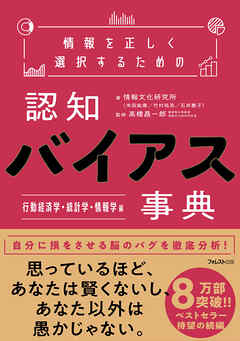感情タグBEST3
Posted by ブクログ
行動経済学…とかのジャンル分けされても浅学なためによく分からなくて、常に「〇〇による先入観」として読んでた。
本当にどれも自分や周りに当てはまるからこの本読むと呪いみたいに「あーこれは〇〇バイアス掛かってるな」って脳内に出てきちゃう。褒め言葉です。
前作(緑)を読んだときの感想で、「人間臭さを決めてるのは何かしらバイアスから生まれる先入観だと思うので、だからこそ人間行動学や心理学、哲学などに繋がって来るとは思う」みたいな事をドヤ顔で書いてて、この本を読んだ時に「人はバイアスのない状態はありえない」ってもう書かれてあって、ドヤ顔してたのが恥ずかしい…
Posted by ブクログ
バイアスを完全に排除して世の中を見つめることも、情報を発信することも、きっとできない。だからこそ、どんなバイアスがかかる可能性があるのか、知識としては一つでも多く知っておきたい。そして、この本自体にも何らかのバイアスがかかっている可能性があることも考慮しておきたい。
Posted by ブクログ
認知に影響を与え、判断を狂わせるバイアス。
本書では、行動経済学、統計学、情報学の領域別に、知られているものが解説されていく。
自信過剰バイアスや、選択肢過剰、モンティ・ホール問題(どうしてもモンティ・パイソンを思い出してしまう)など、以前どこかで読んだものは、おさらいができてよかった。
グラフや図が充実しているので、統計や確率の込み入った説明も理解しやすい。
一方、グーグル効果などは、認知バイアスなの?と不思議な感じがした。
ええと。
ピークエンドの法則にははまらないように気をつけていうと、全体としては満足だった。
(私にとってこの分野のアンカーとなるのかも・・・)
これは続編だそうで、正編は論理学・認知科学・社会心理学編なのだそうだ。
機会があったら読んでみたい。
Posted by ブクログ
面白かった!世の中に溢れるバイアスがまとめられた本書は、バイアスの解説の中に社会問題などの例も入っていた。面白かった〜!
p.65 「終わりよければ全てよし」や「最後の一言で台無し」と言う言い回しがあるが、実は科学的根拠があったと言うことになる。実際、コールセンターいや、顧客へのクレーム対応では、このピークエンド効果が応用されている。クレーム対応の締めくくりは、「このたびは申し訳ありませんでした」と言う社会ではなく、「お客様から私どもの至らない点をご指摘いただき、誠にありがとうございました」とクレーム相手にお礼を伝える。これは、クレーマーをアドバイザーのように思わせることによって、怒りを沈めることに役立てているのだ。
p.208 気分が落ち込んだときに、暗いニュースを見続けてしまう行動をドゥームスクローリングと言う。この言葉は2020年の新型コロナウィルスの流行や、2022年のロシアによるウクライナ、信仰を受けて注目され、しばしば意地悪世界症候群との比較がなされる。例えば、長時間テレビを見ている人ほど、世間は冷たいと感じる意地悪世界症候群に落ちるため、警察や法律がより弱者の保護をするべきと言う考え方になる傾向があると報告されている。
一方、ドゥームスクローリングにおいては、特定の事件や組織、人種、信条を持つ人を偏った視点で批判する記事が多く存在し、差別意識を激しく助長する危険性が指摘されている。さらに、ルームスクローリングは不安や鬱症状を悪化させ、睡眠パターンを見出し、注意力を下げ、過食を引き起こすことが報告されている。人のトラウマ処理能力を弱めることが発見されている。
Posted by ブクログ
有名なものから最近提唱のものまで様々なバイアスを網羅。
説明も分かりやすく、「じゃあどうしたらいいのか」的な気付きが得られるのも面白いところです。
Posted by ブクログ
この手のテーマだと当たり前のことを大げさに盛ってたりするけど、この本は淡々と解説していて誠実。
普段なんとなく感じていることに名前をつけてくれる本。
Posted by ブクログ
以前読んだ認知バイアスが面白く、本書も読んでみた。本書は統計学的アプローチや情報学的アプローチから認知バイアスについて書かれており、理系寄り?な感じがした。前作の心理的な視点の方が興味が持てた。
◯ピークエンドの法則:検査の不快感は痛みの最大時と終了時点の痛みの平均が総合評価に影響。検査時間の長さは関係ない。つまり人は、印象に残った代表的なものと最後で評価する。
→面接でも使える。終わりよければ全てよし。コールセンターの謝って終わるのではなく、「指摘いただきありがとうございました」で終わるという技術は参考になる!
◯ホーソン効果:人は見られていると生産性が上がるというまの。
→聞いたことあったが、スポットライトや給料が作業に影響するか調べる中で、観察者が見ていることが結局作業に影響していたという思わぬ実験結果が得られたのだと初めて知った。ただ、監視では生産性は上がらず、よい人間関係、心理的安全性が重要。
Posted by ブクログ
セールスマンが使ってそうで、自己防衛のためにも読んで良かったです。バイアスの名前まで覚えていなくても、「あっ、これって、なんか書いてあったパターンじゃない?」と思えるだけで、冷静な判断ができそうです。
Posted by ブクログ
タイトル通り認知バイアスのことを教えてくれる本。
へーというものもあれば、あまりピンとこないものもあった。自分にどんなバイアスがあり、考えたかを変えるのに役立つのでは?という期待から読んでみたが、それには自分がどういう立ち位置でいるかを知ってないと役に立たない気がした。
Posted by ブクログ
前作からは多くの学びを得た。翻って今作は、前作と重なる部分もあれば、無理矢理バイアスと名を付けたように感じられるものもあり、ほとんど得られることはなかった。