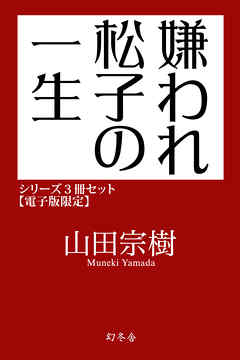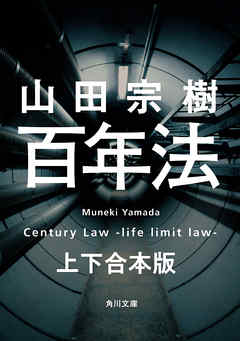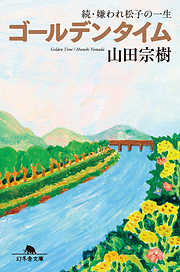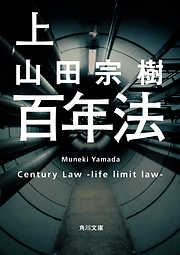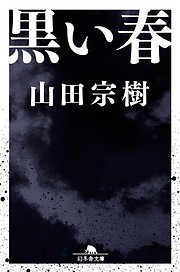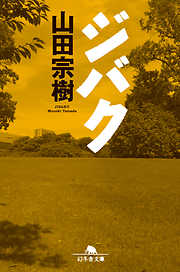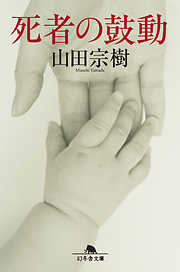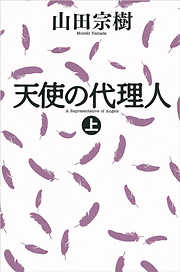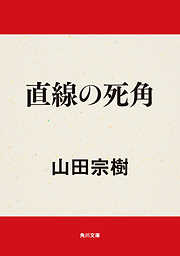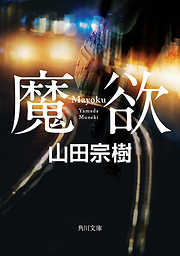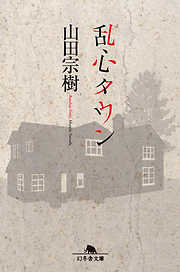『嫌われ松子の一生』『百年法』の山田宗樹先生トーク&サイン会 レポート
トーク&サイン会 目次
- 題材選びは「面白さ」よりも「物語としての可能性」
- どちらが推敲後!?ビフォアアフタークイズ!
- タイトルの決定方法!2つのアプローチ
- 参加者からの熱い質問と山田先生の貴重な回答!
- サイン会、イベント後の様子もちらっとご紹介
題材選びは「面白さ」よりも「物語としての可能性」
まずは「題材選び」についてのお話です。新たに小説を書き起こすとき、どうやって題材を探し、なにを基準に選ぶのかをご紹介いただきました。
山田先生「まず初めに考えるのは、これを小説にしたとして、価値のある作品にできるかということ。この題材に長編を最後まで支え切るだけの発展性があるのか。設定や題材がいくら面白くても、そこから面白いストーリーを展開できなければ意味が無い。物語としての可能性がどれくらいあるのか、時間をかけて吟味する。
今の自分の力でこの題材を書ききれるのか。これなら書けそうだと思ったら要注意。むしろ今の自分には無理だ、自分の手にあまると感じるくらいがちょうどいい。自分にできることをいくら繰り返しても、それは進歩にはつながらない。作家として長く続けていこうという時に、進歩が止まるというのは、とても怖いこと。それを避けるためには、意識して背伸びをし続ける。それが、小説家として生き残るのに大きな要素だと考えている」
『百年法』(KADOKAWA/角川書店)の場合
山田先生「あの基本的なアイディア、「不老化した人々は百年経ったら自分から死ななければならない」というものは、10年以上前にテーマを思いついていたが、その設定をいかすストーリーが見つけられず、ボツにしていた。数年前に編集者の人たちと打ち合わせをしていた時に、雑談の中で『百年法』の設定の話をしたら、そこに居合わせた編集者お二人が、「面白い!」と声が揃った。そこから話が盛り上がり、はっと気づいた時には、書くと約束をしていた。そのおかげで、あの作品を書き上げることができた。その結果、予想を超えて話題になり、売れて、増刷され、推理作家協会賞もいただいた。もしあの時、編集者の方が「面白い」と食いついてくださらなかったら、あの作品は世に出なかった」
『嫌われ松子の一生』(幻冬舎)の場合
山田先生「『嫌われ松子の一生』は、何を書こうかと決める段階で、5つプロットの候補を考えた中の、最後のおまけのように付け加えたものだった。編集者の方に読んでもらったら、「『嫌われ松子の一生』が一番よさそうですね」と言われた。ここでも編集者の嗅覚に助けてもらっている。小説の題材を決めるときに、自分の書きたいものを書くのは大事で基本でもあるが、そこにこだわりすぎてしまうと、いつの間にか視野が狭くなりだんだん息苦しさ・窮屈さを感じることもある。そういう時に周りの人の意見を聞くと、意外なところに突破口が開け、予想もしなかった新しい展開が見えて、自分の殻を打ち破るきっかけになることもある」
どちらが推敲後!?ビフォアアフタークイズ!
次は「推敲」についてのお話です。実際に山田先生が書いた文章を例にして、「推敲ビフォアアフタークイズ」!どこに着目して、どういう効果を狙って、修正を加えたのかを解説していただきました。
第一問
次のAの文章と、Bの文章、どちらが推敲後の文章だと思いますか?
【A】
西原寛治の遺体が、雨で増水した用水路の底から引き揚げられたのは、翌日の午後遅くになってからだった。
【B】
雨で増水した用水路の底から、西原寛治の遺体が引き揚げられたのは、翌日の午後遅くになってからだった。

みなさんお手元の資料にメモを取りながら、真剣に考えていました!
【解答と解説】
この文章は小学館『人は、永遠に輝く星にはなれない』から抜粋したもの。(お客さまにお聞きしたところ、Bだと思った人が圧倒的に多い)先生が選んだのはB。
山田先生「この前の場面は、ほとんどの読者が西原寛治は死ぬだろうと推測できる状態にある。そこで場面が転換して冒頭の文章がこちら。
Aだと、読んだ瞬間に西原寛治の死が確定する。主人公の死なので、インパクトがある。そのインパクトが強いせいで、あとに続く一節が読者の頭の中を素通りして読み流されてしまうかもしれない。
Bだと、場面が展開して読者が最初に目にする言葉が「雨」、次が地上の現象である「増水」、一段視点が下がる「用水路」、「底」、この順番で読者に提示することで、不穏な空気が流れながら読者の視点が空から地上に降りて、用水路の底まで一気に沈んで、そこで初めて西原寛治の死体に対面する。
どちらが正しくて間違っているということではない。何を重視するかによって変わる。読者を物語に引き込んで一気に読んでもらいたい。そのためには、Bの方が効果的であると考えた。
逆に、読者にインパクトを与えたいという作家さんであれば、Aを選ぶはず」

先生がBを選んだ理由を、ぴたりと当てたかたがいらっしゃいました!すごい!
第二問
続いて二問目です。次のCの文章と、Dの文章、どちらが推敲後の文章だと思いますか?
【C】
降り立ったのは男。一人。小ぶりのケースを持っている。軽快な足どりで通用口へ向かう。顔をはっきり視認できた。
間違いない。
彼だ。
僕は急いで社用車を降りた。
【D】
降り立ったのは男。一人。小ぶりのケースを持っている。軽快な足どりで通用口へ向かう。顔をはっきり視認できた。
僕は急いで社用車を降りた。
間違いない。
彼だ。

解答と先生の解説は……
【解答と解説】
この文章は5月にKADOKAWAから刊行される『代体』から抜粋したもの。(お客さまにお聞きしたところ、Cだと思った人が少し多い)先生が選んだのはD。
山田先生「Cでも問題なさそうに見えるが、「間違いない。彼だ」という「僕」という人物の心の言葉の部分で、文章の流れが止まる。何かをずっと待ちわびて、いざその瞬間がきた時は、何よりも先に体が反応するのではないか。そのあとで言葉や感想が意識にのぼってくる。Cはスピード感が削がれて、「僕」の切迫感が伝わってこない。
Dは、顔をはっきり視認して、次の瞬間には体が動いて車から出て、駆け出そうとして、そのあとで「間違いない。彼だ」という言葉が追いついてくる。こちらだと流れが止まらず、むしろ加速している。人間の動作として、このほうがリアル。「僕」のはやる気持ち、切迫感が伝わってくる。そう判断してDを選んだ」
タイトルの決定方法!2つのアプローチ
次は「タイトルの決め方」についてのお話です。実例をあげて、なぜそのタイトルになったのかを解説していただきました。『嫌われ松子の一生』と『百年法』は、別の決まり方をしたそうです!