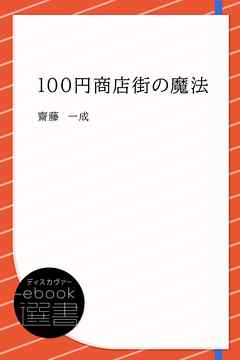感情タグBEST3
Posted by ブクログ
100円商店街をはじめ、いす-1GP、人生ゲームなど商店街活性化のために数々のアイデアを生み出したNPO-AMP。100円商店街は一見単純で簡単そうなシステムに思えるが、その裏には齋藤さんが考えた緻密なロジックが隠されていることが分かった。次はどんなアイデアが生まれるのか非常に楽しみだ。
Posted by ブクログ
五月新月の日におすすめする一冊は、齋藤一成著『100円商店街
の魔法』です。著者は山形県新庄市職員とNPO理事長の二足のわ
らじをはいて、地元新庄市はもとより、全国の商店街の活性化に
飛び回るスーパー公務員。何とまだ30代です。
「100円商店街」とは、商店街と100円ショップとの掛け合わせか
ら生まれたもので、各店が趣向を凝らした100円商品を店外のワゴ
ンに展示することで、商店街全体をあたかも一つの100円ショップ
のようにしてしまおう、という販促イベントです。
商店街の活性化といえばイベントというのは常道ですが、どんなに
イベントで人を集めても、肝心のお店の売上にはつながらない。市
役所職員としてその現実を目の当たりにした著者は、個店の売上増
加につながる商店街の活性化方策を考える中で、100円商店街とい
うアイデアに行き着くのです。
このアイデアが秀逸だったのは、何よりもお金がかからないことで
す。何せ各店が自ら設定した100円商品を店外のワゴンに陳列する
だけですから。しかし、この「各店」がミソなのです。何を100円
商品とするか、それを餌にどう通常商品の購入に結びつけるか、各
店主のアイデアと努力が問われるからです。つまり、店主の主体性
を引き出す点が、行政主導の凡百の商店街活性化方策と大きく異な
るのです。そして、仕掛人である著者達は、「接客は店外、会計は
店内」等のルールをつくることで、実売につながるような仕掛けを
埋め込んでいきます。
このように、100円商店街のコンセプトを生み出したことに加え、
売れるよう、買いやすいよう、店主とお客さまとの双方への仕掛け
(=ファシリテーションの仕組み)を随所に埋め込んでいくところ
が著者達の凄さです。物事を形にするには、コンセプトの力とファ
シリテーションの力との双方が不可欠であることを教えられます。
今の日本では、都心以外の商店街は軒並みシャッター通り。中心市
街地は廃れ、郊外の大型量販店に車で買い物に行くのが普通の暮し
になっていますが、これ以上高齢化と人口減少が進めば、大型店舗
の経営も成り立たなくなるでしょう。郊外の大型店舗が撤退したら、
一体、どこで買い物をすればいいのでしょう?通販でしょうか?
そう考えると、これからの地域の暮しを守るのは、商店街をおいて
ないのです。「商店街は最終的な生活基盤」と著者は言いますが、
まさに地域の生活インフラとして、商店街をどう維持、活性化し、
或いは復活、再生させるかが重要な課題として浮上してくるのです。
その時、お金より何より、面白いと思えることがあること、面白い
ことをしようと一緒にバカをやってくれる仲間がいること、そうい
う仲間と行動する中で、言葉にならないような感動に出会えること、
の大切さを本書は教えてくれます。そして、それらの結果として、ここに
いる人達とこの土地で共に生きて行くんだと肯定できるようになる
こと。それが商店街や地域の活性化が目指さなければいけないこと
なのでしょう。本書を読みながら、そんなことを考えました。
これからの地域社会のあり方について新しい視点をくれると共に、
考えることの重要性や商売の原点についても気づかせてくれる好著
です。是非、読んでみてください。
=====================================================
▽ 心に残った文章達(本書からの引用文)
=====================================================
行政がこれでもかというほど多額の補助金を投入し続けても、一向
に活性化する素振りすら見せない全国の商店街を目の当たりにすれ
ば、最初から補助金ありきの活性化策では、もはや商店街に活気を
取り戻すことなどできないことは分かるはずだ。
大型量販店は、人件費をはじめとする経費をある程度は抑制するこ
とができても、自然人口の減少から生ずる売上高の低下を食い止め
ることは難しいはずだ。彼らは収支のデッドラインを超えれば、す
ぐにでも撤退する構えを見せる。その証拠に大型量販店の底地は、
ほとんどが借地である。
地域で威を張る量販店のデッドラインの到来する時期まで、地元の
昔からの商店街が踏ん張って生き残っていられるだろうか。郊外大
型店が撤退するような事態に陥った時、すでに商店街が消滅してい
たら、その地域は生活基盤そのものを失うことになる。
この広い日本の中で、同じような企画を考えた人間は私以外にも多
くいたことだろう。だが、そこから先の明暗を分けるのは、実施し
たかしないかなのだ。
今、目の前にあふれているお客さまは、単なるイベントに「遊びに」
来たのではなく、「買物」という明確な目的を持って集まってきて
くれた方々なのだ。商店街の活性化とは、そこに存在する個店の収
益の増加だと私は考える。その目的のために考案した100円商店街。
まさに、会心の瞬間だった。
「利益を得る経済活動」である以上、商いを行なう方々は、いかに
して利を得るかを常に考え続けてきたはずである。言い換えれば、
商人の歴史とは、常に「考え」続けてきた歴史といっても過言では
ないはずだ。時代や文化、風習や制度、この世のあらゆるものが千
変万化する中で、唯一、一貫してきたのは、そう、この「考える」
ということ。
商人とは、「考える」からこそ商人なのである。だが、「考える」
ことをしなくなった元商人に、時折お会いすることがある。商店街
の方々と話をすると、「市役所は何もしてくれない」といった類の
話や、「郊外の大型店のせいで」といったグチに近い話を賜ること
がよくある。まさに、これこそが「考える」ことを停止した元商人
の姿そのものなのだ。
ただ人を集めても物は売れない。それが現実なのだ。その現実から
目をそらして、商店街にただ人を集めるためだけに、行政から大量
の補助金を受け取って、さまざまなソフト事業に投下しているのが
全国各地の商店街活性化事業の姿である。「もったいない」を通り
越して、もはや「無駄」と言わざるをえない。
少ない予算の中で、いかにして今の状況を突破するか。そこに存在
する人間の知恵が試されている。お金がなければないほど「腕試し」
ならぬ「知恵試し」の絶好の機会に恵まれたことになる。そう考え
ていくと、お金がないほどワクワクしてくる。
成功している地域には、ある共通点のあることが分かってきた。そ
れは何かというと、成功する地域には必ず「キーマン」がいて、ど
のキーマンも「打てば響く」タイプの方だということだ。簡単に言
ってしまえば「面倒くさく」ないのだ。
キーマンたちの周辺に必ず強力なサブキーマンともいうべき方が最
低二人は存在している。(…)そのため100円商店街の関係者の間
では、「ばかが最低三人は必要」という言葉が普通に語られている。
(…)ここで言う「ばか」とは、「まちのために骨身を削る努力を
惜しまない人間」のことである。
トドメの言葉に、しびれた。
「そういう面白い話、どんどん持って来てくれ。世の中を面白くし
よう!」
すべてが「金」と「時間」に支配されつくしている世の中で、「人
の気持ち」だけでここまで動いてくれる人がいたとは!
「おもしろき こともなき世を おもしろく すみなすものは
こころなりけり」
幕末の志士、高杉晋作の辞世の句である。
商店街は、最終的な生活基盤なのである。
それに気が付いていただければ、企業のCSRに「商店街の活性化」
がリストアップされ、多くの企業がその活動に参加してくださる日
も、そう遠いことではないと信じている。
自分たちの子どもや、その次の世代の子どもたちのため、いずれ高
齢を迎える自分たちのために、きちんと残しておかなくてはならな
いものの一つが、「商店街」である。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●[2]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
連休中、急に思い立って、亡き母の生家がある静岡県沼津市に行っ
てきました。「深海魚水族館」の存在を知ったのがきっかけでした。
母の生家を訪れるのは祖母の葬儀以来ですから、実に30年ぶりの
ことです。30年ぶりに訪れて驚いたのは、沼津が山と海に囲まれた、
とても風光明媚な土地である、ということでした。
母の生家は千本浜の近くで、「海と松林の感じが沼津に似ていたか
ら湘南を選んだ」とはよく聞かされていたことです。でも、こんな
に山が近くまで迫った場所だったということは、今回行って初めて
知ったことです。間近に見る富士山も凄い存在感でした。母は、こ
の山々と富士山と海と松林を見て育ったんだなあと感慨ひとしおで
した。
同時に、湘南育ちで、山とは縁のなかった自分が、それなのに山や
木や森に訳もなく惹かれ、かと言って、山だけじゃダメで、山と海
の両方を求めてしまう理由もわかった気がしました。こういう土地
で、こういう風景を見て育った母の血のなせるわざなのでしょう。
父や母が見ていた原風景を追体験することで、自分が受け継いでい
るものや、自らのルーツを確認することができるのですね。
もっとも、こういう経験ができたのは、海とか山とか松林とか、母
が過ごした時代から変わらずにあるものが沼津にはあったからだと
も思うのです。海や山や森のような自然の存在には、時空を超えて
人々をつなぐ役割があるのですね。