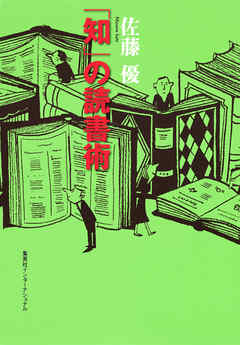感情タグBEST3
Posted by ブクログ
読書術の本だと思っていたらナショナリズムと帝国主義の参考書だった。かなり的確な指摘がなされていて勉強になった。
新・帝国主義とは植民地と全面戦争を避けた帝国主義の続きであり近代現代と連綿と続いている。こういった世界の基本的な論理と構造を押さえておくことが読書(世界の認識)に必要なことだという。道理・条理・義理・合理というものを理解することが読書の基本であるということだと思う。
啓蒙主義が戦争を引き起こす。その論理が非常に明確に示されている。合理主義というものの暴走でもあると思う。暴走は反省に依らなければ止まらないものである。ホッブスのリヴァイアサンもそういったものである。万人の狼は国家としてリヴァイアサンになる。国家間は自然状態となる論理である。ただ狼は非常に哲学的だという本も読んだ。哲学とは反省と帰納により世界を認識し改善の配慮をするものである。狼には哲学がある。そして国家間の自然状態にも哲学が有り得る。それが国連の試みである。
安倍政権へ的確に異議を表明していてすっきりした。立憲主義を理解していないらしい。反知性主義というものらしいがそのメカニズムもわかりやすく書かれている。
安倍の権力維持の姿勢の中身は空っぽということらしい。こんなことになって残念だというしかない。
グローバル資本主義が支配的になることが逆に国家機能の強化へ向かう理由は税収と再分配の破たんを引き起こすことでありそれが新・帝国主義へ向かっている理由であるという。
私に言えることは教養を身に着けるには反省に依るということだ。
Posted by ブクログ
実に耳の痛くなる話。『読書の技法』に続いて読んだ、著書2冊目の読書論。教養といえども、中高レヴェルの基礎を疎かにしてはいけないこと。それを、「受験勉強批判」と称して捨て去るのは、甚だ危険であると感じた。もう一度出直そう。
Posted by ブクログ
"今の時代、世界を俯瞰して眺め、各国の動向を理解し、様々な文化を受容しつつ、育った国の歴史、背景を理解し語れる教養人になるための読書活用法。
電子書籍で購入する本は、すでに蔵書となっている本で、頻繁に読み返したいような2冊目の本にしなさいとのアドバイスはなるほどと思った。
岩波の世界歴史
松岡正剛さんの千夜千冊
は手元にあるが、引っ越しした時の段ボールの中。
早く広げたいが、そのスペースを作れずに今日に至る。"
Posted by ブクログ
時代を読み解く力を身に着ける為の読書術を紹介する本。
対象読者は優秀な若者。
前半は中世~近代の歴史認識を正しくする方法について述べている。
参考になる本を取り上げながら、時代の区切り方や新自由主義から独裁傾向が強まる理由を解説している。
麻生太郎や安倍晋三に見られる立場を超えた思い通りに事を運ぼうとする反知性主義も紹介されている。
興味深いのは「独裁政権の作り方」の様な本が紹介されていて、日本を含め世界各国で独裁や王政に近づいているという事実。
後半は読書に関するツールの使い方について。
電子書籍、インターネット、英語教材、リアル書店を取り上げている。
情報が氾濫しているので、良い知識を身に着けるには古典や、高校の日本史・世界史・公民を読むこと。
その上でリアル書店に足を運び、書店員の知識の恩恵を受け、良い知識を身に着ける。
ウィキペディアなどインターネットの情報は質が悪いので頼らないこと。
平易な文章で分かりやすく語られているが、常に政治や世界に関心を寄せる高い視点に立脚しており、ついて行けない部分も感じた。
世界の政情をハッキリと理解したい人におススメです。
Posted by ブクログ
寝る前のフォトリーディング&起床後の高速リーディング。とても面白い。
近代が教会と国家を分離して始まり、民族自決から民主主義という宗教を経て、再びいま帝国主義が蘇っていると著者は指摘。なかなか深い考察で、単なる読書術の本ではなさそう。
また電子書籍の使い方についてはとても参考になる。でもその未来については私の考えとちょっと違い、電子書籍はそれほど普及しなさそうだと考えているようだ。
下記に付箋を貼った箇所の要約をのせる:
12-15:多くの本が(古典新刊どちらも)まだ電子書籍化していない。故に日本の電子書籍時代はまだ先。しかし電子書籍の利点を挙げると・・・:
1.電子書籍専用リーダーで本を大量に運べ、しかもネット断ちして読書ができる。
2.再読・流し読みに向いている。ちょっとの空き時間で気になる本を出して読める。
3.語学学習に向いている。
15:重要になってくるのは広い知識ではなく、深い知識。
44:ドイツの神学者トレルチが近代の初めと定義するのは1648年のウエストファリア条約。この条約は30年戦争(1618~、中世最大の犠牲者を出した戦争。宗教戦争。神聖ローマvsブルボン王朝・新教vs旧教。)の講和条約。
この時代より国家と教会が分離した。民族自決の初め。
104-105:電子書籍専用端末は自発光しないので目に比較的やさしい。感覚も神の本に近いので頭に入りやすい。
111:電子書籍は神の本より流し読みをしやすい。二冊目の購入に向いている。
118:質の高い本を深く、また繰り返し読めるのは、これからの教養人にとって電子書籍はアドバンテージになる。
132:高校の日本史や世界史の教科書を通読の後、「岩波講座 日本通史」や「岩波講座 世界史」を読む。こうした読書が基礎を強化する。
147:英文法はセンター試験の過去問で鍛える。その基礎が整ってから語彙を増やし、原本を読む。
154:これだけ玉石混交の出版物の中で、目を養うためには先ず古典を読むこと。
159-160:本は身銭を切って手元に置くべし。
Posted by ブクログ
歴史を学ばなければ、と痛切に思う。ただし、学生時代のような学び方ではなく。現在起きていることに過去からのつながりがあることをきちんと考えながら。
学びの重要性を感じた後に、そのための技術も提示されていて、かつ、これからの生き方まで示唆されているという、みっちり詰まった本。
Posted by ブクログ
東洋経済で連載していたコラムを読んで著者を知りました。
すごく勤勉なイメージがある著者の読書法の本です。
価値のある読書の方法や、英語の勉強の仕方、電子書籍の活用法など独自の活用法が書かれています。
読書においては、やはり古典や文学界の有名な本などを読む事が大切なんだなぁと実感しました。
英語も勉強をしては、やめ、してはやめの繰り返しでしたので、また改めて勉強再開します。
本も古典を読む割合を増やします。
勉強に対するモチベーションをあげたい方におすすめです。
下記は読んでみたいと思う本です。
「20世紀の歴史」エリック・ボブズボーム
「ルネサンスと宗教改革」エルンスト・トレルチ
「トレルチ著作集」エルンスト・トレルチ
「歴史と階級意識」ジョルジ・ルカーチ
「帝国主義」ウラジーミル・レーニン
「独裁者のためのハンドブック」亜紀書房
「天守物語」泉鏡花
「資本論を読む」伊藤誠
「外国語上達法」千野栄一
「僕たちの前途」古市憲寿
「ぼくはお金を使わずに生きることにした」マーク・ボイル
Posted by ブクログ
佐藤優さんによる、今の時代を読み解くための一冊。
と一口で言ってもちょっと変わっていて、、
読み解くために必要となる「知識」を得るための、
そのための「書籍」をいろいろと紹介してくれています。
個人的にはホブズホームの『20世紀の歴史』、
こちらとはきちんと向き合わないと、な感じで。
国民国家の再定義、自身の言葉でしておかないと、です。
あと、電子書籍の使い方にまで踏み込んでいたのも、面白く。
五感と紐付けての知識のインテリジェンス化、なんて考えると、、
個人的には、電子書籍はまだ早いかなとは感じています。
出版自体も“紙”の本とはだいぶタイムラグがありますし。
そういった意味では、佐藤さんのおっしゃる、
持ち歩きたい本を電子“でも”購入とはなるほどと。
Posted by ブクログ
教養や読書についての著作も多い、佐藤優氏の新刊本。
内容は2部に分かれており、1部は、ホブズボームの「20世紀の歴史」やトレルチの「ルネサンスと宗教改革」を元に近代の延長上としての現代を読み解いている。また、帝国主義、反知性主義についても述べている。2部では、このような時代を読み解くための教養のツールとしての、電子書籍、ネットの使い方、英語の使い方などを述べた後に、知性として教養共同体の重要性を解いている。
佐藤優氏の本としては、読みやすい部類でイントロダクション的な部分が多い本になっていると思った。
Posted by ブクログ
教養の塊のような著者による読書ガイド。
第一次大戦から始まった20世紀の課題は今も解決されていない、という意見は同感。資本主義の歪みを如何に緩和して帝国主義化を防ぐか、だと思う。
また、今の本から100年後も残る本を探し当てるのは難しい、読まれ続ける古典には普遍的な論理が宿っている、は納得。その理解の為にも、中高の教科書レベルの内容を押さえよう…
Posted by ブクログ
2章の読書周りの話は、前に読んだ著者の別の本と内容が被ってるので感想は割愛する。
(教養共同体というキーワードは心に残った)
この本の出版からさらに5年経っているが、今も「短い20世紀」の延長にあると感じる内容だった。
世界はどんどん右傾化し、中国はさらに帝国主義を強め、空洞化した庶民はオンラインサロンという中間共同体に依存している。
一方で会社のような組織レベルでは、資本主義社会の問題に対する解を見出しつつあるように思う。
ティール組織は労働者を交換可能な合理的存在として見ずに、非合理な存在として見ているともいえる。
あらゆる分野が多面的に絡み合っているため、今後も雑食的に読書をしていきたい。
Posted by ブクログ
著者らしい読書の考え方と選書の数々。
最初の歴史問題から入っている時点で若干めげるけど後半は興味深い内容。
ネットでの情報ソースが一般人とは少し違う。
Posted by ブクログ
タイトルは「知の読書術」だが、内容は漠然とした知識のことではなく、これからの世界情勢のことだった。ウクライナ危機を理解するには、第一次、第二次世界大戦から今は繋がっているので近代史を学ぶべきである、と具体的なおすすめ本とかニュースサイトとかが載っているので役に立ちそう。電子書籍は脳に入りにくいので、紙の本メインに電子書籍は参照するときに使えというのは納得した。