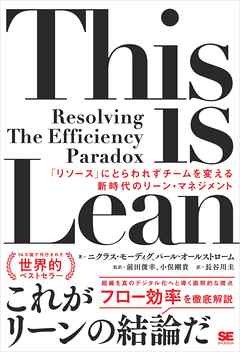感情タグBEST3
Posted by ブクログ
リーンについてググるといろんな分野・レベルの説明があるけど、つまりどういう事なんだろうという読む前に持っていた疑問をまさに解決してくれる一冊だった。
Posted by ブクログ
リーンとは状態ではない。「昨日よりも明日をより良くするためにはどうすればいいか」、の考え方である。
よって、リーンな組織とは、その考え方が全員ができることである。
そのための重要な指標として、「リソース効率」と「フロー効率」というのが出てくるが、本質は、考え方の部分でありましょう。
メソッドなるものは、その考え方を新たな課題の局面に当てはめたときに出てくるものにすぎず、次の瞬間に陳腐化するものでありましょう。
Posted by ブクログ
複雑でわかりにくいリーンを、フロー効率とは何かをさまざまな観点でとらえることで説明している。効率改善といったときに、それはフロー効率のことなのかリソース効率のことなのか自然と疑問に持つように、強烈にフロー効率について意識するようになる。
Posted by ブクログ
リーンとは、フロー効率を高くする事を目的としたオペレーション戦略である。
このために非常に丁寧に分かりやすく説明されていた本でした。
仕事で、会議が多い状況や開発が属人性になってるところを単に変えるのではなく、価値観から考えることで正しい実現方法が見つかると思ったので、さっそく試したいと思った(ただし時間はかかると思う)。
Posted by ブクログ
私が「フロー効率」という言葉を知ったのは、 @i2key さんのスライドからだった。
その参照元である「This is Lean」がついに日本語訳された。
一次ニーズが満たされないことにより発生する二次ニーズ。ふと立ち止まって考えると、我々が日々汗水を垂らして時間を費やしている仕事は、大半がこの二次ニーズを満たすことに終始しているのかもしれない。
元本を返済することができず延々と利子を支払い続けるリボ払いのようなもので、そんな仕事と「ブルシット・ジョブ」の間にはあまり距離がないように思える。
リソース効率が悪なわけではなく、時と場合により重視する効率のモードを変えること。リーンでは、原則としてフロー効率へと接近していくものであること。
そしてリーンはツールやプラクティスではなく、こうなったらリーンという静的なものではないこと。
実に明快に「リーン」が解説されており、とっつきやすかった。
Posted by ブクログ
フロー効率とは、システム境界を定義し、スループット時間が中の付加価値アクティビティ時間の割合を高めること。
スループット時間=システム境界で定義されたプロセス内にあるフローユニットx サイクルタイム。
leanは目的とする状態であり、上がり続けるものである。
目的に達するためにメソッドやアクティビティが存在する。
これだ!すごく理解したって感じではなくなんとなく感覚としてわかったかも?ぐらいの感覚。次はリーン・スタートアップを読んだみたいと思った。
フロー効率は一個流しすることだという単純理解から思考が広がった感じはする。
Posted by ブクログ
職場の人が最近フロー効率ってワードをよくつかい出したので、フロー効率がわかりやすく説明されているということで読んだ本。
フロー効率がどんなものを指すかはわかりやすかったが、途中で出てくるトヨタの話は正直????ってなったので他の本を読んだ方が良さそう。
というかリーンの元になったトヨタ生産方式の根本的な考え方を知って読むのとそうでないのは読み易さが大きく変わるので、そっちも併せて読みたい
Posted by ブクログ
リソース効率とフロー効率を理解できる本
サンプルや事例も豊富で、イメージしやすい。
やればできる、これならリーンという話では無く、組織的の重要性を改めて感じさせてもらった。
Posted by ブクログ
フロー効率とリソース効率を両方とも100%にすることはできない。組織としてどちらを優先するのか、どんな手順で理想的な状況に近づけるように考えるかが重要というのは、この本でいうところの原則
一方で、よくある組織であるはフロー効率について意識を払っておらず、リソース効率のみに着目していることが多く見える。自戒も含めて
Posted by ブクログ
リソース効率とフロー効率について日常生活で起こる出来事を例えに説明していてわかりやすかった。その上で、現在の企業ではリソース効率を重視するあまりにフロー効率が悪く、企業視点ではうまく運営されているように見えても本来主眼を置かれるべき顧客からすると非常に問題のある状態であることが書かれており、フロー効率を目指すために目指すべき価値体系をリーンと呼ぶと理解した。
リーンとはつまり、ツールやメソッドの集合体ではなく根底にある価値「無駄を省く」をもとに原則、メソッドと波及されていくべきものであって、メソッドを取り入れただけで「これがリーンだ」とはならない。
また、「リーン」ができている状態も一律的に評価できるものではなく、フロー効率を上げていくことを目的とするのであれば静的な評価は行えない。常に動き続ける。
Posted by ブクログ
■フロー効率
特定の期間にどれぐらいのフローユニットが処理されているのかを知る尺度となる。この場合の期間とは、ニーズが特定されてから、それが満たされるまでの時間のこと。
■リーンの中核となる原則(「リーン生産方式が、世界の自動車産業をこう変える。」)
1 チームワーク
2 コミュニケーション
3 リソースの有効利用とムダの排除
4 継続的な改善
■新しい5原則(「リーンシンキング」)
1 最終顧客の視点から価値を決める
2 価値の流れを理解し、価値をもたらさないステップのすべてをなくす
3 顧客までの製品のフローを円滑にするために、価値を生む残りのステップの流れをよくする
4 フローが確立したら、顧客のリクエストを起点に、下流から上流工程へと価値の流れを動かしていく
5 ステップ1からステップ4までが終わったら、プロセスを最初から繰り返し、ムダのない完全な価値をつくり出す完璧な状態になるまで続ける
■トヨタの3つの能力レベル「The Evolution of a Manufacturing System at Toyota」
レベル1-ルーチン化された製造能力
レベル2-ルーチン化された学習能力(カイゼン能力)
レベル3-進化能力(能力を育む能力)
■4つのルール(「Decoding the DNA of the Toyota Production System」)
1 すべての作業は、内容、順序、タイミング、結果の点で極めて具体的でなければならない
2 顧客とサプライヤーは例外なく直接つながっていなければならず、要求を送ったり、応答を受け取ったりする際には誤解しようのない「イエス」か「ノー」を用いる
3 すべての製品とサービスの経路は単純で直接でなければならない
4 ありとあらゆる改善は、科学的手法を用いて、指導者の指揮の下、組織内の可能な限り低い階層で行わなければならない
■トヨタウェイ
知恵と改善
・チャレンジ:夢の実現に向けて、ビジョンを掲げ、勇気と想像力をもって挑戦する
・改善:つねに進化、革新を追求し、絶え間なく改善に取り組む
・現地現物:現地現物で本質を見極め、素早く合意、決断し、全力で実行する
人間性尊重
・リスペクト:他を尊重し、誠実に相互理解に努め、お互いの責任を果たす。
・チームワーク:人材を育成し、この力を結集する。
■ライカ―のトヨタウェイ
Ⅰ 長期哲学
1 短期的な財務目標を犠牲にしてでも、長期哲学にもとづいて経営上の意思決定を行う
Ⅱ 正しいプロセスが正しい結果をもたらす
2 継続的なプロセスフローをつくって、問題を表面化させる
3 つくりすぎをなくすために”プル”方式を用いる
4 仕事量を一定にする
5 手直しが必要なときには、品質を即座に正すためにプロセスを停止する
6 継続的な改善と従業員の強化のためにタスクとプロセスを標準化する
7 問題が隠れるのを防ぐために視覚的な監視を行う
8 従業員とプロセスに貢献できる、十分にテストされた信頼性の高い技術のみを用いる
Ⅲ 人材とパートナーを育てる
9 仕事を完全に理解し、哲学を体現し、それを人に教えることができるリーダーを育てる
10 会社の哲学に従う卓越した人とチームを育てる
11 課題を突きつけて成長を手助けすることで、パートナーとサプライヤーを尊重する
Ⅳ 根本的な問題を継続的に解決して組織学習を促す
12 状況を完全に理解するために、現場に行って自分の目で見る
13 時間をかけて合意の上で決断を行い、決断を迅速に実行に移す
14 徹底的な熟慮と絶え間ない改善を通じて学習する組織になる
リーン式のオペレーション戦略には、マトリックス内を右へ移動する、つまりフロー効率を高めるという要素が欠かせない。フロー効率とリソース効率の選択では、迷いなくフロー効率を優先する。トヨタ生産方式の父である大野耐一もフロー効率の重要性を認めていて、こう述べている。「私たちがやっていることといえば、顧客が注文した瞬間から私たちが現金を受け取るまでのタイムラインを見ることだけだ」
■会社を植えたばかり一本の木とみなす
・どんな木を美しいと感じるのだろうか?
・どんな木を美しくないと感じるのだろうか?
これらの問いに共通の答えが見つかったとき、我々は自分たちの考えを価値観にまとめたのです。価値観が、木に対してどう接するべきかを決めてくれました。最も大切な価値観は、つねに顧客を第一にすること。顧客のニーズを満たすことです。顧客のニーズを満たすことは、美しい木にたとえられます。顧客のニーズがほかの何よりも優先される。顧客を満足させることで、木を大きくすることができるのです。いちばん重要なのが顧客で、顧客を何よりも優先しなければならない。トヨタで働く者全員にとって、我々の価値観が困ったときに答えを求める場所になりました。価値観のなかに、あらゆる状況でどうふるまえばいいかの答えが見つかる。価値観が我々にどうあるべきかを示してくれる。それらが我々の社風の中核になったのです。
■二つの原則
長い発展の末、我々の考えは二つの原則に要約できることがわかりました。一枚のコインの表と裏の関係にある原則です。一つ目の原則はジャスト・イン・タイム。フローを生み出すことです。サッカーを想像してください。チームがボールをピッチの一方の端からもう一方の端までパスでつなぎ、最後には対戦相手のゴールに蹴り入れるとき、フローが生まれます。ボールはつねに動いている。選手の全員が協力して、ボールが流れるべき完璧なルートを見つけようとする。ボールはピッチを縦断してゴールまで流れる。基本的にサッカーのゴールは、顧客に望みどおりのものを、望み通りの時間に、望み通りの品質で届けるのと同じこと。カスタマーサービスとは、ゴールを決めることなのです。
■ジャスト・イン・タイムと自働化
ジャスト・イン・タイムはフローを生むことを、自働化とは目に見えるはっきりとした像を得ることを意味しています。それにより、フローを起こしたり、妨げたり、せき止めたりするものすべてを、すぐに把握できるようになるのです。この二つの原則は一枚のコインの表と裏であり、両面がそろってはじめて、つねにしっかりと顧客に目を向けて”ゴールを決める”ことができるようになる。