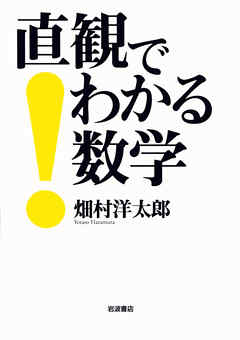感情タグBEST3
Posted by ブクログ
高校数学の教科書では書かれていない背景
いきなり「そういうものだ」的に教科書に載ってることを、それをどういうことか解説してくれている。
巻末の付録・語録がまた凄い。これが頭が良くなるヒントだと思う
Posted by ブクログ
高校の数学の先生に読んで欲しい一冊です。が、この本の内容をおもしろいと思えるのは一通り数学を学んでいることが前提にある気がします。
私は理系で情報科学を学んできたなかで、テストで点数をとるためには腑に落ちなくてもこういくものなのだと、数式の意味を理解せずに覚えてきました。
これまでの勉強の裏側にこんな理屈があるんだと、現実世界にもっと寄せて考えるとこういう意味だったのだと分かるような内容になっているため、自分にとっては大変嬉しいです良書でした。
なので、私みたいにとりあえず、本質を理解してなくても、数学は解ければ良いと思って勉強してきた方にオススメしたいです。
Posted by ブクログ
高校生の時に出会っていたらなー!数学嫌いのせいで理系を諦めた私の悶々とした気持ちを、一気に昇華させてくれました。
具体的な解法を教えてくれるわけではないのですが、考え方と取り組み方を説いてくれる稀有な本です。子どもが高校生になったらぜひ読ませたい本です。
Posted by ブクログ
この本は、名著である。数学に対して何だか違和感があった処の根拠が示されている。「納得できないからワカラナイのである」し、「意味不明の概念を丸飲みさせられている気色悪さを感じる」とハッキリ記されている処が秀逸だ。その上、「わかる」ためには「受け取る人の頭の中にある型紙,テンプレート」に合うように説明しなければならない、ということが指摘されている。なぜ今まで誰も言ってくれなかったのだろう。よくよく考えれば、18世紀にカントが確立した認識論ではないか。哲学と数学では異なるとでも思っていたのだろうか。数学のもつモノを理解するツール性は、後追いのつじつま合わせでないテンプレートの提示が必要である事を高らかに宣言した書である。「教科書は解ける方程式しか取り上げない」ということは、小学校の算数から始まって自明のことだったのだ。一読をお薦めする。
Posted by ブクログ
遠ざけられることの多い数学ですが,この本を読むと,
そういうことやったんやあ〜とあまりにも納得して
一気に数学が自分の頭の中で考えられる範囲内にある
実感を掴めると思います.特に感動したのは複素数の
説明や,対数の説明ですね.
そしてより大事なメッセージとしては数学に
とどまらず物事を見つめるときの視点は本当に
様々で自分が立っているところから自分がこう
思うという一つの視点から物事を見ていては
もったいないよということを密かに感じました.
Posted by ブクログ
だいぶ前に読んだのですが、頭のモヤモヤが少し晴れた気がしました。書かれている通りこれで数学に強くなれるという内容ではないのですが、数学の根底にあるものを理解をする上では、とても大切なことが書かれている書であることは間違いないと思います。読んでいてすごく面白いです。
Posted by ブクログ
本棚で眠っていた本を読んだ。以前この本をぱらぱら見たときには、これだけじゃ分からないと思った。でも、最近、遠山啓の数学入門を読んでいると、この本で説明されているイメージがすんなり分かった。
Posted by ブクログ
数学の本質について、考えさせてくれる。筆者の独特の絵柄もあり、分かりやすく、読みやすい。なぜサイン、コサインという名前なのかとか、行列のタテとヨコの意味とか、読んでて面白いし、理解も深まる。
Posted by ブクログ
数学の世界には建前(定義付け)がたくさんあります。「このように表したものを行列と呼ぶ(ことにする)」とか、「二乗して-1になる数をiと定める(ことにする)」などなど、特に数学が嫌いという人にとっては、「どうしてそうするの?」「それにどんな意味があるの?どんな役に立つの?」と思うようなことがいっぱいです。
この本は、小難しい理屈はひとまず置いておいて、まさにタイトルの通り「直観的に」数学を解説してくれる本になっています。
三角関数、行列、複素数、微分・積分、確率等、色々な分野が取り上げられていて、文章も柔らか目(加えて、数学教育に対する不満がいっぱい?)なので、数学が嫌い!という人にこそぜひ読んでみてほしいと思います。数学が好きになるきっかけになるかもしれません。
Posted by ブクログ
あまり数式の出てこない数学の本。高校数学に対する不満をぶつけた感じが心地よい。直観でわかるはずの数学については、さわりだけでその後がないのがもどかしい。巻末の暗算法は、一時流行ったインド数学と似ている。
Posted by ブクログ
高校時代にただ問題を解くだけに終わり、つまりどういうことなのかよく分からなかったことを簡単に説明された一冊。簡単にしすぎている感もあるものの読み終わってスッキリした。
Posted by ブクログ
「『わかる』とは瞬間的に頭の中で起こる対象の確認動作である。すなわち、『わかる』とは直観そのものである。」(前書きより)
著者・畑村洋太郎氏が大学退官後、最早失う物など何もない、という勢いで(笑)、
三角関数、行列、微積など高校数学の分野を直観的に説明し、
巷の数学教育に毒を吐いたりする本。
数学がキライだ、という人が本当に好きになるかどうかはわからないが、
数学好きな人間はますます数学の面白さに惹かれること請け合いである。
とかく現実世界と距離感を感じていた高校数学がみるみるうちに
日常世界へ引っ張りこまれてくる著者の説明は圧巻。
Posted by ブクログ
これまで抱いて来た、数学にたいする疑問や不信感が
見事に払拭できた。いっぽうで、自分が受けてきた教育というものが、
洗脳に似たものにも思えてしまった。。
物事の単純化や見える化によって
コラボするためのツールとして
偉大な発明であることも事実。
要はお付き合いの仕方といういことか。
Posted by ブクログ
この本を読めばすぐさま数学アレルギーが取れる、
という代物ではありませんが、読み始めるとはまって
しまったような感覚に陥りました。
私も高校時代
「なんで虚数なんて概念があるんやろか。。。
こんなもん自然界に存在するんかいな」
ととても不思議に思ったことがあります。
理系の人が読むと、「そんなことはわかりきって
いる事だ」「もっと別な説明の仕方がある」と
少し物足りないものを感じるかもしれませんが、
理系の人もそうでない人も読んで損は無いと思い
ました。
考え方を変える。それだけでこうも捕らえ方が
変わるものなのでしょうか。
Posted by ブクログ
話し言葉で、注目するところは大きな字で書いてあり、
「本題からづれるが」といいながら蛇足した文章も面白いため、
高校で習った数学を、苦にならずに復習できる。
感覚的に数字を捕らえ計算する方法は、パソコンなど無い環境で実験データを簡易的に観て、問題点の把握、原因の分析を行う際に役に立ちそうである。
Posted by ブクログ
数学がわからないので読んだ。これでわかるようになった。ということはないが、す学をもっと学んで見ようという気になった。「覚えよう」ではなく「やってみよう」は、特に大切だと思った。
Posted by ブクログ
残念ながら、本書を読んでも「直感で分かる」ことはできなかったです。
どの項目に関しても「この先をもうちょっと知りたいのに!」ともどかしくなる終わり方で読み終わってもスッキリ感を得るにはほど遠い感じ。
しかし、教える側の立場の方が読まれるには視野が広がりいいのかもと思います。
数学できないけど好きだし分かりたい、という程度の私向きではなかったです。
Posted by ブクログ
数学の読み物としては異色といっていいと思います。なんせほとんど数式というものは出てこない。代わりに目につくのはゴシックの強調されたフレーズと絵。
数学といえば苦手科目の代名詞といっていいでしょう。数学にやられる原因は人それぞれですが、公式があれば解けるけど何をやっているのかよくわからないというモヤモヤ感に見に覚えのある人も多いはず。
そこで、本書はもっと意味、何をやっているのか、どういうことなのかっていうことを解説してくれる本です。数学でナゼこんなものを、といえば虚数ですが、それについても、複素数とあわせて一章ありますので、そこだけ読むとか、気になるところだけ読んでも大丈夫なオムニバス形式です。
個人的には、最後の「語録」が一番おもしろかったです。暗算の仕方(心構え)とか、「わかる」ってどういうことなのか(逆に言えば学校の数学はなぜわかりづらいのか)、って話です。
Posted by ブクログ
数学の雑学本.
それぞれの単元を習う前と習った後に一読したかったなとつくづく思う.
著者も述べているように読んだからと言って数学の点数が上がることはほとんどないだろう.逆に勉強をしない免罪符にもなりかねないような記述も多かった.
著者は数学が根本では好きだから,数学が嫌いな人や敬遠しがちな人が本書を読んでも,やはり数学というもののとっつきにくさは変わらないように思う.
本書を読んだだけではそこの壁はやはり越えれないように思う.
でも,個人的には数学は嫌いではないので読んでいて楽しかった.
虚数の名づけ方は自分自身の深慮のなさを思い知ったので良かった.
具体的なモノをまず考えるようにしようと思う.
Posted by ブクログ
とりあえずは一読した…最初はかなりとっつきやすかったのだが、自分自身の数学力のなさは相当なもののようで、これだけ噛み砕いてもらってもまだ、追いつけない。。
Posted by ブクログ
数学のコツというよりも、数学の根本的な概念・考え方をやさしく説いた本。数学において何よりも重要な定理や公理はみんなが当たり前のこととして捉えているが、この本ではそれをただ暗記するだけではなく、どうしてそう考えるのか、どうしてそう展開するのかについて触れており、数学がわかるようになるよりは数学が好きになる本だと思う。
でも結局、中には"そういうモノ"として受け入れなきゃならない定理はあるもので、それはまぁ都合のよい解釈だけどそうなるんだから受け入れてネ、のようなゴウインな進め方もあった。けれど、すんなり受け入れられるように現実に即して説明しているのでなぜか許せてしまう。数学を長年使い、かなり深い部分まで理解した筆者だからこそ、ここまで合理的に説明ができるのだろう。
Posted by ブクログ
失敗学の権威から「具体的から抽象へはいけるが、抽象から具体へは行けない(行こうとしてはいけない)」ってことを数学の本ですら言っておられる。
自分の中での完全に消化しきってはいないが、今後も考えずにはおかない何かを感じた。
Posted by ブクログ
数学がもっと分かるんじゃないかと淡い期待を抱いて買ったのだが、期待外れ。たまに感心することはあっても、理解の足しにとかはなかったかなあ。さすがにここに出てくるレヴェルの話は道具として使いこなせてるはずなので。塾で教えるときの参考になるかも?ところで塾で教えていて、数学なんて将来役に立たないやん、て言われる。図形の証明をやらせると、「俺、建築士とかにならへんし」と万事そんな調子。それはその通りなので、「でも仕方ないからやれ」と言ってる。僕自身の場合、物理をやりたいがそのためには数学が必要というわけで数学と付き合う理由がはっきりしているのだが、数学が分からなくても困らない人にとって数学を学ぶ意味はなんだろう? 論理的思考とかそういうこと? 著者はなぜこの本を書こうと思ったのか? 本文中、高校までの数学教育への批判が至るところに顔を出す。ちょっと感情的過ぎるんじゃないかと思うこともあるけど、この人の批判は正しい。けど、少なくとも、数学の真の姿を知ればみんな数学が好きになるだろう的な楽観論でこの本を書いてはいない。書きたいから書いただけなのかも知れんけど、気になった。第1章と最後の語録に出てくる山の高さの例で、現実的かつ簡単に高さを求める方法は、山に向かって一直線上の二点から頂上の仰角を測り、タンジェントを使うことだろね。他の方の感想を見てみると,続編があるようなので,そしてそちらの方が先に読むべき感じのようなので、読んでみようかしら。
Posted by ブクログ
失敗学で有名な畑村先生の書いた数学の本。確かに数学の本質を伝えようという努力の見られる本だが、わからなかった人がわかるようになるためにどのぐらい寄与するかは微妙な感じ。わかってる人が見たら、そーだね、っていう感じ。でも本の最後のほうに書いてある「数学はなぜわからないか?(その2)」の話は重要。