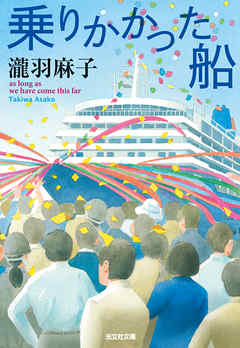感情タグBEST3
Posted by ブクログ
『異動の内示を受けた時点で、さっさと辞表を出せばよかった』。
会社員にとって避けられないもの、それが『人事異動』です。あなたが会社員であれば、人によって回数に差はあれど、今日までに必ずその瞬間を経験してきたと思います。定年までに一度も『人事異動』の経験なく会社員人生を終えられる方はいません。『人事異動』こそ、あなたが会社員であることの証明とも言えます。
とは言え、そんな『人事異動』に対するイメージは人それぞれでしょう。『人事の決定は、社員の人生を左右する』と言えなくもありません。不本意な『人事異動』によって涙を流した方もいらっしゃるでしょう。願っても叶わない『人事異動』に歯がゆい思いを抱えている方もいるでしょう。しかし、それでもあなたが会社員である限りそんな思いを胸にしまって日々、次々とあなたの前に訪れる仕事に立ち向かっていかなければなりません。会社員とは本当に大変な仕事です。”サラリーマンとは気楽な稼業ときたもんだ”とは、とんでもない歌があるもんだと思います。こんな歌は、クソ喰らえ!です。(失礼しました(笑))。
さて、ここに北斗造船という『中堅の造船会社』で働く七人の会社員が短編ごとに主人公となる作品があります。『現時点で、社員の数は七百名を超えている』という会社、『着実に業績を伸ばし、成長を続けてい』るという舞台裏を支える主人公たち。この作品は、そんな主人公たちが、会社員にとって避けられない『人事異動』の先に光と影を見る物語。『人事異動』の希望にさまざまな思いを募らせる物語。そしてそれは、『もう海に出てしまってるんだから。どんな潮目でも、進むしかない』と、社会の荒波に揉まれながらも日々前に進んでいく他ない会社員たちの悲喜交々な人生を見る物語です。
『岸につながれた真新しい大型客船を見下ろして、晴れてよかった』と思うのは主人公の野村雄平。『おはようございます』と入ってきた部長に挨拶した雄平は『朝会がはじまるまで、あと三十分近くある』ことを確認し、『ちょっと一本喫ってきます』と言い残すと会議室を後に喫煙所へと向かいました。そんな中に『一緒に仕事をしたことがある』資材調達部の村井と出会した雄平は、『営業も人手不足なんじゃないの』、『うちももう大変、回んない』、『ったく、人事はなに考えてるんだよなあ』と愚痴をこぼされてしまいます。『村井には、まだ知られていないらしい』と思う雄平は、『人事はなに考えてるんだよ』という言葉を聞いて、『おなじみの文句だ』、自分も『新人研修を終えて配属が決まったときには、同じことをつぶやいた』と振り返ります。『工学部で機械工学を専攻し、大学院まで出たというのに、なぜ営業に回されるのか、わけがわからなかった』という雄平。『三カ月間の研修でも、特に目立つ失敗をした覚えはな』く、それ以降も『年に一度の定期異動の季節がやってくるたびに』ぼやくことになった雄平。『同期入社の』『十人中八人が理系の出身で』、『雄平以外の全員が設計部か建造部に所属している』という中に一人営業で働く雄平は、『少しずつ営業の仕事をおもしろく感じられるようになって』きていました。そんな中に、『三カ月ほど前、三月の半ば』に、『二度目となる異動の内示を受けた』雄平。『とうとう船出のときがやってきた』と会議室へと向かった雄平…。『では、人事部の朝会をはじめます』と部長の声に現実に引き戻された雄平の前で朝会が始まりました。そして、会の終了後、一階へと降りた雄平が、受付に到着すると、『すでに、スーツ姿の若い男女が数人、所在なげに立って』います。九時半から始まる『新卒採用の会社説明会』の『開場を十五分前じゃなくて三十分前に前倒ししませんか』と契約社員の桜木に持ちかけた雄平。『わかりました』と返す桜木のことを『桜木は仕事ができる。ものすごく、できる』と思う雄平。そして、始まった説明会で、『今年でちょうど創業百周年を迎える、中堅の造船会社である』北斗造船について『営業部時代に培われた』『間合いの案配も』駆使して無難にこなし、質問を受け付ける段となりました。そんな中に『お仕事で一番やりがいを感じるのは、どんなときですか?』と訊かれ、『担当した船が無事に完成して、お客様に引き渡せたときでしょうか』と『命名引き渡し式』が行われる今日を意識して答えた雄平。しかし、そんな答えに『あの、人事部でも担当の船ってあるんですか?』とさらに訊かれ、『頬がかっと熱くなった』雄平は、『違います。僕、いやわたしは、営業部から異動してきたばかりなもので…』と『しどろもどろで続け』ます。不本意な人事異動に不満を抱える雄平のそれからが描かれていきます…という最初の短編〈海に出る〉。物語の舞台となる北斗造船の概要を見せながら、”お仕事小説”としての王道を描いてもいく好編でした。
“創業百周年を迎える中堅の造船会社「北斗造船」で働く人びとの苦悩と奮闘を鮮やかに描く、全七編”と内容紹介にうたわれるこの作品。七つの短編が連作短編を構成しながら展開していきます。そんな物語で描かれるのは、直球ど真ん中の”お仕事小説”です。小説にはさまざまなジャンルがあります。”恋愛小説”、”推理小説”、そして”ファンタジー小説”等々、私もさまざまなジャンルの小説を分け隔てなく読んできましたが、そんな中でも”お仕事小説”は最も愛すべきジャンルだと思っています。そして、そんな”お仕事小説”にも光の当て先によって読み味が大きく変化してもいきます。その一つの大きな区分けが、ある人物一人を取り上げるか、それとも複数の人物を取り上げるかという点でしょう。そして、後者とする場合、それはその舞台が、複数の部門を抱える会社組織になるのは必然だと思います。例えば、寺地はるなさん「ほたるいしマジカルランド」、畑野智美さん「シネマコンプレックス」などでは一つの大きな施設のさまざまな部門で働く人たちの生き様が描かれています。施設も会社ですが、もう少し会社っぽい作品としては、テレビ局の舞台裏を描く一穂ミチさん「砂嵐に星屑」などがあります。一つの組織を動かしていくには、さまざまな部門で働くさまざまな人の仕事がそこにある、”お仕事小説”としてとても読み味を感じさせてくれるものがそこにあります。そして、この作品で瀧羽麻子さんが取り上げるのは、さらに普通の会社に近づきます。それこそが、『今年でちょうど創業百周年を迎える、中堅の造船会社である』北斗造船で働く人たちを描く物語です。現場部門から管理部門まで、会社組織にとって当たり前とも言える『人事異動』の悲喜交々が描かれていくこの作品。これが、面白くないはずがありません。
では、そんな”お仕事小説”自体に行く前に、この作品の舞台となる『造船会社』に関してまずは見てみたいと思います。1970年代には世界シェアの約半分という圧倒的な力を誇った日本の造船業。中国や韓国に抜かれて世界第三位まで後退したとされる業界ではありますが、日本の代表的な産業であることには変わりないと思います。しかし、イメージとしての『造船』は分かりますがその詳細についてはなかなかピンと来ないようにも思います。この作品では、各短編で主人公を務める部門の仕事を描いていく中に、『造船』の裏側が浮かび上がるように描かれていきます。
『営業部によって船主との契約が結ばれ』
↓
『設計部が先方の要望もふまえて設計図を作成』
↓
『資材調達部が鋼材やパイプやエンジン、発電機などを発注』
↓
『材料がそろった段階で、建造部の出番となる』
『造船会社』ならではの部門名称が新鮮に感じられる中に展開していく物語では、そんな船が船主へと引き渡される『命名引き渡し式』の様子も描かれていきます。
『開会の挨拶と、船主への花束贈呈を経て』、『続きまして、船主ご令室による支綱の切断を行います』というアナウンスによって社長夫人が『四角い台へと歩み寄』ります。
↓
『小さな銀の斧が、ゆっくりと振りおろされる。支綱が切れ、つながれていたシャンパンの瓶が船首にあたって砕け』ます
↓
『わあっと歓声が上がった』
↓
『船尾のデッキに準備されていたくす玉が割れて紙ふぶきが舞い、さらにその左右から、色とりどりの紙テープが海面へシャワーのように降』ります
↓
『ぼう、と高らかに汽笛が鳴る。無数の風船が空に放たれ、風に乗って飛んでいく』
どんな会社にもメインイベントというものはあると思いますが、『造船会社』にとっては間違いなく一番のイベント、それがこの場面です。もし、この作品が『造船』というものに光を当てていく物語であれば、この場面はクライマックスであり、こんな風に平然と書き記してしまう私はネタバレを平気で行う酷いレビュワーということになってしまいます。しかし、この作品でこの描写がなされるのは冒頭の短編〈海に出る〉の、しかも中盤にすぎません。そうです。この作品は『造船会社』を舞台に描かれていきますが、そのメインテーマは”船”ではなく、”人”なのです。
ということで、この作品の主題でもある”お仕事小説”を描く部分に触れていきたいと思います。この作品は七つの短編が連作短編を構成していますが、そのそれぞれに主人公となるべき人物が登場します。そんな主人公は、年齢、性別、そして働く部門はバラバラです。では、短編ごとに主人公となる人物の情報を簡単にまとめておきたいと思います。航海をイメージさせる短編タイトルにも注目です。
・〈海に出る〉: 野村雄平、人事部採用課、不本意な人事異動に悩む日々を描く
・〈舵を切る〉: 佐藤由美、建造部組立課、まさかの社内××の先の苦悩を描く
・〈錨を上げる〉: 宮下一海、建造部組立課、異動希望を出すまでの苦悩を描く
・〈櫂を漕ぐ〉: 川瀬修、技術開発部第三課、新米管理職としての苦悩を描く
・〈波に挑む〉: 村井玲子、事業戦略室、『造船は男社会だからなあ』という中での苦悩を描く
・〈港に泊まる〉: 太田武夫、事業戦略室、異動の 内示を受けた先の苦悩を描く
・〈船に乗る〉: 北里進、北海道造船所、『じっくり考えてくれ』という内示の先の苦悩を描く
この作品の特徴は、〈櫂を漕ぐ〉以降の四編がいずれも管理職が主人公となることです。会社の中で管理職かそうでないかはやはり大きな違いがあると思います。しかし、私が今まで読んできた”お仕事小説”の中に管理職が登場することはあってもその苦悩に光を当てた作品は読んだことがありません。この作品では、まさしく4者4葉の管理職の生き様が描かれているのがとても印象に残りました。特に管理職に成り立ての人間の心の機微を追っていく〈櫂を漕ぐ〉は秀逸だと思います。部下を初めて持った川瀬の物語は、部下との関わり方に戸惑う新人管理職の戸惑いが描かれます。
『部下がどのくらい成長できるか、また活躍できるかは、上司の皆さんひとりひとりにかかっています』。
そんな風に人事からの説明を受けても
『違うだろう…個人の能力や技術は、他人が伸ばしてやるものではない。本人が努力して積みあげていかなければならない』。
そんな風に斜めに構える川瀬。そんな川瀬は、自身を見る部下の目に戸惑ってもいきます。そんな川瀬が気付きの瞬間を見る物語は、管理職の方にはとても新鮮な思いの中に、一方、管理職を目指される方には、なるほどと、納得感のある落とし所で描かれていきます。
また、事業戦略室からの異動の内示を受けた太田武夫〈港に泊まる〉の物語は、会社員として勤め始めたからには、圧倒的大半の方がどこかで感じることになるであろう複雑な思いが描かれていきます。
『仕事場は、勝負の場でもあった。主任、課長、部長、上っていくたびに階段の幅はどんどん狭くなる』。
そう、会社員というのはその組織の中での出世レースに強制参加させられる運命にあると思います。
『強い者は、それでも上へ上へと勝ち進んでいく。弱い者は敗れて底辺にとどまる』。
そんな弱肉強食の世界の中で一段ずつ階段を上がっていく、良くも悪くもそれがサラリーマン人生です。しかし、ピラミッドの頂点に立つ者は一人のみ。同期入社した者たちの中にもどんどん差が開き、ある者はその場から去ってもいくでしょう。会社組織はぬるま湯に浸かっている時間など与えてはくれません。
『認められたかった。出世したかった。部下に尊敬され、上司に一目置かれたかった。勝ち続けたかった』。
そんな思いの先に描かれていく太田の物語は、深いです。ものすごく深い。あなたが会社員であるかそうでないかで読み味が大きく違ってくるのがこの物語だと思います。700冊近い小説ばかりを読んできた私ですが、こんな立場の人間に光を当てた作品は初めてです。この短編の結末に主人公の太田が抱く感情をどう見るか、そこには読者であるあなたの会社員人生がまさしく投影されることになるのではないかと思います。そして、このことに関して、一点注意事項があります。それは、この作品はその先を読者に委ねていくタイプの作品だということです。それが故にそれぞれの短編の結末に物足りなさを感じる方もいらっしゃるようです。しかし、この作品はそうではないのだと思います。その先を描かないからこそ物語に深みが増すのです。あなたが会社員であるなら、是非自らの会社員としての人生に重ね合わせるようにそれぞれの主人公の胸の内を感じてみてください。物語には描かれない彼らの胸の内が深いところから響いてくると思います。そう、自らも会社員でいらっしゃる瀧羽さんだからこそリアルさが滲み出る、専業作家さんには見えない会社員の実像がここにある、これぞ現実を描いた本物の”お仕事小説”とも言えるこの作品。会社員の方には是非一読いただきたい作品だと思いました。
『仕事は結果だ。結果を出せなければ、どう弁解しても負け犬の遠吠えにしかならない』。
『今年でちょうど創業百周年を迎える、中堅の造船会社である』北斗造船を舞台に、そんな会社で働く七人の人物に順に光を当てていくこの作品。そこには、さまざまな年齢、性別、そして部門で働く人たちの仕事に対する直向きな思いを見ることができました。不本意な『人事異動』に苦悩する瞬間が描かれるこの作品。他にはあまり類を見ない管理職ならではの苦悩に光を当てていくこの作品。
極めて読みやすく綴られていく物語の中に、瀧羽さんらしく丁寧に描かれる心の動きの描写にとても魅了される”お仕事小説”の傑作!だと思いました。