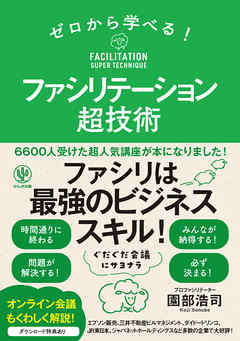感情タグBEST3
Posted by ブクログ
会議の時に、すぐに解決策に話がいってしまいがちな点は納得。だから話の視座が合わなかったり、論点がいったりきたりしてしまったりと生産性のない会議になりがち、、、
本書で紹介されていたステップをたどり、
⑴現状の姿、あるべき姿を洗い出す
⑵原因を洗い出す
⑶解決策を洗い出す
を参考にしたい。
そして、ホワイトボードやスクリーンを有効活用し、情報を可視化して全員の意見が反映される方法も試したい。
Posted by ブクログ
読みやすい本。対面での会議だけでなく、オンラインミーティングでのファシリテーションも書いてあるので参考になります。会議の意見だしや決め方、流れの確認などはスグに使える技として納得感がある。100点を会議で目指すのはナンセンスで70点くらいを目指して行うことがGood。決める時に、人は理屈よりも自分の話を聞いてもらえて決まったという事実が大事だというのは、まさに実感がある言葉だった。
Posted by ブクログ
・オンラインではリアクションは大袈裟に。表情や手の仕草、拍手、声もよりはっきりと
・全員が参加できるように安心安全の場を作る。→アイスブレイクで声出しをしてもらう。締めには必ず『どうでしたか?』と全員に振る。合間合間も、『今の意見を聞いてどう思ったか?』聞く
・表情を見て、不満そうな人がいないか確認
・はっきりした『ハイ』で区切り、切り替える。
・問いの作り方が大事
Posted by ブクログ
会議に関する考え方を整理できた。
種類があることと
それごとに適した進行があること。
基礎的ではあるが徹底できていなかった
問題解決ステップのフレームワークで、
大きく分けて
問題発見
原因分析
解決策の選定
計画の策定と
枠組みを定めて
会議でお互いに言っていることが合っているのにステップが違うことによる
錯綜しない仕組みづくりは大切だと思います。
本書ではその仕組みとその方法を記載されていますが、この構造自体を理解してもらう必要があるなと思いました。
また、KJ法は費用がかからず手軽で
効果も大きく纏まりやすいので、有効な方法だと思いました。
Posted by ブクログ
会議中のファシリテーションだけでなく、会議設定の段階から効果的な会議にするためにはどうするのが良いかが書いてあり、有用であった。
あとKJ法知らなかったので、原著を見て勉強してみようと思う。
Posted by ブクログ
ファシリテーションの入門編って感じ
基本がコンパクトにまとまっている気がするが、「ファシリテーション」に正解はないので、盲信するのはやめた方がいい
Posted by ブクログ
・会議やMTGは現状とあるべき姿のギャップを見極め、あるべき姿を達成するためにどのような解決策、打ち手を展開するかをチーム内/関係者間で議論/検討するための場であり、ファシリテーションはそのゴールに導くリーダーである。
・会議の前にはアジェンダを作成し、自身の進行や議論内容の整理、参加者への内容提示をすることでスムーズな会議を実現するため、不可欠。
・アイデア出しの場合、「質より量」「全員が自由な発言」をできるよう、場のセッティングや参加者への問いかけを意識的に行う。
・アウトプットを行う会議が、情報整理しながら会議を行う鍵。可視化することでMECEやマトリクスを活用した情報整理ができ、議論内容を振り返りながら進めること、全員が共通認識を持って会議が行える。対面ではKJ法も有効。
・話が逸れた際の引き戻しもファシリテーターの重要な役割。時間厳守はマスト事項。
・参加者へ問いかける際は、小学生に説明するようなわかりやすい言い回しを意識。これは自由な発言を促すためにも必要。いい問いを心がける。
・ゴールの合意形成においては、全会一致を基本とし、着地点が定まらなかったら、最終リーダーの一任で決定することで、納得感を得られやすくなる。(そのためにも情報の整理が必要。)
・合意形成には70点くらいの内容でいい。正解がないことの議論をしているのだから、100点は目指さない。
・「心理的安全性」を意識し、クリティカルな態度は取らない、明るい雰囲気を切らさずに、肯定的な反応を返す、ボディーランゲージを多用するなど、ファシリテーターが場の雰囲気、参加者のモチベーションを盛り上げることが重要。
ウェブ会議の情報ももう少し、欲しかったてすが、ベーシックな内容や段取りはこの一冊で学ぶことができました。
Posted by ブクログ
まずはアジェンダをつくることで、会議のシナリオを作り、KJ法を利用し意見を出してもらい、全員に発言してもらうことで、納得感をもたせる。最後は課題を自分が絞り込むことを時間制限をかけることで、同意させて、反感をそらす。
つまり、ファシリテーターは、会議を仕切るというよりは、予測できる着地点にみなを誘導させるのだと理解した。使える部分は会社で採用したい。
Posted by ブクログ
ファシリテーションを改めて学んだことがなかったので、非常に役に立ちました。次回の会議からアジェンダをしっかり作って、KJ法を使って良い会議にしていきたいと思いました。本の後半に書かれている、ファシリテーションの実況中継が個人的には理解しやすく、こういう流れや声掛けができんるだと、気づきが多かったです!
一読しただけだと身につかないと思いますので、実際の会議をして、本を読み直して自分の知識として取り入れたいと思います。
Posted by ブクログ
問題解決のステップやファシリテーションをするときのチェックポイントが分かりやすく解説されていた。
自分もできるところからチャレンジしてみたい。
欲を言うなら、KJ法以外の会議の持ち方も知りたかった。
Posted by ブクログ
今まであまり意識せずにやってきたファシリテーションでしたが、参加者への配慮や、オンラインミーティングならではの注意点など、具体的な例を元にポイントが書いてあるため、明日からでも使えることがありました。
また、著者がお勧めするKJ法は聞いたこともやったこともありましたが、改めて今やってみるのが良いかも知れないと思わせてくれました。
Posted by ブクログ
アジェンダをしっかり作成しよう。
人は正解より納得が欲しい。
自分の意見を聞いてもらえたなら、意見が通らなくても納得が残る。
KJ法ではない方法を知りたかった。
Posted by ブクログ
ファシリテーションという言葉も存在も認識なかったので、そういう役割がしっかり確立されてるんだーっという惚けたところからのスタートです。
まとまりのない、結局結論の出ない会議ってあるあるだけどそこに希望を照らす役割がファシリテーター。雰囲気作りや時間割り決めたアジェンダの重要性など腑に落ちるところが多かったです。問題、原因(課題)、対策をしっかり区別して議論を進めることが中々できず、いつも宙ぶらりんの坩堝にハマってるのはここが曖昧だからかーという気づき。
ただの司会進行ではなく、協調力が試される立派なスキルだ。関連本当たってみて理解を深めたい。KJ法は意外と自分の会社でも文化的に刷り込まれてる。案外ちゃんとしてるな。
Posted by ブクログ
仕事をするうえでの土台はファシリ力。「問題発見・解決会議」を中心にそのスキルを伝授してくれる、すぐ活用できる実践本。ファシリとは事前準備から始まり、進行管理と場づくりを行う。いい会議になるかどうかはファシリの力量にかかっている。リーダーを務め対話の可能性を広めたい私にとって必読書
ファシリ力の重要さと、自分のファシリ力のなさを感じた。読んでからは前よりも準備を入念にし、議論の場全体をみることができてます。もっと磨く
Posted by ブクログ
Audible にて。
ファシリについて最も悩んでいる web会議については内容が薄く、web会議が急速にメインとなった今となっては少し古いと感じた。
別途おすすめされていたビジネスフレームワークやロジカルシンキングの本もチェックしたい。
Posted by ブクログ
会議のはじめに情報格差を埋める。
1人ずっ聞いて意見を出す。
人は正しいか、正しくないかということより「自分の意見が入っているか、聞いてもらえたか」のほうを圧倒的に重視する。
Posted by ブクログ
☆きっかけ
元々苦手意識あり。研修中のワーク等で話を上手に回したかった。
☆感想
ファシリテーションスキルって要は問題解決力のことなのか、、?
テンポよく場を回す能力っていうイメージが強く、今回は後者の能力の話を読みたかった。(電子書籍だったので試し読みはできず)
kj法は素晴らしいと思うけど、なかなか導入する勇気は今は出ない。
kj法ゴリ押しでした。
新たな発見は少なかったけど、改めて大事だと思ったこと。
・何をどこまで行うのか最初に決める。
・問題=あるべき姿−現状 あるべき姿を「こうなったら最高」レベルで考えるとギャップを浮き彫りにしやすい
・問題を解決するときは、原因に対する解決策を考える
→①問題の原因出し ②主原因を仮定して決める ③主原因の解決策を出す
・問いは付箋が5枚かけるくらい簡単に
・受け入れることと同意することは別