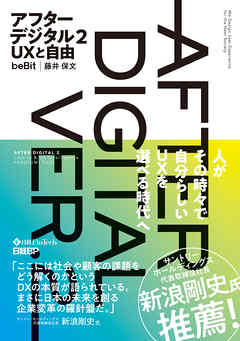感情タグBEST3
Posted by ブクログ
2020/12/6読
凄い、すごい本だ。
前著で中国のIT、DXの進化に衝撃を受け、2冊目が出たというので手に取った。
二匹目のどじょうとやらかと思ったが、そうではない。
コロナ禍を挟んで、DX、UXがさらに進み、中国でもどんどん進化し、
衝撃的な内容はさらにパワーアップしていた。
後半の分析、日本成長のカギというのも魅力的だったが、
何しろ中国だ。
あの、中国で、顧客視点のサービスはかなり進んでいる。
なんで共産党が支配するあの中国で、と思うが、
縛るところと任せるところの加減がいいのだろう。
まず、アフターデジタルの定義。
真に顧客提供価値で勝負すること
とある。
それが中国で実践されているのだ。
NIO テスラとの違いは、電気自動車のカギを渡してからが仕事であるところという。
ライフスタイル高級会員チケットを600-700万で買っていただき、
ギフトとして電気自動車を贈るというのだ。
充電から始まるサービスは、確かに生活の質をあげそう。
創業者は、北京の空を取り戻すために起業したという。
そういう中国人が存在しているのだ。それも大勢
バイクのNIUの例もあった
さらに、若者向け賃貸サービス ZiRoom
エアビー的なサービスがうまく組み込まれている。
家を貸すだけではないのだ。不動産会社との付き合いになる。
衆安保険。損保をカスタマイズしてアリババなどあめぶろ他のサービス形態に組み込む。
著者が前回絶賛したラッキンコーヒーは
スタバが「サードプレイス」にこだわることをやめ攻めに出たこともあって、
不正を働くなどして失速したらしい。
スタバが顧客ニーズにこたえたのだ。
それが素晴らしいと思う。
凄すぎる。
なぜ日本ではこういうアイデアがないか。
この本でも触れていたが、自分でも考えたい。こういう本は読むべきだ!
Posted by ブクログ
現状の業務のスタンスを変えないといけないと思わされたので。UXグロースにおいて、データ起点で短絡的な課題解決に向かわないようにしないといけない。データから課題が見えた時ユーザーの状況理解をした上でUX企画に落とさないといけない。そうしないと真の課題が解決されないので、全てパフォーマンスになってしまうから。
ビジネス書としてだけでなく現代評論としても読める
Posted by ブクログ
「アフターデジタル」オフラインのない時代に生き残る
■世界の状況
〇エストニア:世界で最も政府の電子化
・所有する不動産などの資産全てがオープン、誰が見たかもオープン
・強盗して所持金が増えたらすぐに分かる。
〇スウェーデン
・体内にマイクロチップ。手をかざすだけで会計
〇中国
・8億人の人口の97%がスマホ所有・モバイル決済
■オフラインがなくなる世界
・あらゆる行動が個人のIDと結びついて可視化
・単体事例の先進性ではなく、全体システムのアップデート
■メリット
・社会的評価仕組みが未成熟だった国では、社会的信用が保証され、努力すればいい待遇が受けられる仕組みになった。
・満足度のデータ化
・コンビニ無人化→人件費はそれほど変わらないが、空き時間で人的サービス。顧客満足向上。
→効率化によって、人でしかできない仕事の価値が高まる。
・検索・予約しやすい医療アプリの提案→検索から必要な医療を把握、提案する保険会社
→売上にすぐにつなげるのではなく、ずっと寄り添う事を重視する姿勢
→継続的な価値提供
■OMO(Online Merges with Offline)
・オンライン/オフラインの一体化の上で、オンラインにおける戦い方・競争原理としてとらえる考え方
■UX
・顧客体験
・モノが手に入りやすくなる→顧客が体験価値に気付く。
■今後
・取得したデータを顧客ごとに紐づける
・自社・自部門だけで顧客を囲い込んでもどうにもならない
・大型プレイヤー(決済プラットフォーマーになろうとしている)にとって重要な視点。
■次の時代
・アフターデジタルの到来
オンラインとオフラインの区別がなくなり、デジタル世界に住んでいるような状態になる。
・ビジネス形態の変化
大量データを取得し、OMOで試行できるようになると、企業体の出来る事が変わってくる。
顧客との接点が増える(商品売買だけでなく、コンサルティングで様々な状況で関わる)
■大事な事
・ハイタッチ
特定の人に個別対応:個人対応ならではの対応や感動で信頼を得る
・ロータッチ
ワークショップやイベントなどの「場」:リアルだからこその心地よさや得難い密度の情報提供
・テックタッチ
オンライン:プロセスが短く・便利で高頻度で使うと得をするインセンティブを提供する。
↓
以前:製品単体で価値提供するしかできない
今後:体験全体で価値提供が可能になる。
→顧客の定義/商品の定義が変わる
Posted by ブクログ
中国のデジタル社会を参考に
今後のビジネスにおけるDXを綴っている本
従来サービス提供者は「商品」を売っていたが
これからは「体験」を売っていく必要がある。
「体験」を売れると言うことは
ユーザーはそのサービスの世界観に惹かれている
共感しているということであり、
このブランド共感ユーザーが増えれば
単純な価格競争や機能競争に巻き込まれない域に
行くことができる。
点の「商品」ではなく
線の「体験」をユーザーが欲しているというのは
現代の社会でも既に起こっている事であり、
例えば音楽を聴くときは
特定の音楽を購入するのではなく
音楽サービスの「チルい曲」などから選択し
この体験をする為にサービサーにお金を払っている。
近年では中国で伸びている
【ライブコマース】も商品→体験をユーザーに
与えられるサービスの1つではないだろうか。
従来は、
店舗で購入する「ハイタッチ」での商売
ただコロナをきっかけに店舗来店が難しくなり
ECで購入する「テックタッチ」での商売が
伸びてきている。これは生活様式の変化によって
起こったもので店舗とECそれぞれの強み弱みが
ある中でライブコマースはその中間「テックタッチ」と言われるサービスではないだろうか。
ライブ配信中に商品をカートに入れれる
シームレスな同線設計
販売側と双方間コミュニケーションを取りながら
商品購入のできる楽しい体験
こういったらリッチな購買体験が
ユーザー満足度を上げていくと考えており
商品購入だけではなく体験を売れている例かと思う
記載のようにこういった体験(ブランド)
に価値を感じるユーザーが増えれば増えるほど
単なる優位性の競争ではない域に到達できる為
LTVの高いユーザーがどんどん生まれていく。
ただライブコマースも1つのツールであり
体験の設計をする中で組み込んでいく必要がある。
メーカーに付いている顧客属性によっても様々であり
店舗型なのかEC特化でも良いのかライブコマースのようなサードプレイスが必要なのか
顧客体験がMAXになるように設計すればいいと思う
顧客の中でもそれぞれの場所を選ぶ割合もあり
その人達が自ら最適な場所を選ぶことができる
状態を作っておくことが大切なのではないだろうか。
Posted by ブクログ
日本企業にありがちなとりあえずデジタル化、がバズらない要因を分かりやすく解説してくれている
OMO、D2Cと言葉で理解できていても、本当にユーザー目線に立ったUXが構築されているのか
所謂プロダクトアウトからマーケットイン的思考なのだろうが、ここまで理解し実践できている企業は少ない
企業の精神、所謂ミッションに忠実な中国企業におけるサービス設計は面白い
ペイメント機能の作り方をとってもアリババはシームレスかつ信頼性の高いコミュニケーション、テンセントは人との繋がりを意識させるコミュニケーションを体現するための設計が施されている
物売りの代表格であるクルマメーカーの概念を覆すNIOのロイヤリティ維持向上戦略もサービサー、メーカーの今後の歩み方の参考になりそう。
データの幻想についても印象深く、今後絵に描いた餅となる提案を避けていきたい。データの用途は金融やPHRなどごく一部に限られており、現実問題他社への横展開は相当な難易度を伴いながら実用性は少ない
Posted by ブクログ
DXの誤解に警鐘を鳴らす本。自分もついついDXを業務効率化の観点で捉えるが、その観点が主になってしまうとUXどこへやら。実は効率化できた業務の範囲も小さく、可能性も狭めてしまう。
デジタル化によりできることを念頭に置きつつ、今まで仕方ないと割り切っていたものを見つめ直す。
ゼロペースで見ると、本当は困っているけど仕方がなかったものが分かってくる。
そうすると本当のDX方法が見えてくる。
時代が変われど最も大事なことはユーザー理解。
Posted by ブクログ
前著と基本的な考え方は変わらないが、よりUXの価値にフォーカス。UXを伴わないデータはカネにならない、はビッグデータブームへの真っ当な一石の投じ方だろう。
また後半では、日本と中国のD Xの進展の差を国民性の差で表現していて興味深い。「何かあったらどうすんだ症候群」(為末大)は日本人の病だと私も思うが、これが無知からくる過剰なプライバシー侵害不安となり、世の中のデジタル化を押し止めていると実感。
四章以降はデジタルの話というより、カスタマージャーニーを軸としたビジネス設計の話で、ビジネスモデルよりまずは顧客のペインの特定が先、という昨今の主流である考え方を明快に解説している。
コンセプトの書だった前作から、よりコンサルテキスト的な内容でこちらも楽しく読むことができた。
Posted by ブクログ
・面白かった。読んだだけで、まだ自分の業務に落とし込んでいないため、有用だった と言うのは憚られる。おもしろかった。
・日ごろシゴトしながら感じている違和感(データへの幻想/「それは経営陣が決めることだから」/海外事例をそのままモデルに/…)が登場して、ニコニコ頷きながら読める
これが数年前の本、と思うと笑ってはいられないけれども。
・実ケースの話①:これを書いているほんの数日前、ちょうど(?)イーロン・マスク氏がTwitterを買った。“Twitterが実名性になる”との噂でTLがざわついている。本書4-4で紹介される通り、日本市場でSNSを売る気ならその戦略はとらないわけで、Twitter社は日本市場を切ったのか〜と感じた。
・実ケースの話②:街中でメルカリ教室を見かけるたび これどうやって利益出してるんだ?旗艦店ひとつ出すなら分かるが、なんでこんなあらゆる所でやってんの?と思っていた。利用者の定着率に繋がっている、元々あったサービス形態(ケータイ教室)に乗っかっている、との紹介を読んで腑に落ちた。
・実ケースの話③:マルイの売らない店舗も、当初面白がって見かけるたび立ち寄っていたが、自分は、結局オンライン以上の情報が得られず行かなくなってしまった。②の例からするに、自分はピンと来ていないが、どこかで誰かが喜んでいるのだろうから 理屈を考えたいなあ
Posted by ブクログ
最適なタイミング、コンテンツ、コミュニケーションを捉えて価値提供するには、ユーザーの置かれた状況(ペインポイントや成したい自己実現)を把握してそれに対する解決策や便益を提供し、ユーザーと定常的な接点をなるべく高頻度に持つ必要があります。これは商品販売型のビジネスでは実現が難しく、「体験提供型ビジネス」に優位性が移行していくことを示しています。
NIO、NIU、ズールーは、いずれも商品に関わるペインポイントを解決するだけでなく、ユーザーにより良い生活スタイルを提案する形で、定常的に顧客との接点を持てる「体験提供型」のサービスに変化させています。これにより、商品販売型では提供できなかった顧客との新たな関係を作り出し、これを新たな優位性としながら、いつでも顧客の状態を知ることができています。前著に事例として挙げた「平安グッドドクター」はまさにこうしたモデルの先駆者であるわけですが、「売ること」「成約させること」にフォーカスするのではなく、顧客にずっと寄り添うことを重視することで、他社を圧倒し、人が人を連れてくるというモデルが、多方面に成立し始めているのです。
■第2章まとめ
(1)最上位に来る決済プラットフォーマーは、「決済機能を提供する」という考え方ではなく、それぞれの企業ミッションと元来のケイパビリティを生かして普及させていった。
(2)購入後に接点を持ちにくいメーカーや成約型ビジネスは、「ペインポイントを解決する便利系サービス」と「ライフスタイルに新しい意味をもたらすサービス」の双方に拡大し、顧客との定常的な接点を持つバリュージャーニーに変化している。
(3)これにより、「何かを購入する」という行動がサービスに埋め込まれ、サービスへのロイヤルティーやその利便性の中で「ついでに購入する」ような行動が当たり前になりつつある。これを「コマースの偏在化」と呼んでいる。
(4)上記のようにメーカーもサービサー化する中、その潮流を捉え、サービサー向けの支援を提供するtoB向けプラットフォームビジネスも生まれている。
■O2Oとは異なる
「先日、新宿を歩いていたら、近くにあるショッピングモールからメッセージが飛んできて、キャンペーンの情報を受け取ったのですが、これってOMOでしょうか」
…
私は質問してきた人に、まず聞いてみました。
「ユーザーとしてそれが便利だとか、自分に合ったうれしい情報だと感じましたか?」
するとその方は
「うーん、あまり便利とは思いませんでした。通知が送られただけなので」
とおっしゃるので、私は
「じゃあ、OMOではないですね。まったく顧客目線ではないですから」と回答しました。ただ単にオンラインとオフラインを融合させればよいという考え方は、結局のところアフターデジタル時代に必要な視点に転換していないので、本質を失った「単なるオンラインとオフラインの連携」と言わざるを得ません。
■データのマネタイズの3パターン
(1)マーケティング・広告に活用する
「この人はどのあたりで何をいつ頃買ってくる」という情報から、マーケティングソリューションを企業向けに提供して、そのソリューションフィーで稼ぐことができます。例えばアリババは、ECのシェアを半分以上押さえているため、ウェブ上での購買行動データも潤沢に持っています。モバイルペイメントのシェアも半分以上持っています。「リアルで消費された行動」の方をより参考にしたいという企業もあるので、リアルとデジタル双方を合わせた消費行動を基にマーケティングしたい、という企業にはより高いソリューションを販売できます。
(2)金融に活用する
どれくらいの支払い能力があり、どのような消費行動を取るのかが分かることで、主に個人向け融資の与信管理効率が良くなります。これによって明らかになった「信用度」を別の企業に展開して活用することで、他社もそれに依拠してサービス展開できる「信用スコアプラットフォーム」になり、ソリューションとしてのマネタイズも可能になります。
(3)インフラに活用する
人の動きのデータを活用し、交通や医療の効率を向上させることで、それ自体でのマネタイズは難しいが、スマートシティに対する投資や管理費用として、国、自治体、エンタープライズからのマネタイズが可能になります。
■データを持つ幻想と現実
【幻想】保持しているデータそのものが財産だと思っている。
【現実】ソリューション化して活用できないと、持っていても意味がない(漏洩リスクと管理コストのみが発生する)。
【幻想】社会レベルでの共有、または、他社とのエコシステムによってビッグデータ活用できると思っている。
【現実】データ突合には「目的設定の主導権争いとコストの壁」が立ちはだかり、1社が目的を持って主導しないと実現は難しい
【幻想】ペイメントデータさえ取れれば勝ちだと考える。
【現実】ペイメントデータで直接的にマネタイズする方法は限られ、ビジネスとビジョンに基づいた目的設定が重要である。
■アフターデジタルで提唱している「あるべきDX」
「デジタルとリアルが融合することで膨大で高頻度な行動データを使い、企業競争の原理が商品販売型から体験提供型になる、つまりバリュージャーニーを作って運用していくことを踏まえ、新たな顧客との関係性とはどのようなものであり、どのような体験を提供する存在になるべきかを考える活動である」
■第3章まとめ
(1)データエコシステムやデータ売買を中心に置いた「実現性の見えない大きな絵」ばかりを描かないように、データ活用や共有の幻想を解く必要がある。
(2)「デジタル」という手段にとらわれ過ぎず、デジタルとリアルの強みと弱みを正しく捉え、つなぎ合わせることで顧客との新たな関係を作っていくことにOMOの本質がある。
(3)「広範囲なデータでいかにマネタイズできるか」ではなく、「個社で取得できる行動データをいかにUXに活用するか」が鍵となる。
■「役に立つ」から「意味がある」へ
「役に立つ」=機能的便益の有無
「意味がある」=自己実現的便益の有無
■肝に銘ずべきこと
・「ユーザーが置かれている状況」に関する仮説を持つ。
・実ユーザーや消費者に当たってそれを検証する。
・「その不幸せな状況をどう改善するか、どのような幸せな状況にするか」という仮説を持つ。
・「幸せな状況」の企画が受け入れられるかを検証する。
■第4章まとめ
(1)デジタルとリアルが融合し、オンライン前提となったアフターデジタル社会は、UXとテクノロジーを使うことで1つの企業がアーキテクチャを作ることが可能になった。
(2)その分、データを悪用したり、ユーザーを監視・管理・コントロールしたりすることも可能で、こちらに進むと社会発展が止まるため、断固として防ぐ意志が必要になる。
(3)DX・UXに携わるすべてのビジネスパーソンは、ユーザーに不義理を働かず、在りたい自己実現ができる世界観や、心の底から共感する世界観を提供しているUX(バリュージャーニー)があふれ、UXの善さを競う環境になることで、ディストピアではない「多様な自由が調和するアフターデジタル社会」を目指すべき。
AI・データをはじめとするテクノロジー前提・オンライン前提社会において、企業から発信する新しい自由の在り方(アップデート)を示し、これに挑戦し、ディストピアを防ぐ勇気を持とう、というのが前提となる精神です。
これを持った上で、その実現(つまりバリュージャーニーを作って運用すること)において最も重要なケイパビリティが「UX企画力」であり、すべてに通底するのは「ユーザーの置かれた状況を捉える」ことです。これには「ビジネスを構築するためのUX企画力」と「グロースチーム運用のためのUX企画力」の2つがあります。
この2つを行うことでバリュージャーニーが実現されますが、これはアフターデジタル社会にとって「UX選択の自由における選択肢の1つ」としてのUXを提供しており、こうした「今まで以上の自己実現を可能にする、自由の選択肢」を皆さんとたくさん作り、それがあふれる社会にしたい、という願いと方法論が、本省のメッセージとなります。
■第5章まとめ
(1)社内の意識変革や説得を通して、どのように会社全体で話を通りやすくするのか。
【地盤固め】DXの必要性と目的の認識をそろえる。
【目指す絵の確認】事業そのものだけでなく、ケイパビリティ取得や、高LTVモデルへの転換といった大義設定を行う。
【まずは体験する】失敗を恐れずなるべく早く開始してラーニングし、より具体的な成功への道筋を示すことで社内全体を巻き込む。
(2)ケイパビリティをいかに調達するのか。
【対話型組織】上からの情報共有が十分行われ、かつ下も上も横も一緒に対話と議論ができる組織を作り、自ら価値を考えて動ける文化を作る。
【オンオフの補完関係】オンラインとオフライン、双方のプレイヤーにおいてケイパビリティを補完したいと考えているため、「目指す世界が近い企業」と補い合うべし。
Posted by ブクログ
前作のOMOをベースに、UXを軸とした説明。
バリュージャーニーの作り込みについて具体的な説明がされていた。
データはソリューションとセットでないと価値がないこと、DXを目的化しないこと。
DXって何をすればいいの?に
データーを制するものがビジネスを制する、わけでは無いことが明確に説明されており、モヤモヤが晴れました。さらにUXの大切さとそこから生まれてくるトランスフォーメーションこそがDXであること、それをきちんと成し遂げるには正しい思想が必要と続き、目指すべき姿のひとつを示しています。
後半のケースの説明でほカタカナ用語が多く一読では理解が追いつかなかったので、星は4つとしました。
Posted by ブクログ
気づき
行動データ、状況ターゲッティング、バリュージャーニー
ハイタッチ、ロータッチ、テックタッチ
アフターデジタル時代に合わせた新しいUXを作る事がDXの目的 UXインテリジェンス
Posted by ブクログ
◯このようにたまったデータをUXに還元し、さらにUXを良くすることでより粘着度の高いサービスに改善され、進化し、さらに行動データがたまっていく、といったループを作ることが「体験型ビジネス」の成功の最重要ポイントになります。(25p)
◯もともと商品であった「楽曲・アルバム」は接点の一つになり、様々な接点・価値を統合したジャーニー全体を売っていると言えます。(27p)
◯商品の購買がサービスのジャーニーの中に埋め込まれていく状態が進んでいる(72p)
★UX時代の企業家精神を説く。考え方が間違ってなければ成功するということか。
Posted by ブクログ
オンラインとオフラインが融合する世界を、中国の事例を紹介しながら紹介した前作は刺激的で面白かった。
続編の本作では、中国のビジネスのアップデートに加え、日本で実際にOMOビジネスを企画導入する際の考え方、進め方が解説されている。
UXが全てであるという指摘には納得感がある。データを集めても、UXに具体的に活用できないデータ収集は無意味であるということにも同意できる。
鋭い指摘が多いのだが、やや、OMOの世界を理論化しようとしすぎるあまり、解説が少し上滑りしている印象も受けた。日本でOMOの事例が増えてくると、これらの理論にも腹落ちしやすくなっていくのだろうけれど。
ともあれ、これからのサービス設計には、OMOの発想は欠かせない。Consumer向けビジネスに携わる人には特に、一読をお勧めしたい。
Posted by ブクログ
顧客情報を状況レベルで理解している企業が強い
アフターデジタルのビジネスモデルは顧客との接点をさまざまなところで持ち、顧客の自己実現に寄り添うバリュージャーニー
アリババとテンセントは類似したサービスを提供しているものもあるが、ミッションが異なるので方向性が違う
ロイヤルティが高まることで、他のものと比較せずそのブランドのものを買ってしまうようになる
サービスの利便性や世界観が優位性を持ち、商品の購買がサービスのジャーニーの中に埋め込まれていく
=コマースの偏在化
OMOは顧客にとって嬉しいものであったかが重要。ただ単にオンラインとオフラインを融合させてもそれはOMOではない。→目的を決める。現象を理解する
DXはUXを提供するためにやる
(手段の目的化状態に陥ってしまっている)
Posted by ブクログ
中国で日系企業のデジタル化を支援している著者による、デジタルを学ぶための1冊。
コロナ影響も踏まえつつ、「UX」の観点を分かりやすく掘り下げており、『アフターデジタル』よりも実務的には刺激を受けたかも。どちらも良著ですが、人に薦めるならこっちかなぁ。
さて本著、ビジネス、サービスにおいて「どう世の中が変わりつつあるのか?」を、主に中国の最先端事例を通じて解説しているのですが、図も充実していてわかりやすいです。
加えてより実戦度を高めているのが、「第5章 日本企業への処方箋」で、日本企業における例や、あるべき考え方/進め方が示されていて、読んでいて非常にワクワクします。
ただ、ビジネスを離れた個人としては、企業がデータを大量収集する社会に対する著者のスタンスは、少し企業寄りだなぁと感じました。
企業がビッグ・ブラザーになってしまうことへの懸念について、著者は下記のような考え方を示しているのですが・・・
「AI・データをはじめとするテクノロジー前提・オンライン前提社会において、企業から発信する新しい自由の在り方(アップデート)を示し、これに挑戦し、ディストピアを防ぐ勇気を持とう」
これは、結果的にユーザにとってメリットがある体験を提案できるなら、ユーザの情報を収集/分析しても構わないという自己肯定に繋がるような気がします。
現れ方の違いだけで、ヤラれているコト自体は変わらない気がしていて、このユーザにとっての心地良い体験が連続していった先に、本当のディストピアが待っている可能性だってある訳です。
営利企業な訳ですから、経営危機に陥った際にユーザを脅しつけるマーケティングをしない保証があるのか。大昔の例ですが、Googleだって広告ビジネスを始めたんですし。
…と言いつつ、企業に勤める自分としては、本著の内容はメッチャ有益で、この考え方をこう活用したら面白いコトできるんじゃないか…なんて考えてしまっています。
何と言うか、非常に複雑な気持ちにさせられる1冊でもありました。
Posted by ブクログ
これからのデジタルの時代、アフターデジタルでは、
UXを中心としたOMOを加速させることが鍵になる
逆にUXを求めないD2Cは意味を持たない
デジタルが浸透し、行動データを集めることができるようになった現代では、
そのデータを元にUXを高める行動が大切
商品を販売して終わりではなく、顧客の自己実現のための体験を提供し、
自社の世界観に共感得ることで、顧客の心の奥まで届く価値提供ができる
このときに最も大切なのはデータをどのようにUXにつなげるのかという考え方であり
ただデジタルを普及させるO2Oの考え方は意味を持たない
Posted by ブクログ
アフターデジタルの続編。何気なく過ごしている日常も、知らぬ間に常にオンライン状態であることに改めて気づかされる本です。そして近未来も想像できて、とても面白い。
Posted by ブクログ
i felt a big dilemma for investment to DX in internally at big private company.
we have to make UX story before planning its business model.
then we have a difficulty to get a investment for building up it platform or DX from stakeholders before indicate them its business model.
thus we cannot start making UX stories internally.
so we need to communicate with outside of startup UX story makers and discuss with them about how to integrate to our data or products or services .
if this book provides solution to this i could give 5 star.
Posted by ブクログ
UXは、デザインそのものだ。
これからは、販売型バリューチェーンではなく、価値体験型バリュージャーニーが価値創造の軸となる。
その為には、当然、製品サービス、及び自社のパーパスを一貫して表現する世界観があり、その上で、ジャーニーボードを設計する。
そこで集められるデータは、また、UXに還元し、常にカスタマー体験を刷新し続ける仕組みを作ることが重要。
そこには、リアルとサイバーの隔たりない世界、OMOてあったり、更にはSociety5.0につながっていくものと思われる。
これは、単にカスタマーに限った話ではなく、Employee(従業員、パートナー含むサービス提供側)、Industry(産業、業界そのもの)、Social(社会)、the Earth(地球)の全てが対象になる。
このスコープでのUXを考えること自体が、デザイン経営ではないか。
中国が、何故デジタル先進国になったかも記載あり、勉強になった。
自由には、二つあり、負・不から解き放たれる、利便性を追求する自由(freedom)と意味性を追求する自由(liberty)があり、中国は前者が顕著だった為に、デジタルの恩恵を受ける層が広かった為、UXを伴う形で社会へのデジタル実装が進んだ。
Posted by ブクログ
世界観を見せるデータとバリューのジャーニー
■概要
前回のアフターデジタルの誤解をふまえ大幅にアップデート、より企業の姿勢に着目している。データ偏重のDXの限界を解き、DXとはUXと言わんばかりにUXの大切さを主張。
・文脈に依存するUX
WeChatペイとアリペイのように、同じに見えるサービスでも世界観や企業のミッションによって変わる。
・データの価値
- ソリューションとして活用してはじめて価値がある
- エコシステムは幻想に終わることが多い、個社データをいかに上手く使えるか
・バリューチェーンではなく、バリュージャーニーを描け
データをいかにUXに還元していくかのサイクルを描く
■所感
内容は素晴らしいが…
前回は粒々の事例が多く読みづらかった。今回は事例は減ったけど内容が冗長だし、若干精神論にろも見えて心が折れかけた。おそらく企業の姿勢が大切だと言いたいんだろうが、それにしても読みづらかったというのが第一の感想。
内容はそのとおりだし、UIレベルのUXではなく、世界観を含めて顧客の体験とデータをデザインするUXの大切さと要諦をまとめてくれているのありがたい。
世界観推しなのは、ややD2Cに影響されすぎな気もしたが、それだけD2Cで解かれた内容が芯を食っているのだろう。
疲れはしたが、読んで得られるものは大きいので★4つとしました。
Posted by ブクログ
データ=お金になるというのは幻想、体験提供型の事業をするなら失敗を重ねてノウハウを蓄積していく組織でなければならない、というのが身につまされる。
中国はブラックリスト型、日本はホワイトリスト型という根本的な違いがイノベーションの発現の差という考察にも膝を打った。
内容のインパクトとしては前作のほうが大きかった。
Posted by ブクログ
顧客の行動を計測して、即時にビジネスモデルから逆算する(売上に直接的に関連する行動データにつなげるようUX/UIを設計する。購入ボタンを押してもらうには?を考える)のではなく、まずはより詳細な個別ユーザーの状況把握(細かな行動やインサイト、何に困っているのか?など)に努めること。
それが把握できて初めてUXの企画に入る。あの顧客層が抱える課題のカイゼンにどんなUXを提供できるか?に答え(仮説)を出す。この流れについて解説されている。四半期などの期間で収益を見るだけでなく、LTVでユニット(顧客)エコノミクスで売上を管理することの重要性を説く。
中国だけでなく、日本での成功事例も豊富。
Posted by ブクログ
【アフターデジタルver.2】
p.109 顧客接点3分類
・ハイタッチ
1対1の接点で、訪問、相談などの個別対応
・ロータッチ
1対多の接点で、リアルで複数人に対応するワークショップやイベントなど
・テックタッチ
1対無限の接点で、オンラインコンテンツやメールなど、量産可能でいつでもどこでも触れられるもの
<注意点>
「デジタルをやる」ことが先行してしまった結果、デジタルに閉じてしまい、ハイタッチ・ロータッチで自分たちが持っている
強みをデジタルで生かすことができず、ユーザーから見て大して価値のないものになってしまう。
<重要点>
ハイタッチ、ロータッチで得られた信頼や関係性を、テックタッチで高頻度な行動に還元し、テックタッチで得られたユーザー行動を基に、
再度ハイタッチやロータッチに誘導したり、別のアクションをお勧めしたりしています。このように、デジタルとリアルの接点におけるそれぞれの強みと
弱みを使って、相互に行き来できるようなUX(ユーザーエクスペリエンス)を作っていくことで、ジャーニーとしてつながっていき、
ユーザーが使い続けてくれるようなサービスになっていく
p.130 UXへの注力なきDX
ユーザーの状況理解とそこに提供するべきUXの企画がないまま、DXを進めようとしてしまっている現状。
UXとは「ユーザー(デザイン)、ビジネス、テクノロジー(機能)」の3つがそれぞれ関わり合うときに生まれる体験・経験
・DXによる2つの変化
1. 「顧客との関係性を新たにする」ことから生まれる提供価値やビジネスモデルの変化
2. コストや生産性の効率・パフォーマンスを高めるための変化
p.135 2種類の「自由」
「フリーダム(Freedom)」「リバティー(Liberty)」
フリーダム:「制約や負・不からの自由」を指し、制約がない状態に解き放たれることを意味する
リバティー:「主張して獲得する自由」を指し、自分の権利や生き方を獲得することを意味する
日本の良さは「日本人は中国人に比べて、一人ひとりが独特なユニバース(宇宙・世界観)を持っているように見えて素晴らしい」
p.182
アイデアをたくさん出すというよりも、「不幸せな状況」のどこをどのように変えたら、幸せなサイクルを生むことができるかをひたすら考えるのがコツ
Posted by ブクログ
本の中で紹介される、DXが進んだ中国の事例はなんて便利なんだろうと考えさせられる。コロナ禍で半ば無理矢理オンライン化を強制された日本では、O2Oの域を出ておらずDXとは言い難い。データも集めるだけではなくUXへの還元によってこそ価値を生む、というのも言われるとその通りだがまだまだデータそのものに価値があるように語られる事が多い。オフラインもオンラインも一続きの性格の異なるツールなだけで、その両方を使うための確固たる世界観の構築とバリュージャーニーの策定が重要だと学びになった。
Posted by ブクログ
1を読んだので続けて読みました。 DX時代のマーケティングの基礎的な部分を解説した本、実例を色々盛り込んでくれているので非常に読みやすかった。
主義主張は1とそこまで大きく変わらない。
Posted by ブクログ
属性データ時代は人を単位で、行動データ時代は人を状況単位でとらえる。
サービサーが主で、メーカーが従となる時代へ。
データは売り上げではなく、uxに使え。この発想は簡単なようで難しい。