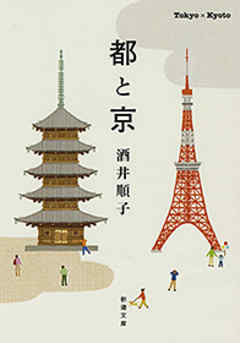感情タグBEST3
Posted by ブクログ
以下、へーっと思ったこと。備忘録。
京都は薄味のイメージあるが普段飯はそんなことはない→天下一品、力餅食堂。普段はユニクロ着てても礼服持っているのが京都人。「東京資本」の店への嫌悪感。贈答文化、セックスと同じ面倒さ。東京には山がない、高いタワーは山の代替物?国道367号で日曜午前にある大原朝市。京都の宗教的雰囲気を高めているのは比叡山。同業者街=清水焼団地、両本願寺の仏具、寺町電気、二条薬、夷川家具、小川通茶道、太秦映画。ミスコンを巡る京大と東大の対応差。恵文社の文化的雰囲気、イノダコーヒーは朝が面白い。綿矢りさと金原ひとみの比較。紫野高は禅門立紫野中が起源で、水上勉が在籍。旅館の御三家は炭屋、柊屋、俵屋。JRの存在感薄さ、東西線から浜大津に直通の京阪京津線が良い。京ブランドの一方、「京都人しか知らない」もブランド化。おじいさんが群れている→女が強い?京女を演じてきた歴史。
Posted by ブクログ
五重塔と東京タワーの絵に惹かれ、思わず買ってしまった。
特に、京都での敬語の使い方についての考察には、目からウロコ。
Googleマップで羅城門遺址から大極殿遺址まで歩いてみました。
今度、京都に行ったらリアルに歩いてみよう。
途中にある「冷やしあめ」ってまだあるのでしょうか。
天一は本当に箸が立つ。
Posted by ブクログ
文庫本で読んでいたら、河原町のBOOK1stにあったので購入しました。
心地よい都会の孤独感を味わうには良い本です。それでもって、京都の街をときどき歩く東京人として納得することも多いです。(この項続く)
Posted by ブクログ
「負け犬の遠吠え」で有名なエッセイスト、酒井さんの著作。高校生時代から連載を抱えていた(!)だけあってサクサク小気味良い文体で、東京と京都の違いを探り出す。そこで試みているのは今や日本中に広まった東京的価値観に晒すことで、京都的価値観を浮き彫りにするということ。
ぜひ京都に縁ある人は読んでみて!
Posted by ブクログ
都と京。
両方とも「みやこ」と読む。
今の日本の首都は、東京都。
……ん?
東京は、ひがしの京都なのか?!
そんな古都、京都と東京の違いを
言葉、大学、文学、交通と
様々な視点から比較している。
堅苦しくなく、ユーモアいっぱい
京都雑学もたくさん出てきます。
個人的にも2011年くらいから、
縁あって毎年訪れるようになった京都。
今年も行けるかなぁ。
また新たな京都に出会えそうな予感…!
Posted by ブクログ
著者、頭がいい人だなぁ、とつくづく思う。 「文学」の綿矢りさと金原ひとみの比較も面白かったけれども、「敬語」の「いーひん」→「いはらへん」→「いたはらへん」→「いやはらへん」→「いはあらしまへん」の下りには、思わず膝を打ったのでした。 全部で19項立てて、いずれも面白うございましたが、最後「京女と東女」で締めているのが、興深い。 何よりも、肩の凝らないエッセイでありながら、最後にきちんと参考書籍を挙げているのが、素晴らしいと思うのでした。
Posted by ブクログ
「う~ん、東京の人って、やっぱり京都に対してこういう捉え方をするのかなぁ」と、京都(市)のすぐ近くで育った人間としては思ってしまうのでありました。(^^ゞ
ところどころ鋭いなぁと感じるところもありましたが、そんなに「京都はこう」「東京はこう」と定形化・類型化できるもんでもないし…。
例えば「はんなり」という言葉は、京都の人なら感覚的にわかるけど外部の人には説明できないし、外部の人は本当のところは理解できないというのと同じかもしれない。
まぁ、逆も同じで、どこの地域もヨソの人にはわからない所というのは必ずあるので、比較して優劣を論じること自体がナンセンスなのですが。
Posted by ブクログ
文庫化されたときにすぐに買ったのに、ちょっとずつ
読んでいて、ようやく一昨日読み終えました。
遅い・・・。我ながら、遅い。半年もかかってる。
なので、もう最初のほうの話の内容が頭の中で
ボケボケになってます。←読んだといえない・・・
でも、面白かったです。
私は京都で育ったけれど、生粋の京都人ではない。
両親は島根の出だし、修学旅行の印象が良かったから
結婚を機に京都に住んだという両親のおかげで、私は京都で
育つことができたけれど、ずっと先祖代々京都に住んではる
方とは、やっぱりどこか違うことを長年感じていました。
そして、京都を愛して止まない酒井さんの京都・東京比較論にある京都は、外から見た京都だなぁと思うのです。
書いてあることが正しい正しくないという話ではなく、なんというか目線が違う。京都のディープな部分を知人の話や取材や文献から掘り起こされているので、改めて自分がよそ者だと感じるほど、私の知らなかった京都がこの本には書かれていますね。
いつでもいける、と思ったから行ったことがないところ、
やったことがないことも、よそ者(今や府外に住んでいるので本当によそ者・・・)だからこそ、限られた時間の中で見聞きしようとする。その感覚が、今の私にはわかります。
この本の最後のほうに、言葉のことと京女の話が出てくるのですが、これにはうなずけました。
「〜はる」っていう言い回しは、同じ関西圏でも「敬語」と誤解されたりするけれど、少なくとも私の中では自分ではない他人のことを話す時に一般的に使う、ちょっと丁寧な言葉、というかんじでしょうかね。
「お母さん入院したはるんやてね?お加減どう?」
「あの先生のいわはる言葉はいちいち嫌味やなぁ」
「ダンナさん、今家にいはる?それとも出張にいったはんの?」←よく友人に聞かれる(笑)
作者はこの「〜はる」が、仰々しすぎず丁寧にも聞こえ、
また他人と近すぎず遠すぎない距離をとっていえる、
とても便利な言い回しだと思われたようですが、
確かに便利な言葉かもしれません。人のことをあげつらうような時にも使ったりすることがあるのだけど(要するに嫌味、噂話の類)言ってる内容ほどひどく聞こえにくい、響かないかもしれません。
京女は一種のプレイなのではないか、という話にも
笑えましたが、鋭いものを感じました。
はんなりたおやかに見える京女は、実は天性の演技者。
それはどうかなぁ?!
なるほどなぁ、あぁそういえば・・・!
がいっぱい詰まった一冊です。
京都を愛する「東女」目線での東西の都比較論。
なかなか指摘が鋭く、楽しい本でした。
Posted by ブクログ
京都がすきになります。
東京から 四六時中京都を想っている人にはうってつけ。
ただ、読んでる途中で京都に住もうという意欲が少し減ります。
地方出身者は 東京の人から見た京都 だけでなく 東京の人から見た田舎 はこんなふうなんだ、と確認することもできます。
Posted by ブクログ
彼女のエッセーはすきだし、うまいなあとおもう。なんだけど、京都在住としては、彼女にとっての京都は現代=東京の逆でしかなく、同時代的な京都が見えてないように思えてしまうのがちょっとざんねん。
Posted by ブクログ
京都と東京の比較エッセイ。酒井さんらしい軽い感じで書かれていて楽しく読めるけれど、かなりしっかりと地理的にも歴史的にも文学的にも調べたうえ、京都の人のナマの声?も取材しているようで、すごいなーと思った。観光案内や旅行エッセイ風にとどまらない、深いものがある感じ。酒井さん、どれだけ京都に詳しいんでしょう?たまに、「三越さん」とかお店や会社にさんづけする人がいて、不思議な感じだったのだけれど、京都の人だったか。そのへんの事情?(考察?)がおもしろく、へえーと思った。ほかにもいろいろ、へえーと興味深く思うことが多かった。そして、観光案内や旅行エッセイじゃないのに、やっぱり京都に行きたくなる。
Posted by ブクログ
こういうタイプの本は、褒めすぎだったり、けなしすぎだったりしすぎて嫌になるものが多いが、
これはなんとも軽く、ただ「好き」ということが爽やかに書いてあるので、すんなり納得して読める。
なかなか面白い。
Posted by ブクログ
3/14 京都に行く前に、と思って読んでました。いつも独自の視点をもつことと自分の好きなことの交差する感じがおもしろい。飽きないってすごい。ふむふむ、と思って読んじゃう。「かゆいと思う前にかいてくれる」という京都人の接客の描写に超納得!
Posted by ブクログ
京都旅行目前に、本屋さんで発見.....
本を片手に飛行機に乗り込み、じわじわと京モードに切り変えよう!
と思って買った一冊....
読み始めます。出発は明日の朝。
京都旅行の前に是非読まれたし!お勧め本です。「カウンター席の事」「いけずのこと」「モッサイの事」
色々事前情報があって助かりました。
東京都と京都を見事に比較分析、か〜くる読めて良かったです。
Posted by ブクログ
いつまでたっても夢と憧れと謎の土地、京都。
京都の人じゃない人が書く、京都案内。衣食住のことだけでなく、歴史や文学についてもちらりと。そう、綿矢りさは京都出身だけど、『インストール』も『蹴りたい背中』も京都の話ではない。収録された内容はやや古く、インバウンドの大波が押し寄せている京都では、ちょっと状況が変わってきているところもあるけれど、またこの大波さえ、一時のことと流して平然としている真の京都人がいることを信じて。
Posted by ブクログ
東京出身で京都好きの筆者が、東京と京都を、「言葉」、「料理」、「節約」など19の観点から比較するエッセイ。
京都人がドヤ顔で「京都とは云々…」と語ると興醒めしますが(筆者によると、また、私の肌感としても、京都人はそういったことを出来るだけ避けようとするのでそんな機会は滅多になさそうですが…)、東京出身の方が、憧れつつも、客観的に(主に)京都について考察を巡らせるという形で、本社は読者にとって取っ付きやすいように思います。
「嗚呼、なるほど」と膝を打ったのは、「観光客という生き物は常に、『地元の人しか知らないもの』を欲しているし、また『私だけは凡百の観光客とは違って、特別に地元から愛されているのだ。だから私には、地元の人しか知らないものを知る資格がある』という根拠のない自信を持っているのです。」という部分。(p242)
京都人に対して京都語りをする京都以外の出身者に対し、京都人はやはりその自信の匂いを敏感に嗅ぎ取って、苦々しく思っているものだなぁと思いました。
Posted by ブクログ
言葉、料理、贈答、祭り等々での東京と京都の違い。「~してはる」というのは敬語かと思えば、天皇陛下にも、犬にも、犯罪者にも使える不思議な言葉らしい。なんだか奥が深い。著者が京都出身でない事が、却って切り口が鋭さを生んでいる気がします。
Posted by ブクログ
東京から見た京都。酒井さんの京都への憧れとものすごい下調べとフットワークの軽さで地元の人のより詳しいじゃないか?と思うところも多々。私は逆に普通だと思ってたことが実は京都以外では普通じゃなかったことに気付きました。
Posted by ブクログ
‘みやことみやこ’。
都も京もどちらもみやこと読みますが、
やっぱり都の方は東京都を思い出し、京は京都を思いますね。
‘東京都’にも‘京都’にもどっちも都も京も入っているのにね。
Posted by ブクログ
酒井順子さんの京都への憧れが詰まった1冊。
その独特の鋭い視点と丹念な取材に「へぇ~」の連続・・・
多少の思い込みは、この際、東国女の目線ということで楽しみたいとこですね。
そしてこの憧れ、やはり背景に東京への無意識の愛があればこそ…なのかもしれません。。
Posted by ブクログ
東京と京都の比較エッセイ。
内容が、ものすごく京都に気を使っている。東京の人にすると、京都様の気を損ねたらイカン!と思うのでしょうか。
さすがというか、比較ポイントは鋭い。確かにそうだよーって思うところがたくさん。
Posted by ブクログ
東京生まれの東京育ちで京都好きの作者が、西と東の京を比較検討してます。
うなずける事もあれば、ちょっと「?」な部分もあるのはご愛嬌でしょう。
だって、これはお堅い比較研究書ではありませんから。
私が最も肯けなかったのは、女が神社仏閣に行く理由。
著書は「恋愛成就」や「神頼み」「占い好き」と同列で語っていますが、私が神社仏閣に行く理由は「建築物としての魅力」。
その視点を抜きにして語られるのには、納得いかないわ〜。
そして、勿論、私も京都好きです♪
Posted by ブクログ
もう、長年一緒に過ごしている(というかこちらが勝手に読んでいる)酒井さんだけあって、辛らつな文章すら心地よい!
京おんなに関する分析は、関西人の私でさえ「ほほう」と勉強になることばかりでした。
Posted by ブクログ
日本の二つのみやこ、東京と京都。両方のみやこを愛する筆者が、色々な事柄について比較しながら両方のみやこについて考察した一冊。京都に対する考察はとても好意的。東京に対する考察の方が「東京は節操がないのう…」と感じるような印象。筆者が東京出身という事で至極当然なのかもしれない。今まで知らなかった京都を垣間見、興味深い。
中でも「贈答」という項目における東京と京都の違いに表現に笑うと共に、ある種の感動を覚えた。
東京人はプレゼントをあげる行為を自己満足を高めるためのものであるとし、またもらったらもらいっぱなしと言うのが基本(何かの機会に返すというのはあるが)。しかし京都人はもらったらそれに見合ったものを返すのが当然という考え方で、それを例えて筆者はこう書いた。
「東京人にとっての贈答行為が自慰行為のようなものだとしたら、京都人の贈答行為はセックス」
「下品なたとえで恐縮ですが」と前置きしているのが、なんともこの筆者らしいところでもある。
Posted by ブクログ
関西の女性が関西弁をしゃべるだけで5割増しにかわいく見えるというのは間違いない。
ただし、この本を読んで一番頷いたのは、「東京大学の麻布気質」である。「勉強以外に何かができる」のが今の東大生の実態であり、それは「ある一つのことを達成した」受験戦争の勝者ではなく、「何においてもすぐれていたい」上流階級のステータスである。
こうした感覚がはびこる社会はうっ屈としたものにならざるを得ない。ちょうど明治の戊辰詔書の時代のようである。
戊申詔勅(明治41年10月13日)
「朕惟フニ、方今人文日ニ就リ、月ニ将ミ、東西相倚リ、彼此相済シ、以テ其ノ福利ヲ共ニス。朕ハ爰ニ益々国交ヲ修メ、友義ヲ惇シ、列国ト与ニ永ク其ノ慶ニ頼ラムコトヲ期ス。顧ミルニ、日進ノ大勢ニ伴ヒ、文明ノ恵沢ヲ共ニセムトスル、固ヨリ内、国運ノ発展ニ須ツ。戦後日尚浅ク、庶政益々更張ヲ要ス。宜ク上下、心ヲ一ニシ、忠実、業ニ服シ、勤倹、産ヲ治メ、惟レ信、惟レ義、醇厚、俗ヲ成シ、華ヲ去リ、実ニ就キ、荒怠相誡メ、自彊息マサルヘシ。抑我カ神聖ナル祖宗ノ遺訓ト、我カ光輝アル国史ノ成跡トハ、炳トシテ日星ノ如シ。寔ニ克ク恪守シ、淬礪ノ誠ヲ輸サハ、国運発展ノ本近ク斯ニ在リ。朕ハ方今ノ世局ニ処シ、我カ忠良ナル臣民ノ協翼ニ倚藉シテ、維新ノ皇猷ヲ恢弘シ。祖宗ノ威徳ヲ対揚セムコトヲ庶幾フ。爾臣民其レ克ク朕カ旨ヲ体セヨ」
去華就実、この感覚とは何か。時に泥臭いものかもしれない。福沢諭吉の漢詩に、実業界で活躍する教え子たちを「泥の中で咲く蓮」にたとえたものがある。僕の感覚はそちらに近い。