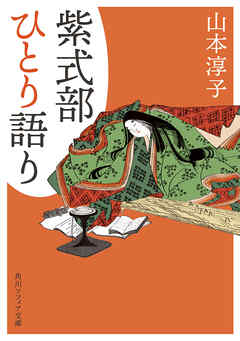感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ビギナーズクラシック「紫式部日記」を買った時近くにあった。冒頭を読むと、~それにしても私の人生とは、なんとまあ次々と大切な人を喪い続けた人生だったろうか。思えば、この悲しみから目をそらすまいと決めたことが、私を『源氏の物語』の作者、紫式部にしたのだ。・・
「姉君」の話をしよう。あれは長徳元(995)年、私がまだ若い娘で、父や弟と一緒に京の邸に暮らしていた頃のことだった・・ と始まる。
そう、これは山本氏が残された史料をもとに、想像を駆使して描いた『紫式部』の人生の独白なのだった。これがめっぽうおもしろい! ずんずん読み進めて一気に読んでしまった。
・・私は後になって書いた『源氏の物語』で、登場人物たちを次々に私と同じ目に遭わせた。光源氏は三歳で母を亡くし、六歳で祖母を亡くす・・
本文には独白の合間合間に「紫式部日記」、「紫式部集」の本文と読み下しが入る。独白の根拠を示している。これが私にはとてもしっくりきた。山本氏の解釈としての独白文が、なるほど、と真実味と凄みをもって迫ってきた。また歴史的出来事もはさんであるが、それらは「小右記」「権記」「御堂関白記」から「日本紀略」「今昔物語集」、また「枕草子」「蜻蛉日記」「古今和歌集」「栄花物語」などなどによって、心境を紡いだ。いやはや実に多くの史料を読み込んで書いてある。
私は和歌が苦手なのだが、当時は自分の心境を和歌によって現わしてしたのだ、ということがわかった。
「紫式部日記」では清少納言を悪しざまに書いている、と流布されているが、山本氏の解釈は少し違う。そこには清少納言と紫式部との漢詩への思い入れと解釈の深さの違いがあるのだ、とする。定子はじめ道隆一族、清少納言は、『香炉峰の雪は』の一文に見られるように漢文の素養があり、それが定子後宮を輝かしいものにしている。そして「枕草子」の存在で10年後の今になっても輝きが増している。それが『枕草子』の力だ。それに比べ彰子後宮は地味だ。彰子様もそれを分かっている。が、しかし定子後宮にとって、漢文とは風流な装飾品でしかなかった。漢文とはもっと自省的な深い意味を持つものなのだ、とする。
また、「紫式部日記」は4つの部分に分かれ、後段のつけたした部分は何故そうしたのか、その紫式部の真意を推理するのも日記を読む醍醐味です、とビギナーズクラシック「紫式部日記」で言っていたが、この「ひとり語り」では、娘の賢子のために書き足したとしている。賢子は父も早くに亡くし後ろ盾がない。あの子は女房になるしかない、と紫式部は考えていて、女房の心得をつけたしの部分で書いた、としている。
しかしこれを読む限り、紫式部と道長は、紫式部が『源氏物語』を書く以前には面識はなかった。大河はドラマなのであるが、ちょっと設定が大胆かなあ、という気もする。でも、倫子と紫式部は母方のはとこ同士、道長とは6代遡る冬嗣からの子孫。お互いの曽祖父の曽祖父が冬嗣なのだった。
単行本「私が源氏物語を書いたわけ 紫式部ひとり語り」角川書店2011.10 を文庫化したもの
2020.2.25初版 2022.11.25第7版 購入
Posted by ブクログ
例によって大河ドラマの影響で読んでいます。紫式部さんの内なる思いが肉声で聴こえてきそうなほどリアルな描写でスイスイ内容が入ってきました。肉声というか吉高由里子さんのお声で再現されてしまっていますが。笑 それはそれでまたドラマを楽しめるのでぜんぜん良しとします。
Posted by ブクログ
大河ドラマ「光る君へ」に触発されて読みだした本。紫式部って源氏物語の作者であることは知っているもののそれ以外のことは意外と知らなかった。
源氏物語を書きだしたきっかけは、夫、藤原宣孝が突然になくなり、その後、物語を書くという作業を通じて、自らを昇華させていったという所なのかな。
初めは、雨夜の品定めといった一編を収録している「箒木」、「空蝉」、「夕顔」の三帖から物語は始まったそうだ。その後、「桐壺」の巻やいろいろな物語を書き足していって源氏物語が完成していく。その間、物語の成立には、藤原道長などの援助もあったようだ。
読んでいていると、結構他の女房達の批評が乗っているが、特に清少納言などについての人物評は手厳しい。かなり口で言えない分、書くことで発散する人だったのだろうかとも思う。
一条天皇の皇后で、紫式部がつかえていた上東門院藤原彰子が徐々に人間として成長していく様を描いている所がまたいいなあ。
注目は、道長との関係。昔、読んだ北山茂夫氏の「藤原道長」では、関係があったという記述があった記憶があるが、実際はどうだろう。この人の性格を見ているとそういう危ない橋は渡らなそうだし、召人のような関係は好まなさそうだから、ない様な気がするのだが、どうだろう。
「紫式部日記」や歌集の「紫式部集」の成立の事情にも触れている。この人は、根っからの作家のような気がする。こういう人は、これまでの文学史上居たのだろうか?
紫式部とはどんな人だったのか、その生涯、述作などを知るための入門書としてはちょうどいい本だと思う。
Posted by ブクログ
紫式部の書き残したもの、歴史的資料などを元にした紫式部の人生が小説風にまとめられています。
偉大な物語作家ではあるけれど、シングルマザーでお勤めをして、仕事や職場の人間関係に悩み、ついいじめに加担するなど、あぁ、普通にいそう、こういう人…と紫式部が身近に思われます。また、主人である中宮彰子の人柄についても述べられています。藤原道長の娘で、政治の道具としてしか印象がなかったのですが、そうではなかったのだな、と。
全体の印象としては、紫式部の心のなかに入り込んで世界を見ているような。心の奥に沈み込むでいくような。そんな感覚を覚えました。
Posted by ブクログ
自伝風評伝
紫式部の姿が浮かんできて興味深い。
清少納言が機知や意志の人、紫式部はねちっこくてリアリスト。それも彰子の女房だったからか。枕草子や清少納言へのいらつきっぷりに、枕草子の力(「枕草子のたくらみ」)が感じられておもしろい。
Posted by ブクログ
私は紫式部にはかなり偏見を持っていた。単純に若い頃に枕草子を先に読み、手に入れて大事に読んでいたからなのだが(笑)
その後、紫式部日記等も学び、子供だった私には彼女はとてもいけすかない女性に思えた。
それから、私も当時よりたくさんの人間関係を経験し、母を亡くし、改めて、源氏物語を読んでみたいと思った。
谷崎潤一郎翻訳の源氏物語を読みながら、紫式部と清少納言の関係を見直してみたくなり、何冊かの本を選んだ。
その一冊である。
読み終えて、二人とも変わらない。会社に勤めて理不尽なことや人間関係に悩む女性。
才があるだけに宮廷暮らしは辛い事も多いことだったろう。
そう考えると日本の女性たちは変わらない環境の中で、今も頑張っているのだと胸が熱くなる。
さぁ、源氏の続きも読まなくては(^^)
Posted by ブクログ
タイトル通り、紫式部が己を語る。
あいかわらず、陰険なひと。
その辺りのキャラがぶれんなあ(笑)
あと、作者が彰子贔屓の先生なので
後半はそれ推し。
素晴らしい上司に出会えた幸せは
今も昔も変わらない。
Posted by ブクログ
紫式部研究者が病膏肓に入って遂に小説に手を染めたかと思いきや、著者によると、あくまで評伝であり、紫式部日記及び紫式部集という、式部が独白体で自らを語った資料に依拠するからには、「本書も、本人の独白の形をとらなくてはならないと考えた」とのこと(あとがき)。著者自ら「冒険的」な試みと述べているが、正直、フィクションでなく評伝なのであれば、1人称にしなかったほうがよいのではないかと思う箇所が結構あった。また、基本的に、結構年行ってから振り返る(後年にならないと得られない知見による記述があるため)という視点で叙述されているようだが(その時点は明示されていない)、若干揺らぎがあるように感じた。
・本書は、歌のやりとりが家集に残る「姉君」との交流で始まるが、この血のつながらない「姉君」が誰かは記されない。研究上、判明していないからだと思うが、1人称で語られる場合、なんとも不自然でもどかしい。また、「道長妾」の真相については口をつぐむのは、史料からは事実がわからないからだろうが、踏み込んだ内心を綴る独白体という形式からすると、白々しい印象を与える。
・漢学の才はろくでもない、それをひけらかす者には惨めな末路が待っているとして、高階成忠やその女婿一家である中関白家を謗っているが、1人称だと生々しすぎて、紫式部が悪口ばっか言うイヤな人間に感じられる(そう表現したくてそうしているのかもしれないが。プライド高いくせに(から?)うじうじ言っている、かなりメンドクサイ性格に描かれているので。中宮彰子に仕える者として、中関白家周辺への反感を隠さないのは、人口に膾炙するするとおりで、当然清少納言の悪口も言っているが、「清少納言と〔曾祖父は中納言であった〕私のことを、同じ受領階級に属するなどと、一緒にしないでほしいものだ。」(p.35)とか、また、漢学への屈折した思いを記しつつ、父為時に越前守をかっさらわれて失意の内に亡くなった源国盛について「だが父と違って漢文ができなかったのだもの、すまないが仕方がないと思うしかない。」(p.60)とか、相当感じ悪い)。
・基本的に紫式部視点で、式部が知りえなかったことは知らなかったこととして記述されるので、客観的にどうだったかが表現できない。例えば、長徳の変や寛弘の呪詛事件など、伊周の失脚に係る事件について、「道長殿にとっては、静観している間に敵が自滅してくれる(略)」(p.60)、「殿が指一つ動かさぬうちに」(p.198)というのは、3人称つまり通常の評伝だったら、別の観点での指摘も入れることができたであろう。一条帝が譲位に当たって長子の敦康の立坊を「意外なほどあっけなく折れてしまわれた。」(p.276)というのも(本書では、古日記・古記録(どころか栄花物語まで)の記述でも、内容が紫式部が属す世間が知りうるものであれば使っているが、天皇と藤原行成のさしの交渉のようなことは、紫式部は知らないこととして記述されていると思われる)。
・リアルにはライバルになりようもなかった清少納言を紫式部日記でああも口汚く罵ったのは、枕草子による定子後宮の残影が彰子後宮にとって不都合だったから、ということを論じており、あの悪口につながるように、枕草子記述についても、「空虚な嘘」「定子様をことさらに美化するための欺瞞」(p.213)と強い言葉で非難している。1人称小説だったら自然でも、評伝として考えるとドン引き。他の著書では、これゆえにこそ枕草子を評価しているわけで、あくまで紫式部として書いているわけだが、学術書です、と言われると、反発を感ぜずにいられない…。
・紫式部日記に記された左京の君事件(いじめ)に、「汚点」として1章を割いて、娘への告白と教訓としているが、同じ事件を紫式部集では取り繕って記し(正に欺瞞!)、しかも、「それを恥ずかしいと思うだけの分別が、今の私にはある。」(p.255)などと、悦に入るは、日記の後年の段で別の女房仲間への悪口に乗らなかった(といっても、こっちの悪口は衣裳の色合わせがダサい、程度のもの)ことを記し、「自律した自分の姿を記すことができた」(p.256)とこれまた悦に入るはで、いじめた側あるあるとは言え、胸糞悪い。これも、3人称で論述すれば、普通に興味深い分析だと思ったと思うのだが。
・一条帝の辞世の「君」については、紫式部であっても、(『源氏物語の時代』同様)両論併記している。本書でのキモは、源氏中の自歌が本歌になっているのかも!というところなので、それには、君=定子とした場合の歌の解釈が1クッション入るほうが、わかりやすいからかもしれない。ところで、現実問題、このとき一条にとって最も懸案だったのは敦康の処遇だったと思うので、この子を濁世において逝くのが心配だよ、というのが一番しっくりくると思うのだが、そういう解釈はないのは、「君」は女君しかありえないから、なんだろうか。
それにしても、一条の急逝ぶりは、陰謀論者だったら、道長による謀殺を疑うところだよね。ただ、それだったら、三条もとっととヤられてないとおかしいから、そんなことないんでしょうけど。一体何の病だったのだろう。
父の赴任先での弟の客死と、それを嘆く父への思いなどは、1人称ならではの魅力が出ていた。
まあ、第三者的な記述はさんざんしてきた著者が、それでは飽き足らず、敢えてこの冒険に挑んだのだから、読者のモヤモヤは想定内で、それを超えた思いを受け取ってくれ! ってことなのかな。