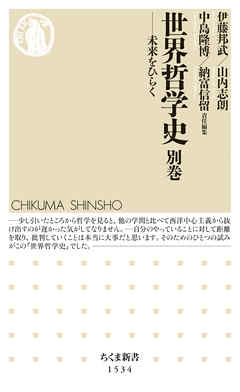感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書は、世界哲学史シリーズのふりかえりと、シリーズで語られなかった漏れを補完することが目的である。
見た目、各章の流れや、並べ方については、どうして、そうなっているのは、理解できませんでした。読むの長い時間がかかってしまいました。
<ふりかえり>
古代Ⅰ 世界と魂がテーマであった。世界哲学の始点をどこにおくか、それはギリシアである。哲学とは、ギリシアから始まる大系であることを始点におく。
古代Ⅱ ギリシアからローマへの流れとキリスト教の成立が軸となる。この時期に世界宗教が成立したことを捉えて、その成立には、聖なるテクストの整備が必要であったことを論じる。
中世Ⅰ 中世のはじまりと、古代が用意してくれた哲学をつかみなおすこと、それが、ルネサンスへとつながっていくことを解説しています。それとイスラームへの考察。
中世Ⅱ トマス・アクィナスを例に「神学大全」を中世スコラ哲学とキリスト教との集大成といて論じています。この時代は、個人の覚醒という概念を次の時代につなげています。
中世Ⅲ バロック、大航海時代、宗教改革、利子の問題から、プロタンティズムへ。
近代Ⅰ 感情と理性の対立、啓蒙の世紀を扱います。科学が発展するにつれて、宗教は世俗化していきます。
近代Ⅱ マルクス主義、プラグマティズムの成立。ヨーロッパの列強による植民地主義は、現代までその禍根を残すことになります。キリスト以前の古代の発見、文献学、実証主義。
現代 20世紀は戦争の世紀であり、哲学は、ナチスなどの全体主義や、科学技術に対抗できずに、戦争という悲劇をもたらした。哲学はこうして、反省を強いられる。
<世界哲学と辺境>
哲学を内部と外部ととらえて、その境界を辺境ととらえ、辺境へとおもむくことを旅ととらえる。辺境と接し、刺激を受けることで新しい思考を生んでいく。
中央で生まれた宗教は、辺境に生きる落差に苦しむ人々を搾取から救済すること、それが普遍的な宗教と説く。
<世界哲学としての日本哲学>
まず、空海が紹介される。三蜜 身体・言語・心、関与しあう知の在り方を、空海は、世界哲学を実践したと語る。
つぎに、道元の正法眼蔵を扱う、荻生徂徠の先王の道、本居宣長の漢意(からごごろ)、和辻哲郎、西田幾太郎、鈴木大拙、井筒俊彦へと続く。
井筒は、再び、空海の真言密教の核心へともどってくる。日本の哲学を時系列に再構築したものである。
<世界哲学のスタイルと実践>
哲学を論ずるのは、その論理性からなのか、それとも、その哲学を記述している言語の文法からなのか、伝えられ、翻訳されたテキストをどう読み解くかという問題を扱っている。
<漏れ>
・ふりかえりに、近代の哲学は、デカルトに始まるという紹介があり、そこで、デカルトの情念論が、この冒頭にあるのであろうか。わからなかった。
・フランシスコ・ザビエル宜しく、イエズス会と中国との関連性が述べられている。それまで中国の原典までさかのぼっていなかった、中国研究は、四書におよぶようになるのである。
・考える私をめぐっての論議。鈴木大拙は、考える私を、空にすること、そして、シモーヌ・ヴェイユに対しても大拙の考えが受け継がれていく。「善は四方八方にあるのに、おまけにみずから身まで差し出しているのに、意志には善が見えない。意思をどれほど行使しても、善は手に入らず、みずからの力を放棄したときにようやく願いが始まる。」という考えが示されていた。
・インドの論理学についての紹介、インドの論理学は、「因明」といい、主張、論理因、実例の三項目かを提示するもの。インドでは、推論という形式の論理が、学術的基盤になっている。
・イスラームの聖典であるクルアーンはアラビア語でかかれていて、その論争は、本来の論理学と、アラビア語の文法の解釈からくるものとがある。それを言語神秘主義と、象徴文字論といっている。
・道元が再び登場する。「日本の生んだ最も偉大な哲学者のひとり」である道元の修行と悟りを軸として、自己とはなにか、世界とはどのようになりたつのかをかたっています。「自己をわするるといふは、万法証せらるるなり」。包括性、一貫性、透徹性、綿密性に富んだ道元の思想は、「正法眼蔵」を先駆として、西洋哲学と比較されていたことを語っている。
・ロシアの現代哲学、ロシアの知識人は、自らを、西洋哲学なのかそれとも東洋哲学なのか、という問いで悩みつづけている。ビサンチンに伝わった東方キリスト教は、ロシアにも伝えられで、西欧とはちがった発展をした。また、共産主義のもと、冷戦後は、近代の超克にも近い形での影響をうけた。
・イタリアの現代哲学は、フランスやドイツとちがって、国家の縛りをうけてこなかった。イタリアの哲学は、感性の学、思想からではなく、美学から出発していることを示される。
・ユダヤ哲学は、19世紀からのユダヤ人の西洋世界への同化の失敗と、大戦による、西洋的価値の崩壊という二重の危機に遭遇した。それゆえ、現代のユダヤ哲学は、西洋哲学を全面的に否定する。
・ナチスの農業政策については、アーリア人が森から平野にでてきた農耕民族であること「森への愛着」そして、血と土が語られてる。この場所のナチスの農業が挿入された理由はわからない。
・ポスト世俗化、チャールズ・テイラーを軸に、宗教と世俗の二分法がかたられている。
・モンゴル仏教について、共産主義を生き残ってきた僧侶については、現世の救済のためのシャマニズムとして生き残ったという話。宗教家ではなく、呪術師としてである。
・ジョン・ロールズの正義論がかたられています。脱西洋主義、聖徳太子の17条憲法、イスラームのサラディン王国、ネルソン・マンデラのタウンミーテイングが非西洋的な事例として紹介されている。
目次は以下の通りです。
はじめに
Ⅰ 世界哲学の過去・現在・未来
第1章 これからの哲学に向けて 「世界哲学史」全八巻を振り返る
1 「世界哲学史1 古代Ⅰ 知恵から愛知へ」
2 「世界哲学史2 古代Ⅱ 世界哲学の成立と展開」
3 「世界哲学史3 中世Ⅰ 超越と普遍に向けて」
4 「世界哲学史4 中世Ⅱ 個人の覚醒」
5 「世界哲学史5 中世Ⅲ バロックの哲学」
6 「世界哲学史6 近代Ⅰ 啓蒙と人間感情論」
7 「世界哲学史7 近代Ⅱ 自由と歴史的発展」
8 「世界哲学史8 現代 グローバル時代の知」
第2章 辺境から見た世界哲学
1 辺境から見た哲学
2 辺境とは何か
3 源泉としての辺境
4 哲学における辺境
5 非中心への希求としての世界哲学
第3章 世界哲学としての日本哲学
1 空海へのリフ
2 フィロロジー
3 世界崩壊と自我の縮小
4 古さはいくつあるのか
5 反復せよ、しかし反復してはならない
6 世界戦争と生
7 戦後の日本哲学の方位
第4章 世界哲学のスタイルと実践
1 哲学のスタイル
2 テクストと翻訳
3 世界哲学の実践
Ⅱ 世界哲学史のさらなる論点
第1章 デカルト「情念論」の射程
第2章 中国哲学情報のヨーロッパへの流入
第3章 シモーヌ・ヴェイユと鈴木大拙
第4章 インドの論理学
第5章 イスラームの言語哲学
第6章 道元の哲学
第7章 ロシアの現代哲学
第8章 イタリアの現代哲学
第9章 現代のユダヤ哲学
第10章 ナチスの農業思想
第11章 ポスト世俗化の哲学
第12章 モンゴルの仏教とシャーマニズム
第13章 正義論の哲学
あとがき
編・執筆者紹介
人名索引
Posted by ブクログ
各分野に詳しい学者の知見を集めた,新書サイズにして専門分野に踏み込むことができる良シリーズ。あえて「世界」哲学史というだけあり,意図的に西洋以外にも範囲を伸ばしている。
Posted by ブクログ
これまでの哲学を根幹から揺さぶる世界哲学史のまとめ編に相応しい内容。特に冒頭の鼎談。後の各論は、小論集なだけに、刺激には乏しいが示唆には富む。
Posted by ブクログ
昨年の前半は、「世界哲学史」が月1冊出るので、読まないと次がまたくるという強迫観念があった。というわけで、せっせと読んでいたのだが、第8巻がでたら、そのプレッシャーはなくなり、昨年末にでた別巻をようやく3月に読んだ。
前半は、編者による対談での振り返りと編者による追加的な論考。そして、後半は、全8巻のなかで扱えなかったトピックをカバーするという構成。
もともと20世紀以降の哲学は1冊しか割り当てられていないので、仕方のない面はあるのだが、現象学や実存主義に関する記載はかなり薄い感じがあったのだが、編者はそこは意識しているのだけど、そこはこの別館でもあまり扱われない、というのは、面白いな。(個人的には現象がよくわからないというのもあって。。。。)
今回、面白かったのは、中国哲学のヨーロッパへの影響とか、ナチスの農業思想、モンゴルの仏教みたいな話し。どれも知らない話しなので、新鮮な驚きが。。。。
で、締めは、「正義論」。現代の「正義論」といえば、ロールズを起点とするわけだが、そこに対する批判の視点の視点。そして、それも西洋哲学内の批判ではなく、「世界哲学」という立場からの批判の視点の整理は、納得性は高い。
全体としては、別巻ということで、本巻ほどのテンションはないのだけど、ちょっとリラックスして余韻を楽しむみたいな感じかな。
Posted by ブクログ
世界哲学史全8巻が好評だったそうなので、編者のお一人である伊藤先生の発案により、別巻発刊となったそうだ。ただ、伊藤先生がご病気ということになってしまい、本巻の座談会は残りの3名の編者による鼎談となっている。その他、16編の論考を収録。うち13編は「Ⅱ.世界哲学史のさらなる論点」でさまざまな論点が提示されている。個人的には頼住先生の「道元の哲学」や岡田先生の「イタリアの現代哲学」、乗松先生の「ロシアの現代哲学」、そして神島先生の「正義論の哲学」などが興味深かった。もちろん短い論考が多いので、隔靴掻痒というか食い足りないというか、そういう部分も多いのだが。それは参考文献を読んでねということなのだろう。
あとがきでは別巻の続編も考えられているそうなので、期待したい。