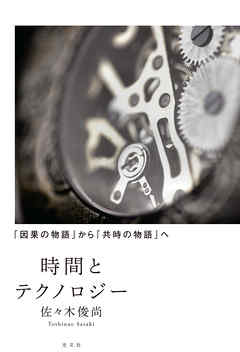感情タグBEST3
Posted by ブクログ
過去現在未来時間軸は一方向に進むことが当たり前である
しかしその概念もない人民族がいる
クラウドの登場により音楽映像の世界では当たり前のように起こっている
記憶は美化されるのだろうか 過去は消滅しなくなった 体験も夢も幻である忘れてもらえない
因果を超えた認識 大数 数式なし⇒確率 べき乗 ⇒AI 学習
自由を考える 見えない支配 ナッジの本質 選択 vs 抑圧 選択は自由ではない
空間遍在のテクノロジー 3次元感覚
「生」に目的は必要ない
ゴンドクナ神話と ローラシア神話
知能と知性 田坂広志
強いAI 弱いAI 特化型 汎用型
ポストトゥルース(脱真実) フェイクニュース ナッジ(セイラー)リバタリアニズムでありパターナリズムである
Posted by ブクログ
21世紀の世代にとって音楽はコレクションではなく、
全ての楽曲が目の前に存在している。
第一世代プラットフォーム
インターネット上での水平統合
第二世代プラットフォーム
サービスとしての流体、ストリーミング
過去:失われていくものから、押しつけがましいものへ
「確率」の物語 大数の法則
「べき」の物語 自己組織化臨界 かろうじて維持されている安定
「機械」の物語 パーセプトロン
誤差逆伝搬法:結果から逆算、重みの数値を変えていく
自己符号化器
「物語」が優先される時代、脱真実、脱「因果」の物語
同化型→対面型(スクリーン、マイク)→
ゼロUI 指示しなくても最適な状態を作る フォグをクラウドの下に
判断疲れ
「アーキテクチャ」見えずに行動を物理的に支配
「ナッジ」ささやかな誘導に従う
社会は臨界状態、単純な選択肢では進まない
自由の価値
未来への期待、過去との関係における相対的なもの
ピュアなデータの周りにある空気感と、そこから生じる「摩擦」
三次元触感
カーナビは平面的な案内。
スマホの設定は記述的。直感的でない。
「空間」のすべてがUIへ、空間コンピューティング
機器は見えなくなる
空間認識能力
時系列tでなく、xyz軸での世の中と自分との関わり
小説家ではなく、脚本家
仮想と現実の区別は意味がない、そこにあるもの
同期と非同期 ;メール
「偏在」(ユビキタス);華僑
マインドフルネス
「摩擦」「空間」「偏在」の重なった感覚が深化
「ライバルとの闘い」=因果の物語
孤独なフリースタイルスポーツ=瞬間
多重プロット =多視点 中心がない 映画「バベル」
因果からこの瞬間へ『共時の物語』
Posted by ブクログ
見た目にはしっかり分厚い本で,中身もぎっしり詰まっている。読むのはちょっと骨が折れるところがあるけれど,同時にどんどんページをめくりたくなって,知的興味がそそられる。
人工知能などの科学の話から社会・文化の話まで論じられている領域の広さに驚かされ,しかも各章のなかに散りばめられていて,全体としても美しい。
それでいて何よりも個人的に前々から気になっていたトピックが華麗に論じられていて,そうだったのかと腑に落ちるとともに,感動した。
一言で言えば,過去でも未来でもない,「今を生きる」っていうことに尽きるけれど,特に感じたことは次のとおり。
◆自由と婚活
正直,恋愛感情を抱けていないで生きてきている。友達で話す好きな子の話とかもあまり好きではなかった。まさに恋愛ができない自分にとっては,恋愛は抑圧でしかなかった。なかなか言い出せなかったんだけどそれを書いてくれていて,そのとおりと嬉しく感じた。
そんな僕も婚活を始めた。といっても,数年やっていて正直上手くいってない。相手の方を自分からお断りすることもあるけれど,多くは断れれている。結婚は必須ではない時代だけれども,しようと思ってできないのが続くと,周りで上手くいっているという話を聞けば聞くほど,自分が人間的に欠陥があるのではないかと思ってしまう。だけどそれは,「因果の物語」に縛られている考え方。「確率の物語」「べき乗の物語」という考え方は楽というか救いになる。
自分のことを棚に上げていてば,婚活は何らかの方法で紹介された人と恋愛しないとゴールできないと思い込んでいる(最初ゲームと書こうと思ったけど訂正した)。
そして問題は結婚相談所や婚活アプリといったネットワークが広がり,ガチャのように,新たな人が紹介される(または見つけられる)ので,目の前の人が果たして理想の人なのかの判断が難しくなってしまった。先に,「確率の物語」「べき乗の物語」という考え方は救いと書いたけれど,一方で次にもっといい人と会えるかもしれない,という誘惑も拭えない。実際,結婚相談所のアドバイザーの人にどうすればいいかと聞いたら,もっとたくさんの人に会うことを薦められた。それが結婚相談所のビジネスモデルだから仕方ない部分もあるけれど。それはさておき,そう思っているうちに目の前のそこそこの人を断り,時間ばかりが経っていき,泥沼にはまっていく。
ちなみに,恋愛が「べき乗の物語」という前提に立ったとき,恋愛と結婚を切り離すと,そこには猛烈な恋愛格差が生まれることになる。つまり,子どもは増えるかもしれないが,父親の数は間違いなく減るだろう。それは結婚を放棄しない恋愛弱者からすると地獄絵図でしかない(経済格差には敏感な人にこの発想が多いことに驚く)。
ちょっと婚活疲れしている自分には,「確率の物語」「べき乗の物語」から脱して,AIが選んだ人と関係を気づきあげていく方が合っているような気がする。と思っていたら,参加したとあるセミナーで,理想という正解を無意識に叩き込めば,どうやって叶うかは考えなくていいというと教えてくれた。まさに「機械の物語」的な発想だった。
◆物語<ストーリー>ゲームの発展と没落
以前,ゲームが与える影響に対しては,登場人物の性格とプレイヤーの性格の差異がヒントになるのではないか,と思っていた(大学の卒論のテーマもこれで書いた)。
本書の表現を借りれば,「持続させるためには、自分ごと化が必要」(p415)ということなんだけど,そのためのツールが物語の中で語られた内容から読み取れる性格という要素であったということだ。
いわゆるJRPGの可能性を考えていたんだけど,ゲームが備えているインタラクティブ性から多重プロット(p367)やナラティブ(p415)の方向性も模索しながら,
ゲームは「因果の物語」を捨てなガチャ的なゲーム(まさに「確率の物語」)が結局主流になっていく。そうなってくると,最後に残るのは海外で主流のMMORPGということになるのか。
まあ,これは人生の話であって,物語そのものが無くなるというわけではないはず。小説や映画は無くならないのだろうけれど,JRPGはMDのように無くなってしまいそうな気も。
最近はゲームをする時間を確保できていないし。ここは過去は色褪せなくなるというところを信じたい。
Posted by ブクログ
<目次>
プロローグ未来は希望か絶望か
第1章鮮明な過去は常に改変され郷愁は消える
第2章過去は物語をつくってきた
第3章因果の物語から、機械の物語へ
第4章自由という未来の終焉
第5章摩擦・空間・遍在のテクノロジー
第6章新しい人間哲学の時代に
エピローグひっそりと、ともに歩く
p173~いったん安定したように見えますが、再び臨界
状態へ徐々に進んでいく~つねに安定、臨界、崩壊の
間をふらふらと揺れ動いているのが自然の姿
p233選択したり判断したりする回数を減らしたい
~判断疲れになるから
p237ナッジ、そっと注意喚起をすること
p3593つの感覚、摩擦感覚、空間感覚、遍在感覚
~これらが重なりあったときに、世界にしっかり
つなぎとめられているという感覚い変わる
佐々木氏はこうした内容の本を書く人とは、知らな
かった。でも、いつもヒントがここにある。
Posted by ブクログ
テクノロジーの進化に伴い生じる時間と空間の認識における大きなパラダイムシフトを、因果・確率・べき乗則・機械の4つの物語、摩擦・空間・遍在の3つの認知感覚によって解きほぐし、新たな哲学を指し示す。
卑近な具体例と広範な論理的裏付けを多用しながら丁寧に論を積み重ねた上で、オートポイエーシス及びユングのシンクロニシティに思想的な出口を求め、やがてナラティブに哲学的解答を見出していく。著者の知識的守備範囲の広さ、一つ一つの糸を織り込んでいく知性と慧眼に拍手。
Posted by ブクログ
過去を色褪せさせないテクノロジー、機械の性能が人間を上回る可能性の出現により、時間と因果が支配する物語よりも、今何を組み合わせるかということが人間社会にとって重要になってきている。
Posted by ブクログ
私たちを取り巻くテクノロジーの変化によって、私たちの「時間」の捉え方は明らかに変容している、という話。
印象的なエピソードとして挙げられているのは、スピーカーから流れてきた70年台のプログレッシブロックについて父が「当時はこういった音楽も、受け入れられるのに時間がかかったんだ」というと、小さな娘が「ということは、この曲は古いの?」と問いかける一幕。
あるいは、永遠に残り続けるネット空間に残されたデジタルフットプリント。データは古びることなく、その人の思考の変遷や社会的立場、あるいは犯罪歴に至るまで忘却が許されない。
「古い」「過去」という価値観や体験は、すでにある種のあざとさを持ったUI/UXとして提示されないと、気づかれないし体験されない価値になってきた。私たちはノイズ(時代性)の取り除かれたデジタルコンテンツを、まるで池から水をすくいとって飲むように消費するようになったので。
はたして一方向に進んでいく、線形の時間軸のモデルをこれからも持ち続けていくことができるのか?あるいは持ち続けていく必要があるのか?という問いと、時代の連続性が希薄になっていく中で、私たちは自己同一性を、あるいは生きている意味をどうやって担保するのか。あるいはそれを担保する必要があるのか?という問い。
いずれも答えることはとても難しいのだが、変容していく人間の意識と社会を俯瞰して捉えておくことは、単純におもしろい。決して全ては同じ場所にあり続けるわけではない。
禅問答のような本。でも僕はこういう「答えがなくてもいいという答え」にふれることで、結構安心できる。
-----
「私たちは自分の自己意識をとても大切なものと考えていて、自己意識こそが自分をコントロールし、身体の行動や脳の思考に命令を下しているのだと考えています。しかしオートポイエーシス的な視座で人間の心を捉えると、心のシステムは作動することによって初めて自己意識が生み出されているのです。つまり主体は自己意識ではなく、意識や思考、行動などを生みだしている脳の神経細胞のシステムそのものであるということ。
つまり、私たちの自己意識が主体なのではありません。思考が思考を、思考が行動を、行動が思考を、あるいは思考が自己意識を、行動が自己意識を、とさまざまな要素を生み出し続けるその「過程」のシステムこそが、私たちの主体であり、人間の本質だと言い換えることができるでしょう」p.410
「アニメ『GOHST IN THE SHELL/攻殻機動隊』の続編『イノセンス』。この映画の終わり近くで、主人公草薙素子はブッダの言葉を口にします。
「孤独に歩め。悪をなさず、求めるところは少なく、林の中を象のように」
もしよい同伴者が作ることができなかったら、一人で歩いた方がいい。愚かな人を道連れにするくらいなら、森林に歩みを進めているゾウのように孤独に歩く方がいい。しかし彼女はそうやって孤独への決意を口にしながらも、懐かしい同僚バトーにこう伝えるのです。
「バトー、忘れないで。あなたがネットにアクセスするとき、私は必ずあなたのそばにいる」
森林の中を孤独に歩くゾウであっても、そのゾウは一人ではない。そこには孤独な道を歩くものたちの親密さがあり、ひっそりとともに歩いて行こうという共感があるのです」p.430
時間とテクノロジー
Posted by ブクログ
哲学と科学の間という感じだろうか。
「未来は前方にあり、過去は後方にある」は絶対的な真理ではない。
過去は既に終わったことだから目に見えるが、未来はまだ起きてないから見えない。
だから過去は顔を向けている前方にあり、未来は背中にある。
すなわち、Back to the Future。
上手いし、なるほどなだし。
序盤の掴みから、テクノロジーと文化を行き来しながら、因果と共時を論じる。
ちょっと個人的に咀嚼できないというか、難解な部分もあるので、何回か読んで理解していきたい一冊。
Posted by ブクログ
テクノロジーが直線的な時間によって因果を司る物語を無効化し、新たな人間哲学として共時の物語に突入しつつある今を描いた一冊。分量が20万字と厚めですが、文学から映画まで幅広く渉猟されており、サラりと読める。
Posted by ブクログ
時間の概念は無くなる、物語は機械によって作られる、今までの法則が使えなくなる。。テクノロジーの発達によって・・今からの時代に、人間は如何あるべきかを考えされられる一冊でした✋
Posted by ブクログ
・時代の早さに驚いたりついていけずに焦ったり、それが無意識的にストレスになり不安を抱える。この時代を生きることは本当に難しいのかもしれない。どう生きるかは永遠の課題だし先の見えない予測できない未来に対して思考し続ける事は現代人の悩みでもある。そんな現実への処方箋のような形でこの本は希望を与えてくれる。テクノロジーの進化で世界は劇的に変わる。その中で自分が最適化できれば視野が広がりそうな気がする。過去、現在、未来を材料にさまざまな角度から人間を考察する深みのある哲学の本でした。
Posted by ブクログ
理解できなかった。部分部分は分かりやすく解説されているのだが、全体を通して掴めなかった。
学び
因果でも確率でもない、共時の物語があると捉える←集団的無意識
空間の認知能力は必要、世界を立体で捉える
機械学習は画像である。
Posted by ブクログ
ここ30年くらいの電子機器の進化とそれがもたらした人間の時間の捉え方の変化、社会の変化についてまとめてある本。映画や音楽、SF、アニメについても交えて書いてあるのでサラッと読めた。
インターネットと自分との関わり方をみつめ直すいい機会になった。あまり考えすぎるのもよくないのでたまにはスマホの電源をオフにして散歩に行こうと思った。
以下、ネタバレを含む詳しい感想。
・デジタルは場所をとらず劣化もしないので便利だが、本当に好きなものはある程度、物理的に持っておいた方がいいと思った。
・記憶が一貫しているというのがその人であるという考え方のことを経験主義というと知った。先日読んだ『クララとお日さま』にも通じるものだと思った。
・高度な思考をするためには抽象化が必要。抽象化のためには忘れることが必要。色あせない記憶は抽象化できないのでむしろやっかいなのだそうだ。忘れることを恐れないようにしよう。
・ポナンザの開発者曰く「知能=画像」かもしれないとのこと。記憶力のチャンピオンも頭のなかに画像を思い浮かべているというのをきいたことがあるし、イメージすることを大切にしよう。
・「人は目的のために生きているのではなく、今生きているから生きるのだ。」
・SNSでは過去は消えないものになりつつあるので、どんな言葉もネット上にあげた時点で他者と繋がっているということを忘れてはいけない。SNSは壁打ちではないし、そこには壁ではなく生身の人間がいる。生身の人間に言えないことはSNS上でも言うべきではない。当たり前だけど忘れてはいけないこと。
Posted by ブクログ
世界の理解を根本から覆す本である。
マインドフルネスにも通じる「私たちは生きているからこそ生きているのであって、そこには過去も未来も現在もなく、「生きよう」と思った瞬間に「生」はただ立ち上がるのだという直感的な認識なのではないだろうか。」がこの本のハイライト。
ユークリッド幾何学やニュートン力学において時間の存在は疑いようがなく因果としてそれを理解している。一方、量子物理学は確率で示され因果が成り立たない。(例えば「シュレーディンガーの猫」)