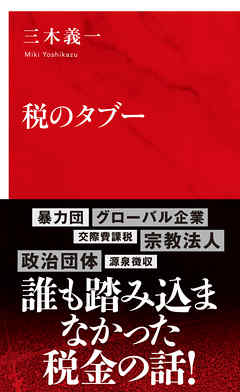感情タグBEST3
Posted by ブクログ
難しそうだけど身近な税のことを、わかりやすく書いている。著者の東京新聞コラムも楽しく読んでいるが、単にわかりやすくではなく、面白く書くのは著者の癖なのだろう。素晴らしい!
【宗教法人】
宗教法人も収益事業は課税が発生
収益事業以外も課税したら、利益が出ないよう経費を使うのでどうせ税収は増えない→経費を使えば経済は活性化する
固定資産税は理屈から言って課税の必要はない。宗教法人の不動産は当該宗教法人しか使えないので、評価額はゼロ。(→疑問を持った。浅草寺は固定資産税払わなくて良いので土地を売らずに保有し続けて借地料収入を得ている。谷中もお寺の土地ばかりで借地物件が多いと聞く)
【政治団体と税】
パナマ文書に日本の政治家が出て来なかったのは、日本の方が政治家にとってタックスヘイブンだから。小渕優子は政治団体が事業を引き継ぐことで、1億2千万円を無罪で相続。
税制が政治家に都合良すぎることが多い。税制を開催するのは議員だが何人も自己の審判官たり得ない。政治家ではない学者たちの検討委員会で法案を作らせ、議会に承認させるべき。
【暴力団への課税】
そもそも違法な所得への課税の理屈を明文化するのはすごく違和感あった。結局、違法所得(用心棒代など)の存在を公式に認めることになっているではないか?税収を得るためにそれで良いのか?
【必要経費】
前にも著者の本だったかで読んだ、サラリーマンの所得控除の話。税務署の「家事費」の考え方は本書がわかりやすかった。「家にいても食事はする」の理屈で、ランチ代はまだしも、シングル母が働くためのベビーシッター代まで業務の直接の経費ではなく私的生活のための「家事費」としか認めないとは。個人事業主であれば必要経費として認められるはずだが、「認められない」と考える税理士が圧倒的に多い。給与所得者は収入に応じて一定の額が控除されるため、必要経費の控除が認められていないので、事業所得者にも認めるべきでない、と言う。しかし本来、給与所得者にも必要経費が認められるべきだし、不利に扱われている人に合わせて皆を不利にする発想はおかしい。
【交際費】
交際費は事業活動において必要な費用だが、損金に算入できない。(1人1回五千円未満は算入できる。さらに資本金1億円以下の中小企業は年間800万円まで算入できる)話は1954年に遡る。朝鮮戦争特需で日本企業が潤い、多額の交際費で繁華街は賑わっていたが、政府は今の日本には資本蓄積が必要と考え、3年の時限措置で交際費の損金算入を規制したが、なぜか65年経った今もそのまま。
【印紙税】
お礼状に確認の意味で料金を記載していたら領収書と認められ、3年分8万1000通の印紙税2700万円を払わされた葬儀業者、セミオーダー下着の「お客様控え」を作ったばかりに、「請負契約書」とみなされ、印紙を貼っていなかったことを指摘されて過怠税3200万円を納付したワコール。。。印紙税が日本で採用されたのは明治6年。オランダ、ふらんす、イギリスに倣って始まる。農民に偏っていた税を商工業者にも負担してもらうために考案されたが、範囲が不明でトラブル絶えない。電子契約書なら課税されないが、文書にすると、メモでもベニヤ板に書いた場合でも課税の可能性がある。契約書が作成される場合、何らかの経済的利益が生じているというのが、政府税制調査会の説明だが、所得税や消費税で課税されているはず。経済界からは毎年廃止要望があるが、自動車重量税並の税収を占めるため、廃止には踏み切られていない。
【固定資産税】
自治体の税収の4〜5割を占める固定資産税は課税ミス続き。複雑すぎるのでAIにやらせた方が良い。バブル崩壊後も固定資産税収入は伸びている。時価は建前で、バブル期に固定資産税が安すぎてみんなが土地を所有したがるから上げることになり、急激にではなく徐々に上げている。家屋の評価額は明らかにおかしい。(高い)
朝日の記者は、隣家との固定資産税の違いに気づき、市担当者と数回にわたり交渉。最新の測量図より公図を優先していると言われる。測量図は法務局に届けられていることを証明でき、固定資産税と都市計画税が年間計約6000円安くなった。
【酒税】
2016年5月27日の参議院本会議で、酒税方改正案が、与党野党全会一致で可決。反対した議員は1人だけ。販売免許を盾に安売り規制とも言える独禁法違反まがいの法案。
酒類販売業免許制が導入されたのは昭和13年。国家総動員法が制定され、戦時経済統制法制が本格的になった時期。あらゆる小売業に免許制を導入するのが課題だった。
不当廉売の定義を考えさせられた。仕入値を下回る価格、当該商品では利益を出さず、他の商品で稼ぐやり方はご法度。
【特別措置】
日本の裁判制度は憲法裁判制度ではなく、司法裁判なので、権利が侵された当事者でなければ違憲性を争えない。フランスでは合理的理由なく、特定層を優遇する制度があれば、自身の権利を侵害されていなくても違憲訴訟ができる。
【源泉徴収】
徴税事務を企業に負わせている。取りすぎがあれば企業に不服を申し立てるようになっていて税務署に都合が良い。「ちゃんとやればお金が返ってくる」確定申告と違って「愚民化」につながる。雇用主に副業収入や家族の健康状態などプライバシーが知られるのでフランスでは、雇用主には税率だけが伝わる仕組みになっている。
【国境】
タックスヘイブンは金持ちの牢獄。脱税のために海外で暮らすのは幸せなのか。
Posted by ブクログ
税金の徴収方法は、公平ではない。
税制の複雑怪奇さも、政策目的ありきの挙句だ。
しかし、逃げ道を塞ぎ正しく創り上げようとしても、その正しさの裏側をすり抜ける道もまた、同時に生まれてしまう。
万人への公正かつ平等は非常に困難だ。やっかいだ
故に時限的な税制度で「短期的に」やりくりしている。
やりたい事と出来る事の、理想と現実にもがいている。
『毎年の税制改正の大半は、この特別措置の新設・延長を巡る攻防戦といってよいと思われます。』
大局的には、政治家も官僚も、分かり易く効果的な制度を考えるてるはずが、気が付くと、「効果を図りつつ、時限立法」のやりくりに追われ、いつの間にか、誰も望まない、複雑怪奇な塊が出来上がる。
総論賛成、各論反対。
それが日本だけではなく、世界の民主主義の最大の弊害になってきているのが、税制度の話だけでもよく理解出来た。
とはいえ、今後も、「時限的なはずの特別措置が作られ、継続させるための努力」が、永遠に繰り返されるしかないのだとも感じた。
もっと一人一人が税金に近づくこと。
これしかないはずだが、それが一番、近くて遠い・・・。
高率な源泉徴収をした後、年末調整を廃止し、確定申告の制度だけにする。
それがシンプルでいいと、やっぱり思うなー。
Posted by ブクログ
タクシーの領収書にはGPSコードがあり場所位置を調べることができる(政治家の不正利用で発覚)という。よって不正に場所位置を提示できない。それにしても政治家の活動費、非課税対象は緩すぎる。政治家を制する「政治家監視委員」なるものが是正しなければいつまで経っても「金がまつわる疑惑」の問題が残り続けると思う。
Posted by ブクログ
読みたくて結構前から買おうと思っていて、ようやく買って読んだ。難しい税金の話も意外な切り口で書かれており、読みやすかった。ホントに税金は奥が深い。自分に関係がある話しとしては、交際費の話しが勉強になった。でも途中よく分からなくなってきた…まだまだ勉強不足か。
Posted by ブクログ
宗教団体や暴力団への課税、個人的にそもそも何なのか不思議に思っていた印紙税などの税に関する気になるけれどもあまり皆んなが知らないことへフォーカスしている良書。
読み進めていくほど、どれほど税制が泥臭く人の手によってねじ曲がっているか理解できる。政治家、財務省に比べて納税者の地位の弱さたるやと言えば目を覆いたくなるもの。
著者の軽妙な筆致で多少は緩和されるのが救いか。
Posted by ブクログ
税のタブー
著:三木 義一
税金の制度は人間が自分たちの社会の都合に合わせてつくりだしたものであり、宇宙を支配している原理や法則とは全く異なる。きわめて公正で合理的な税制も、まったく逆に、きわめて不公正で恣意的な税制も、制定することは可能である。ただ、その社会の人々がそれを政治的に受け入れるかどうかの問題である。
税は、主権者になった私たちにとっては、時の統治者や権力者から一方的に収奪される年貢のようなものではなく、自分たちで決めるべきものであり、実際に決められるのである。本書ではそれを一緒に考えるきっかけを与えてくれている。
以下の11章から成っている。
①宗教法人
②政治団体と税
③暴力団に課税できるか?
④必要経費を考える
⑤交際費課税はそろそろやめよう
⑥印紙税はいらない
⑦固定資産税はミスだらけ
⑧酒の販売と免許
⑨特別措置は必要か
⑩源泉徴収・年末調整
⑪国境
義務として課せられており、その仕組みを完全に理解したわけではないけれども、なんとなくしっかりと課税している現状。それが当たり前であり、揺るがないものであり、ただ払い続けている。
その課税体系や仕組みにおいては、日本という国を信頼して、正しいものを正しく運用してもらっているから従っているものの、よりよく知るとそれだけではないこともわかる。
同じ環境においてもやり方を変えれば課せられるそれも変わることもある。知っておいて損はない。やみくもに悪意を持って税と関わるのではなく、より良く知り、良い付き合いをすれば自分だけではなく、自治体や国にとってもプラスになることもある。
本書ではその全てがわかるというものではないが、わかりやすくそしておもしろく興味を惹くように記されており考えるきっかけを与えてくれている。