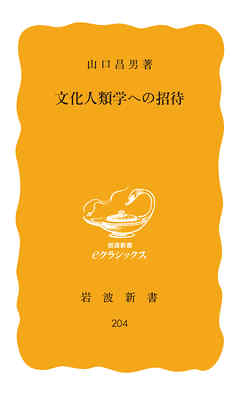感情タグBEST3
Posted by ブクログ
多摩市の市民講座で開講された「文化人類学入門」という連続講演をまとめた本です。巻末には、講座に出席していた大江健三郎の感想も収録されています。
本書ではまず、トロブリアンド諸島の「クラ」について調査をおこなったマリノフスキーについての解説がなされています。つづいて、モースの贈与論やレヴィ=ストロースの構造人類学などへと話が展開して、交易と互酬性が社会の基礎をかたちづくっており、文化のなかにおける家族・親族関係の基礎に通じるしくみをそこに見てとることができるということが説明されます。
さらに、レヴィ=ストロースの『親族の基本構造』における女性の交換の議論を手がかりにしながら、著者自身が研究・調査をおこなったフローレス島の事例を参照して、政治のもっている演劇性についての考察が展開されています。最後に著者は、マリノフスキーと交流のあったポーランドの劇作家であるヴィトケヴィッチをとりあげ、演劇性をめぐる議論がなされています。
「あとがき」で著者は、「せいぜい一人の文化人類学者にできるのは、自らの知的戦略にとって文化人類学とは何か、何故に、自分は文化人類学という知の戦略を選び、この分野にこだわり続けているのかということを示すことでしかない」と述べていますが、本書は文化人類学の概説ではなく、「中心と周縁」というテーマなど著者自身の関心にもとづく議論がなされています。とはいえ、マリノフスキーからレヴィ=ストロースへいたる文化人類学の潮流が、上述の観点からごく簡単にたどられており、さらにヴィトケヴィッチとのつながりという、西洋精神史の一コマにも目くばりがなされていて、興味深く読みました。
Posted by ブクログ
自分には時期尚早だった。
前半は構造主義の入門本の類を読んでいて、かろうじて理解できた。
個別具体的な事象に演繹し、考察する部分は面白かった。
後半は前知識が全くなく、読み進めるのに一苦労。数年後、また読み返そうかな。
新書に稀に出没する、初見殺しシリーズ。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
ポーランドの知的風土に始まり、交換という経済行為の背後に見えがくれする宇宙論的構図、女性が開示する文化のルーツ、政治の演劇的解釈など、現実の多義性を読みとき文化の全体像を回復しようとする試み。
文化人類学が内包する知の挑発的部分のありかを示し、学問の形式を使って知の深層にふみこもうとする人のための入門書。
[ 目次 ]
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]