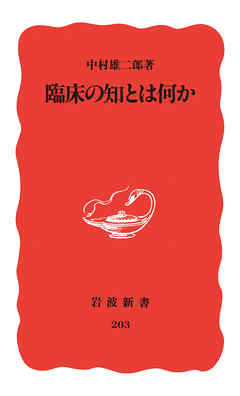感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書で注目したい点は、平易な言葉によって、日々の中で人が生き、自然に感じる言語まで至らない、非言語的な現象を捉え、言語化している事実にある。もし本書を読み、その内容があまり記憶に残らなったとしても、それらは既に自分の中に前々から無自覚に自覚されていた現象であっただけとも考えられ、全く不思議ではないように思える。それゆえ、本書の内容は近代科学が苦手としてきた日々の生活の場を、学問体系の水準まで高める際に十分な指針となってくれるであろう一冊である。
Posted by ブクログ
数字を用いた量的な研究って詰まるところ平均であり確率論だと思うんですが、その限界を語るとともに、これから来たるべき「臨床の知」について、歴史を振り返りながら述べている。途中の哲学のお話は難しかったですが、科学史の話や医療との関係は(比較的)わかりやすく、面白かったです。心理学の人や医学系の人は読んで損はない一冊。
Posted by ブクログ
留学時代にこの本を読んだ。15年以上前のことである。すごく新鮮だった。氏の考えは将来、日本のカイロプラクティックの発展にとって非常に重要になる。これが私の確信だ。本書の骨子。今日の医療の限界は近代知の限界そのものであり、新たな医療の展開は近代知の限界を超えた臨床の知でなければならない。近代知は普遍主義・論理主義・客観主義の構成原理を持つ。それに対し、近代知を超える臨床の知はコスモロジー(宇宙論的考え方)・シンボリズム(象徴表現の立場)・パフォーマンス(身体的行為の重視)を構成原理とする。著者は「科学の知は、抽象的な普遍性によって、分析的に因果律に従う現実にかかわり、それを操作的に対象化するが、それに対して、臨床の知は、個々の場合や場所を重視して深層の現実にかかわり、世界や他者がわれわれに示す隠された意味を相互行為のうちに読み取り、捉える働きをする」と要約する。
この本は、西洋医学の特定病院論の誤り、プライマリーケアを全科医療と考える見方、健康と病気に対する哲学的意味など、いろいろ示唆に富む。臨床に携わるすべての人に読んでもたらいたい本である。
Posted by ブクログ
わが師匠の集大成の一冊。大学時代に出版されたときは貪るように読み、ゼミで質問しようとすると『自分で考えて、そう思ったものが正しい答えなのだ』という内容のことを言われたのが、懐かしいです。とにかく必読の書。
Posted by ブクログ
IV 臨床の知の発見 を読むと、分厚い雲の隙間から「臨床の知」が少しだけ垣間見れる気がします。でもよくわからない。とてももどかしい、もう一度読み直そうかと思います。
Posted by ブクログ
「臨床の知」という新しい知のあり方を提唱した本。
普遍性、論理性、客観性を原理とする科学の知だけでは、人間の全部はわからないよね、ということを言っている。
医療の世界に限らず、ものの見方全体に関わる話だったので面白かった。1992年発売の本だけど色あせていない。
Posted by ブクログ
哲学の歴史とともに、科学とは何かを解説しておられる。
僕にとっては難解な本で、ゆっくり時間をかけて読んだ。
読み進めて、「臨床の知」の頁に行き当たって、『そうだった、「臨床の知とは何か」を読んでいるんだった』と思い起こされるほど、前置きが長かった。
5章、6章になって、やっと医療に関るないようなのだけども、それも医療とは何か、生命倫理とは何かといった深い者で読み応えがあった。
何度も繰り返し読んで深めていきたい本。
難しいけれど・・・。
----------------
【内容(「BOOK」データベースより)】
科学に代表される“近代の知”は大きな成果を生んだ。しかし今日、その限界も指摘されはじめている。人間存在の多面的な現実に即した“臨床の知”が構築されねばならない。著者の積年の思索の結実である本書は、人間の知のあり方に新たな展望を開き、脳死や臓器移植などの医学的臨床の問題にたいしても明快な視点を提供する。
----------------
【目次】
1 “科学”とはなんだったのか
2 経験と技術=アート
3 臨床の知への道
4 臨床の知の発見
5 医療と臨床の知
6 生命倫理と臨床の知
----------------
Posted by ブクログ
あの河合隼雄先生が「参考になった」と書かれていたので読んでみた本。なにか大事なことが書いてあるとは感じるものの、どういうわけか、内容をうまく読み取れない。もう一度読んでみないといけない本。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
科学に代表される〈近代の知〉は大きな成果を生んだ。
しかし今日、その限界も指摘されはじめている。
人間存在の多面的な現実に即した〈臨床の知〉が構築されねばならない。
著者の積年の思索の結実である本書は、人間の知のあり方に新たな展望を開き、脳死や臓器移植などの医学的臨床の問題にたいしても明快な視点を提供する。
[ 目次 ]
序文 なぜ〈臨床の知〉なのか
1 〈科学〉とはなんだったのか
2 経験と技術=アート
3 臨床の知への道
4 臨床の知の発見
5 医療と臨床の知
6 生命倫理と臨床の知
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
実は難しくて、よく分からなかったのが本当だが、かろうしで、以下の文章を記憶できた。
つまり、医学はサイエンスの面を持つだけではなく、具体的な場面・事物の多義性・相互行為に対応する知恵に充ちた技芸・アートである。
自己をカッコに入れて、責任を回避する客観主義や普遍主義の落とし穴におちいらない。
Posted by ブクログ
科学は「普遍性・論理性・客観性」から成り「生命現象や関係の相互性」を見え難くしてしまった。臨床の知は、「コスモロジー・シンボリズム・パフォーマンス」から成り、科学の仮説と演繹推論に対して、直感と経験と類推の積み重ねで成立させるらしい。
知の手法にも色々あるもんだと思わされた。筆者の提案は今風に言うとパターン認識に近いのだと思う。よく知らんけど。しかし、難し過ぎた。前半何とかついてってたけど、中盤からイミフになって、後半の医療的な話は興味なくなってきてた。修行足りんわ。
Posted by ブクログ
<普遍性><論理性><客観性>という三つの原理を擁する「近代科学」は、この2、300年来文句なしに人間の役に立ってきた。それ故に我々はほとんどそれを通さずに<現実>を見ることができなくなってしまった。
しかし、近代科学によって捉えられる<現実>がすべてなのだろうか。近年の社会問題、環境問題等、それだけでは解決し得ぬ状況、現実とのズレが顕在化しているが、その原因は、近代科学が<生命現象><関係の相互性>を無視しているため。
筆者は近代科学が排除した<現実>の側面を捉え直す重要な要素として、<コスモロジー(固有世界)><シンボリズム(事物の多様性)><パフォーマンス(身体性をそなえた行為)>をあげ、それらを体現したものを「臨床の知」としている。
Posted by ブクログ
何分,哲学用語に疎いものだから,非常に読みにくく感じました。しかし,何かこれまでの科学思想とは異なる観点を提出していそうではある。これはもう一度心して読む必要があります。
*****
では,演劇本来の特質とはなにか。それは,…,人間と世界とを凝縮化して重層的に捉え,描き出すことダル。等身大の日常的な人間ではなく可能的な人間を表現することによって,人間の隠れた本質を捉えることである。(p.116)
したがって,コスモロジーとシンボリズムとパフォーマンスの3つの特性あるいは構成原理とする<臨床の知>は,近代的な<科学の知>と対比して,次のようにまとめられることになる。すなわち,科学の知は,抽象的な普遍性によって,分析的に因果律に従う現実にかかわり,それを操作的に対象化するが,それに対して,臨床の知は,個々の場合や場所を重視して深層の現実にかかわり,世界や他者がわれわれに示す隠された意味を相互行為のうちに読取,捉える働きをする,と。
ことばを換えていえば,科学の知が冷ややかなまなざしの知,視覚独走の知であるのに対して,臨床の知は,諸感覚の協働にもとづく共通感覚的な知であることになる。というのも,臨床の知においては,視覚が働くときでも,単独にでなく他の諸感覚とくに触覚を含む体性感覚と結びついて働くので,その働きは共通感覚的であることになるのである。(pp.135-136)
病気のために生命の危機感に見舞われることによって,深い生命に目覚めることは,多くの人々に見られたところである。(p.159)
[重要なことは]病気が,<リズムとバランス>の,つまり<安定した自己調節機能>の破れであるという,まさにそのことによって,生命有機体であり精神=身体的存在であるわれわれ人間にとって,危機を通して自己を更新し,リフレッシュする働きをもちうる,ということである。このような危機が意味をもつのは,それがわれわれを境界性(リミナリティ)に置き,日常性の惰性化を突き崩すからである。境界性とは異界の性格をもったものであり,すぐれて人生の節目を構成するのである。(p.162)
Posted by ブクログ
著者の考えは伝わって来たし、共感出来たのだが、いかんせん文体というか言い回しが難解である。哲学特有の語句であったり、ある程度背景をしらないと「?」になる。読み進める過程で何度も前に戻って読み返してしまった。もう少し、読みやすければいいのに。