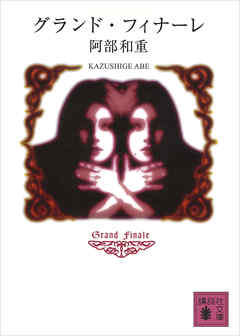感情タグBEST3
Posted by ブクログ
自分と他との距離感がつかめていないという実感を持つ「わたし」。この実感を持てることが自分を知るということなんだろう。外見で個性を主張するとかあほくさいって思った。自分と言うフィルターを通して世界がどう見えるかというとこに個性がある。
Posted by ブクログ
もうすぐクリスマスですね。
ー 二〇〇一年のクリスマスを境に、我が家の紐帯は解れ…
芥川賞受賞の表題作は、ロリコン趣味が露呈して、妻と最愛の娘に去られた男の再生の物語。
とは言え、反省はしてるんだろうけど、主人公はきっと変態なままだ。
気持ち悪いまま読み終えた。
阿部和重さんは、そんな病んでいる男を一人称でドライに描き上げる。
村上龍さんは芥川賞の選評の中で「少女に対する偏愛という、いろいろな意味で危険なモチーフについて、作者が踏み込んで書いていないのが最大の不満だった」と言っているが、そこがこの小説をかえって不気味にしている、と思った。
主人公の内面については薄っぺらく描かれてるので、引き起こした事象から主人公のヤバさを読者は受け止める。なんかね、もういや〜なもやもやが残るんですよ。
人にあまりおすすめはしたくないが、僕はこの短編にかなりやられました。
そして、meguyamaさんもレビューでおっしゃってたけど、収録された最後の短編の「20世紀」と「グランド・フィナーレ」がループしているように思えて…
読み終えて、さーっと全身に鳥肌が立ちました。
人生って、ほんとにコワイ…
あと、「グランド・フィナーレ」の作中に登場するジャズ曲、アーチー・シェップの「Quiet Dawn」は危なっかしい少女のヴォーカルが心をすごく不穏にさせます。
くれぐれも、この曲を聴きながら「グランド・フィナーレ」を読まないように。
おかしくなります。
Posted by ブクログ
終わり、それとも始まり……神町を巡る物語「グランドフィナーレ」という名の終わりの始まり。毎日出版文化賞、伊藤整賞W受賞作「シンセミア」に続く、二人の少女と一人の男を巡る新たなる神町の物語。
自分の過去をまるで他人事のように小さく語る主人公。刑事事件になっていないからなのか、それとも思考を停止しているだけなのか。クライマックスもこじんまりしていてサイコパス感が出ていて良かった。阿部小説は文体にかなり特徴があるらしい。とある芥川賞作家は、この作品についてこう書いていた。「多くの読者は疲れるだろう」と。だけどグランドフィナーレを読み終えた直後の感想は「普通に読めるし面白い」だった。
Posted by ブクログ
度し難いクズのお話。なにかおかしいと読み進めると、徐々に明らかにされるクズのクズたる由縁がおもしろかった。最後はなー、きっとこの主人公は変わらないだろうなとも読めて、評判悪いのもわかるが個人的にはかなり読ませる小説で面白かったです。この2ヶ月くらい、芥川賞受賞作を10作近く読んだけれど、『推し燃ゆ』の次くらいに面白かった。
Posted by ブクログ
これは神町絡みって分かりやすかったし、ニッポニア関連の話題も出てきたけど、やっぱりそれぞれの相関性はほぼ皆無なんですね。独立した物語になっていて、これ単独でも十分楽しめる内容でした。まあ、どこまで楽しめたかってのは別問題で、アブノーマル描写が多いなってこと以外、とりたてて言うことはない感じでした。でもそのアブノーマリティも、前2作の方が極端に思えましたが。表題作以外のおまけ(?)短編に関しては、読み流した程度で、特に感慨は覚えませんでした。やっぱりシンセミアが最強と思います。
Posted by ブクログ
とても重いテーマだった。
児童性愛者の主人公。
なんだかこう、はじめてこういう人の主観にたってみて、きっと子どもに対するときめきみたいなものは抑えられないんだろうと思い、なんと少し同情の気持ちが湧いてしまった。
子どものことはみんな、好きでしょう?それを、性的に好きになるかどうかって、意外と紙一重だったりしないのかな………
主人公の異常性が露骨にえがかれていなかったからか、彼の子どもへの愛情が強いからか、2人の女の子が非常に愛らしくえがかれていたからか、案外ぽろっとハマってしまうものなのかもしれないと感じた。
主人公の男性的な事実のみの思考、離婚やドラッグや法に触れる仕事といったハードな現実。これに対応するのが、子ども達の純粋無垢な姿なのかな。これだけキツイ汚い世界に生きていると、より子どもというものが輝かしい存在に思えてくる。
そして自殺、という行動について。
「愛する人に自殺してほしくない」
という気持ち。
主人公はIからこれを突きつけられ、終盤では自分がこの気持ちに駆られて動く。
なんとも……
子どもを愛することをやめられないから避けようとしていた主人公にとっては、子どもを自分の欲望によって傷つけることなく、幸せに、生きていってほしいと思う行動、そんな自分との折り合いの付け方はハッピーエンドじゃないだろうか。
終始主人公は愛情深く、意外と、憎めなかったんだよな。
あまり評判よくなさそうだけど、終わり方含めてあたしは含みのある現代小説でよかったなぁと思いました。キモイ暗いテーマだけど、主人公が無機質なので割と軽くなってる印象。
阿部和重の主人公の執着思考は何だか読んでて臨場感がある。あと漢検の勉強になりそうな本笑。
Posted by ブクログ
2005年芥川賞受賞作。作品全体の暗さ、不気味さが体に残る。前半は主人公の気持ち悪さが際立つが、意外と自己反省的で、自分の悪い部分を分析する一面も見られる。掴みどころがない。掴みどころのなさから多少の人間味が出ていて(とても魅力とは呼べないけど)、憎みきれない。
Posted by ブクログ
私は佳作だと思います。
設定から奇を衒う内容を思わせます。しかし本作品では普通に、大人から見た子供、大人になったが故遠く感じてしまう子供、その純粋なものに触れたい気持ちを抑えられない不純な大人が描かれているのです。
設定のマニアックさのバイアスがあるので酷評されている感がありますが、普通の純文学と見ていいのではないでしょうか?
Posted by ブクログ
シンセミアほどの衝撃はないが、ありそうにない話でいながら、リアリティのある、筆者の真骨頂が発揮された作品であると思う。救われない内容でありながら、何か心温まるものが感じられて、とても味のある作品ではないかと思う。
Posted by ブクログ
幼女ポルノのビジネスに手を染めた冴えない中年の話です。
離婚され、最愛の娘と引き剥がされ、でも未練たっぷりで。
さて困りましたね。
面白いかと聞かれれば「そこそこ」です。さらに文学性も高いと思います。どこがと言われても困るのですが。
しかし、何が書きたかったのか良く判らない。少なくとも表面を流れている物語では無いような気がするのです。どこかに何かのバックグラウンドが存在しているように思えます。しかしぞれが何か判りません。
どう評価すべきなのか悩んでしまう、そんな作品でした。
Posted by ブクログ
表題作もスキだけど、
『馬小屋の乙女』がよかった。
ええ、あの人が乙女?なのかなぁっていう。
『20世紀』も『新宿ヨドバシカメラ』も企画モノらしいけど、良かった。
書きたいものしか書かないって言うのも作家だなぁって思うけど、こういう企業とのコラボレーションなんかでも文体の特徴なんかを損なわないで見事に書けていると実力を感じる
Posted by ブクログ
読書開始日:2021年10月13日
読書終了日:2021年10月17日
所感
台詞がかなり好み。
表現方法も多彩。
でも内容としてはあまり好みではない。
台詞や言い回し図鑑のような作品だった。
半導体技術はもはや何の手助けにもなってくれず
置いてけ堀
期待が大きいほど外れくじを引きやすい
うすばかげろう
彼なりの動物愛護精神
どう転んでも原物とは一致し得ないまやかし=磁気的記録
不道徳の匂い
今現在は露悪趣味に走って自身であえて貶めることにより逆説的に自らを際立たせた気になって悦に入る
ちっぽけでぼやけたデジタルの像を見つめることによって感受されるのは、やはりどうにも埋め難い、被写体との距離だった
沢見さんは、田舎に帰って、こっちにいる人たちの顔を見ないで暮らしていけば何もかも忘れ去られるんだろうけど
古典的メロドラマ
デジタルの象を守るあまり変え難い現実を手放す羽目になった後悔を抱く
都市化の推進とは一方で、新市街地の周囲に無数の小さな田舎を同時に生み出してゆく
素寒貧
少々てれ気味に腹を立てていた
わたしの中に巣食うナルシシステイックなセンチメンタリズム
無責任を玩味しながら孤独に酔っていたかったのだ。完全から孤独を恐れながら
子供たちの社会は、大人のそれよりも遥かに人間関係の変化に富んでおり、濃密な時間が流れているものだ。
死にゆくものから託されたねがいは、それを受け止めたものに対して絶対的な命令のごとき強制力を及ぼしてしまう
貫徹は美徳
イエローベースの春の肌色
ブルーベースの冬の肌色
馬小屋の乙女
素性もわからぬものに対してこうもあっさり明け透けになれるのは、きっと本心ではそれなりに不満が鬱積しており、自身の現状についてだれでもいいから話して聞かせてみたかったのだろう
シャブもしくはスミ子の名器
しんじゅくよどばしかめら
新宿のなにもかもが鬱陶しく、わたしたちを逆説的に惹きつけてやまない。
渋谷=どこもかしこも広告の一部として存在するだけであって、ただ消費者のみが交通を許される
新宿=人情味の排除=ヨドバシの罪
姿見ずを克服するためにカメラは、あえて「淀」の中へレンズを向けねばならないという逆説
20世紀
ダゲレオタイプの登場により、存在という概念が明確化。観測可能なものだけが存在。
心霊写真がいい例
人間が観測技術よってしか存在を認めなくなると、無神論が蔓延る。そのため神は存在の刻印を世界中に残し続ける。
Posted by ブクログ
現代を描いたものはすべて『コンビニ人間』と比較してしまう。
取って付けたような犯罪歴や自殺の匂わせなどは『コンビニ人間』と比べると「人間が描けていない」と思えてしまう。
Posted by ブクログ
短編集。表題作は、ロリコンがバレて離婚させられた男が会えなくなった娘に未練を残しつつ田舎に戻ったら、ある経緯から二人の少女の演劇指導をすることになった話。演劇指導を依頼されるまで随分と退屈だったけれど、救いようのない結末でなくてホッとした。仮構に人物を当てはめてコミュニケートした気になってる、は、改めてそうだと思った。他の短編では、ホームビデオは画面の映像と記憶の映像の2つを観ている、との記述が面白く思った。
Posted by ブクログ
何だか文というか漢字が難しかったです。
芥川賞だから難しいのか、難しいから芥川賞なのか。
文の雰囲気としては、コメディ要素を抜いた森見登美彦さんって感じでした。
内容はどうなんでしょうね。
何だか盛り上がりそうだぞ、って思って読んでたら、やっぱそんなに盛り上がらなかったかって場面が何度かあったような。
Posted by ブクログ
ロリコン趣味が露見して、妻と娘に見捨てられ
友人関係にも暴露されたことで軽蔑を受けるおっさん
それも仕方の無いことだ
幼少期に受けた性的虐待の、心の傷というものは
悪くすると自らの命を絶ってしまう原因にもなりかねないのだから
ただ、ここでおっさんがその気になりさえすれば
反論することは可能である
というのも、心に傷を負わない人間などいない
おっさんがロリコン趣味を持ったことは
これもやはりおそらくは、幼少期に受けた心の傷が原因であって
そこに不可抗力は、認められるべきだと
だけどもちろん、おっさんはそのようなことを言わぬ
なぜなら現代社会において
そのような憎しみの連鎖を断ち切ることは、大人たちの責務だからだ
その矜持だけでも守りとおしたおっさんはえらい
いやえらくない
まあそんな感じで郷里へとひきこもったおっさんは
なにも知らない昔の友人から、児童演劇の指導役を頼まれたりして
人間的な再生をはかっていくわけだ
本来なら小学生女児の前になど顔を出せないおっさんだが
子供たちの真剣さにほだされて、なんとか「大人」を演じようとする
…劇作家で演出家の故・つかこうへい氏は、演技指導の際
役者を徹底的に批判することで
無駄な自意識をはぎとり、役柄に集中させたのだと聞く
おっさんが、ロリコンとしてその人格を全否定されたことは
結果的にプラスに働いたと言えるだろう
しかし彼の演じる芝居には、脚本がないのだった
ロリコンは「大人」というものについて知っているのか?
ラスト、おっさんは女児たちに
セキセイインコをプレゼントしようと考えるのだが
僕にはそれが村上春樹の短編「蛍」に重なって見えたりもした
Posted by ブクログ
もうあんまし覚えていませんけれども、ロリコン男の話だったかと思います! この題材で芥川賞を受賞できるだなんて…さすが阿部先生ですね! ←え?? 社畜死ね!!
ヽ(・ω・)/ズコー
まあ、取り立てて感想めいた感想はないんですけれども、解説にもあった通り、現実味・人間味に欠けるかのような描写の主人公ではありますけれども、実際にはこういった、特に電脳化著しい現代においてはこのような男が幾多も存在するんじゃないでしょうかねぇ…みたいなことを思ったのでした。僕も実際、人間としての大事な何か、つまりは感情・情緒といった面が欠けているのかと思いますし… ←え??
といった感じで世間的な評価はあまりよろしくない芥川賞受賞作ではありますけれども、個人的にはそこまで酷い作品だと思いませんでした…おしまい。
ヽ(・ω・)/ズコー
Posted by ブクログ
「グランド・フィナーレ」「馬小屋の乙女」「新宿ヨドバシカメラ」「20世紀」の4本からなる短編集。
この本を読んで最も印象に残ったのは阿部和重の「時間」というものに対する感覚。ロリコン犯罪者の、子供にとっての「時間」と大人にとっての「時間」はまるで別のものだという認識。ある年齢まで、ビデオカメラによって生活を詳細に記憶された女性の「時間」に対する感覚の歪み、すごく面白かった。思えばわたしは時間の経過による思い出の美化、風化といった、「時の欺瞞」とも呼べる何かに対して、ずっと疑問を抱いて来た。こういった時間に対する感性に出会えてとても興味深かったです。
Posted by ブクログ
多彩で奇抜な文章は、読みすぎるとお腹をこわしそう。ロリコンとかドラッグとかテロとか、読む人によっては気味悪い小説だろうけど、奇妙な魅力がある。
ニッポニア・ニッポン、シンセミアと並ぶ阿部和重「神町サーガ」のひとつ。
Posted by ブクログ
表題作は最初から最後までずっと違和感があって気持ち悪い。
先入観によって、物語の顛末を嫌でも予想してしまい、不安を抱きながら読む自分が居た。
結局予想とは違う方向へ進みそうになって話は終わったのだけど、中途半端で肩透かしを食らった気分になってしまった。
個人的には表題作よりも共に収録された短編三本のほうが面白かったなぁ。
Posted by ブクログ
阿部和重作品で、まだ読んでなかったことに気付き購入。
神町絡みの作品なので、『シンセミア』が非常に面白かったことから期待して読んだのであるが大したことはなかった。主人公の行く末と物語の展開に期待して先を読み進めたのであるが、結果は結局よくわからずあいまいなままという結末で心動かされず。解説で、高橋源一郎が絶賛しているが、これもよくわからず説得力は無し。
神町を舞台にした話が出てくるので、神町に絡んだ他の作品を再読してみたいとは思うが、今すぐに!というほどの力は無し。
Posted by ブクログ
離婚したせいで愛娘ちーちゃんと会えなくなってしまった。
DVと言ってもたった1回妻を突き飛ばしてしまっただけなのに。
その原因も妻が勝手にわたしのデータをコピーしたからだ。
ちーちゃんや他の女の子の写真のデータを。
田舎に帰り大人しく実家の文具屋の店番をしていると
2人の女の子が演劇の指導をして欲しいと訪ねてきた。
小学生は避けていたのにどうしたものか。
「グランド・フィナーレ」ほか全4編。
装丁:スタジオ・エス・アンド・ディー 装画:さわのりょーた
どこか壊れている。自分のしたことが社会的にどう見られるか
わかっているのに抑えきれないのは自己愛なのか。
いろいろなことを予感させる文章が散りばめられているのに
特筆すべきことは起きないという不完全燃焼感。
Posted by ブクログ
T:私は「オタク」「ひきこもり」「ロリコン」「ストーカー」・・・メディアが取りあげ、時に社会問題として扱われるような特殊とされる人間ではないと思う。しかし阿部和重の作品に登場する一般的に特殊とされる人物には共感させられるところがある。ここに阿部和重の作品の面白さを感じる。
M:まったく知らない作家なので質問。「社会問題」の人物像づくりには特殊化(アブノーマルというラベルを貼ること)によって社会の中に外部を作るからくりが隠されていると私は思うのだが、そこらへんは言及されているのだろうか。
Posted by ブクログ
第132回芥川賞受賞作。表題作のほか「馬小屋の乙女」「新宿 ヨドバシカメラ」「20世紀」の3編を併録。
離婚して職を失い、故郷へ戻って古い木造の一軒家に住み、仕事もせず、妻に引き取られた一人娘の形見の品であるジンジャーマンのぬいぐるみを抱っこしながら、あてもなく町をブラブラしている、37歳のロリータ・コンプレックスの男のお話。もともと東京で教育映画の監督をしていた彼は、地元の小学生の女の子2人に請われて、演劇の指導をすることになりますが・・・・。
この本に収められた小説は、どれも一読しただけでは理解不能なものばかり。けれど、ちょっと硬めの文体と、内容のアンバランスさが面白く、なぜかしら一気読みさせられてしまいます。
Posted by ブクログ
とりあえず文庫版の高橋源ちゃんの解説がすごい、あざやか。評価が割れがちな作品を解説させたら彼の右に出る人はいないんじゃないだろうか。その上で評価がイマイチなのは、これが阿部和重の決定版ではないと思うからである。以下、各編のあらすじ。
「グランド・フィナーレ」は事情により離婚に追い込まれ、愛娘と会うことを禁じられた映像作家が、故郷・神町へ逃げ帰り新しい「希望」を見つけるまで。まわりの人間が感情を爆発させるのに対して、主人公はいちじるしく欲望や感情を欠いているように見える(けど、やってることは異常そのものだ)から、彼の見た希望が本当に希望なのか、答えは宙吊りにされる。
ちなみに物語中、トキセンターに忍び込んで警備員を殺した少年の妹が登場する。
「馬小屋の乙女」では、まぼろしの性玩具を求めて辺鄙な町(神町)へやってきた男が、奇妙な老婆に出逢う。とことんコミカルでそこはかとなく恐い話。
「新宿ヨドバシカメラ」は企業用に書かれた小説。雄弁な男がみずからのセックスを実況中継しながら新宿の地誌をつまびらかにする。バカバカしいくらい陳腐な比喩がむしろ生きてくるのは、やはりこの街だから?
「20世紀」も、やはり地誌。東北地方にある神町を取材する私は町の歴史を調査するうちにだんだんこの土地へ取り込まれていく。ホームビデオ、父と娘など、「グランド・フィナーレ」に連なるテーマがあらわれる。
Posted by ブクログ
芥川賞受賞作である表題作を含む4つの短編集。
表題作は、作中で書かれているある諸事情によって離婚させられ、愛娘の親権も妻に奪われ、娘に会うことすら不可能な「わたし」が故郷へ帰り、双子のような二人の女児に出会う。
すべての話を読んだ限りでは、私のごくごく個人的な感想をいえば、この文章はあまり好きになれない。どちらかというと苦手なタイプである。まるで早口でまくし立てられているような感覚。実際に、登場人物が相手に相槌もなく、早口に言いたいことを言っているだけの描写がある。コミュニケーションとは言いがたいようなコミュニケーションしかとれないのが「わたし」なのかもしれない、なんて思ったりもする。
なんとも、その行動意図が測りかねる「わたし」ではあるが、表題作全体のイメージとしては嫌いではない。ただ、文体が苦手、というだけで…。
Posted by ブクログ
学生に勧められて。
なるほど、なるほど。
しかし、この手の描写を、
笑えばいいのか(いいんだろうけど)、
まじに取ればいいのか、ちょっと分からない。
いくつか読んでみないと分からない、
ってことは何冊か読むことになり、
それはそれで、コンシューマーになるという罠か。
Posted by ブクログ
ロリコンのいろいろ。
都庁の話は意味不明。
ロリコンが異常かどうかはおいといて、異常な性癖や嗜好って多分自分で望んで得たものじゃ無いとおもうんだけど、
おれらが(一般的に誰かが決めた)「普通」のセックスで昇華していることを、「異常」な方法でしか昇華できず、そのために人間扱いまでされなくなってしあわせまで剥脱されてしまう姿に、
全てのことの表裏が紙一重な気がして、ぎりぎりのところでバランスを取っているのかもと感じた。 結構ふかく考えさせられる。 けいた
↑あたまよさそう。 さとこ
Posted by ブクログ
コピーと本の内容が違う、というのはありがちだけど、阿倍和重の本で特に多い気がする。
芥川賞をとったけど「この人ほかにもっと良いの書いてただろ!」という声があちこちからあがったって訳で他の作品の方が良いです。
「話最後まで終わってないじゃんつまんなーい」という初心者?に対して自称上級者(文学なんて学問はない。知識の差。正解がないという意味で)がニヤニヤしながら御高説をたれるのにうってつけですね!
これが良い文学なら永遠に追いつかなくて良いよ。