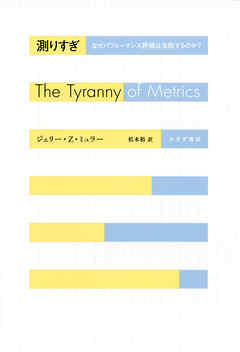感情タグBEST3
Posted by ブクログ
評価のための計測が結果的に教育のレベルを下げてしまったりといった、計測の悪い部分をかなり明瞭に説明した本。成功した医療の分野の話にも触れていてバランスも取れているが、一貫して計測を悪とみなす観点に貫かれている。
Posted by ブクログ
組織の目標設定を継続的に考えるにあたり、参考にするため読みました。「計測できないものは制御できない」という思想に偏りがちだったことを自覚できました。定量目標がダメなわけではなく、測定執着がダメ。測定はその対象に影響を及ぼすし、利害関係が生じると歪む。測定自体のコストがそのメリットを上回る。本当に達成したいことは何か、そのために必要な手段かを絶えず考え続けようと思いました。
Posted by ブクログ
表紙の「業績評価が組織をダメにする根本原因を分析」という文句に惹かれて購入.
データを集め,分析し,カイゼン,というループは今では当たり前の行為なのだが,その行き過ぎに警鐘を鳴らす.
我が大学も,まさにそうで,学部別の就職率の順位をつけて予算配分したりする.ただそのリストをよく見てみると,みんな進学率が95%以上で,学部間に優位な差はない.本書で挙げられる典型的なダメ統計主義(統計執着,というらしい)である.
本書には,測定が有効に機能する例と,その5倍ぐらいの無益,いやむしろ有害な例が挙げられている.
多分に著者の主観(恨みつらみ?)が色濃いのであるが,行き過ぎた統計主義について,事例を豊富に紹介して,その問題点を解説した上で,最終章では「いつどうやって測定基準を用いるべきか −チェックリスト」と結んでいる.経営者や管理職の人は必読.
Posted by ブクログ
エビデンス至上主義、計測指標至上主義の弊害をわかりやすくまとめた論考。簡単に短期で測れるものへの歪みや対象者選別などは目に浮かぶ。ただ、この本を頼みに成果計測を忌避するのも違う。問題は「至上主義」や人事評価やインセンティブとの連動にあるということをきちんと読み取る必要がある。NPOにおいて自組織の達成が何を指すのかや、多くの場合抽象的なビジョンに対して近づいているのかという問いを立て、スタッフや受益者をエンパワメントするために成果の定義や計測に向き合うことはやはり大切だと感じる。外部からの評価支援者は必読。
Posted by ブクログ
なんでもかんでも分析し管理したくなる。完璧を目指すうちに物足りなくなり、少しでも気になったポイントがあれば、あらゆるデータが欲しくなるし、あらゆる側面から管理したくなる。そうしているうちに、データと管理の沼に足を取られ、本質を見失っていく…
データ分析は繊細な作業なので、没頭してしまうと、いつの間にか大局的な視点がすっかり抜け落ちた状態でずんずん歩みを進めていってしまう。
だからこそ、本当に絶対に必要な大事なものは何かを考えることを、意識的に思い出すようにしなければならない。
また、とりわけパフォーマンス評価(管理はセーフだが、管理し始めるとほぼ間違いなく組織はそれを評価に繋げたくなってしまうものだ)の元ネタに自己申告のデータを使うことは鬼門であることも忘れてはならない。
自分を戒めたい。
Posted by ブクログ
成果主義の名の下に成果の測定を求められることが、営利企業はもとより役所や学校・病院など非営利組織でも一般的になっている。しかし、測定するという行為は組織が本来やるべき業務を妨げ、意図せざる副作用をもたらしてしまうことがある。例えば、医師の成績を手術の成功率で測ると、難病の患者は手術してもらえなくなり、警察の成績を凶悪犯罪の発生件数で測ると、強盗事件が単なる盗難事件とカウントされてしまう。
測定結果を絶対視して組織や個々人に対して鞭のように使おうとする事が生み出す様々な歪みや悪影響を筆者はしつこいくらいに列挙しているのだが、測定すること自体は決して悪い事ではないし、測定の効用も筆者は認めている。
では測定結果をどう活用すればいいのか、それを筆者は最終章で提言しているのだが、なるほどと思える穏当かつ妥当なものである。
外部からパラシュートのように降りてきた経営者やコンサルに対して何とも言い難い胡散臭さを感じている人が本書を読めば、首がちぎれそうになるくらい頷きたくなるだろう。
Posted by ブクログ
世界中の経営者、管理者の必読本にすべき名著。「測れるものは改竄できる」といった原理原則が、昨今の不祥事につながっていることをもっと危惧すべきだ。
Posted by ブクログ
本書で取り上げられている国は、米国や英国などの欧米諸国中心ですが、様々な実績評価が企業だけでなく病院や学校、軍隊など幅広い領域に拡大し、それがある種の機能不全や弊害をもたらしている、という指摘になります。なかでも一番わかりやすい指摘は、実績評価(計測)に費やされる時間とコストがばかにならず、肝心の本業に支障が出ているというものでしょう。これなどは目的と手段が転倒している好例です(実績評価自体が目的になってしまっている)。そしてそれよりも深刻な指摘は、実績評価が個々人の評価(報酬、昇進)と紐づけられてしまうと、腐敗や数字操作、また評価指標以外の要素が不当に軽視されてしまうなどの(重大な)副作用を生み出してしまう、というものです。
後者の指摘は日本でも事例に事欠きません。賃金統計の意図的な操作のように現政権に不利になりそうな統計の数値操作、また企業の利益操作などがその例として挙げられますが、実績評価という「それ自体は害のない行為」が人間の評価に紐づけられた瞬間に腐敗していく可能性がある、ということです。その意味では、終章に書かれていた「測定される対象が無生物に近ければ近いほど測定はしやすい。・・・測定対象が人間の行動に関するものであればあるほど、測定の信頼性は低下する」という言葉は意味深でした。ハーバード熱血授業で有名なマイケル・サンデルは、「お金は道徳を腐敗させることがある」と述べていますが、本書の内容を織り込んで言い直すとするならば「人間は金銭評価されると腐敗する可能性がある」ということだと思いました。
Posted by ブクログ
論文形式で、主張が明確。
数値データを絶対視し、それを用いる事で組織に説明責任を果たす事、更に、そこから能力給や評判、ランキングを得る事を信念とする「測定執着」思想の危うさについて、指摘する。
まず、測定行為自体に限界がある。例えば、簡単に測定できるものしか対象としない。また、数字を良くするために簡単な目標のみを設定しがちである。あるいは、目標値を下げようとするインセンティブが働く。実績数値を見栄えを良くしようと操作し、最悪は、達成する目的にとらわれすぎて不正行為に及ぶ。ここで言われるのはあくまで可能性の話だが、しかし、誤ったKPI設定による悲劇は十分起こり得るし、実感がある。医療行為の成功率を設定すれば、「上澄みすくい」で成功率の高い患者のみ手術されるという事例が挙げられる。恐ろしい事だ。
また、測定による弊害が結論として挙げられる。測定可能なものに労力が割かれて目標がずれる事。短期的になる事。効用逓減、規則の滝、右に報酬を与える、リスクを取らなくなる、イノベーションの阻害、協調や目標共有の阻害、仕事の劣化など。よく分かる。例えば、コストダウンの進捗報告の資料印刷の誤字に気付き、何百枚も再印刷するなんていう誤謬、欺瞞も目にする事になる。
KPI管理が流行っている気がする。それさえ見ていれば良いかの誤解がある。勿論、組織には何かしらの羅針盤は必要だが、これらの設定は余程慎重さが必要。個人としても、刷り込まれた偏差値教育や出世信仰、拝金主義、価値倒錯等に気を付けなければならない。価値観が歪み、自ら誤った劣等感を植え付けてしまい、人生が楽しくない。
趣旨明確ゆえに淡白ながら思考させる良書。また、この本で初めてGoogleのngramの存在を知れた事も読書の収穫だった。
Posted by ブクログ
測りすぎの背景にある大きな要因は以下の2つのように思います。
・透明性/客観性の問題
・統制性(コントロールの欲望)の問題
透明性/客観性の問題は本書でも論じられていますが(pp.162-167),コントロールの欲望については十分に論じられていません。
そして,実はこの「コントロールの欲望」こそが,問題の本質だと思います。
なぜなら,透明性/客観性の問題も「コントロールの欲望」に由来するからです。
どうやって統制性の問題(コントロールの欲望)と対峙するのか?
これを考えなければいけないなと思いました。
Posted by ブクログ
事例はそこまでおもしろいと感じませんでしたが、結論としているものには心当たりのある項目が山ほどあり、大いなる共感を覚えています。日本の生産性の低さの一端を説明している感じがしました。
Posted by ブクログ
■測定執着というパワーワード
この本は、世の中のあらゆる組織にはびこる実績評価のための「数値測定」がもたらす弊害について、実例を用いて詳細に分析、解説された本です。
組織を管理する有能マネージャー(自称)は、部下の売り上げ数、部下が出した不具合の数、部下の残業時間、部下の技能熟練度を数値化したスキルマップ、何でもかんでも測定して美しいグラフを作成して仕事をした気になってしまう、これを本書では「測定執着」と呼んでいます。
なぜ、組織に、この「測定執着」から逃れられない有能マネージャー(自称)がこうも多く存在してしまうのか、その理由が実例を交えて解説されています。
■製品の不具合の数をカウントします
「あなたの部署が開発した製品の不具合の数をカウントします、不具合が少ない部署には報酬を、多い部署には罰則を設けます、みんなで不具合を撲滅しましょう」
例えばあなたの職場で、このような崇高な数値目標を掲げられた経験はないでしょうか?
この時、不具合の数を測定する目的は、製品の品質を担保してエンドユーザーを満足させよう、というものであったりします。
では実際のところ、この目標の元に働くあなたの職場では一体何が起こるでしょうか?
不具合の数が増えないよう、不具合は隠され改ざんされ、あるいは不具合が露見しにくいような当たり障りのないテストだけが実施されるでしょう。
そればかりか、不具合が出る可能性が高いチャレンジ志向の開発は避けられ、イノベーションあふれるクリエイティブな製品づくりへのモチベーションをあなたから見事に奪い去ってくれることでしょう。
いつの間にか、品質の担保やエンドユーザーの満足度の向上といった当初の目標はどこかに追いやられ、半期ごとの不具合数が右肩下がりに見えるようなきれいな棒グラフをパワーポイントにおこすことが目標になってしまうことでしょう。よく言う目的と手段の入れ替わりというやつが発生してしまうわけです。
■有能マネージャー(自称)が「数値測定」が好きな理由
筆者は、なぜ現代では、不具合数やセールス数や犯罪検挙数などの測定、いわゆる「数値測定」がここまで人気になったのか、という問いに対し、社会的信頼感の欠如がそうさせている、と答えています。
これはつまり、エリートと呼ばれる管理者の立場の入れ替わりが激しい能力主義の現代において、自分の立場の維持に安心できない有能マネージャー(自称)が、「数字」という万人に公平に見える測定基準を利用して自分の立場の客観性を主張して信頼を勝ち取ろうとする動きであるというものです。
そして筆者は、このような体制になってしまうと管理者は自身の裁量(これは目に見えない)で物事を判断することができなくなってしまう、と書いています。
またこの時、測定に費やされる膨大なリソースは無視されるばかりか、簡単には測定できないけれど組織にとって本当に必要なアウトプットまでもが無視されてしまう、と述べられていました。
■測定値を能力評価に使うことの弊害
本書では、測定値を能力評価に使うことの弊害について、数々の実例とともに紹介されています。
例えば、アメリカで子どもの教育格差をなくす目的で政府主導で行われた教育改革の話。
その改革の一部に「教師の能力評価による適切な報酬配分」というものがあり、それは「教師の能力を正しく数値評価し、いい教師にはいい報酬を出そう」といったものだったそうです。
では、教師の能力をどうやって評価しよう?となったときに、当然校長の裁量で評価するわけにもいかず、客観性を可視化してくれる「数値測定」が必要、となり、結果、その教師が受け持つ生徒の定期テストの点数で評価する、となったそうです。
すると何が起きたか?成績の悪い生徒を「障碍者」クラスに分類するような細工がされ、彼らの回答用紙は集計に加えられなかったそうです。教育格差をなくすという当初の目的は完全に忘れ去られています。
■医療業界での実績測定の成功例
実績測定の欠点だけでなく、本書ではその成功例についても書かれています。
それは、米国のガイシンガー・ヘルス・システムという電子医療記録システムで、患者の既往歴、治療計画、実績などすべてを電子記録し、その記録を患者当人だけでなく医者や看護師や薬剤師が共有することで統合チームによる治療を提供しようとするシステムです。
このシステムにおける実績測定が成功した理由について本書には2つ書かれており、1つは、このシステムの目標を、患者が払う医療費の削減およびシステムが有効活用され場合の診療報酬が医療従事者へ支払われるという、患者と現場の医療従事者双方の実利に設定した点。もう1つは、このシステムにおいて何を測定するべきかという測定基準と、それをどのように測定すべきかという測定方法を、現場を知らない管理者ではなく、現場の医療従事者が直接主導して決定したという点です。
この2つ目は実績測定を成功させるために特に重要で、現場にとって何が有効な測定データであるかを現場の人間が決めることで、実績測定についての現場の同意が得られるし、測定データが現場従事者の提供するサービスの向上に直接貢献できることになります。
要するに、現場従事者が、自身が提供するサービスをより良くしようという自発的な動機で、実績測定を有効活用したから成功した、という訳です。
■自分たちの経験と見事にシンクロする
本書では、先の教育現場で起きた「測定執着」の顛末のほかにも、警察、医療、軍隊、ビジネス、慈善事業など、さまざまなシーンで起こった実例をありありと紹介しており、読んでいくうちにそれらの事例は僕たち読者自身の職場や組織の中で起きていることと見事にシンクロしてみじめな気持ちにさせられます。
しかしそれと同時に、自分たちが日ごろ心に抱えていた「数値測定」に対する違和感を見事に言い当ててくれていてすっきりした気持にもなれますので、ぜひ読んでみてください。
逆に、数値評価を愛してやまない有能マネージャー(自称)にとっては目を背けたくなる本だと思いますので、そういった方は読まないことを推奨します。
■能力給は理にかなっているのか?
最後に、「とは言え利益を得ることが目的であるビジネスの世界では、数値測定による能力給は理にかなっているのではないか?」という問いに対する筆者の考えについて紹介します。
『たしかに、能力給がその約束を果たしてくれる場合はある。こなすべき仕事が反復的で非創造的であり、標準化された商品やサービスの生産または販売に関するものである場合、仕事内容に関して判断を求められる可能性が少ない場合、仕事に内在的満足があまりない場合、実績がチーム全体ではなくほぼ完全に個人の努力に基づいて測定できる場合、他者を手伝ったり励ましたり助言を与えたり指導を行ったりする行為が仕事の中で重要な位置を占めていない場合がそうだ。』
Posted by ブクログ
KPIの設定について議論すると、経営者の経営センスや部門運営者の運営センスが如実に表れるが、本書はその言語化が難しい「センスの善し悪し」を具体的事例を多数研究して「数値目標」という切り口から見事にあぶり出している。
みんな一様に可視化、見える化、KPIと叫ぶが、現場感覚なくダッシュボードを眺めたり、偉そうに論評して、仕事をした気になっている人はいくらでもいる。それだけならまだしも、なんちゃって経営のために膨大な労力と時間を使って可視化に携わる人達がいるのが残念でならない。
そもそも何を可視化するのか、何故可視化するのか、あなたやあなたの組織の目的はなんなのか?
そんな当たり前の話が理解できない人に是非読ませたい一冊。
ただ、原書からそうなのか、文章が回りくどい感じで、読む気が萎える所もあるのは残念としか言いようが無い。
給料によるモチベーション
測定に力を入れすぎる、見かけ上の目標達成を目指してしまうと、本質を見失い、損失がうまれるという内容。
ビジネス以外の事例が豊富。
測定可能な数値による外的動機付け(給料)は、内的動機付け(仕事内容からくるモチベーション)を損なわせる。そして、特に学校、病院といった非営利組織において、組織としての目標を達成する上で、給料によるモチベーションアップは逆効果であるといった内容が印象に残った。
Posted by ブクログ
証拠ベースの政策決定。アカウンタビリティ(説明責任)。PDCAサイクル。それらのためにはまずは測定することが第一歩。ということで何でもかんでもまずは数値化という昨今。本書は、測る仕事ばかりが無意味に増えて頭にきた大学教授が専門外の文献を読んでまとめた論文の形になっている。測ること自体が問題だと批判しているわけではない。測ることが万能だと思うのが間違いである。数値化して可視化すれば何でも上手く行くわけではないのだ。測ろうとしている対象、例えば、学校の教師の能力だとか、会社組織のパフォーマンスなどのうち、実際に数値化できることはそのほんの一部分限られているし、測るのは数値化しやすい部分に限られるということ。測りやすいものだけ測って全てのように評価すると、測れない重要な事項が無視されることになる。欠点を認識せずに導入することは問題だし、測定に執着するのが間違いの元凶。測りすぎることのコスパも考えるべきだ。それらのことがもうずいぶん前から研究者によって明らかにされていることを、本書は教えてくれる。
本書は言うなれば、”測りすぎ”の失敗学とも言えるだろう。こうすれば失敗するという分かり易い実例がたくさん紹介されているので、「さぁ測ろう!」という組織のトップには、本書を読んで過去の失敗例を学んでから測りはじめて欲しい。しかし、本書で紹介される失敗例をなぞるような「改革」が自分の所属する組織で進行していくのを知ると残念な限りかもしれない。
本当に有意義で機能する「測定」システムは現場を担当する内部から改善運動のための起こる測定であって、測定される対象の人々が測定の価値を信じている場合のみだということを忘れてはいけない。最も失敗するのは、上からの「測定」を「報酬」と連動させる場合のようだ。特に、公的な仕事。公務員、警察、教師、医師、大学教授など、人々への貢献による精神的な内的報酬を重要視する分野では、数値化しやすい項目による実績評価を使った成果と給与とを結びつけることは、逆効果になることと結論付けられているらしい。うーん。
Posted by ブクログ
測定が生み出す様々な弊害がまとめられた本。仕事などで定量的評価をする際の害がわかって良い反面、どうすれば良いかという対策に関して考えるには不十分な内容。さりとて定量的評価を今更捨てられはしないし…みたいな。
Posted by ブクログ
データをもとに国の政策や企業経営、従業員の報酬体系がが決められていくというのは、当然のことだし、科学的で良いことと思われている。しかし筆者は、測定に執着しすぎることには多くの悪い側面があるという。本書では、「測りすぎた結果かえって悪くなった」例がいくつか紹介されているが、ここではアメリカの学校の事例を取りあげたい。
2001年にアメリカで、通称「落ちこぼれ防止法」が施行された。これは、成績に関して民族間の根強い格差が存在していたため、その解消を狙って作られた法律だ。
この法律ものとで、毎年3年生〜8年生に算数、読解、科学のテストが受けさせられた。テストの結果、特定の生徒のグループの進歩が見られない場合、学校には罰則が与えられる。これにより成績の悪い学校や教師は頑張るはずだから、成績は改善されるはず。
しかし、10年以上経ったいま、成績の改善効果は証明されなかった。
何が起こったのか?まず、教師は、テストの対象の科目しか教えなくなった。つまり、歴史や音楽、体育といった科目がおざなりにされたのだ。また、テスト対象の教科でも、幅広い認知力の育成よりも、テスト対策が重要視された。そして、学力の低い生徒を「障害者」として対象から除外して平均点を上げようとしたり、さらには、教師が生徒の回答に手を加えたり、点数の悪そうな生徒の答案用紙を捨ててしまうといったあからさまな不正も行われた。
測定は役に立つ。テストをすれば、教師は生徒のつまづきポイントが分かるので次の指導にフィードバックできる。でも役に立つのは、測定が「重要性を持たない」ときだ。測定結果が重要になると測定自体が捻じ曲げられてしまう。
アメリカ人社会心理学者の名前をとったキャンベルの法則というものがある。「定量的な社会指標が社会的意思決定に使われれば使われるほど、汚職の圧力にさらされやすくなり、本来監視するはずの社会プロセスをねじまげ、腐敗させやすくなる」
この本ではほかにも医療現場や軍、ビジネスにおける測りすぎの事例が紹介されている。測定基準を使用する場合に気をつけるべき点をまとめたチェックリストも載っており、読者が職場などで測定を利用するときにも参考になるはずだ。
Posted by ブクログ
良かった。簡潔に様々な事例が散りばめられていて、読みやすくわかりやすい。そして嬉しくないことだが、非常に共感することが多い。測ることの信頼性、妥当性、測ったものの使われ方について、もっと我々は体系立てて理解し、常識として共有しないといけない。官僚主義が進むことによる疎外の問題、と考えれば社会学者や社会心理学者は無視できない問題がたくさん含まれている…
Posted by ブクログ
徹底して可視化や透明性など、昨今の大学に求められる測定主義の落とし穴について批判的に論じている。本書を書くきっかけも、著者が大学の執行部にいる時にアクレディテーションに疑義を感じたことであるとのこと。色々考えさせられた。
Posted by ブクログ
パフォーマンス評価の「あるある」集といったところで、読んで納得というか溜飲が下がる思いをする人は少なくないだろう。ただ著者も認めるように測定自体は有益というか多くの場合は必要不可欠ですらあり、ほとんどのケースは程度問題ということになって白黒割り切れるものではない。
本書では測定基準の副作用について数多くの例が挙げられているが、そのほとんどは測定基準をもとにしてインセンティブを与えたがために、対象となる人々の行動・動機や測定そのものを歪めてしまった例である。そういった意味でアメリカ的。
あと透明性が政治や外交交渉にとって妨げになるよね、なんてことも書いてあるが、近年の米国政治の二極分化なんかも行き過ぎた透明性のせいなのだろうかと考えてみたり。
Posted by ブクログ
学校、医療、ビジネスと様々なシーンでの具体例が載っておりとても面白い。
学校の予算を成績の上がり具合で決めたら、よりお金を投入すべき下位のグループが点数上がらないのに予算減らされて悪循環を生むとか、医師の評価を手術成功率にしたら難しい手術をみんなやらなくなったとか
うーん適切な設定をするのは難しい。
Posted by ブクログ
測定には良いところもあるが、負の側面もある。この負の側面を無視して数値指標を作り続けるような状態を「測定執着」と読んでいる。
様々な分野において、測定が成功した例と「測定執着」と思われる上手くいっていない実例を示した本。
数値化して管理する事により、数値化されなかったものが放っておかれる、数値をあげるために本末転倒な行動が起きてしまう、かけたコストに対して効果がない、などの例が満載。
結論のパートでは、測定すべきか否か、測定した項目をどう使うべきか自問するためのチェックリストを提案している。
数値目標の設定と達成を、仕事の「目的」ではなく「手段」として行いたい方々にお勧め。