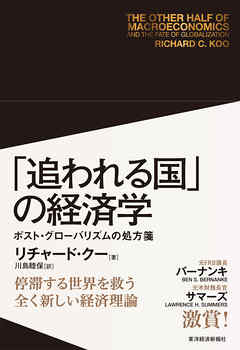感情タグBEST3
Posted by ブクログ
個人的に全面賛成というわけではありませんが、積極的財政政策の中にはちょっと無理がありすぎる主張の人も多い中で、バランスシート不況論は説得力があると思いました。
600ページを超える大作ではありますが、丁寧にわかりやすく解説していてオススメしたい本です。
公共事業に関しては日本やアメリカでインフラの老朽化が問題になりつつあるので、それなりに有効ではないかと思います。近年の自然災害の多さを考えると整備は必要でしょう。
とはいえ旧来の公共事業的なものが今後有効なのかという視点も持つ必要があるかなと。
投資と国の金融政策は切っても切れない関係ですので、マクロ経済とかの面も含めて知識を高めてくれる良書だと思います。
Posted by ブクログ
経済を専門としてるわけではないので、難しいところもありましたが、被追国の問題点や対処方法がロジカルに説明されてとても面白く読めました。
政治家の方には、桜問題などやっていないで、しっかり読んでもらいたいと思います。
しかし、本書で述べられているケース3・4のフェーズから、1・2に戻るのは、いろんな意味でかなりパワーが必要となりそうです。
Posted by ブクログ
伝統的なマクロ経済学の基礎から始まり、それを含んだ形で著者の理論を展開しているため非常にわかりやすい。
この理論を用いると現在の国際経済を簡潔に説明することができる。著者はその上で、日米欧の不況の解決策とその効果を実施例と共に提示している。
FRBはこの理論のもとで経済政策を行なっているようで、現にアメリカの経済は日欧よりも順調である。
この点で根拠も十分であり、少なくとも現状成果を上げていない伝統的な経済理論と比べれば信頼に足ると思われる。
おそらく現在最も有力な経済理論をわかりやすく解説している。とても良い本。
Posted by ブクログ
600ページ超の大著だけど、それを感じさせない読みやすさだった。一読を進めたい良書。
【以下ネタバレあり】
民間部門が利潤最大化を目指していることを前提とした今の経済分析・政策論議は誤りであり、人々が債務最小化を行なっている現状を踏まえた議論が必要だ。
本書の主張を一言に要約すると、以上のようになる。
2008年の世界金融危機(GFC)や、日本におけるバブル崩壊よりも前の経済は、資金の借り手が豊富で、物価面ではインフレ体質だったので、金融政策が有効だった。
しかし、GFC・バブル崩壊以後はバランスシート不況になっており、政府が「最後の借り手」として減少した民間部門の資金需要を補わなければならない。
また、先進国では、自国よりも新興国の資本収益率が高い状態となっているため、企業は国内ではなく海外での投資を小なうようになっていることも、国内での資金需要減少に拍車をかけている。
「追われる国」が直面する、バランスシート不況と資本収益率の低迷という問題に対しては、財政政策で前者に対処しながら、構造改革で後者を解決するのが望ましい政策だ。しかし、日欧では財政健全化のプレッシャーが財政政策を困難位にしている。
本書のこうした主張は、既存の経済学や、今の政策のあり方に疑問を投げかけるもので、説得力も感じられ、とても興味深かった。こうした挑戦的な主張をするには、勇気もいることだろう。
本当に財政政策を拡大させて良いものなのか、素人の僕にはよくわからないけど、それを脇においても、良い本だった。
少し気になるのは、なんとなく主張が強引に感じられる箇所もあることと、同じような内容が何度も何度も繰り返されること。
後者については、重複を排除すれば50Pくらいはページ数が減るかもしれないと思う一方で、これだけ丁寧に主張を繰り返してくれるので、筆者の主張したいことがわかりやすいので、むしろ良い方向に作用していると思う。
Posted by ブクログ
リチャード・クー氏の書籍は通読しているが、本書は、これまでの主張に加え、バランスシートがキレイになった後の状況についての解説が新たに加わったこと、更にその処方箋、そして貿易不均衡に関する資本移動の制約提言が加味された。バブル崩壊以降、各エコノミストの主張(構造改革派、リフレ論者など)を追っかけてきたが、結局クー氏の主張が一番正しかったと証明された。
Posted by ブクログ
マクロ経済学の現実への適用について理解できました。様々な識者の意見の正確性について評価できるようになったように思います。それが正しいかについては、生涯をかけて検証してまいります。
Posted by ブクログ
自分がどういう派閥・視点からマクロ経済を眺めるか、そういう骨格をつくるのによい。分厚いがサクサク読める。同じことをしつこく書いてるのでサクサク読める。じっくり読み込まねば理解不能というような本ではないので分厚さにビビる必要はない。
著者の主張 なんとなくまとめ
------------------金融政策は効かない------------------
・高度成長が終わった成熟国家では金融政策(低金利)が機能しない。
・量的緩和をしても民間貸出は増えない。なぜかって民間に借入ニーズがないから。
・民間にニーズがないので低金利も量的緩和も効果がない。
・おカネが動かない状態を解消するには政府が使うしかない。政府が公共事業をして民間におカネを回し続ければいい。低金利で国債でカネを集めれる。その低金利を上回る社会的利益があるプロジェクトを第三者委員会みたいので発掘してやればいい。
・米国は金融正常化に動き出している。FRBは急激で制御不能なインフレを恐れている。利下げという政策手段を確保するために利上げをしていってる。
・日欧が正常化するのは大変。まだ動いてない。やるなら10年レベルの時間がかかる。金融緩和をやっても効果はないうえに、出口戦略が大変すぎる。
------------------主流経済学は間違ってる------------------
・旧来の経済学では金融緩和が効かない理由を説明できてない。間違ってる。マネタリズムの考えは高度成長の国には適応できる。国の発展段階によっては効かなくなる。グローバル経済という前提も旧来の経済学は取り入れていない。
・効果のない経済理論が現実の政策に大きな影響を及ぼしてきた。
・為替市場は貿易収支を考慮にいれていない。金利の高い低いで動く。間違ってるのだが、みんながそう思えばそう動くので。
------------------アメリカの姿勢の変化------------------
・アメリカは寛容に市場を開放してきた。その路線に変化。日本など各国が莫大な恩恵をうけてきた。中国は自国を関税で守りつつ米国で大儲け。米国は正常な関係を求め始めてる。
・トランプ以前の米国は貿易赤字を気にしなかった。気にしないでいいという理屈が影響力を持っていた。トランプはそれに賛同してない。
------------------国境はあるのに資本移動は自由。その歪------------------
・ユーロ圏では各国の金融政策に縛り。ドイツには輸出しまくって貿易黒字になると自国通貨高になる法則が発動しない。?。スペインなどは苦しくても勝手に利下げできないし、スペイン国内に投資してほしいとしても、ユーロ圏内でもっと収益の望める場所におカネが移動していく。
・ユーロの取り決め(マーストリヒト条約)で財政赤字のラインが設定されてる(GDPの3%かなんかだっけ)ので、ユーロ圏の国は自分で財政出動をしたくてもできない。
・国際金融資本は投資効率を高めようとするので、世界の中で国境をまたいで投資効率のいい案件、国へ資金が移動していく。
・政治や経済には国境があるのに、資本移動に国境はない。金融グローバル化によって各国の金融政策は効力が大幅低下。国内投資を冷やすための金利引き上げが海外から投資資金を引き寄せてしまう、など。
Posted by ブクログ
MMT現代貨幣理論入門を読んでいたので、本書はとても興味深い内容が盛りだくさんでした。、
どこかのお偉いさんが構築した学派・技術というのが、必ずしも世の真理ではなりということ。
特に経済学のように「人間の心理行動に影響を受ける」若い学派は、完全に信じきってはいけない。常に新しい学びと改善が必要だということが判った。
例えば経済学の基本として、民間企業は利益の最大化を目指して行動する。
だから金融正確で金利を下げれば、民間は資金調達(債務)して利益の最大化を測るという考えが根底にあります。しかし、先進国のほとんどがゼロ金利&量的緩和を行っても、資金調達は増えなかった。
なぜなら既存の経済学の対応方法は資本収益の向上とバランスシート不況を区別されておらず、金融政策は後者には効かないというのが著者の主張である。
日本や欧州はバランスシート不況なので、金融政策では財政政策が必要とされています。
つまり借金に苦しんだ民間は、どれだけ低金利で金を貸してくれるといっても借りようとしないということ。
米国が過去20年に大きな経済成長を成し遂げたのも、民間努力以上に適切な国家政策が功を成したと考えるのが正しく、その国家の舵取りがいつまでも続くかは不明っぽいですね。
追われる側となった立場の国がとるべく政策に関しては、著者の問題提起・分析は腑に落ちるものの、対応案がはたして正しいのかは判らなかった。
しかし既存の経済学では説明できない資本自由化の流れから発生した保護主義誕生の仕組みも、幅広く網羅された一冊でした。
かなり殴り書きのレビューになってしまった(笑)