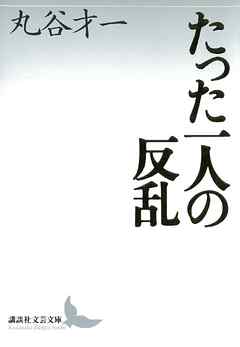感情タグBEST3
Posted by ブクログ
面白かった。繰り返し読みたいけど値段にびっくり。
昭和47年刊行、谷崎潤一郎賞受賞作。
昔の小説だし、いつ主人公が不幸に陥るかと恐れつつ読み進めたが
最初から最後まで朗らかで何度も吹き出してしまうユーモラスな小説だった。
構成も物凄く凝っていて、語れる人はどこまでも語れてしまうだろう。
ラストもあっけらかんとしていてすごく好き。
巻末の解説も面白かったが、他の人の書評も読んでみたいと思った。
Posted by ブクログ
一見600p超の大作だが内容自体はライト。
掛け合いもユーモアの中に知性があり感心しながら読み進めてしまった。
途中数十pも続く、作者の思想代弁とも言えるスピーチシーンが個人的に面白く良い装置だと思った。
Posted by ブクログ
題名の『たった一人の反乱』は絶妙。誰かの個人的な決意とそれと独立した誰かの決意が相乗的に重なり、ユーモラスながら何処か悲哀に満ちた物語を紡ぎ出す。この「反乱」とは自我の芽生え、悪く言えば自分勝手な主張といえよう。
作品自体は中盤まで非常に退屈。しかしながら半分か三分の二を超えたあたり、ツルのある決意から物語は面白くなってくる。本作品を読むと赤塚不二夫氏の漫画を思い出す。学生運動や授賞式のくだりなんか、もうわけがわからない。散漫にして奔放。なぜこういうプロットになるのか。理解に苦しみながら、またそれが面白い。丸谷氏の魅力はこのナンセンスさにあるのかもしれない。
Posted by ブクログ
反乱。それは秩序への反逆。あるいは自由への疾走。あるいは理由なき破壊衝動。あるいは……滑稽な喜劇。
登場人物の一人ひとりが引き起こす滑稽な反乱はカーニバル的であるが、その中から期せずして市民社会の中に潜む欺瞞が一つひとつ暴かれていく。しかし、市民社会が欺瞞に満ちていることを認めた上で、それに代わる新しい社会は構想しえないのだから、この市民社会を大切にしていこうとする主人公のセリフは、時代背景(本書刊行は1972年)を考えると、著者の当時の学生運動に対して向けられた言葉でもあるのだろうと思う。
だが、当初は人一倍体裁や世間体を気にして臭いものに蓋を閉め続けていた主人公が、終いには囚人を利用するというあけすけな行動に出ることができたのは、「欺瞞を利用する」という狡知を身につけたお陰ではなかったか。反乱を経て、反乱のおかげで、既成の秩序が強化される。この主人公の内面における秩序の強化は、そのまま市民社会の秩序が新しく生まれ変わったことをも予感させる。
Posted by ブクログ
昭和47年発行の書籍ですが、今読むと当時にしては随分挑戦的な内容だと感じました。話はとてもおもしろい。
モデルとの再婚、犯罪者の祖母、教授の地位を捨てた父など。
話は別として、当時の女性の話し言葉が美しい。また文体としていまでは使用しない言葉が多く出てくる。
改めて日本語を勉強する必要があると思った。
Posted by ブクログ
馬淵英介(主人公)のスノッブな思考に珍しいもの見たさの覗き見趣味を刺激される。日本型学歴階級社会エリートの、うちに秘める異常な優越感と貴種意識に違和感と嫌悪を感じながらも、引き込まれる自分自身の俗物性を痛感しながら、むず痒く複雑な感覚で読めた。
ストーリーがユニークで内省語りの多い軽やかなハイテンポの読み物である。「たった一人の反乱」という題名への疑問はいろいろ考えさせられながらも、解決することなくそのまま最後まで続く。
Posted by ブクログ
丸谷才一というと、旧仮名遣い、ジョイス、博識というイメージ。
エッセイは読んだことがあっただけ。
本作は、まず思ったのは、芝居にしたら面白そう、ということ。
みなキャラが立っているからか。
ただ、どの登場人物も表と裏を持つものばかり。
時々立ち止まって、自分の来し方行く末を思う。
そして、唐突に動き出す。
そこには理由・背景はいらないのだ。
とはいえ、600ページは長いな。。
Posted by ブクログ
日本では人の良い小説はいけない,たちの悪い,冷ややかなものの見方や人生への態度が文学者の理想とされる,長編小説というものは成熟した知的な中流階層があって成立する,という朝日新聞の記事を読んでなかったら間違いなく切れてた。読んでる最中は一冊でいいやと思ってたけど,読み終わるとこういうのもありかなと思う,不思議な本。