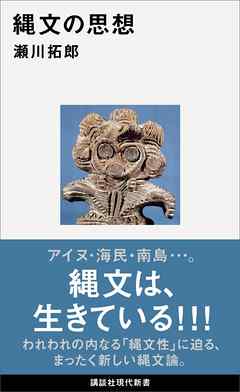感情タグBEST3
縄文びとが残したもの
過去の民俗学や文化人類学の遺産である民話や伝承と、最新の考古学が合わさって、雄大な物語を読むように感じました。日本人の起源がアイヌと不可分であること。海民の旅のスケールが昔から非常に大きかったことなど有史以前の世界が目の前に蘇るようです。
Posted by ブクログ
貧富の差のない縄文時代に、農業がもたらされて弥生時代が始まった。こんな直線的な理解を打ち砕く名著。
南方から渡来した原日本列島人=縄文人のもとに農業がもたらされる。縄文人は農業を部分的に受け入れ、渡来人と混血しつつも沿岸部を拠点とする「海民」として幅広い交易で繁栄する。縄文と弥生は長く併存するのだ。
沖縄とアイヌの共通の文化的属性、DNAの解析、山陰と東北の言語的共通性などから「日本人の源流」が浮かび上がる(ここで、奥出雲弁と東北弁が非常に似ている、ということが推理のカギとなる松本清張「砂の器」を思い出す人はするどい)。
日本各地の神話で、海にある洞窟はなぜ山の頂上につながっているのか。そして美しい姫が黄泉の国で醜い姿になっているのはなぜか。著者はこうした点を丹念に分析し、海の民が農耕系王朝に駆逐されていく過程を描いていく。
本来の(美しく多様な)日本像を実感できる本。
Posted by ブクログ
アイヌ学からの流れで。
縄文の沈黙貿易や解体場所の隔離が国家と階級の回避への必死の試み、という感覚はとても納得しやすかった。男女間の役割分担にその平等性への志向はあったのだろうか。
Posted by ブクログ
この本では、あわゆる縄文時代に日本列島のほぼ全域に住んでいた人びとを縄文人と呼んでいますが、その縄文人の核ゲノムの解読によれば、かれらはアフリカ、ヨーロッパ、東ユーラシア(中国、日本、ベトナムなど)の人びとのいずれにも属さない、孤立的な遺伝子的特徴がある、現生人類のなかでも古層の集団なのだそうです。なんと!
そして現代の「本土人(本州の人)」の中にはその縄文人のDNA的特徴が10数パーセントも残っているそうです(アイヌや南島の人びとはもっと)。なんだか、とてもうれしい!
Posted by ブクログ
考古学者が、縄文人の生き方を律した思想、あるいはかれらの他界観や世界観といった、生々しい観念の世界に新たな発想・アプローチの仕方で、われわれ日本人の鬱なる「縄文性」に迫った著作です。
その方法ですが、芸術的な感性などではなく、考古学と神話から具体的な資料にもとづいて縄文の思想を明らかにしたのです。
内容
はじめに
生き残る縄文/なぜ共通する神話/伝説があるのか
周縁・まれびと・修験者/アクチュアルな生の思想
なぜいま縄文なのか
序章 縄文はなぜ・どのように生き残ったのか
第1章 海民と縄文――弥生化のなかの縄文
1 残存する縄文伝統
2 海民の誕生
第2章 海民とアイヌ――日本列島の縄文ネットワーク
1 海民のインパクト
2 交差する北の海民・南の海民
3 離島の墓に眠るのはだれか
4 謎の洞窟壁画
第3章 神話と伝説――残存する縄文の世界観
1 共通するモティーフ
2 他界の伝説
3 縄文神話とその変容
4 伝播した海民伝説――アイヌの日光感精・
卵生神話
第4章 縄文の思想――農耕民化・商品経済・
国家のなかの縄文
1 呪能と芸能
2 贈与と閉じた系
3 平等と暴力
4 動的な生へ
おわりに
ですが、日本の歴史、弥生〜商品流通経済・現代なのですが、縄文人が培ってきた日本人の原点は現代の日本社会に必ずや残されているはずだという私の思いにこたえてくれる素晴らしい本でした(感謝)。
Posted by ブクログ
縄文時代から現代に至るアイヌと日本の海民との神話的連続性を、微に入り細に入り読み解いた労作。
私も大学の卒論で同じテーマを考えたことがありましたが、伝承が共通していることを同起源の証拠とするわけにはいかない難しさがあるだけに、慎重に冒険する立場が必要ですし、これはその基準をクリアしていると思います。
Posted by ブクログ
縄文文化、アイヌ文化、南島(鹿児島など)海民文化に、共通性が見られる、というところから、そこに残っているのは縄文の思想ではないか、という視点から書かれた本。
(縄文文化に文字はないので文献等から知ることはできない)
根底には、農耕(日本の弥生時代)を起源とする資本主義社会の生きづらさへに対するヒントとを縄文思想に求めようという著者の意図が伺える。
弥生の農耕文化が朝鮮半島を経由して日本に広がったことはほとんど間違いない。
このとき、縄文人は弥生人に駆逐されたのかというと、遺伝子が大陸の人々と十数%異なることから、縄文人は弥生人と同化もしたであろうことが書かれている(逆に言えば現代人の80%以上は中国や朝鮮半島と共通していることになる)。
著者が縄文の思想を残しているとしているのは、アイヌと海民だ。
イレズミや抜歯といった文化が共通しているという。
また、縄文の思想はそれらの地域の口伝の神話と、『古事記』『風土記』などの文献との共通性からも見出だせるという。
それは海の神と山の神がいて、海の神が山に向かうという共通性に見られる。
もう1つはそれらの神話における(農耕の場である)平野の不在にある。
あるいは女性が太陽光により赤い卵を授かり、そこから神的な人物が生まれる神話は朝鮮とすら共通しているという。
この仮説通りであれば『古事記』などの神話の源流は縄文文化にあることになる。
この本を読むと、確かに立地的に離れた地域で神話や文化の共通性が見られ、それが縄文の思想であると考えることもできる。
一方で「共通性のみに言及」しているため、各地域の差異が分からない問題もある。
アイヌや海民のような狩猟採集文化は平等な社会、農耕文化は支配・被支配的な社会になりやすいことはすでに知られている。
狩猟採集は食物を蓄えられず小規模で、また獲得できるかは運次第にであるから、コミュニティ内で平等な分配が行われる。
ただし、本書で贈与と呼ばれている行為は物々交換に近い。
そのためマルセル・モースの『贈与論』的なものとは異なるが、「神により命を授かった」ということ自体が贈与を受けたことを意味し、その「負い目」がアイヌや海民に贈与文化を生んでいるというモース的な記述もされている。
一方、農耕は食料の生産性の高さと定住から、人口が増える。
(採集民族は多数の乳幼児を抱えて移動することは困難なので人口は一定以上増やせない)
また食料の余剰が生まれ備蓄が可能なことから、管理者=生産に直接関わらない権力者や官僚が生まれる。
(彼らは生産しなくても税金、昔で言えば年貢などで暮らすことが可能だ)
アイヌや海民のような狩猟採集集団が、農耕の導入を拒否した理由は本書では明らかにされていないが、本州では同じ村に住んでいてさえ、農耕民と漁業民(海民)の交流はほとんどなかったとされる。
そのため近現代でさえ、地域によっては縄文文化の痕跡と思われる信仰などが残っているという。
なお、海民は時代によっては海賊(倭寇など)でもあった。
Posted by ブクログ
自然との共存とは、低開発ではなく、
自然と結び付いていた世界観、他界観が現実の世界そのものであり、
自然自体が人々の生と死を結び付けるものであった。
海民とアイヌは自らの社会に不可欠な自由と自治のために縄文の思想を選んだ。
平等と分配
神からの贈与は魂でもあり、商品化して売り払ったり独り占めすることはしない。
商品経済は人間性を否定している?
ブログには、もう少し詳しく書いてあるので、よかったら見てください☆