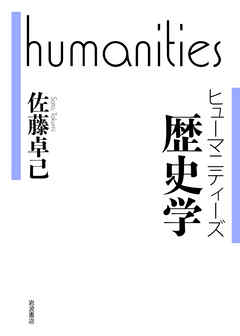感情タグBEST3
Posted by ブクログ
メディア史の泰斗、佐藤氏が自身がいかにして歴史家になったかを振り返っている。
教訓的なジャーナリズム史から実証的なマスコミュニケーション史、そして批判的歴史学のメディア史へ。未来への問いを含むメディア史は歴史学のフロンティアであり、そこに可能性を感じるとも。
氏の研究遍歴が豊富なエピソードとともに語られている。大学でのゼミナールの大切さ、師を見つけること、そしてその読書量に追いつこうと努力すること。氏の基本姿勢が語られている。
事実誤認を発見してくれた古川隆久氏や優れた自分史を書いた原武史氏への言及もあり、個人的に興味深い。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
情報化、グローバル化が加速するメディア社会。
公議輿論の足場として、歴史的教養の重要性はますます高まっている。
しかし、こうした現実の課題に対して、「大きな物語」が失われたあと、これまでの歴史学は充分に応えてきただろうか。
公共性の歴史学という視点から、理性的な討議を可能にする枠組みとして二一世紀歴史学を展望する。
[ 目次 ]
1 歴史学ゼミナールの誕生―歴史学はどのように生れたのか(教訓的歴史から歴史研究へ;大学の歴史学 ほか)
2 接眼レンズを替えて見る―歴史学を学ぶ意味とは何か(社会史が輝いていた頃;世界システムとメディア史 ほか)
3 歴史学の公共性―歴史学は社会の役に立つのか(趣味の歴史と大衆の趣味;国民大衆雑誌の公共性 ほか)
4 メディア史が抱え込む未来―歴史学の未来はどうなるのか(メディア史の発展段階論;進歩史観と情報様式 ほか)
5 歴史学を学ぶために何を読むべきか(「読む歴史」のために;「書く歴史」のために)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
著者自身認める通りタイトル詐欺感はぬぐいきれないが、歴史学をきっかけにしながらメディア史研究にのめりこんでいく様子を、著者自身が自著を紹介しながら語っていくスタイルの本で、個人的にとても良い読後感が得られた。(著者の本をよんだことがあり割と好きだというのもあるが・・・)。タイトル詐欺なので星4つです。
歴史学は「ここまでわかった」「これより先は分からない」と明言することが大事。ということから、歴史学の史料批判を情報リテラシーにつなげていく。歴史学に向かうものにひちようなのは不全感に堪えながら一歩づつ進もうという姿勢である。ランケ「それが本来如何にあったか」を追求する。そのなかでゼミナールという形式が大学で誕生し、それこそが歴史学のすすみかたである。フンボルトに継承される。言語論的転回をうけて、史料実証主義への批判は高まったが、結果としてテクストの揺らぎを自覚したうえでの史料実証主義がやはり大事だと議論される。p16あたり。この辺の議論は重要であるが説明がわかりづらい感がある。
ブントをうけて「それは本来どのように成ったか」いいかえれば「それは本来どのように作用したか」を念頭に置いているという。
Posted by ブクログ
現・京都大学大学院教育学研究科准教授(メディア史)の佐藤卓己による自らの研究遍歴紹介
【構成】
1.歴史学ゼミナールの誕生 -歴史学はどのように生まれたのか
2.接岸レンズを替えて見る -歴史学を学ぶ意味とは何か
3.歴史学の公共性 -歴史学は社会の役に立つのか
4.メディア史が抱え込む未来 -歴史学の未来はどうなるのか
5.歴史学を学ぶために何を読むべきか
『現代メディア史』『言論統制』『8月15日の神話』『輿論と世論』などのメディア史研究で知られる佐藤卓己が大学の学部時代から現在に至るまでの自らの研究遍歴を通して、歴史学のあり方を論じようとするものである。
著者は京都大学文学部西洋史学研究室において、ランケ以来の実証主義歴史学の伝統であるゼミナール形式で「批判」「精密性」「透徹性」を確保するための方法論を学び、1910年代のドイツ社会民主党の宣伝活動を中心とした修士論文を書く際に、ハバーマスの影響を受けてメディア史へ関心を移していった。
その際、大衆の『国民化』や大衆公共性、社会主義を手本としたナチの「宣伝」といったキーワードを用いながら、ナチス時代を連続する現代ドイツ史の中に位置づけようとした。
著者は、「高度情報化社会」「メディア社会」と表現される現代の歴史はメディア史であると見なし、メディアによる宣伝効果、情報の受け手である大衆の反応などを明らかにすることが、既存の歴史学の枠組みをメタ化することになり、歴史研究者自身の位置拘束性(ポジショナリティ)を批判的に検証することも可能となったという。
個人的にはメディア史=現代史だとは全く思わないし、論文も含め佐藤氏の著作はいくつか読んだことがあるが、氏の研究手法が既存のものと大きく異なると感じたことはない(内容は大変面白いとは思うが)。「歴史学」のガイドブックとしては、内容に偏りがありすぎるように思う。