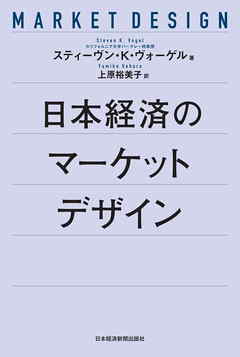感情タグBEST3
Posted by ブクログ
書きたい事、主張が明確な本なので、硬い文章の様な気もするが、分かりやすい。
要は「規制緩和と言っても、それで自由競争になるわけではないよね」、「政治が市場介入する事をゼロ百で善悪を論じることは間違いだ」という話。
規制緩和について。現実には競争を拡大するためには規制を減らすのではなく、規制を増やさればならないことが多い。例えば電力などの公益事業のように、自然独占的な性質を持つセクターに政府が競争を導入する場合は、競争促進する規制を適用すればならない。金融市場においても取引ルールを精密化し、徹底した監督を行うなど、規制を強化することによって市場を支えなければならない。製造や運輸に関わる市場においても、環境、健康、安全に関わる規制を強化しなければならない。
市場原理に任せておけば、やがて一強の一人勝ちになって、競争が起こらない、という事である。独占して大量に安く作れたりノウハウや設備、技術者を囲い込んだりすることで、他社が参入できなくなるという事は往々にしてある。
- 政府と市場を2項対立とみなす前提は、両者の関係性に対する高度な理解を妨げる。政府と市場の関係は対立ではなく補完的なものだ。独占禁止に関する政策を自由放任主義的アプローチから、より競争促進的アプローチにシフトするとしたら、どちらのソリューションが良いと言えるのか。同様に、著作権を伴う資料の構成利用についてもどうか。
- 市場制度主義と市場自由主義では、学問的分析や政策的な処方箋についての見解が大きく異なる
もちろん規制緩和により競争を増やすと言う文字通りの規制緩和が成り立つ場合もある。政府による規制と民間セクターによる調整は、市場阻害するのではなく、むしろ市場の創出、拡大、ダイナミズムを支える必須条件となっている。では、どのようにデザインしていけばいいのか。企業など市場参加者を定義する制度、財やサービスを成り立たせる知的財産権のような制度、市場に株式取引等の特別な領域を確立させる制度、交換のルールを定める取引慣行のような制度、独占禁止法のような競争を促進する制度。
健全な競争が起こり、切磋琢磨していくには、それなりの制度設計が必要で、制度設計には、市場に任せる部分と政治が介入する部分があるという話だ。この分かりやすい話を歪ませているのが、いずれかの既得権益なのだろう。
Posted by ブクログ
日本の政治経済や経済政策の専門家としてUCバークレー教授を務める著者が、マーケットデザインに関する種々の誤解を解きながら、日本経済が復調するために取り入れるべき政策的含意をまとめた論考集。
マーケットデザインとは近年になり着目を集めている経済学の一種である。従来の経済学が市場というものを比較的スタティックなものとして捉えるのに対して、マーケットデザインでは、市場そのものを種々の政策によって操作することで、経済的ベネフィットを獲得することを目指す。周波数オークションのような政策はその一種であるし、様々な分野でマーケットデザインの注目は集まっている。
さて、マーケットデザインが対象とする市場を考えるときに、その対概念として我々は国家の存在を想起する。そして、あたかもア・プリオリに、”自由市場”なるものを想起する。著者によればこの全てが間違っている。なぜなら、完全に自由なる市場というものは存在せず、その市場が成立しているのは、明らかに何らかの規制・政策によるものだからだ。本書では、一見日本に比べて自由市場だと思われているアメリカの金融市場が、実は規制により制御されたものであるという事実などを示す。そうしたエビデンスを経て、我々は日本の経済成長のためには、自由市場を求めて規制緩和するよりも、むしろ適切な規制により自由な市場を創出すべきだという示唆が提示される。
本書の学びとして、マーケットデザインという観点で読むのは当然面白い。また、いわゆる日本的経営に関心を持つ人にとっても、各種の規制改革がどのように日本の高度経済成長を実現したかなどの示唆が得られるだろう。一見難解な本であるが、真っ当な経済学の書籍として様々な人にお勧めしたい。