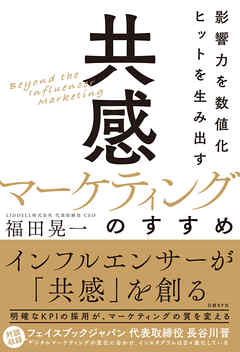感情タグBEST3
Posted by ブクログ
現在「共感マーケティングのすすめ」を読み進めている者です。
普段インスタグラムを使っている私にとって非常に分かりやすく共感できる内容です。個人の共感という者がマーケティングに直結することが身に染みて分かりました。インフルエンサーそれぞれの世界観の中でのPRだからこそより強い共感が生まれ、そこにマーケティングの醍醐味があるのではないかと思います。これからの時代ビジネスを展開するにあたってSNSを活用せざる終えない時代がやってくると思います。その中で踏まえるべき視点、SNS運用の仕方へのコツがこの一冊に詰まっています。是非手に取りたい一冊です。
Posted by ブクログ
インフルエンサーの実情や影響指数の記述がとても興味深く"フォロワーが多ければ良い"やなどの短絡的考えでは通用しないと実感する一冊だった。主にインスタでのマーケティングについて書かれているが、Twitterなど他のSNSにも応用できる内容だと思う。
Posted by ブクログ
インフルエンサーマーケティング、興味ある人にはいいかも
仕事柄、インフルエンサーマーケティングについて注目していたのだが、
なんとなく抽象的な部分が多い業界イメージもあった。
この本のように、インフルエンサーマーケティングについて数値化しているのは興味深い。
KPI・効果についての指標が図りづらい分野だと思っていたのでなおさら。
本の後半、案件事例もあって実践できそうと思えた。
最後の方ちょっと横文字多かったけど、勉強になった。良書。
Posted by ブクログ
マーケティングを勉強してる私のような学生にとってはテクニカルすぎる内容ではないため、勉強するにはちょうどいい書籍だと感じた。
Instagramユーザーとインフルエンサーが彼らに与える影響の構造が平易な語り口で説明されていて、とても分かりやすかった。Instagtamは2015年から2017年の2年間でユーザー数が大幅に増え、キャズムを超えたことで、とがってたSNSから総合的なビジュアルコミュニケーションプラットフォームに変化しこれに伴って憧れのメディアから参考のメディアへと変化したと本書では説明されていて思わず膝を打った。
また共感指数という共感を数値で評価する新たな指標を紹介しており、興味深い。定性的で感覚でしか捉えられなかったものをなんとか数値に落とし込んでる感は否めないが、一つの指標として参照するには便利なのではないか。
結論を言うと共感を完全に解明することは難しいが、インフルエンサーマーケティングの代理店として培ってきた暗黙知を形式知化する試みという点で、非常に面白かったし参考にしたい。
Posted by ブクログ
ビジネスにおいても「インフルエンサー」というワードが
ここ数年かなり飛び交うようになってきたため、
これは知識をつけねば…ということで勉学のため手に取りました。
私がイメージしていた以上に
ソーシャルを意識したプロモーションは重要性を増しており
インフルエンサーがなぜ存在しうるのか、
ということもクリアになり大変参考になりました!
"影響力の数値化" は若干理解するのが難しかったですが、もし叶えば、ますますSNSマーケティングは加速していくことは理解できました。
Posted by ブクログ
インフルエンサー起用してもその効果が結局わからない・わからなかった人、インフルエンサーマーケティングを検討している人には最適な本だと思う。
今まで広告枠としてリーチなどでしかインフルエンサーを捉えてこなかったけれど、そこを見るのではなくインフルエンサーを人・メディアとして捉え、そこにひもづくファン・フォロワーへの発信から生まれる共感に目線を移すという考え方はデジタルマーケティングを行なっている方必見。
ただ、5章は数字の話が多く読み切る意思がないと途中で投げ出してしまいそうなのでその点で星4。
Posted by ブクログ
SNSやインフルエンサーマーケティングの効果測定は難しいと改めて認識。
Instagramアカウント運用方法やインフルエンサーの選定に関して、共感指数の視点を参考にしてみようと思う。
TwitterやFacebookに関しても内容があればより良かった。
Posted by ブクログ
概念的なマーケティング本ではなく、どちらかというと実践編の参考書といった立ち位置。前提にSNSやInstagramの運用知識があれば、比較的読みやすいと思うが、その辺の知識があまりないと若干腹落ちしにくいかもしれない。
特におそらくこの本の一番画期的な主張である「共感指数」は、がっつり分析系、数学的思考に基づいているので自分にとっては難しく、実際のアカウント事例などで何度もトライしていかないと本当の理解にまでできない感じがした。
でも、共感ってとてもあいまいだし共通認識が持ちにくい抽象ワードなので、こんなふうに計測に基づく数値化をしてくれると実務には採用しやすいかもしれない。
Posted by ブクログ
・消費者はただの消費者ではなく、プロモーターにもなり得る存在。その先に「共感」が生まれ、さらなる消費が生まれる。
・「共感指数」でインフルエンサーの強みを数値化することで、適切なインフルエンサー選びができる。
ーーー
フォロワー数だけを見てインフルエンサーを連れてくる企業も多い中で、しっかり質を数値化されているのは素晴らしいと思う。
算出の仕方については、そもそもそれでいいのか、という話もありそうだが、共感指数がないよりはあった方が意味のある効果検証が出来そう。
インフルエンサー施策を検討中の企業側、支援会社側、双方におすすめの一冊。
Posted by ブクログ
(レビュー初心者です。読みにくかったら申し訳ありません。)
インフルエンサーのことを勉強したくて読みました。
マーケティングには共感が大事で、SNSは「共感の連鎖」を生み出す媒体ということに納得しました。
SNS利用者は商品の消費者でもあり、宣伝者でもあること、またフォロワーがインフルエンサーを支持するのも、同じ商品が欲しいからではなく、その人のライフスタイルを真似したいから、ということも分かりました。
今の時代は、個人が企業のマーケティングにも関与できる時代なんだなと改めて実感しました。
Posted by ブクログ
マーケティングのお勉強として読みました。
主にInstagramをメインとしたインフルエンサーの活用方法についてでしたが、時代の変化によりメディアや消費、SNSの活用方法はどう変化したのかといった基本的なことにも触れられており、理解が深まりました。
マーケティングの根幹となる「共感」の大切さも実感。
また、インフルエンサーを「フォロワー数」だけで選んではいけないこと、その他の評価軸を数値化しているところが面白い。
実際に自分の会社のサービスに置き換えて考えたらどうなるか…脳が刺激されて色々とアイディアが浮かび、途中脱線しながらメモをしまくりました。笑
企業でPR活動をしている方はもちろん、影響力のあるインフルエンサーになりたい方にもオススメです。
Posted by ブクログ
SNSのお勉強。
むしろ、彼女たちより2桁も3桁もフォロワーが少なく、テレビに出演しているわけではないのに、時間をかけて工夫をしながらコツコツとフォロワーを増やしてきた一般のインスタグラマーの方が、より強力なインフルエンサーたり得ることも多いのです。
強力とは、そうしたインフルエンサーを活用した方が、狙ったターゲットに向けてより低コストで、より効果的にマーケティングできるということです。
先ほど、有名店の行列を例に挙げましたが、行列は長く続くほど、より多くの人に、その行列に加わりたいと思わせます。「あの人だけが持っている・やっている」より「あの人もこの人も持っている・やっている」のほうが、「買いたい・やってみたい」という思いを喚起し、より多くの生活者を刺激し、新たな起承転結を起こし、消費を喚起させるのです。
インスタグラム上でのこの現象を、私たちは”雰囲気売れ”と呼んでいます。
私たちの経験上、100万人のフォロワーがいるタレント一人に一度投稿してもらうのと、1万人のフォロワーがいるインフルエンサー100人にそれぞれ一度ずつ投稿をしてもらうのとでは、後者のほうが確実により広く共感を得て、雰囲気売れを起こすことができます。また、コストも圧倒的に抑えられます。
一般に、フォロワー数が増えていくと、エンゲージメント率は減少してきます。
これはおそらく、フォロワー数の増加がインフルセンサーの意識を変えるからです。
フォロワーが、実際に顔も名前も知っている友人ばかりのとき、インスタグラムは写真がメインのコミュニケーションツールとして使われています。その使われ方は、フェイスブック的でもあり、交換日記的でもあります。インスタグラム上で、私は今日、どこで何をしたかを伝え、友人がどこで何をしたのかを知るのです。
しかし、フォロワー数が増えてくると、エンゲージメント率は下がっていきます。フォロワー数からの「いいね」の割合が減るのです。これは、頻繁に「いいね」してくれるリアルな友人ではなく、読者やファンのように、投稿をただ眺めているだけの人の増加を意味すると解釈できます。
しかし、フォロワー数が6000から3万のところでは、少し不思議な現象が起きています。フォロワー数が増えているのにもかかわらず、「いいね」の割合も増えているのです。
ここで考えられるのは、インフルセンサーの態度です。フォロワーがこのくらいまで増えると、インフルエンサーはフォロワーを増やすことに強いやりがいを感じ始め、フォロワーを増やすような工夫を重ねるようになります。
インフルエンサーの投稿がどれだけの共感を呼べるのかの基準となる共感指数は、「影響の範囲の値」「承認の値」「発見の値」「参考の値」「印象の値」という5つの要素から構成されます。