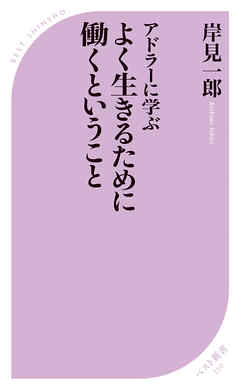感情タグBEST3
Posted by ブクログ
なんのために働くのか?働く意味とは?
「リルケ」がキーワード
怒りの感情とは?
失敗を恐れるな、怒られてもいい。
子供を褒めたり叱ったりしてはいけない理由を説明できますか?
Posted by ブクログ
アドラーに学ぶ。よく生きるために働くということ
【著者】
アドラーの「嫌われる勇気」の著者、岸見さんの執筆です。
【関心深い内容】
岸見さんが、岸見さんの人生を振り返りながら、執筆されていること。
1.40歳まで定職につけなかったこと。
2.哲学者として歩むも、哲学を通じてどう生きるのか?のカウンセラーに進んだこと。
3.アドラーとの出会えたこと。
4.心筋梗塞で手術し、入院されたこと。
多くの文献を学んだ岸見さんが、その文献を引用しながら展開しています。
一ページで、ワンメッセージと読みやすい展開でした。
【学び】
①アドラーの共同体の概念。
自身は、多くの関係のなかで成り立っていること。
仕事も仕事以外も。
②働くは社会貢献
社会貢献とは、Social Interest、そう社会への興味、関心と訳すこともできます。
コンビニで働く
→深夜、早朝に用事のある人に役立つ場所で働いている
③貢献感
他者から与えられる貢献感、納得感ではなく、自ら探し、見出すこと。
④横の関係
対等。仏教でいえば、同時ということ。
⑤プライベート
プリヴァーレ(ラテン語)=奪うと訳す。
そう、自ら自らの時間を奪う感覚で創るものだということ。
Posted by ブクログ
アドラー心理学における第一人者、岸見一郎氏が働く意義について書いたものです。
アドラーをはじめとする心理学者や哲学者の教え、そして著者の実体験を織り交ぜながら話は展開されています。
仕事をする上で大切なのは、その仕事で自分が貢献できているという感覚を持てるかどうかにあります。勇気を持って臨む、すると勇気は伝染していくのだ。現状と向き合って行動することが大切なのである。
また、人間関係を上下で捉えるのではなく、横並びで考えるところもポイントになっており、職場での人間関係を考えるうえで参考となる一冊。
Posted by ブクログ
「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」を熟読し、岸見一郎先生の解釈によるアドラー心理学にとても興味を持った。岸見先生の本は、いろいろと読んでいきたいと思っている。まずはこの本を読んでみたが、これもとてもよかった。「仕事」がテーマ。生活するうえで、働くことは避けて通れないので、いろいろと有意義な内容だった。これからも、読み続けていくつもりだ。
Posted by ブクログ
働くとはどういうことなのか、改めて考え直してみたいと思い、読んでみました。一番共感したのは、働く=貢献感という話です。
これに照らし合わせれば、家事や子育て、自宅介護もれっきとした仕事です。
会社勤めだけが仕事ではないんですよね。
アドラーの教えの重要なポイントととも言える、人間関係を上下で捉えるのではなく、横並びで考えるところも押さえられていて、仕事上の人間関係を考える上でも参考になります。
Posted by ブクログ
アドラーに興味を持ったので読んだ1冊。著者はアドラー心理学の第一人者。著者自身の人生、考え方を交えながら、働くこと、生きることについて書いた1冊。働くを考えるときに、働けなくなることも視野にいれ考察。仕事をする意味、他者との関係性。How to本のような明確なわかりやすさはないが、深くていろいろ考えさせられる言葉が多かった。アドラーや哲学について、他の本を読んでみようと思う。
⚪仕事の課題を、解決する最善の方法は交友の問題を解決することです。分業を可能にする。
⚪エーリッヒ·フロム
愛とは、愛する者の生命と成長を積極的に気にかけることである。この積極的な配慮のないところに愛はない
⚪アドラー
私は自分に価値があると思えるときにだけ勇気をてる
すべての悩みは対人関係の悩みである
⚪仕事も、それに合わせて自分が受動的に入っていく場所ではありません。自分もまた仕事のあり方や職場の環境を変えていくことができますし、そうする責任があるわけです。会社という組織に自分を合わせなければならないわけではないのです。
自分にしかできない仕事はないが、どんな仕事であれ、自分にしかできない仕方で取り組むことができます。
⚪精神科医 神谷美恵子
愛に生きる人は、相手に感謝されようとされまいと、相手の生のために自分が必要とされていることを感じるときに、生きていくはりあいを強く感じる
⚪叱る上司の屈折した承認欲求
叱るときに怒りの感情を介在させるのは、上司が理不尽な怒りを爆発させてでも、部下に承認されたいと思っているからなのです。部下を押さえつけることで自分が優位であることを誇りに思う。
世の中に強制できないことは2つ。愛と尊敬
⚪いつも何が一番大切なのかを見極めることが必要です。君はお友達に会いたいの?それとも洋服を見せに行きたいの?
⚪母が病に倒れ、お金に加え名誉心すら意味がないと知ってしまいました、人生のレールから大きな音をたてて脱線したように思いました。生きることの意味は何か、幸福とは何かと考え抜いた結果、哲学の歴史ではなく哲学そのものを学ぼうと思いました。
⚪アドラー
結婚はつまるところ人類のためになされる
Posted by ブクログ
自身にとって〝働く〟とは?
アドラー心理学における第一人者が、現代人の働く意義について考察した新書です。
アドラーをはじめとする心理学者や哲学者の教え、そして著者の実体験を織り交ぜながら書かれています。
仕事中心の生活に疲れてきたなぁ、、と生きづらさを感じた時、アドラーの定義は勇気へ繋がる力をくれます。
他者の存在を認め、自分の価値を認める。
難しいことですが、対人関係を築く上では何より大切なことかもしれません。
Posted by ブクログ
タイトルのとおり。「よく生きるために」働くのである。
プライベートの語源は自分で奪い取るもの、というのは印象に残った。
仕事というのはよく生きるために行われるものであり、ではよく生きるとはなにか、というと、全体の幸福に貢献すること、である。わかりやすく言えば、人類の歴史に何かを残すこと。それはスケールの大きいものもあれば、そうでないものもあるが、その大小に優劣はない。
存在するだけでも、だれかがいる、ということになり、だれかのためになる。仕事によってそれを消してはいけない。仕事というのは最もよく生きる証に最たる手段なだけである。
Posted by ブクログ
岸見一郎先生は、単にアドラーが残した言葉を伝えるだけではなく、哲学者としての視点からの解釈を加えることによって、アドラー心理学を現代に蘇らせる仕事をなさっているような気がします。
2014/12/24『嫌われる勇気'13/12/16』、2015/01/24『アドラー心理学入門 (ベスト新書)2014/6/27』、2016/11/20『アドラー心理学実践入門 (ワニ文庫)2014/6/27』、2016/11/22『人生を変える勇気 (中公新書ラクレ)2016/10/14』、2017/01/21『幸せになる勇気2016/2/26』、2017/02/19/『アドラーに学ぶ よく生きるために働くということ (ベスト新書)2016/7/9』と刊行順とは違うが、岸見一郎先生の本を読んできた。
本書は、序盤、同じ文章が何度も繰り返されるので若干読みにくいが、アドラー以外の先人による言葉も引用され、最後の第四章では、心理学というよりも哲学、哲学というよりも宗教?と思えるような昇華を見せる。どれか一冊を選ぶということであれば『実践入門』を薦めるが、脳に擦り込みたい方には、本書も決して無駄にならない。
Posted by ブクログ
岸見先生が「働く」ことに特化して書いた本。
哲学的な捉え方から、実際の職場で起こりうる人間関係まで、さらに、働き方に対する先生の考察。
盛りだくさんながら、色々とヒントをいただける内容だった。
Posted by ブクログ
最も印象的だったのは「人生の課題に優劣はない」です。ワーカーホリックで家庭を顧みないのは、家庭を顧みないために仕事に熱中している。それが良いわけではない、というのは納得でした。ただ、人生のあるシーンにおいては、特定の課題を優先するのを妨げないことは頭の片隅に置きたいです。人生の調和を重視したいと思っていたので、その考えを言語化してもらったように思います。
Posted by ブクログ
アドラーだけでなく筆者が学んできた多くの思想家・哲学者や筆者本人が人生で経験してきたことを踏まえて、働くことの意義が書かれた本でした。
私は哲学の知見が浅いため多くの思想家の名前が出てくるところは難しく感じたので、哲学初心者は全体を通して何が言いたいのかを意識して読むとよいと思いました。
休職中の仕事に悩んでいるときに読んだため、「生きていることそれ自体に価値がある」という考え方に心が救われました。
Posted by ブクログ
「貢献感」がキーワード。
アドラー曰く、人生には「仕事の課題」「交友の課題」「愛の課題」の3つの課題がある。
それぞれ独立して解決はできず、各々の課題を解決するには他の2つの課題も解決する必要がある。
働くことで「貢献感」を得られれば、自分に価値を感じることができ、対人関係の中に入っていく勇気を持てるというロジック。
以下、メモ書き。
・自分に価値があると思えない仕事に意味はない
・自分で仕事のあり方や職場の環境を変えていく
・「誰が」言ってるかでなはく「何を」言ってるかに注目する
・仕事が楽しいとは、仕事に習熟してこそ言えること
・周りの人間は敵ではない
Posted by ブクログ
仕事をする上で大切なのは、その仕事で自分が貢献できているという感覚を持てるかどうか。自分の思いがどこにあるのかによっても、この感覚は変わってくるのだと思う。勇気は伝染する、らしい。今と向き合って行動することが大事なんだな。
Posted by ブクログ
前半は色々と気づきがありましたが、後半は著者の体験談も多く、少しダラダラと感じました。また、章によって想定読者が異なるように思いました。
「部下を自分の支配下に置こうとする…その行動/育成が、指示待ちの部下を生む」というあたりは注意しようと思いました。
Posted by ブクログ
「嫌われる勇気」「幸せになる勇気」の解説本ともいえるが、岸見氏の既刊本とかぶる内容も多い。アドラー心理学はわかったつもりでも実は本質はわかっていない、と再認識させられた。
Posted by ブクログ
現在、働かないと人は経済的に暮らしていけないため、働くか働かないかという選択肢は事実上ない。したがって、なぜ働くのかということを考える意味はあろう。
アドラーは、「誰かが靴を作るとき、自分を他者にとって有益なものにしている。公共に役立っているという感覚を得ることができ、そう感じられるときにだけ、劣等感を緩和できる」と述べている。すなわち、人は働くことで他者に貢献すれば貢献感を持つことができ、そのことで自分に価値があると思えるため、働くことは自分のためでもある。その意味で、自分から働くことに意味はあり、働くことは生きることと密接な関係にあると言えよう。
自分が仕事をすることで共同体(職場)に役立っていると感じることは、自分に価値があると思うことになる。上司は部下に〇〇すべき、〇〇すべきでないという様々な主張がなされているが、そのことを踏まえれば、上司は部下が貢献感を持てるように援助することが大切なのである。この貢献感は、誰かから与えられるものではないので、部下に貢献感を持たせようとするのではなく、あくまで自発的に持てるように援助すべきである。
一般に、仕事が楽しくないと考えられるのは、第一に、自分が取り組んでいる仕事の遂行に必要な知識・技術が十分に身についていないとき、第二に、その仕事に貢献感を持てないときである。自分には不向きと思うような仕事でも、その仕事を極めることで、自分の力に自信を持てるようになったり、貢献感を持つことができるようになったりする。一見、自分に向いていないような仕事であっても、全力を尽くすことで、自分に価値を生み出すことがある。したがって、まずは、目の前の仕事に前向きに全力で取り組むことが大切なのである。
全体を通して著者は、働くことを通じて、貢献感を持つことの大切さを説いている。貢献感を持つことができれば、自分に価値があると思うことができ、価値があると思うことができれば、対人関係の中に入っていく勇気が持てるし、その分プライベートも豊かになるという流れである。
確かに社会人として働いてみて、自分がその組織に役立っているという満足感が働くインセンティブになっているときもあるが、著者はその貢献感を絶対視しすぎているようにも感じられた(その意味で本書の内容は、理想論のようにも思われた)。
また、儲かる仕事か好きな仕事かどちらかを選ぶという問いに、著者は当然、好きな仕事を選ぶべきであると主張している。しかし、仕事は、自分に合っているか合っていないかで決めるべきであり、その仕事の好き嫌いを気にしすぎない方が良かろう。好き嫌いだけではなく、自分の性格、能力、得意不得意に適合した仕事を選ぶべきではなかろうか。
Posted by ブクログ
働くということをアドラーの視点から見る。
幸せに働くにはどうしたら良いか。
部下に対してどう、接したら良いか。
決して怒らない。誉めない。感謝の気持ちとヨコの関係になる。
共同体への貢献を感じた時だけ、ひとはその仕事に遣り甲斐を感じる。遣らされたり不本意なままやる仕事には決して幸せは見出だせない。
至って、シンプルな考え方。何かを変えるのは最後は決断力と勇気なのかもしれない。
Posted by ブクログ
岸見一郎氏によるアドラー心理学を「働く」ということにフォーカスした著書。著者のアドラー心理学の本を読まずにこの本だけを読む分には有益かもしれないが、既にいくつか読んだ人からすると繰り返しの内容に聞こえてる部分も多々ある。
根底には当然ながらアドラー心理学の思想があるため、著者によるアドラー心理学の著書と同じような内容が多数散見される。さらには、著者の実体験や著者の哲学者の側面も多分に要素として含まれており、特に後半部分にはその側面が多用されている。
・仕事も、そこで仕事をする職場も、それに合わせて自分が受動的に入っていく場所ではありません。自分ちまた仕事のあり方や職場の環境を変えていくことができますし、そうする責任があるわけです。会社という組織に自分を合わせなければならないわけではないのです。
・評価とは評価される側だけでなく、評価する側の教師、あるいは上司の指導方法について、それが通切なものかを知るためです。試験をしてみて点数が低い時、無邪気に学生や部下の無能を責める教師がいますが、そのような教師や上司は自分の指導が問題であることに目を向けたくはないのです。
・仕事が楽しくない時に考えられるのは、一つにはまだ自分が取り組んでいる仕事のことがわかっておらず、仕事の遂行に必要な知識、技術ともに十分身についていないということです。初めから楽しくて仕方ないというような仕事はないと考えた方がいいでしよう。次に考えられることは、仕事にどれほど習熟したとしても、その仕事によって何らかの仕方で貢献感を持てなければ楽しいとは思えないということです。仕事は自分を犠牲として誰かに尽くすことではありません。
・やる気が出ないというのは、多くの場合、本当ではありません。実際には目下取り組んでいる仕事がら逃げたい、少なくとも積極的に取り組みたいとは思わない人が、やる気が出ないことを仕事をしないことの理由にしているのです。仕事をしたくない人には、いつまで待ってもやる気は起こりません。
・まず、自分が何のために仕事をしているのかという本書で考えてきたことをしっかり理解しなければなりません。自分がしている仕事が何かの形で他者に貢献していると感じられなければ、仕事を続けることは難しくなります。次に、待っていてもやる気が出ないのですから、やる気が出ようと出まいと、例えばパソコンの前にすわってみることは必要です。
・行き詰まったのであれば、そこで決断し直せばいいだけです。困難、あるいは不可能だと思つた時、目標の達成に固執したり、反対に、一つの方向で道を遮られても、目標そのものを放棄したりしなくてらいいのです。目標を変えず、それに固執することは、人生の無駄遣いになってしまいます。
・今を楽しめる仕事というのは、楽な仕事であるということではありません。ちょうど自分について自分に価値があると思い、そんな自分を好きだと思えるためには、自分が誰かに何らかの形で役立つている、貢献していると思える。自分の仕事が誰かの役に立つていると思える時、自分のことを好きになれるのであり、そんな仕事であれば楽しむことができるのです。
・先に、自分に価値があると思えたら、対人関係の中に入っていく勇気を持てると書きましたが、自分に価値があると思えることがすでに勇気のいることです。仕事の場面で「競争社会で多言てきた人じとっくは、結果を出せないことば恐怖以外の何物でもあません。とたえ、競争に勝っていると思っている人であっても、いつ負けることになるかもしれないと思っていると安閑としていられません。
・仕事も、生きることも決して競争ではないということを知ることが最初に必要です。さらに、競争するのでなくても、人と関わることで何らかの摩擦が生じ、そのため傷つくことを恐れ、対人関係の中に入っていこうとしない人には次のことを知ってほしいと思います。他者は隙があればあなたを陥れようとする強い人ではないということです。
Posted by ブクログ
経済的な自立は人間関係の上下には関係ない!!貢献感を持てる仕事があればいい!!人間の価値は生きていることそれ自体!!上司と部下は人間としては対等であり役割が違うだけ!! 第一義を決めたらあとの不要なものは捨てる!!儲かる仕事より好きな仕事を選ぶ!!
Posted by ブクログ
人生における働くことの意義を考えさせられる本だった。
「自分に価値があると思える勇気を持とう」という考えには同感できるが、「成功は人生の目標ではない」という考えには納得できなかった。後日、もう一度読み直してみよう。
Posted by ブクログ
2つの新しい考え方を得た。
①すべての対人関係は横の関係であるべき。
②貢献感を持てればすべての仕事に価値がある。
まず①。今まで全く気付かなかったが、これまでの対人関係において、常に上下で考えていたし、そのように振る舞ってきたように思う。上司や先輩に対してはときに媚びへつらい、自分が上位に位置して反感を買わないように常に意識し、低く見せようとしたりすることもあった。女性の先輩には特に気をつかった。友人に対しても、経済的に上か下か、とか、置かれている環境が自分の方がベターかどうか、実はよく意識していたように思う。無意識のうちに、自分は相手よりも上か下か、ということを常に意識しながらやってきたように思う。難しいかもしれないけれど、これからは対人関係を横の関係として考え、接し、振る舞うことができれば、人間関係に疲れることもなくなるかもしれない。難易度は高そうだが、さて、行動を変えることはできるだろうか?
次に②。やりたい仕事とやりたくない仕事、という概念で仕事を切り分けてきたような気がする。やりたい仕事、とは、それによって周囲や会社や社会に貢献できるかどうか、なんて意識は皆無で、ただ自分が気分良く、ノッてできるかどうか、その仕事そのものが好きかどうか、興味を持ってルンルンな気分でできるかどうか、そういう視点だけ。そうでない仕事は「やりたくない」「なんでこんな仕事私がしなくちゃいけないのよ」と不満でいっぱいになり嫌々ながらする。でも、どんな仕事についても、誰かや何かの役に立っている、貢献している、と思えれば、やりたい仕事とかやりたくない仕事、という概念はなくなるのかもしれない。
①も②も結局、意識の問題、考え方の問題かもしれない。うまく考え方を変えられるか?変えた上で行動を変えられるか?行動に良い影響が出てくるか?納得して自分の生活に反映していけるかが課題。