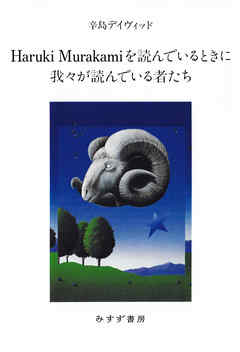感情タグBEST3
Posted by ブクログ
村上『走ることについて語るときに僕の語ること』(そもそもこれもカーヴァー『愛について語るときに我々の語ること』を模しているわけだけれど)を模すタイトルが差すように、私たちが村上春樹を読むときは、実は村上だけでなく編集者翻訳者エージェントなどなどの関わった人々の解釈と情熱をも読んでいる。
1つの作品が英語圏に出て読まれて評価されて売れるためには、作家の力もさることながら、それ以上に、関わる多くの人の力があることをまざまざと思い知らされる。
インタビューや年代を追う記述も多く、丁寧に取材したんだなあと思う反面、若干盛り込み過ぎの気も。
Posted by ブクログ
良書。素晴らしい。筆者の丁寧な仕事ぶりに好感がもてるとともに、この主題でちゃんと読み物になっていて退屈もしないし面白い。
海外でも村上春樹は人気で、ノーベル賞候補になっているとなんとなく思っていただけで、翻訳者を中心に関係者のインタビューやエピソードを通じて知らなかったことを知れた本。
翻訳のみならず、"本づくり"を感じ取れた。
Posted by ブクログ
村上春樹が世界でどのように紹介されて売れていったかが分かった。これまでは作品が良ければ自然と世界でも読まれていくのだろうと漠然と思っていたが、特に翻訳小説で成功を収めるには実は一人の作家に対して翻訳者や編集者などのたくさんの人たちが様々な思いで関わって、そしていろいろな偶然(必然?)が重なっていることが背景にあるようだ。これから翻訳小説を読むときには、翻訳者などにも注目していきたいと思った。
Posted by ブクログ
日本の現代文学において、最も海外で読まれている作家は村上春樹を置いて他にない。本書はなぜ彼の作品がここまで海外で受け入れられたのかという点について、彼の英語圏での出版を手助けした翻訳家・編集者・出版エージェントといった文学の”裏方”の人間たちにスポットを当てることで解を出した労作である。
こうした”裏方”については、村上春樹本人が、アメリカで翻訳された短編作品だけを収める形で半ば逆輸入的に日本で出版された『象の消滅 村上春樹 短編選集1980-1991』の序文で本人の口から細かく語られている。その中では英語圏の出版業界の比類なきプロフェッショナリズムが、大いなる賛辞と共に示されているが、その内実がどのようなものかは正直不明なところも多かった。本書ではそのプロフェッショナリズム、そして何よりも文学に対する愛情に、文学を愛する一人の読者として心を揺さぶられた。
特に、海外での出版にあたり最も重要となる翻訳者については、本書でもかなりのページ数が割かれている。村上春樹の英語翻訳については、彼が贔屓にしている数名の特定の翻訳家がいるが、その一人、アルフレッド・バーンバウムは初期の傑作『羊を巡る冒険』の翻訳にあたり、特徴的な登場人物である羊男のセリフ「音楽の鳴っている間はとにかく踊り続けるんだ。おいらの言っていることはわかるかい?踊るんだ。踊り続けるんだ。なぜ踊るかなんて考えちゃいけない」を以下のように翻訳したという。
「Yougottadance.Aslongasthemusicplays.Yougottadance.Don`teventhinkwhy」(本書P262より)
バーンバウム曰く、訳文を何度も読み返す中で聞こえてきたのがこのボイスであるとのことだが、『羊を巡る冒険』の読者であれば、羊男の饒舌なボイスとそのリズムを表すのに、この字続きの表現が適切だということを同感されるのではないだろうか。
村上春樹のファンはもちろん、英語圏における文学や出版というものの実態を知りたい人にとって非常にお勧めできる一冊。