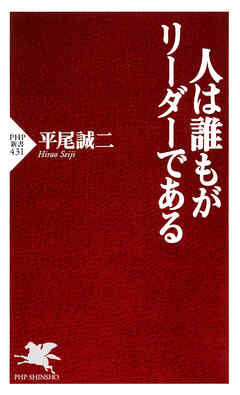感情タグBEST3
Posted by ブクログ
人は誰もがリーダーである
著:平尾 誠二
PHP新書 431
平尾誠二は間違いなく、カリスマ型のリーダだとおもう。押しもつよいし、何よりもかっこいい
それが証拠に本書の表紙も男が惚れるようないい男である。荒くれ者をまとめ上げて何連覇もできる男が何をいっても、そこはそうだと、素直に聞くしかないではないではないか
気になったのは、以下です
・型をつくって選手をそこに当てはめるのではなく、個々の技術と判断でゲームを組み立てていくことこそが真の強化と呼ぶべきものであり、そのためには、選手個々の力をベースアップさせる必要があるとジーコも私も信じていたわけだ
・すなわちフットボールというゲームでは、監督は選手をピッチに送りだしてしまえば、ひとつひとつのプレーについて細かく指示を出すことはできない
・その都度、選手たちがその状況に対応し、自分自身で適切な判断を下しながら、ゲームを進めていかなければ、最終的にゴールにたどりつくことは不可能である
■弱さを知って初めて「強い個」は生まれる
・そもそも自信と不安は表裏一体のものだと私は思っている。このふたつが本人の中で行ったり来たりしているのである
・これからは、こんなことは何回もあるだろう。そのたびにこうやっていつも逃げていたら、自分はずっと逃げ続けなければならなくなる。そんなことはできやしない。いつかは逃げられなくなるときが来る
・自分の弱さと向き合い、外から自分を見ている「もうひとりの自分」と対話することが大切だ
それを繰り返していくうちに、弱い自分をコントロールできるようになる
それが、セルフコントロールだとおもう
・だいたい、不安や弱さを感じなければ、人間はそうそう努力などできるものではない
・つねに最悪の状況も想定し、その場合の対策を考えておかなければならない
・不安で満たされることがないゆえに、つねに努力するし、より高みを目指そうとする
・考えてもしかたないことをいつまでも考えていれば、行動力は鈍くなるし、結果的に生産性が下がるのは必然である
・状況によっては問題を先送りしても構わないと思う
どうしても突破口が見つからないときは、あるいは緊急に解決を迫られていない問題なら、少し時間を経たあと、違う状況で考えて見る
それは逃げたことにはならない
・組織に必要不可欠な人間になるには、どのような存在になればいいのか
それは組織の、「内部」ではなく、「外部」で大きな力を発揮できる人間であれ、ということになる
・失敗を経験してこそ強くなれる
どうすれば、恥の意識から脱却できるのか
それはやはり、たとえ失敗したって恥ずかしくない、と思えるかどうかにかかっているだろう
失敗すること、ミスをすること自体は、決して、恥ずかしいこと、ではない
大切なのは、失敗を、恥、だと思わず、それを、次への糧、だと考えらえるかどうかなのだ
失敗や挫折を経験することで、自分の弱さや情けなさと正面から向き合うことが、人間が生きていく上では非常に大切であると私は考えている
・人からやらされるのではなく、自分で自分を律し、目標を達成することは、想像以上につらいものだ
困難や苦しさが伴うし、ときには高い壁にぶち当たることもあるだろう
人間は弱いものだから、どうしてもそこから逃げようとする
しかし、困難を自分の力で乗り越えなければ、強い個、の確立など望むべくもないのはいうまでもない
・視点を切り替えることで活路を見いだす
・苦しいのは自分だけじゃない
・壁にぶち当たって苦しんだり悩んだりしたとき、そこから逃げることなくやる気をかきたてるためには、置かれた状況を冷静に見つめ、悲観的にならずに、ポジティブに物事を捉えて、思考や目線を切り替える、ことが重要なカギになると思う
■部下の弱さを克服させ、強さを生み出すリーダー力
・モチベーションとは、あえて、日本語にすれば、動機づけ、という意味になる
すなわち、行動を起こすための源泉となる意欲のことである
・人はとうてい実現不可能だと思える目標に対しては、そうそう努力できるものではない
逆にいえば、もう少しがんばったら、達成できる、という感触があるからこそ、やってやろうじゃないか、と思えるのである
・それでは、コーチングの本質とは何か
それは、モチベーション、にあると私は考えている
・やる気を起こさせるには、マイナスに落ち込んだ自信を、ゼロの状態に戻してやることが必要なのである
・人間というものは、悪いところを指摘して、ここを直せ、と言っても、なかなか主体的に努力できるものではない
だからこそ、本人のいちばんいい部分をグンと引き上げてやるのがいちばんよい方法だと思うのである
・臨場感を感じたうえで、さらにもう一歩踏み込んで、この人間は何を求めているのか、を察する力、すなわち、洞察力を指導者は持たなければならない
・コーチングにおいて、もっとも大切なのは、やる気をさせることだ
・コーチの役割とは、分かりやすく言えば、ゼロの状態をプラスにしてやる、ことである
・強制させて何かをやらせるときに大切なのは、結果を出させる、ということなのだ
やればできる、という実感を味わわせなければならない
■人は生まれながらにしてリーダーである
・こうした時代において、求められるリーダーの資質とは何か
それは、一言で言えば、キャパシティであると私は思う
すなわち、異質なものやいびつなもの、対立するものを排除するのではなく、取り込んでいく力のことである
・たとえ、上司であっても、人間として信頼できなければ、ついていこうとは思わないはずだ
そして、信頼関係を築くために、最も大切なのは、相手の話をよく聞くことである
・間合い つまり人と自分との距離、物事と自分との距離感のことである
人には、自分を活かす間合い、自分が行かされる間合いがある
あまり対象に近づきすぎては、身動きがとれなくなってしまうし、離れすぎると影響力が及ばない
自分にも周囲にも適切な距離があるのだ
・監督や、管理者になるということは、群れから出ることである
・結論をいえば、自分の立ち位置は自分で探すしかない
・リーダーは孤立を恐れてはいけない
だが、組織としての目標を共有させ、個々を連帯させることは絶対に必要だ
・リーダーの立場にある人間は、フォロワーの管理にはできるかぎり力を使わないほうがいい
なぜなら、リーダーの本来の仕事とは、組織の外、すなわち、競争相手と闘うことであるからだ
■強い組織は成熟した個人の集まりから生まれる
・アクティブコミットメント、自発的連係とでもいおうか
チームにコミットしようとする意欲、チームとしてまとまろうとする気持ちのことである
ただし、ここが肝心なのだが、それは強制されたのでは意味がない
個々の内側から滲み出るこのでなければならない
・そもそも、私は、組織内の人間の目標を無理やり一致させる必要はないと思っている
要は、それぞれの目標を達成することが結果として組織としての目標達成につながればいいのだ
■個人と組織の力を最大限に活かす戦略とは
・ゲームの本質を見誤っては、勝つことは非常に難しくなる
戦略と立てるときには、ラグビーならラグビー、野球なら野球というゲームにおける、競争相手との構図をまず認識しておくことが重要になる
・戦略と立てる際、もうひとつ大切なのは、自分たちの強みと弱みとを正しく認識することである
・何か一点でいいから、相手を上回る強みを身につけ、そこから活路を見いだすことが絶対に必要だ
いわば、一点突破、全面展開、だ
・相手がほっとした瞬間を見逃さず、一気呵成に攻めるのである
目次
はじめに
第1章 弱さを知って初めて「強い個」は生まれる
第2章 部下の弱さを克服させ、強さを生み出すリーダー力
第3章 人は生まれながらにしてリーダーである
第4章 強い組織は成熟した個人の集まりから生まれる
第5章 個人と組織の力を最大限に活かす戦略とは
おわりに
ISBN:9784569656427
出版社:PHP研究所
判型:新書
ページ数:192ページ
定価:700円(本体)
2006年11月29日第1版第1刷
2007年12月11日第1版第4刷
Posted by ブクログ
平尾監督の本はよく読みます。
リーダーの心構えとしてラグビーを通じて論じてあるのでとても参考になります。
不安やコンプレックスという負の要素は仕事につきものなので切り捨てるのではなくうまく付き合う必要があります。
そのためには視点を切り替え物事の捉え方を変えることが重要になります。
「勝ちたい」と考えるとプレッシャーに負けず選択肢が広がる。
それが「内発的モチベーション」につながります。
逆に「負けたくない」と考えると萎縮して自滅するパターンになります。
「外圧的モチベーション」はプレッシャーになります。
コーチングの要諦はヤル気にさせることにあります。
ただコーチする側が「ミッション」「ビジョン」「パッション」を持ってやらないと伝わらないです。
リーダーは常に「キャパシティ」がどれくらいあるか考える必要があります。
「大局的損得勘定」ができて初めてリーダーになれるというものです
まあ自分も含めて客観視しないといけないです。
「聞く力」を持つということは相手を知ろうという意思を持つことです。
常にアンテナは高く持つことと同じです。
逆に話すときは反射神経を持って臨機応変に。
その後チーム力が上がればアクティブコミットメント(自発的連携 )ができるようになって直感的連携が可能になるんでしょうね。
最終的にチームを引っ張るためリーダーは自身を鍛えて強い個である必要があります。
これはラグビーに通じますね。
Posted by ブクログ
平尾誠二の本です。知ってる人も多いが、ラグビー界ではトップレベルの著名人。説明は不要かと。
著者の講演を聞いてきた。話はたいへん面白かった。でも中身は正直たいした内容ではない。でもラガーマンとして聞けばたいへん参考となるな。
決してラグビーのカリスマだからと言うわけではない。
中身がいい。
特に第一章『弱さを知って初めて強い個は生まれる』は、超共感。
特に、
・弱さ→強さ
・内的モチベーションと外的モチベーション、
・失敗をしてこそ、
などは、超超共感。
今さらって内容かもしれんが、7つの習慣なんかよりもよっぽど良く、ぜひ実践したいという気になった。
Posted by ブクログ
日本ラグビー界の平尾氏の本。こういう類の本には2種類あると思う。ひとつは、色んな人の生き方を学び原理原則と説くもの。もう一つは、自分の人生から原理原則を導きだすもの。この本は後者。そして、圧倒的に後者のほうが良書が多い気がする。やはり自分の経験から、自分の言葉で語られる以上に響くものはない。一番心に残っとるのは、内発的モチベーションと外圧的モチベーションの話。自分の心から勝ちたいと思うか、外部環境からの何かしらの影響を受け、勝たなくてはいけない、負けてはいけないと思うか。これって似ているようで大きく違う。内発的モチベーションで仕事を取り組めれば、どれだけ楽しいじゃろうか。この本を読んで以来、今の自分はどうかと意識するようになった。
Posted by ブクログ
指南書やハウトゥーものは読まない。でも、それでも平尾誠二は魅力的だし、昭和のおじさんが真面目に世界や日本の旧体質と戦った痕跡を垣間見ることができる。
Posted by ブクログ
弱い自分を自覚し、その弱みを強みえと転化することができて初めて、人は強い子足り得るのである
人と組織は矛盾を潤滑にして成長する
教えるより考えさせろ
自分の置かれている状況を見つめ、自分と対話する中でどこまで落ちるのか底が見えてきた時に初めて不安は払拭される
人間と言うものは、不安や自信といった相反するものを常に自分の中に抱えながら、その葛藤の中で成長していくものではないだろうか
日本人は、勝ちたいと言う意欲より、失敗したら恥だと言う意識がどうしても先に立つ
人間と言うものは、興味のあること面白いと感じたことに対しては、能動的になるものである
いわば、リーダーの賞味期限とも言うべきものが非常に短くなっているのが現代と言う社会なのだ
攻めている間は守らなくてもいい
Posted by ブクログ
皆がリーダーであるということは?
→各々が自らの意志で目標に取り組む内発的モチベーションを強く持ち、そのために自分で考え、判断し、行動できる強い個である必要がある
それには、まず弱い自分を知る
ミッション、ビジョン、パッションを持ち、キャパシティつまり異質なものを取り込んでいく力
個人の目的を許容し組織目標を共有する
リーダーの本来の仕事は競争相手と闘うことであり、組織の内部を管理することではない
弱みをマイナスではなくプラスとして捉え直す
Posted by ブクログ
ラグビーの平尾誠二の本。課題図書。マーケットプレイスで。サッカー日本代表のジーコスタイルを例に、強い個、を主張されている。どちらかというと、弱いチームならチームワークを、なんて思っていたが、読み終わったら一蹴された。もうちょい早く読んどけばよかった。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
組織は生きている―組織を動かし、成果を上げるためには、自分で考え、判断し、行動できる「強い個」が求められる。
そして「強い個」であるかぎり誰もがリーダーであり、その集合体が、つねに矛盾や問題を抱えた組織を前進させていく。
そのときリーダーとは、もはや肩書きではない。
著者のラグビー人生は、不安と葛藤の連続だった。
しかし、そのほうが試合の集中力も高まったと言う。
「弱い自分」を自覚して初めて不安から脱出し、「強い個」に変わることができるのだ。
リーダーをめざす人、現在リーダーの人必読の書。
[ 目次 ]
第1章 弱さを知って初めて「強い個」は生まれる(弱い自分と向き合う;「弱さ」は決して否定されるべきものではない ほか)
第2章 部下の弱さを克服させ、強さを生み出すリーダー力(「内発的モチベーション」と「外圧的モチベーション」;成功体験が内発的モチベーションを誘発する ほか)
第3章 人は生まれながらにしてリーダーである(キーワードは「キャパシティ」;大局的損得勘定を持て ほか)
第4章 強い組織は成熟した個人の集まりから生まれる(「パズル型」から「積み木型」のチームワークへ;「チームスポーツの個人化」が不足している日本 ほか)
第5章 個人と組織の力を最大限に活かす戦略とは(勝負の本質を的確に把握せよ;じつは神戸のペースだった三洋戦 ほか)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
「教えたいこと」と「教えてもらいたいこと」を一致させるには洞察が要る。そいつに何をしてほしいか、それがチームにどれだけプラスになるかを言葉で説明できなければならない。何も求めていないのなら無用。
Posted by ブクログ
2016年31冊目
ラグビーで有名な平尾誠二氏が語るリーダー論。
本人は元ラグビー選手であり監督を務めた方だけあってラグビーをベースに語る。
また、書かれたのが2006年ということもあり、ジーコ率いる日本代表のドイツワールドカップ敗退についても多く語られている。
私が印象に残ったのはラグビーのパスの話。日本での指導ではとかくパスの出し方をいうのも教えてしまう。そのため、パスの出し方はきれいなのだが、みんな一緒だそうだ。
平尾氏がいうのは元々パスは戦いを有利な形にもっていくもの。その本質を忘れるとパスが目的化してしまい、パスを受けた選手がすぐつぶされるような自体を招いてしまう。
本書全体に通じるが自分がやっているいることが、どこに位置づけられるのか?それが理解できていないと今やっていることの意味への理解がすすまない。
スポーツは本番ではやったことおの結果がすぐでるので、話がわかりやすい
ビジネスにも参考になる一冊でした。
Posted by ブクログ
ラグビーの全日本元監督による、「強い個」を育てることで「強い組織」を作る方法が書かれた本。各個人が考える力を身につけ、モチベーションを持って行動することで、強い組織が生まれる。価値観の多様化など、変わりつつあるこれからの時代に必要とされるリーダー・組織について、自らの経験を元に語っている。誰もが目指す”活き活きとした組織”がここにあるのではないかと思います。
M2 森下