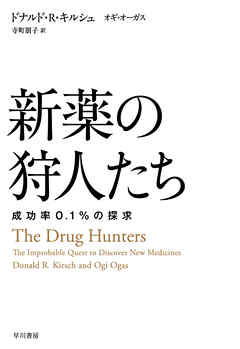感情タグBEST3
Posted by ブクログ
日本語の副題「成功率0.1%の探求」とあるように、現在の新薬探しはビジネス的に成功する確率が非常に低く、さらに巨額の研究費が必要でほとんどの努力が無駄に終わることが多い。実際、創薬プロジェクトのうち、経営陣から資金を提供されるのが5%、そのうちFDAに承認されるのはわずか2%だそうだ。本書は、新薬を見つけ出すのがなぜ難しいか、新薬がなぜ法外な値段で売られているのか、新薬探求や創薬の歴史を振り返りながら解説している。
ノバルティス、バイエル、メルク、エフ・ホフマン・ラ・ロッシュ、ベーリンガーインゲルハイム、ヘキストなど、名だたる製薬会社がなぜライン川沿いに本拠地を置くかにもふれている。19世紀後半、合成化学による合成染料産業の勃興と関係ある。
Posted by ブクログ
薬に関わるものとして、非常に面白く読んだ。解説にも書かれていたが、医薬品にまつわる経緯をこれだけ集めて、比較的分かりやすくまとめた本はなかなか無いと思う。植物からの薬の発見に始まり、化学合成のこと、抗生物質のことなどが製薬会社の動きなどと合わさって展開していくのは、ためになるところも多かった。
Posted by ブクログ
話は面白くわかりやすく,しかも扱っている内容は深い.薬の開発にかける情熱の狂気じみた凄さや,偶然とも言える幸運や,製薬会社などの思惑など,アドベンチャー小説よりもワクワクした.
Posted by ブクログ
大昔から現代まで、どうやって新薬が開発されてきたか、かなり分かりやすく説明してくれる。大収穫本。
以下気になった所を箇条書きメモ。
・マラリアの薬で儲けたのは、ルイ14世の王子を治療した英国人薬剤師のタルボー。彼は薬の原料を秘密としたが、死後それがキニーネだと明らかにされた。(多分マラリアの予防として飲まれていた)トニックウォーターには、キニーネが含まれていたが苦くて飲みにくいので、ジンが加えられ、ジン・トニックというのがカクテルが生まれた。(好きで呑んでたけど、そういう経緯があったのか)
・19世紀、バイエルがアスピリンとヘロインを作った話が面白い。また、フェンフルアミンというあまり効かない痩せ薬と、フェンテルミンというやはり効かない痩せ薬があった。その双方を合わせて摂取すると痩せられると分かった。しかし心臓に疾患をもたらすことが分かったとか。
・微生物から作ったペニシリンはとても貴重だった。摂取した患者の尿から排泄されるので、その尿を回収した。
・抗菌薬はせいぜい一週間ぐらいしか使ってもらえないので儲からない。ゆえに製薬会社はもう新薬を開発していない。耐性のある細菌の感染症には対処できなくなっていく(マジか!)
そんな話がてんこ盛り。新薬を開発するのは、意外なほど科学的ではなく、単なる偶然と一部の天才による思いつきによるものだと分かった。なぜ効くのか分からない(現代でも分からないの!?)薬があるそうだ。新薬開発は科学というより博打らしい。
Posted by ブクログ
訳者あとがきや解題に書いてある通りなんだけど、影響力が大きく、泥臭くてドラマになりやすいジャンルなのに取り上げられにくいという創薬分野の歴史とその時々の人物の挿話集。それぞれの話も面白く、分野全体としても得意性が強いので興味深い。特許などの制度は創薬に適応してるのかというとなんともインセンティブが歪んでる感は強い。
Posted by ブクログ
新薬の開発はますます困難になってきており、ファイザーのようなメガファーマもこの頃では創薬からは手を引いて他社が作った薬の導入に専念したいと考えている。ここまで薬剤はどのようにして見つけられ(作られ)てきたのか、わかりやすい歴史的背景と豊富なエピソードで描かれた良書。
・薬剤の創造は当初は自然にある物質をそのまま使っていた。アヘンからモルヒネが合成され、さらにその誘導体としてヘロインが作り出された(日本におけるアンフェタミンのように当初は依存性のない薬として市販されていた)。ペルーのキナの木の皮からはキニーネが合成された。
・次に純粋に工業的に製造される時代が始まり、エーテルが麻酔薬として用いられるようになった。高価な塗料(巻き貝から作るティリアン・パープルやカイガラムシから作る深紅)の染料を作ろうとする中で、化学物質の構造を少し変えるだけで劇的な変化が起こることが知られるようになり、合成化学による創薬の時代が始まった。サリチル酸はすぐれた抗炎症作用を有するものの、胃痛や耳鳴り、吐き気などの副作用が強く使いにくい薬であったが、これにアセチル基を付与することでアスピリンが合成された。
・さらに、受容体仮説が提唱され、分子レベルで標的を定めた薬剤合成の時代が始まり、サルバルサンが作られた。
・そしてペニシリンが発見され、土壌由来の医薬品、特に抗生物質が大きなトレンドになった。当初はペニシリンは極めて貴重であったため、患者の尿は一滴残らず回収され、ペニシリンはリサイクルされていた。
・その後、分子生物学の発展により、大腸菌でインスリンが合成された。
・ピル、壊血病とビタミンC、セレンディップな抗精神病薬の発見
・グッドマンとギルマンはもともと大学の同僚であったが、ギルマンの方は息子をアルフレッド・グッドマン・ギルマンと名付け、この息子はGタンパク受容体に関する研究で1994にノーベル生理学賞を受けた。
Posted by ブクログ
低分子から、中分子、遺伝子・再生、と新規モダリティの探索が進められている話を最近気にしているが、そもそも「低分子」の前はどうであったのかを知りたくなり、読みました。事前の期待以上に、知りたかったことをレビューできてよかったです。
Posted by ブクログ
過去からの創薬にまつわるエピソードが紹介されている。
結局創薬は、今に至るも偶然に支配されている部分が大きいようで興味深い。
現在私がお世話になっているキイトルーダ(本庶先生のノーベル賞受賞で有名になったオプジーボと作用機序が同じ抗ガン剤)が使えたから、今生きながらえているので、今後もっと工業的手法で創薬ができるようになることを期待したい。そうなれば、創薬の確率が上がりもっと安価に開発できるようになり、もっと多くの人が救われると思う。
Posted by ブクログ
新薬をめぐるドラッグハンターの歴史的攻防が描かれている。ドラッグハンターの思惑や、葛藤も記されていて親しみを持って読める。薬と同様に研究者も個性的である。
新薬探索のいつもの成り行き…新薬になりそうな分子の新しいライブラリーが発見され、主要な発見がいくつかなされ、業界全体がそのライブラリーに群がって短期間でライブラリーが枯渇する。
土壌、動物、植物、タンパク質、ホルモン、DNA操作
白血球は体で病原体を感知するとB細胞が速やかに増殖させる。短期間に数百万種類もの白血球を作り出せる。これらの白血球はそれぞれ異なる種類の抗体を作り出す。体は必要な時に必要なだけオンデマンド武器を作り出せるという事。人間ってすごいなぁ。