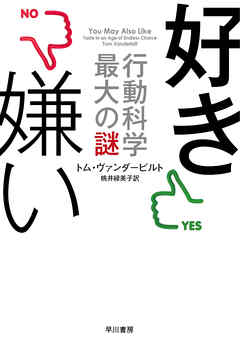感情タグBEST3
Posted by ブクログ
好きか嫌いかはなかなかわからない。好みについて語ったりすることでそれが好きになる。どんなところが好きかを話すことが大事。という至極当たり前のことが書いてある本だが、ワインのテイスティングの話に行ったり、味覚や嗅覚が好きに与える影響を考えていたり、色んな可能性を感じられる本だった。特に私は昆虫食や昆虫を関心領域とするので、なぜそれが嫌いになるのかに関心があったが、目に入るものが好きになり、好きなものが目に入るという理屈は(美術館の話)とても面白かった。要するに身近にあるかが大事なのだ。
趣味や好みで選ばれる対象の場合、「賞の最終選考にとどまった作品は受賞作よりも評価が低かった――受賞作が決まる前は。ところが受賞作という広告が添えられたとたんに、その本の評価は最終選考にもれて負けたほかの候補作への評価よりも急激に低下しはじめるのだ。」という風に、本のレビュー研究や動画の再生回数、音楽の好みの話も面白かった。
Posted by ブクログ
結局好きか嫌いかはなかなかわからない。
分類したり、今まで知っていることの方が好きになりやすい。
好きか嫌いかを話すよりもどんなところが良いかを話す。
結局最後の上を読めばこの本は終わり
もう少し端的に結論を書いて欲しかった
Posted by ブクログ
好きなものを選ぶとき、選ばれるものの良さを計測するとともに、その選ぶ人間の趣味の良さも計測されるというところは面白かった。
また、素人と専門家で判断が異なることも書いてあって勉強になった。レビューを書くときのコメントで、わかるという。このレビューも素人であることが分かってしまうのだろう。
Posted by ブクログ
・私たちは選ぶのが好きなのだ。選ぶ楽しみは、自分で選ばずに何かを楽しみにするよりも神経活動を活発にするようだ。
・きっと気に入ると思っていれば、本当に好きになる可能性が高い
・人の評価は願望から生まれる。自分ってこうなんだ、というのを示すために、「ホテルルワンダ」に星5つ、キャプテンアメリカに星2つをつけておいても、見るのはキャプテンアメリカだったりする
・私たちは肯定的な意見に追従し、否定的な意見には懐疑的でいる傾向にある
・やや否定的なレビューは役に立ったかどうかの評価において、やや肯定的なレビューに比べて結果が悪かった。不確かな場合には、私たちは肯定的な方へ傾くのである。
・否定的なレビューに好意を持てるか、つまり信用するかどうかを決定づける非常に重要な変数が一つある。系建材(本や映画など、経験しないと良しあしが判断できないもの)か探索財「カメラや交換用ワイパーなど、品質や性能を購入前にある程度把握できるもの」かという変数だ。多くの経験材では好みが大きくものをいううえ、消費者が自分の趣味や主観的評価に非常に自信を持っている場合が多く、他の人々の極端な意見に懐疑的になるため、否定的なレビューへの評価は厳しくなる。本や映画の場合は、車のワイパーとは違って、レビューに目を通すときにすでに態度が決まっていて、他人の星一つの批評は一種の認知的不協和として除去される。探索財の場合、消費者は製品の性能や仕様、欠陥、ユーザへのお役立ち情報などをレビューから知ろうとしている。バイアスや趣味は介入しないので、否定的なレビューは欠陥があることを示す間違いのないシグナルだろう
・消費の仕方は消費するものと同じくらい趣味を表している
・すきになることは学習すること、学習することは好きになることだ。
・美術品を見て心が動くのは、自分の周囲の世界だけでなく、自分自身についても何かを学べるひらめきの瞬間を経験している
・愛好家は、よいものについてのバイアスがありすぎて、そもそも何に心が躍るのかということを忘れてしまっている
・人は分類できるものを好む
Posted by ブクログ
人は情緒的にまず判断し、その後で理由をつける。なぜ好きか自分でわかっていないことも多い。言葉で説明してみるといい。分類できるものを好む。わかりやすいものにはすぐ好意を持つが記憶に残りにくく飽きられやすい。目新しさ/なじみ深さ、同調/差異化、単純/複雑。いいね!はあるけどダメ!はない、ネガティブは実は強力。
最大の謎、解けるかなと期待しましたが、謎はやっぱり謎でした。周辺のいろいろな知識は得ましたが。
Posted by ブクログ
人間のよろこびはみんな砂糖からくる。全員味覚顔面反応が起きる。嫌いな人はいない。好きの程度が違うだけ。
フランス料理のアミューズブーシュは口を愉しませるもの。
何か一口おなかに入れるとインスリンが分泌される。空腹の合図。空腹を感じる。アペタイザー効果。
料理がバラエティーに富んでいると食欲も刺激する。感覚特異性満腹=進化にとって有益なメカニズム。
最後にデザートを食べるのは、満腹であっても絶対的に美味しいものだから。
Googleのads/preferemses で、好みがわかる。
若いころの音楽がいちばんいいと思う=焼き印を押された。
接触効果=接する頻度の高いものを好む。
知覚的流暢性=知覚情報の処理が容易になり好きになる。
ローレンツの刷り込み効果
Posted by ブクログ
「行動科学の最大の謎」とタイトルされているように、「人の好き嫌いは説明できない」というのが常識のようだ。
そのテーマにあえて挑戦した著者の中間報告的な書ととらえた。全体的に著者の調査や研究の過程で得られた情報が羅列的に書かれているように感じるが、客観的な分析結果が述べられているものではない(と思う)。
しかし、その「好き・嫌い」というものの特徴をおぼろげながら掴んでおり、それを表現した一つの言葉が、以下のものではないだろうか。
「好みにはさまざまな無意識のバイアスがつきまとい、そのときの状況や社会からの影響であっけなく揺れ動く。」
「今日好きなものを明日も好きでいる可能性は思いがけないほど低く、以前に好きだったものを何が好きにさせたのかを覚えている可能性は低い。」
「好き・嫌い」というのは絶対的なものではなく、なんらかの影響により存在し、変化するものなのだということを知ることができた。
自分がなぜ本書を手に取ったのかのそもそもを考えてみると、「好きとか嫌いとかがどうして発生するのか?」とか、特に「嫌いなものが好きに変わることはあるのか?」というようなことが知りたかったからだと思う。
「野菜嫌いの子供が毎日食べることで好きになる」というようなことから接触回数が嫌いを好きにさせるというような話もあったが、それだけでは世の中で離婚する人がいることと矛盾するようにも感じた。
やはり、接触効果により嫌いが好きに転じるには、他に別のバイアスがからんでいるようにも思われる。
今後そのへんの仕組みまで明かしてもらえれば、嫌いを好きに転じることができ、ハッピーライフをもっと拡張できるのではないかと感じた。