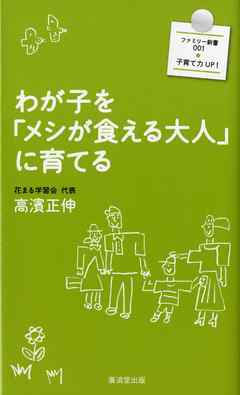感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ひとこと日記やりたい
子どもへの声かけを変えるのではなく、子育ての考え方を変えないと、本質的に声かけは変わらないと感じた
もっと子どもを認めて、まずは話を聴こうと思った
親が手を出せない場面を増やす、体験型のところに連れて行く、見守る意識をもっと増やす。
子育てを見直すキッカケに。
Posted by ブクログ
子供が自立・自活できる大人になるために必要となる基礎力について書かれた本。
幼稚園児~小学生を対象とした学習塾・花まる学習会の代表である高濱正伸さんが、10歳くらいまでに育ませたい基礎力(自分で考える力・ことばの力・想い浮かべる力・試そうとする力・やり抜く力)について、本書で詳しく解説しています。
一番大事なのは国語力(ことばの力)。国語をしっかり学ぶことで、他の科目にも好影響が出てきます。
Posted by ブクログ
息子の将来が不安で読んだ本。普段のガミガミした接し方を反省しつつ、なるほどなぁと感心しながら、読み進めた。
否定ではなく肯定されていると感じること、万能感を無くすことのバランスが重要。母の心の安定が子供の安定につながるなど、思い当たることが多々あった。
定期的に読んで反省しながら子供と接すると良いかもしれない。
Posted by ブクログ
しっかりメモしながら読みました
自分の子供の良いところはすぐ出てきます
でも、気になるところ・直して欲しい所はたくさん気づいてしまいます
つい小言が増えてしまうので、正しくサポートができるようにこの本を読みました
特に、試そうとする力、やり抜く力を強化できたら素敵な大人に近づけると思いました
お金を稼ぐだけじゃなくて、自立して安定した生活ができる人になって欲しいです!
Posted by ブクログ
将来社会で生きていくにあたり、周囲と対話しながら貢献して稼ぐという目標に向かって、どんな力を身に着けるとよいか、どのように身に着けるかを具体的に実践ベースの知識を元に展開されている。
1. ことばの力 Words
2. 自分で考える力 Thinking
3. 思い浮かべる力 Imaging
4. 試そうとする力 Trial
5. やり抜く力 Grit
4.試す→自己肯定感→5.やりぬく→達成感→次へのチャレンジ精神
▼読書メモ
思考の自走力。思考の内燃機関を作る。
笑わせようという意識=試す力
ユーモアセンスは、人を惹きつける+仕掛ける意識をもって仕事に取り組む
笑い・ユーモアは、人の心への仕掛け。一歩踏み込む。
「ウケるかどうか、わからないけれど、とりあえずやってみよう」が信条。
試してみよう。
お手伝いでは工夫させる。工夫→脳みそが活性化する。
失敗を織り込んで、任せる。
家族生活に影響のある重要な家事。
靴磨きで「思いを込めて磨いてごらん」→脳みそが活性化される
異年齢の子どもたちの間に置く。→他者貢献したがる。人は貢献したがる生き物。
▼トライすること
・試す
・ざくっと任せて工夫させる(振り返りで質問だけする)
・小さな成功を事実として認める
Posted by ブクログ
基本の5つの力
1.言葉の力
2.自分で考える力
3.想い浮かべる力
4.試そうとする力
5.やり抜く力
言葉をきちんとすることが基本でそのために手に届くところに国語辞典を置いておく。
自分の言葉の引き出しを多くするために、日記や対話を行う。会話を重ね、自分の言葉が出てくるのをじっと待つ。
親が聞くだけではなく、子が聞く側にまわることも有効。
チャレンジする力を伸ばす。
結果よりプロセスを楽しむ意識を持たせる。
ピグマリオン効果。人は期待されると期待通りの結果になる傾向がある。
小さなことでも出来たことはほめる。
大人になり、必要な力はやはり、子ども時代に育む。
Posted by ブクログ
「メシを食っていける大人」にする5つの基礎力
(1)ことばの力 ・・・ 人が言っていることや文章を的確に理解してポイントをつかむ力と、自分の考えを的確に分かりやすく相手に伝えたり表現する力。
(2)自分で考える力 ・・・ 勉強でも日常生活でも、自分なりに考え、判断する力。これまで身につけた知識や技能を活用する力。物事を筋道立てて考える力。
(3)思い浮かべる力 ・・・ 具体的な物や事象だけでなく、人の心など抽象的なこともイメージできる力。細かな点だけでなく、全体を俯瞰して見ることが出来る感性。
(4)試そうとするする力 ・・・ 興味・関心のあることや面白うそうなことにチャレンジしたり、与えられた課題を解決するためにさまざまな方法をためそうとする意欲。
(5)やり抜く力 ・・・ 一度始めたことを、多少の困難があっても最後までやり抜こうとする力。やり始めたことに集中して取り組む力。コツコツ続ける力。
これらを10才までに育み、受験に必要な教科学力をつけ、大学では専門的な知識・教養をつける。これが社会人として必要な様々な能力に結びつくという内容でした。
全般的に、どんぐり倶楽部の『絶対学力』に書いてあった内容から、「これをやってはダメ」という内容を省いたソフトな感じに仕上げています。だからといって理想論では無く、現実に社会に出て行くことを考えた教育論で、著者の温かい人柄と子供に対する愛情が出ていて読みやすいです。
Posted by ブクログ
カンブリア宮殿や情熱大陸で取り上げられた「花まる学習会」代表の高濱氏の著書。
「メシが食える大人」とは、経済的な自立、克己心や耐える力といった精神的な強さ、問題解決の突破口を見出すときに発揮される自立的な思考力をもつ社会人のこと。
そのために欠かせない5つの基礎力をいかに10歳までに家庭で育むかが力説されてます。学力をどう上げるかというようなウワベではなく、本質的にどのような力を身につけさせることが結果的に「メシが食える大人」になれるかが具体的に書かれています。
Posted by ブクログ
まともで常識的なことが書いてあって安心した。共感できる部分が多かった。
「ことに、大人になってからのひきこもりは、子どものころの『耐性が身につかない教育のあり方』が大きな原因になっているように思います。
たとえば、『話せばわかる』という対話重視の姿勢。『体罰は絶対にあってはならない』という平和的な教育観。『誰とでも仲良くしよう』という開放的な人間観。いずれも、耳に心地良いことばが並びます。しかしそれだけでは、世の中の片側しか映らない鏡を子どもに与えるようなものです。
社会に出れば、会社には力ずくで部下を押さえつけようとする上司がいたり、感覚的に合わない同僚がいたり、非常識な要求を突きつける取引先もあれば、クレーマーの顧客もいる。善意で行動している人間を誹謗中傷したり、人をだますことを生業としている人間もいます。理不尽なことが多いのが、この世の中なのです。
社会に一歩踏み出したら、そういう世間の荒波が待っていることを、小さいころから子どもにしっかり教えておくべきだったのです。そのうえで、『だからこそ高い志をもって、前向きに困難を乗り越えていくたくましさが必要なのだ』と説き続けることが、親の役目だったはずです。」
Posted by ブクログ
「達成感は必要だけど、万能感は根付かせないようにする」というのは、なるほど確かに。これって顔面偏差値にも言えないかな。かわいい(愛嬌がいい)ことは褒めても、高飛車な美人にしてはよくないというのに似ている。
メシが食える、という表現はとてもいいと思う。そのために学歴が必要だと思えばそうすればいいし、手段と目的を履き違えないようにしないとね。
Posted by ブクログ
割と面白い。
僕の、子育て理論と似てる。
自立させようとする考え方。
あえて子どもに道案内させてみたり、そのとき、どう思ったの?って聞いたり〇〇って、どういう意味が?って聞いて、一緒に調べたり、どんなところが良かった?って聞いたり。
参考になったのは、子供へのインタビューではなく、ぎゃくに子供にインタビューさせてみるとか。面白そう。
ただ逆に新しい発見は少なく。まあそうだよなーって感じだった。
Posted by ブクログ
幼児教育論だが、人生哲学でもある。
おそらくは彼自身の体験談からくるものであり、大いに同意できる。
経済的自立は果たしているが、精神的には大人になれなかった人。物事をじっくり考える習慣をつけない、根気強さがない、空間把握能力、意思決定、判断力が乏しいなど。
勉強の成績も大事だが、生活習慣や親の物の感じ方、考え方も大事。
自分が不遇なのを他者のせい、環境のせい、自分が絶対にそうならない逆の立場(異性、土地柄、年齢)のせいにする、という思考回路を子ども時代に身に着けられないのは不幸だと思った。ネット上にはそういう人が多すぎるけども。
Posted by ブクログ
親は自分の価値観を押し付けてはいけない。やらされ感が、主体的に考える力を奪ってしまう。そんな一見陥ってしまいがちな間違いに気づかせてくれる。子供の万能感を根付かせないために、無駄な買い与えをしない。など、耳が痛いことも。子育ては親育てと言うが、この本を読んで改めてそう思った。子供のなぜ?に答えたり、語彙力を増やす手伝いをしてあげるには、親もしっかりと学ぶ姿勢を持たなければいけない。
Posted by ブクログ
子育てや教育の本では「10歳くらいまでに」と書かれていて焦る。
1言葉の力
2自分で考える力
3思い浮かべる力
4試そうとする力
5やり抜く力
を小学校低学年までにはぐぐむこと。
これこそ「知力と意欲の源」。
まだ間に合うかしら?
読みすすめるうちにSには意識してやってきたことをMにはやってないな、まずいかもと思い始める。
*言葉の力
・「音読ゲーム」つっかえたり、読み間違いをしたら減点1点。読みきる精読力をつける。
・1,2行でも良いから日記をつけさせる。
*考える力
・「種は芽を出す。芽は伸びる。そういうふうにできている。」親の価値観で無理やり芽を引っ張り出さない。
・少しでも疑問点が残ったら、あとで調べて教える。「親のしつこさ」を心がける。
*思い浮かべる力
・「初めてその場所へ行く人のために説明する」ゲーム。
*やりぬく力
・熱くなったり必死になることは、けっしてカッコ悪いことではないことを、遊びを通して身体を張って子供にみせる。
やりつくす感覚を身体で覚えさせる。
うちのチビちゃんたちはいっつも笑いをとろうとがんばってる。
これは「試そうとする力」を育んでるわけか!
きみら、ダイジョウブなの?と心配になってたんだけど。
Posted by ブクログ
はなまる学習会を主催している著者が、体系的に説得力をもった”メシが食える力”について説明をされています。メシが食えるというのは、社会で仕事をちゃんとやっていける力を付けるということです。私は、仕事で新入社員が職場に配属された後の教育を担当しています。なんとはなしに、色んな力の不足を感じますが、著者が整理している色んな種類の力が不足してると再認識しました。しかし、メシが食える力は10歳までに身に着ける必要があるそうで、自分の子供たちには、手遅れであることを”納得”せざる得ません。残念!
Posted by ブクログ
子育て本でありながら読んでいる自分自身の身につまされることの多い本でした。
わが子を「メシが食える大人」に育てる前にむしろ自分が「メシが食える大人」に
なれているのか問いかけながら読んでいました。
私も子育てをしている者としては子どもを「学校の成績が良い人」
になるように育てるより「世の中の役に立つ人」になるように育てようという
方針で子育てをしているので色々と参考になることがありました。
自分の中で考えていたことを体系立てて解説してくれたような
そんな感じを受ける本でした。
それにしても途中に付いている問題が解き応え満点でした。
特に算数オリンピックに出題された問題などは1時間近く悩んで解答に辿り着き、
物凄く達成感を得られました。
Posted by ブクログ
今日も高濱先生の講演会に行ってきたが、メシを食うために大事なことはすべて、日常的な経験の中にあるのだと気付かされる。生きる力は、当たり前だけれど問題集を解くだけで得られるものではない。むしろ本気で遊ぶことが学力につながる。学力は後からついてくるものなのだと解る。
子どもの芽を伸ばすには、まず親である自分の言動に気をつけること。そしていつも笑顔でいたいなぁと。
Posted by ブクログ
メシを食っていける大人の5つの基礎力まとめ
1)ことばの力・・・人が言っていることのポイントをつかむ力、自分の言いたいことを表現する力
2)自分で考える力・・・判断力。自分の知識や技能を活用する力。筋道立てて考える力
3)想いうかべる力・・・想像力と感性。
4)試そうとする力・・・試行錯誤しながら考える姿勢
5)やり抜く力・・・やり始めたことに集中して取り組む力。コツコツ続ける力。
基本、上記の5つの力に関して詳しく解説してくれていますが、むしろ序章に当たる部分のほうが重要なことが書かれているような気がします。
身につけるべき3つの自立の話や人間力を鍛える必要性について書かれています。
うちの息子、宿題のプリントをやってもすぐに「わからへん」「でけへん」って言って教えてくれって言ってくるけど・・・ヤバイ。
Posted by ブクログ
塾講師の経験をもとに書かれた言葉は、具体的でわかりやすいものだった。きっと意識されて書かれたのだと思うけど、「どうすればいい子に育つか」と、筆者が常に考えていたからこそ、具体的な言葉で表現できたと思う。しかも「筆者だけができる内容か」というと、そうでなく誰でもどの家庭でもできる実践なのが非常によかった。
その例を少し書く。
「小さい頃に自然に触れた経験が豊富な人の方が、意志力や意欲力が高い」
「このあいだ、いったでしょう?」「何度いったらわかるの?」「なんで、こんな簡単なことがわからないの?」このことばが、子どものやる気をくじく。
「他者を思いやる経験は、お手伝いでできる。お手伝いが終わったら目いっぱい誉めてあげる。子どもはお母さんが喜んでくれることが、何よりもうれしい」
「他者性を意識しながら、空間認識力を高める親子遊び。「道順遊び」」
「結果よりも、プロセス。プロセスを楽しむことが何より大切」
「やり抜く力は、体験の量によって強化される後天的な力」
「親自身が何かに熱中している姿を子どもに見せる。お父さんは、遊びを通して、身体を張って子どもに見せてほしい。」
「一つひとつの誇れる体験が学力向上や人間の成長には、大きなバネになる。」
「日記を書くこと」
「10歳くらいまでなら、音読することに抵抗がない。3ページ半をつかえないように読み合いする親子ゲームもできる」
「やり抜く力は、そうした”小さな達成感”を日常生活のなかで積み上げていくことによって、どんどん力強さを増していく」
Posted by ブクログ
筆者は「はなまる学習会」という塾を主宰している人物。
小学校低学年のころの過ごし方、学び方が将来の「メシを食える」自立した大人になるための能力を育むという内容が筆者のみた実例から語られている。
幼児・児童教育に関心がある人はもちろん、中学生を過ぎても、音読を実践することで国語力に飛躍的な伸びがみられた例など、興味深かった。
Posted by ブクログ
最近テレビでよく見かける「花まる学習会」。小学校低学年向け・関東で展開されている学習塾で、なんと3000人待ちとか。
その設立者の高濱さんの本。すごい気になってた人なので見つけて即購入。
「メシが食える大人」を育てるために塾を開いたそうで、予備校で教えていた浪人生たちにあまりに覇気がなかったのがきっかけだったらしい。
「はきはき声を出せない」 「意欲がない」 「言われたことしかやらない」・・・。確かにどれも現代っ子に当てはまる気が。
高濱さんが言うように、小学校低学年までの家庭教育が大事なんだと思う。
母親の手伝いをする
外でめいっぱい遊ぶ
「なぜ?」という疑問をもつ
親はたくさんほめてあげる(自己肯定感を育てる)
とにかく国語算数。音読をする
最後まで考え抜く力を育てる(文章題)
ことばの力・自分で考える力・想いうかべる力・試そうとする力・やり抜く力
これが「メシを食っていくために欠かせない基礎力」なんだそう。
確かに基本の基本やな。メシを食っていく、というか、私の中では、社会に出ても適合して生きていける力だと思う。これさえ身につけとけば、社会不適合にはならない。幼児教育や小学校での教育は専門じゃないけど、高濱さんの言うことはなんとなく腑に落ちる。
他の著書も読んでみよう。
Posted by ブクログ
良い評判を聞いたので読んでみた1冊。
だけど、感想は「まあまあ」かな。
理由は、そこまで新しい発見がなかったから。
自分が受けてきた教育+足りなかったと感じていた部分がそのまま本になっていた感じがした。
私の母は、私に勉強しろとは言わなかったしいつも安定していた。
そして年5、6回はキャンプへ連れて行ってくれ自然と触れ合った。
足りなかったところは、母が私の世話をしすぎたところだと思う。
少し自立が遅れたと思っていた。
そして今、二児の母として間違っていないことを確信した。
もっと遊ばせて、もっと話を聞いてあげて、もっと生きる力をつけてあげよう!
Posted by ブクログ
・5つの基礎力「自分で考える力」「ことばの力」「想い浮かべる力」「試そうとする力」「やり抜く力」を育むことが大切
・経済的自立,社会的自立,精神的自立
・小さな成功体験の積み重ねが大切
Posted by ブクログ
大人になった時にメシが食えるように育てる。って考え方に非常に共感。そのためには、幼少期に5つの力を身に付けさせることが必用と説く。自分の子供を育てるって観点だけでなく、大人になった自分自身がこの5つの力があるだろうか?と自己点検するのにもいいかな。
以下、参考になった点、引用、自己解釈含む。
・幼少期は大人に守られており、子供は自然と万能感≒王様感を感じる。が、年を取るにつれ、自分に都合の良いことだけでは済まなくなる。自分は王様だと勘違いさせ過ぎてしまうのは危険。世の中には理不尽なことも多いということを、小さいころから教える視点も持ち合わせるべき。ニートが増えている根柢には、過保護に甘やかされて育てられたことが大きい。
・冷めた子が増えているのは、親が冷めているからではないか。親が何でも良いので、一生懸命にやる姿を見せていれば、子供は自然と熱中する姿勢を持つ。子どもに「一生懸命にやれ!」という前に、自分自身が一生懸命に生きているのか、自問自答する必要がある。
・飯が食える大人になるための5つの力
①言葉の力。人が言っている言葉のポイントをしっかりと把握でき、また自分が伝えたいことをしっかりと伝わるように伝えられる力。
②自分で考える力。勉強でも日常生活でも他に答えを求めるのではなく、自分で考える力。
③思い浮かべる力。具体的な物事や事象だけでなく、相手の心など目に見ないものもイメージできる力。
④試そうとする力。興味関心のあることにチャレンジしたり、与えられた課題に色々な方法を試そうとする意欲。
⑤やり抜く力。一度始めたことを多少の困難があっても最後までやり通す力。
・逆インタビュートレーニング。親が子どもに、今日は学校でどんなことがあった?と聞くことはよくあるが、この逆を子どもにやってもらう。今日お母さんはどんなことがあった?どんなことを感じた?と聞いてもらう。楽しんでやるのがコツ。インタビューを通して、人の行動や感情に意識が自然と向くトレーニングとなる。
・目的地までの道順を説明するゲーム。
・いつもふざけて笑いを取ろうとする子は、人を笑わせるための様々なチャレンジ=試す力をいかんなく発揮している状態。人を中傷するような内容で無ければ、叱らずに、受け止めてやるのが良い。
Posted by ブクログ
★★★☆☆
小学生低学年のお子様がいる親向け
【内容】
10歳までに育むべき5つの力が、社会人としてメシが食える力にどう結びついているのか、どう育めばいいのかを丁寧に解説。
【感想】
小学生低学年のお子様がいる親向けです。
僕にはちょっと早すぎました。
大切なのは、「体験」ってことです。何事も体験させるとこが大切で、それを楽しむ!
【引用】
・大人の頭には「一度行ったことは理解できる」「簡単なことは理解できる」といった"大人の方程式"があって、それを子供に当てはめようとしているのです。しかし、子供にはそんな方程式はありません。
・5つの基礎力→10歳までが勝負
1.言葉の力
2.自分で考える力
3.想い浮かべる力
4.試そうとする力
5.やりぬく力
・人はイメージで考える動物
・やる気になってやったことは必ず伸びる
・楽しいからやってみる価値がある。結果よりプロセス。プロセスを楽しむことが何より大切。
・本当に納得するまで食い下がり、自分で解くことにこだわるしつこさは、多少の頭の良さなどははるかに凌駕する。
・お手伝いでも生活習慣でも「できたこと」はどんどん褒めて、言葉を投げかけてあげてください。やりぬく力はそうした"小さな達成感"を積み上げることで強くなります。